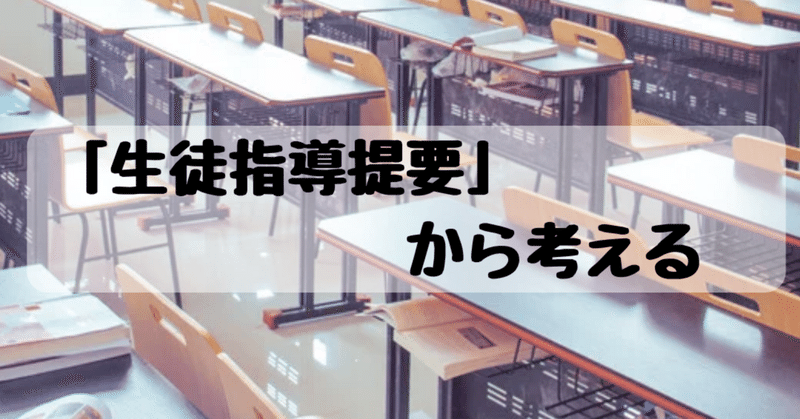
児童・生徒指導㊾生徒指導提要から考える その3(生徒指導の実践上の視点2)
今回は「生徒指導提要」を読んで、考察をしてみたいと思います。あくまでも、読んで感じたことや考えたことなどの、個人の一見解です。また、読み進めながら書いていくため、全体像を見通した内容になっていなかったり、解釈の仕方が変わっていったりする可能性もあります。
さて、生徒指導の実践上の視点としては以下の4つが示されています。
(1) 自己存在感の感受
(2) 共感的な人間関係の育成
(3) 自己決定の場の提供
(4) 安全・安心な風土の醸成
今回は、(2)から(3)に視点を当ててみたいと思います。
「自己存在感」においては、ありのままの自分でいられることを大切にしたいこと、そしてそれは個人内だけでなく周りの影響を多分に受けるという考えを前回の記事でまとめました。
この4つは互いに関連し合うものだと強く感じます。
「共感的」に相手のことを見る気持ちが土台にある学級でこそ、ひとりひとりがありのままを出して生活でき、「自己存在感」を得ることができる。ひとりひとりの選択が受け入れられる、または、それについて建設的に意見が交わされる雰囲気があって、「自己決定」しようとする気持ちになれる。それらによって、「安全・安心な風土」がつくられていくのではないでしょうか。
そして、(4)安全・安心な風土の醸成の説明の中に、
児童生徒一人一人が、個性的な存在として尊重され、学級・ホームルームで安全かつ安
心して教育を受けられるように配慮する必要があります。
と述べられています。
「個性的な存在として尊重され」ることは、よく述べられることではあると思いますが、実際にどのような様子が見られれば、そのように言えるのか非常に難しい考え方であると思います。
例えば、「発表を笑う」「意見に対して聞く耳を持たず、否定する」など、よくない行動を列挙して、「それらがない状態」と説明するのこともできますが、それは一面的な姿でしかありません。
(1)から(3)についての状態を具体的にイメージしてみることで、実際に増やしたい姿を教師の頭の中に具体化することができると感じました。
私が思い描いたのは、まず土台に(2)の「共感的」な姿があることです。相手の立場を考慮した発言ができること、それが学級全体に広がることで、気が強い子も控え目な子も「言いたい」ときには、アサーティブな表現ができる。相手の価値観や願い、目標を理解しようとし、支え合い、励ますことができる。
そして、その土台があり、(3)の「自己決定」についてです。「共感的」な雰囲気があることで、学習、生活、自己の目標において、考え、選択し、決定して取り組んでいくことができる。
(3)のような自己決定が「できている」と感じられることが、「ありのまま」の自分を出して生活しているという実感につながり、多くの他者との中でも、自分という人間の(1)「自己存在感」を得ることができる。
このような状態が子どもたちの、心理的・物理的な安心と安全につながっていく。
このような相互関係として捉えました。
皆さんは、こられの4つの視点についてどのように考えますか。ぜひ教えてください。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
