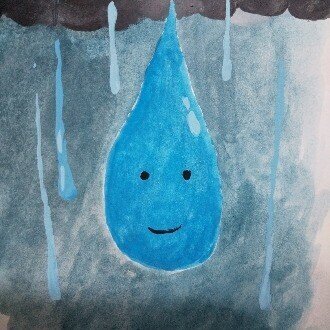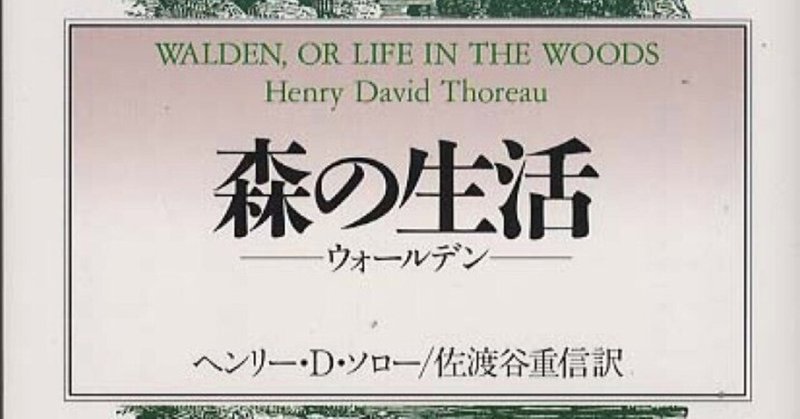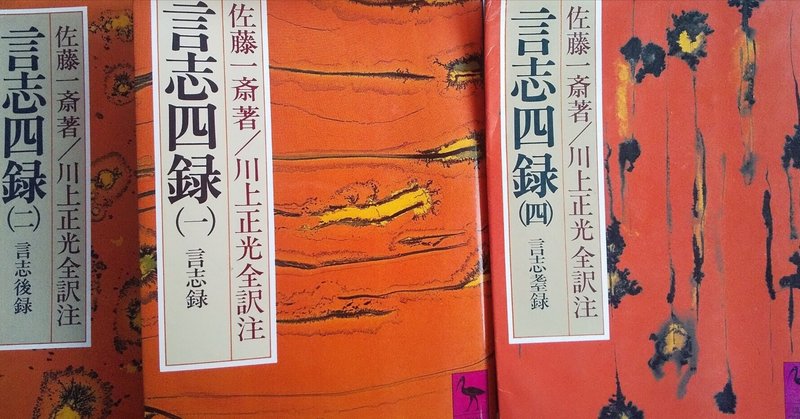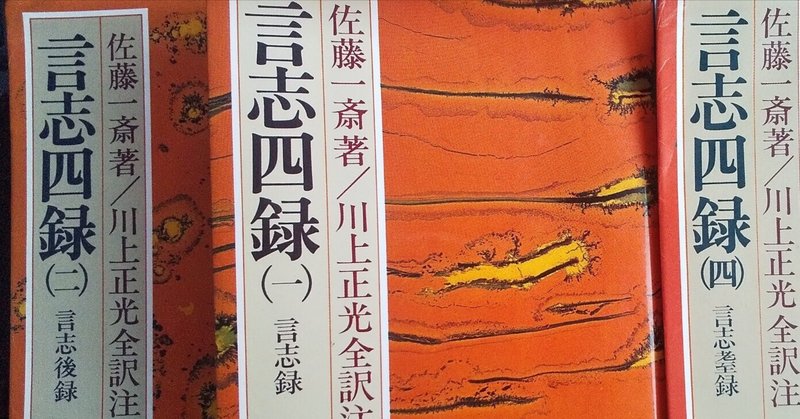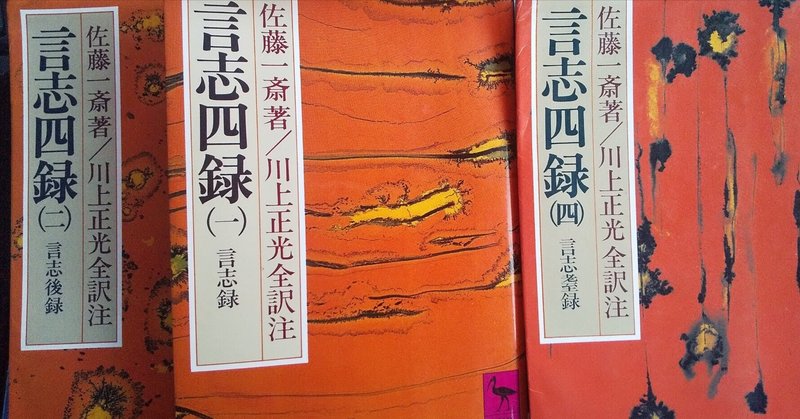#本
『森の生活−ウォールデン−』 ソローと2人の親友
『森の生活−ウォールデン−』の著者、ヘンリー・D・ソローは森の中に建てた小屋で約2年間生活しました。そう聞くと、ソローは非社交的で孤独な人物に思えるかも知れませんが、実際にはとても話し好きの社交的な人間でした。
ソローの小屋には、色んな人々が訪れます。『森の生活』の[訪問者][先住者、そして冬の訪問者]という章には、ソローの交友関係が記されていて、彼の親友が2人登場します。
一人は、ウイ
『森の生活−ウォールデン−』
ヘンリー・デイヴィッド・ソローは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州コンコード、ウォールデン池の畔の森に自ら小屋を建て、1845年7月から約2年2ヶ月一人で生活をしました。
ソローは、森の動物や植物を観察し、農作業をしたり、人間や社会について考察しながら生活し、その経験をもとに『森の生活−ウォールデン−』を執筆します。
ソローの思想を要約すると。文明の進歩によって人々の生活はより便利で快適にな