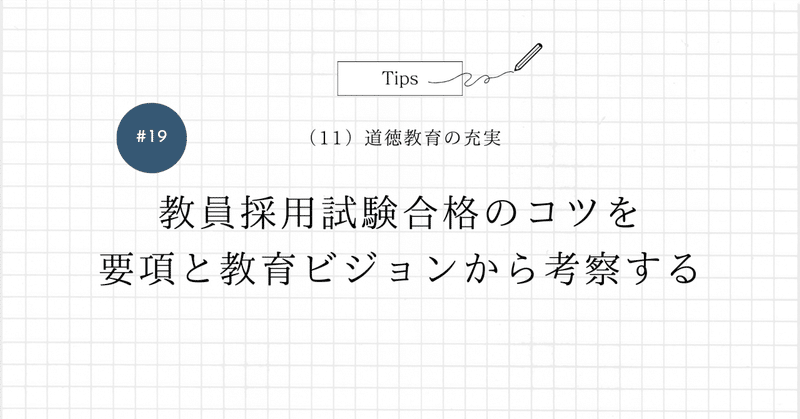
教採合格のコツ 道徳教育の充実 解説と試験官へのアピール方法 【あいちの教育ビジョン2025 -第四次愛知県教育振興基本計画-より】教員採用試験対策
教員採用試験に向けて、多くの受験生がどんな準備をすればいいのか、どんな考え方や言葉を使って答えると良いのかと悩むことがあるでしょう。この記事では、近年の教育方針や重点項目に基づき、その要点と教育のビジョンを考察します。
まず、小中学校での道徳の特別の教科化について、今の社会には様々な価値観があり、それぞれに合った答えがあるということを重視しています。この変革をしっかりと進めることが求められています。一方、高等学校での道徳教育も、人間としての存在や生き方を深く考えることを目指して、学校全体の教育活動を通じて強化することが大切とされています。
そして、自己肯定感や感謝の心、生きる喜びといった道徳的価値の深化が強調されています。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、人々の中に不安や恐れが生まれる中で、他者に対する差別や偏見を避け、理性的に判断できる力を子供たちに育てることが求められています。
高度な情報社会においても、スマートフォンやSNSの普及に伴い、情報の真偽や安全性などの問題が増えています。このため、情報モラルを身につけ、適切に情報を扱えるような教育の進行が必要とされています。
このような背景や方針を元に、教員採用試験でのアプローチや回答の考え方について、具体的な提案やヒントを本文中で考察していきます。この記事が受験生の一助となり、より良い教育の実現に繋がることを願っています。
現状と課題、施策の方向
○ 小中学校における「道徳」の「特別の教科」化は、多様な価値観が存在する現代社会においては道徳的な課題についても様々な答えがあるという立場に立ち、発達の段階に応じ、児童生徒が自分自身の問題として向き合う、「考え、議論する道徳」への質的転換を図るものであり、この転換を着実に進めることが必要です。
○ 高等学校における道徳教育では、人間としての在り方や生き方を考える教育を、「公民科」や「特別活動」のホームルーム活動などを中心にして、学校の教育活動全体を通して充実させることが重要です。
○ 「自分にはよいところがあると思いますか」の問いに対して肯定的に回答した本県の児童生徒の割合は、「あいちの教育ビジョン2020」の策定時に比べて増加傾向にありますが、引き続き、児童生徒に、生命の尊重や感謝の気持ち、生きる喜びなどの道徳的な価値についての考えを深めさせるとともに、自己肯定感・自己有用感を一層高めるための取組を推進します。さらに、同じ場にいられなくても、様々な方策で人間関係をつくり、それを通して、自分の命を大切に思うことと同じように他の人の命を大切に思う気持ちを育んでいけるよう取り組みます。
○ 2020年初頭から、世界中に拡大した新型コロナウイルス感染症は多くの人々の命を奪っています。過去の歴史においては、こうしたパンデミックを機に、不安感の増大から、他者に対する差別や偏見、あるいは命を軽んじたりする風潮が生じたことを踏まえ、児童生徒に正しい知識をもとに考え、理性的に判断することができる力を育みます。
○ 一方、高度情報社会の進展に伴い、スマートフォンやSNSが子供たちにも急速に普及しており、それらを発端とした犯罪の増加や個人情報の流出、虚偽の情報の流布などの問題が生じています。そのため、情報社会での行動に責任をもつ、情報を正しく安全に利用する、コンピュータ等の使用と健康との関わりを理解するなど、高度化する情報社会において適切に行動できるよう、児童生徒に情報モラル3を身に付けさせるための教育を推進していきます。
小中学校における「道徳」の「特別の教科」化:現代社会では様々な価値観が存在し、それに応じて道徳的な課題についての答えも多様である。この点を重視し、児童生徒が自らの問題として道徳的な課題に向き合う「考え、議論する道徳」を目指す取り組みである。これは、児童生徒がただ教えられるのではなく、自分の頭で考えるスキルを養うことを重視する動きである。
高等学校における道徳教育:こちらでは、生き方や人間としての在り方についての教育が強調されている。具体的には「公民科」や「ホームルーム活動」といった場を利用して、学校全体を通じた道徳教育の充実が求められている。これは、高校生が社会に出る前に、自らの価値観を形成し、他者との関係性を深めるための基盤となる。
児童生徒の自己肯定感・自己有用感の高揚:ここでのポイントは、児童生徒の自己肯定感が「あいちの教育ビジョン2020」策定時より向上していることである。それにも関わらず、引き続き、生命の尊重や感謝の気持ちを深める教育が求められている。また、物理的な距離があっても人間関係を築く技術や、他者の命を尊重する心の育成が強調されている。
新型コロナウイルス感染症との向き合い方:この感染症は多くの命を奪っており、過去のパンデミックと同じく、不安や差別の風潮が生じるリスクがある。この点を踏まえ、児童生徒には正しい知識をもとに、理性的な判断ができる力を身につける教育が必要である。
情報社会と児童生徒の課題:スマートフォンやSNSの普及に伴い、犯罪の増加や情報の誤流布などの問題が生じている。このため、児童生徒が情報社会での行動に責任を持ち、情報を正しく安全に利用する教育が必要である。また、コンピュータの使用と健康の関連性についての理解も求められている。
施策の展開
① 「特別の教科道徳」を核にした道徳教育の推進
○ 児童生徒が、それぞれの道徳的諸価値の理解をもとに、自己を見つめ、様々な物事を広い視野から多面的・多角的に考え、人間としての生き方についての考えを深めることができるように、研究指定校において授業方法や評価の在り方等について研究するとともに、その成果を各学校に伝達し、道徳科の授業の充実を図ります。
○ 地域の人々や保護者等に道徳科の授業を公開し、学校と家庭や地域が連携して児童生徒の豊かな心を育みます。
○ 市町村教育委員会における道徳教育実践の取組を、道徳教育総合推進サイト「モラルBOX」に掲載して、学校間で共有します。
○ 道徳教育指導参考資料「明日を拓ひらく」や、地域ゆかりの偉人をまとめた副読本、地域に根付く伝統・文化や地域でのボランティア活動などを取り上げた教材等を活用するなど、学校の教育活動全体において道徳教育を展開します。
児童生徒の多面的・多角的な考察の育成:児童生徒は、道徳的な価値観を持ちつつ、様々な視点から物事を見る力を身につけることが求められています。具体的には、彼らが自分の価値観や道徳的な価値を元に自分自身を見つめ、多様な物事に対する視点を持つことです。このような能力を育てるために、特定の学校、研究指定校で授業方法や評価方法の研究が進められています。そして、その研究成果を他の学校にも伝えることで、道徳の授業がさらに充実していくことを目指しています。
学校と地域の連携:学校は地域や家庭と連携し、道徳教育の授業を公開する取り組みを進めています。これにより、地域の人々や保護者が道徳教育の現場を理解し、子供たちの心の育成に関与することができます。共同での育成を促進することで、児童生徒の心の豊かさをさらに深めることが期待されます。
道徳教育の共有:市町村教育委員会では、道徳教育の取り組みが進められており、これらの実践内容は「モラルBOX」というサイトに掲載されています。このサイトを通じて、様々な学校での道徳教育の取り組みが共有されることで、教育の質の向上が図られます。
教材の活用:教育現場では、道徳教育の参考資料や副読本、地域の文化や伝統、ボランティア活動に関する教材などが使用されています。特に「明日を拓ひらく」という資料や、地域に関連する偉人の情報、伝統や文化などを取り上げることで、児童生徒たちが地域に根ざした教育を受けることができます。これらの教材を活用することで、道徳教育は学校の教育活動全体に展開されています。
教員採用試験で、試験官にアピールするには
特別の教科道徳を中心とした道徳教育の推進に取り組んでいることを強調する。
児童生徒の広い視野からの思考や生き方についての考えを深めるためのアプローチや取り組みを具体的に紹介する。
地域や保護者との連携を強化し、道徳教育の授業を公開する活動に意欲的であることを示す。
「モラルBOX」のようなサイトを利用して、学校間での道徳教育実践の共有を提案する。
道徳教育指導参考資料「明日を拓ひらく」や地域ゆかりの偉人、地域の伝統や文化を取り入れた教材を活用する取り組みを紹介する。
学校の教育活動全体における道徳教育の展開に意欲的であることを強調する。
② 差別や偏見を許さない、命を大切にする教育の充実
○ 価値観や考え方、生活習慣の違いから、人を差別したり偏見をもったりすることがないよう学校の教育活動において、人権について考える活動を継続し、一層充実させます。
○ 災害や感染症等への不安から、被災した人や感染症に罹患した人を排除したり、うわさや誤った情報から弱者を差別したりする行為は、重大な人権侵害であることを子供たちに学ばせ、考えさせるための活動を行います。(再掲)
○ 世代や年齢を越えた交流、異校種間での交流、集団での交流活動等、学校と地域が協力して、様々な体験活動を一層推進します。
○ 家庭では愛情豊かに育てる、地域では豊かな人間関係を育む、幼児教育では人やものとの関わりを大切にする、学校教育では一人一人の存在を大切にするなど、あらゆる機会を捉えて、全ての大人が子供たちの模範となって行動するよう努めるとともに、命の大切さを子供たちに伝え、自己肯定感と他の人への思いやりの心を育てる教育活動を行います。
価値観や考え方、生活習慣の違いからの差別や偏見を防止:学校の教育活動において、様々な背景や文化を持つ人々の違いを尊重し、それを基にした差別や偏見を持たないようにすることが強調されています。これは、多様性を受け入れ、共生の精神を根付かせるための教育方針として重要です。
災害や感染症等への不安を基にした差別の防止:災害や感染症の状況下で、被害を受けた人や病気に罹った人を排除したり、誤った情報に基づく差別を行うことは、人権の重大な侵害とされています。子供たちには、こうした状況下でも正しい情報をもとに公平で適切な対応をすることの重要性が教えられることが強調されています。
世代や年齢を越えた交流の推進:学校や地域が協力して、異なる世代や背景を持つ人々との交流活動を進めることで、互いの理解を深め、共生社会の形成を目指します。この交流は、人々の絆を強化し、共感や理解を生むための鍵となります。
全ての大人が子供たちの模範として行動:家庭、地域、幼児教育、学校教育の各場面で、大人たちは子供たちに愛情を示し、命の尊さや人との関わりの重要性を伝えることが強調されています。この教育活動は、子供たちが自分自身を大切にし、他者への思いやりの心を持つための基盤として考えられています。
教員採用試験で、試験官にアピールするには
人権についての教育活動への取り組みや経験を強調し、具体的な実践例を伝える。
災害や感染症への対応や、それに関連する人権教育の実践経験を共有する。
学校と地域の連携を重視する姿勢をアピールし、具体的な交流活動の事例を話す。
幼児教育や学校教育における「命の大切さ」や「自己肯定感の育成」に取り組む意義を伝える。
具体的に、どのようにして子供たちに思いやりの心を育てる教育活動を行ってきたか、または行いたいかを話す。
③ 情報モラル教育の充実
○ 「特別の教科道徳」やICTを活用した教育活動に取り組む中で、児童生徒の発達の段階に合わせて、情報発信による他人や社会への影響、ネットワーク上のルールやマナーを守ることの意味、不用意な情報発信により他者の権利を損ねる場合があること、情報には誤ったものや危険なものがあること、健康を害する側面があることなど、自らの行動等を考えさせる学習を実施します。また、情報モラルに関する指導力を向上するため、教員研修の充実を図ります。
○ 関係機関と連携しつつ、出前講座等を通して児童生徒の情報モラルの向上を図ります。
○ 保護者を始め県民に向けて、インターネット・スマートフォン等の適切な使い方や情報モラルについての啓発を継続します。
○ 生徒への情報モラル向上に関する講演会、研修等を実施している私立高等学校を支援します
特別の教科道徳やICTの活用:教育活動の中で、特別の教科としての「道徳」や情報通信技術(ICT)を使用して、情報の発信やネットワーク上のルール、マナーに関する教育を実施します。ここでの目的は、児童や生徒が自分の行動が他者や社会に与える影響を正しく理解し、情報を適切に扱えるようにすることです。
情報の誤情報や危険性:情報モラル教育では、正しい情報と誤情報を区別する能力、そして情報に含まれる危険な要素を識別する能力を育てることが強調されています。健康や安全を害する可能性のある情報に対して、適切に対応できるようにすることが求められます。
教員の情報モラル教育研修:教員自身が情報モラルに関する知識や技術を習得することで、児童や生徒への指導が更に向上します。そのため、教員向けの研修の機会を増やすことが重要とされています。
関係機関との連携:学校だけでなく、関連する機関や団体と連携して、情報モラル教育の普及や啓発を進めることが計画されています。出前講座などを通じて、より多くの児童や生徒に情報モラルについての教育を提供することを目指します。
県民や保護者への啓発活動:児童や生徒だけでなく、保護者や一般の県民に対しても、インターネットやスマートフォンの適切な使用方法や情報モラルに関する知識を伝える活動が行われます。これにより、家庭や地域全体での情報モラル教育の意識が高まることが期待されます。
私立高等学校の支援:私立の高等学校で情報モラル教育に関する講演会や研修が行われている場合、これを支援する方針が示されています。これにより、公立学校だけでなく私立学校でも情報モラル教育の水準が向上することが期待されます。
教員採用試験で、試験官にアピールするには
情報モラル教育の取り組みに精通していることを強調し、具体的に「特別の教科道徳」やICTを利用した教育手法についての経験や知識を共有する。
教育現場での情報発信の重要性やネットワーク上のマナー、情報の正確性など、児童生徒に情報モラルを教える際のポイントを語る。
自らが参加した教員研修や学んだ情報モラルに関する教育方法を紹介する。
学校や地域での情報モラルの啓発活動や出前講座の実施経験を話すことで、積極的な教育活動への参加をアピールする。
保護者や地域の人々と協力して、インターネットやスマートフォンの適切な使用方法や情報モラルに関する指導を行った経験や取り組みを紹介する。
私立高等学校での情報モラル向上の講演や研修の実施に関与した経験がある場合、その内容や成果をアピールする。
現代の情報社会において、情報モラル教育の重要性を理解し、その教育に熱心に取り組んでいることをアピールすることで、教員としての適性や熱意を伝える。
おわりに
現代社会では、様々な価値観が存在し、子供たちが自らの問題として向き合うための「考え、議論する道徳」の教育がますます重要になってきました。特に、多様な背景や立場を持つ人々が共生する中で、差別や偏見を持たず、命を尊重する心を持つことは不可欠です。また、急速に進行している情報社会の中で、情報を正しく、安全に利用する情報モラルも大切になってきました。
子供たちが自分を肯定的に見ることができるように、生きる喜びや他人との関係性を深める教育の取組は、今後もさらに進化し続けることでしょう。これに加え、新型コロナウイルス感染症のような世界的な危機に直面する中で、理性的に判断する能力や、他者を尊重する心を育てることが、私たちの社会をよりよくするための鍵となります。
高度情報社会の中で子供たちが安全に情報を扱うことができるよう、情報モラルの教育も進められています。その背景には、スマートフォンやSNSの普及による犯罪の増加や、虚偽の情報の拡散などの問題があり、子供たちが情報社会で正しく行動できるよう支援することが求められています。
これらの教育の取組を進める中で、私たち大人も子供たちの模範となり、命の大切さや他者への思いやりの心を伝える役割を果たしていくことが必要です。
最後に、この記事が、教員採用試験を受験される方々の参考となり、より良い教育の実現に繋がる一助となることを心から願っています。皆さんのこれからの道は明るく、充実したものとなることでしょう。
記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます。
もし、この記事に対して
「なるほど!」
「面白かった!」
「他の記事も読みたい!」
と思ったら、
「❤スキ」を押していただけると嬉しいです。
そして、これからも役立つ情報や考えを共有していく予定なので、フォローもお願いします。
また、あなたが感じた「記事の価値」や「応援の気持ち」に応じて、サポートをしていただけると本当に嬉しいです。あなたの貴重なサポートは、より洗練された記事の作成や、深いリサーチのために活用させていただきます。
よろしくお願いいたします。
あなたが感じた「記事の価値」や「応援の気持ち」に応じて、サポートを選択してください。あなたの貴重なサポートは、より洗練された記事の作成や、深いリサーチのために使用されます。あなたが感じる最適な金額をお選びください。
