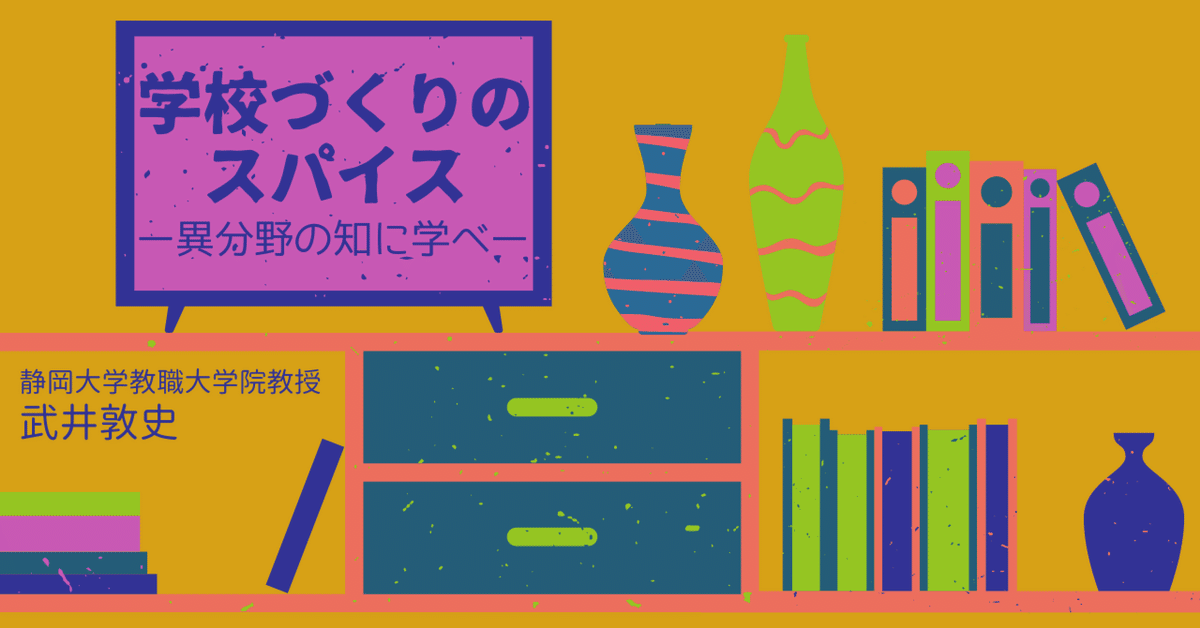
#46 不条理とともに生きる力~佐々涼子『エンド・オブ・ライフ』より~|学校づくりのスパイス
今回と次回は「死」と教育の関係について考えてみます。これから生きていこうという子どもの教育を考えるのに、どうしてあえて「死」の問題を取り上げるのか、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。けれども、もし死が存在せず私たちが永遠に生き続けられるとしたら……と想像してみてください。人の生は緊迫感を失って味気ないものになってしまうのではないでしょうか? ならば、教育が死と無関係であるはずはありません。
まず、今回はノンフィクション作家の佐々涼子氏の『エンド・オブ・ライフ』(集英社インターナショナル、2020年)を手がかりに死と向き合うことの意味について考えます。
「普通の死」というドラマ
この本で描かれているのは、一人の訪問看護師の死です。特別な人の華々しい最期を描いたものではなく、普通の人が死と向き合いながらも生への希望をつなぎ、もがきながらも最後は自分の運命を受け入れていく姿です。
ドラマの主人公は訪問看護師の森山文則氏(2018年当時48歳)ですが、この本のなかでは氏が在宅看護師として、患者の最期に献身的に寄り添ってきたエピソードが記されています。娘と潮干狩りに行きたいという末期がんの患者の願いに寄り添い、看護師として潮干狩りに同行することで、患者の最期の願いを叶える手伝いをします。
今度はその森山氏が膵臓がんに冒されます。氏は訪問看護師として200人以上の患者を看取ってきたと記されていますが、それでも自分の死を受け入れることが容易だったわけではなかったようです。がんの告知を受けた当初は次のように奇跡を信じます。
「がんは自分の一部でしょう? 身体の一部が僕にわざわざ悪さをしたいとは思えない。身体は何か言い分があってがんを作ったと思うんです。がんは身体からのメッセージです。がんの言い分をきちんと聞いてあげて、自分が変わりさえすれば、がんは癒えるはずです。だから僕はがんに対してありがとう、ありがとうと言い続けているんです」(179頁)。
しかし、心の持ち方によってがんが治癒するわけではありません。その困難に直面し、病気に勝てないことが明らかになっていくと氏の語り口も次第に変化していきます。
「死というものが、誰よりも早く、自分の身に降りかかって来た時には、それは恐怖じゃなくなる。何なんだろうな、自分はまだ大丈夫なのかな、とか、自分はがんにならへんのかな、とか、自分は何で死ぬんだろうかとか、そういう正体不明の不安が全部クリアになるじゃない。そうすると、漠然と恐れていたものが具体的に見えてくるんだよね。自分の持っている恐怖の正体がはっきり見えた時、人はどこかでほっとするんやろうね」(269頁)。
こうして次第に自分の死を受け入れるようになりつつも、一方で身体の痛みから「情けない。もっと恰好よく逝きたかったのに」(277頁)と男泣きしながらも鎮静剤をかけてもらうことを自ら希望します。そして「おとうちゃんは早く逝ってしまうけど、時間の長さなんて全然関係ない。短くても充実した時間やった。大きくなる姿をきっとどこかで見守っているからね」(279頁)という言葉を二人の子どもに残して逝きます。

不条理と生きるということ
学校教員にはハッピーエンド好きな人たちが多いな、と感じることが筆者にはあります。学校の先生方の書いた実践論文や通信等をみると、たいていの場合、児童・生徒たちがみんなで努力して成果を上げ成長を果たした、というように、その活動プロセスはハッピーエンドなストーリーに仕立てられています。
でも考えてみるとこれは当然のことなのかもしれません。というのも、私たちの社会では、「公正さ」というものを求めるからです。
がんばった人が報われ、怠けた人は報われず、罪を犯した人は罰を受け、他者につくした人は称えられる……公正さの基準自体は人や社会によっても異なりますが、総じて言うならば民主主義社会のなかでは、人の意思や努力と、その結果との帳尻の合う状態を理想として、社会のあり方をそれに近づけるように設計努力が続けられていると言ってよいでしょう。
そしてその「公正な社会」の担い手を育てるのが公教育の役割であるとすれば、学校の教員がハッピーエンド好きになるのは、ある意味で自然ななりゆきであるといえます。
けれどもハッピーエンド仕立てのドラマばかりがよいドラマというわけでもないはずです。私たちの一生の旅路のなかでは、どう考えても道理に反する世界の現実や不条理な結末に出合わずにはいられません。
この本のなかで森山氏は迫りくる自分の死を自覚していくなかで、死がタブー視される現代社会における子どもの成長環境について次のような言葉をもらしています。「死が遠ざけられて、子どもたちが死を学ぶ機会を逃している。亡くなる人が教えてくれる豊かなものがいっぱいあるのに、すごく残念なことだと思うんです」(288頁)。
どんなに優れた人でも、また温かい心をもって人に尽くして生きてきたとしても、報われることなく生涯を閉じることもある……そうした世界の現実に否が応でも思い至らせてくれるのが、「死」というものの存在ではないでしょうか。
きっと戦争を体験した世代の方々はこのことを肌感覚として知っているのでしょうが、合理的に仕立てられた現代に生きる私たちは、ともすると世界の内外には不条理が潜んでいることを忘れてしまいがちです。
けれども、そういうことがあるんだ、と知るだけでも、世界の不条理や自分の理解の及ばないことに対する耐性は高くなり、私たちが生きる営みは、その深みを増していくのではないでしょうか?
森山氏の述べる「豊かなもの」を私たちはどのように受け止めたらよいのでしょうか。次回はこの点について筆者なりに答えを模索してみたいと思います。
【Tips】
▼佐々氏は本書の背景にある「死」というものの意味について赤裸々に語っています。
(本稿は2018年度より雑誌『教職研修』誌上で連載された、同名の連載記事を一部加筆修正したものです。)
【著者経歴】
武井敦史(たけい・あつし) 静岡大学教職大学院教授。仕事では主に現職教員のリーダーシップ開発に取り組む。博士(教育学)。専門は教育経営学。日本学術研究会特別研究員、兵庫教育大学准教授、米国サンディエゴ大学、リッチモンド大学客員研究員等を経て現職。著書に『「ならず者」が学校を変える――場を活かした学校づくりのすすめ』(教育開発研究所、2017年)、『地場教育――此処から未来へ』(静岡新聞社、2021年)ほか多数。月刊『教職研修』では2013年度より連載を継続中。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
