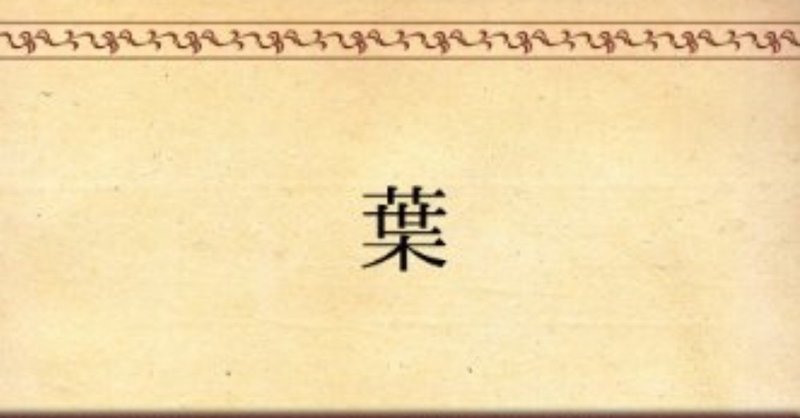
「死にたい」とかいう奴は五年後のことを考えてから死ね(ウサギノヴィッチ)
どうも、ウサギノヴィッチです。
今日は太宰治の『葉』についての自分の感想みたいなものをあげたいと思います。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「死のうと思っていた。ことしの正月、よそから着物を一反もらった。お年玉としてである。鼠色のこまかい縞目が織りこまれていた。これは夏着るであろう。夏まで生きてみようと思った。」
これが出だしの一文である。「死のうと思った」がいかにも太宰治らしい言葉のチョイスだし、読者を引きつける。
ただし、この着物の件や夏まで生きてみようと思ったということはまったく関係ない。
唐突な「ノラ」という登場人物の登場しかも一ページしか出てこない。ここから一人称と三人称が混在したドストエフスキーの『悪霊』のように進んでいく。
落ち着いたところで、主人公とは対照的な兄が出でくる。「いい気なものではない」と嫌がっていた。
そう言われても主人公は、自分は自殺を処世術にしていると思っている。
これから話は姉の祝言の話や育ててくれた
婆様の話とプライベートな話に飛んで行く。
また、話は主人公の参加していた運動にも話は展開される。
最終的には、日本橋で花を売る少女の話に落ち着く。
ざっと、あらすじみたいなものを説明をしてしまったが、以上のように話が進むにつれて「死」というものには遠ざかっていく。むしろ、最後には花を売る少女が屋台の雲呑屋さんからチャーシューをおまけしてもらうというほっこりしたところまである。
しっちゃかめっちゃかである。一人称と三人称が入り乱れている時点で、太宰は病んで書いてるのかもしれないが、どこかに正気な部分がある。後期も後期の『人間失格』には、そんなカタルシスはない。ただ、未完の『グッド・バイ』には、人間喜劇のようなところがある。僕もそうなのだが人間なんて二つに割り切れることなんてなくて、だれもが陰と陽を持っている。それが最後に表れたのかもしれない。それで死んでしまっては意味がないのではないかも知らないけど。
だが、これ太宰っぽい出だしだからいいっ! って思って読み始めたらどんどん話はスライドしていく。初期の方だからすべてが整っていなくて当然なのかもしれないが。でも、その裏切っていくのも太宰らしいかもしれない。太宰イコール死を直接結びつけることのない作品なのかもしれない。
ぼくがこの作品を読んで言いたいことは、「結局お前死にたくないだろ?」という事だ。お年玉に貰った夏用の着物貰ったくらいで夏まで生きてみようかと思ったとか、兄貴が自殺を嫌うからって言うのを知っているから、なんとなく自殺するのは胸の奥に控えておこうとか。
作中にブルジョワジーに寄生することは、プロレタリアートに貢献することは違うとという話が出てくる。つまり、主人公は生温い生活を送っていて、考えているのも実行に移さずにただ悶々と考えているだけの人間だと言うことだ。
そんな人間が自殺をできるだろうか?
自殺なんかしたところで世界を変えられるたろうか?
だからこそ、この作品は拙いのかもしれない。もちろん、これに似たような作品はあるが、これは頭の中で書いた小説なのであって、現実とは乖離しているのではないだろうか。いや、乖離してるのは、僕の頭の太宰像なのかもしれない。これが太宰治という人間の弱さのリアルであって、これが積み重なっていくことが『人間失格』へと繋がっていくのかもしれない。
このとき太宰は死ねなかった。それはまだ頭の中で浮遊した自殺の明確な動機がなかったからかもしれない。いや、太宰治に自殺の動機なんてものはいらないのかもしれなかいが、太宰が玉川上水で自殺するとき彼はなにか爆発的なエネルギーを持っていたに違いない。
ただ、この作品にとっては、「死にたい」だのなんだのと言うのはあまっちょろい戯言である。ただ思った言葉を書いた、もしかしたら私小説に近いなにかかもしれない。
僕はこの小説を読んで、これを書く前なら「死にたい」とかいうヤツは読むなとか思ったが、ここには太宰の原初があることを発見したような気がする。
やっぱり、太宰治という作家は生と死の危ういバランスの中で小説を書いていた人間なのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
