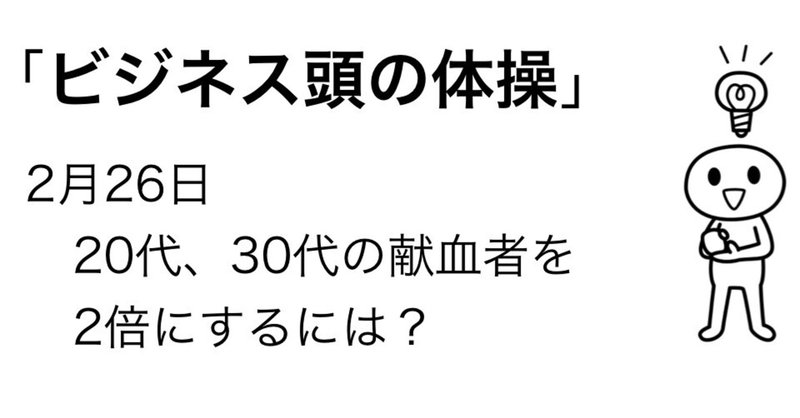
2月26日 20代、30代の献血者を2倍にするには?
今日は何の日?をビジネス視点で掘り下げ「頭の体操ネタ」にしています。 今日の「頭の体操」用質問例はこちら。
→献血者、特に20代30代の献血者を増やすには、どんなマーケティングアイディアがあるだろうか?
1951年(昭和26年)のこの日、日本初の血液銀行・株式会社日本ブラッドバンク(後のミドリ十字、吉富製薬と合併する等して現在は田辺三菱製薬)が開業した「血液銀行開業記念日」です。
「血液銀行」と聞いて、「献血の歴史」程度に気軽に調べ始めたら、知らなかった事実が出てきました。
当初、日本ブラッドバンクは血液を「買い取って」いたのです。
買取価格は400ccで1,200円程度。当時の高校卒業の国家公務員(一般職)の初任給が約14,000円(現在は15万円程度)でしたから、結構な金額です。
これを目当てに売血を繰り返すと、体内で作るのに時間がかかる赤血球が少なくなり、血の色が黄色くなるそうです。これを「黄色い血」といい、ある事件をきっかけに世間一般でも問題視されるようになりました。
それは、1964(昭和39)年に起こった「ライシャワー事件」です。
ライシャワー駐日大使が暴漢に刺されてその治療で輸血を受け、「これで私の体の中に日本人の血が流れることになりました」と発言、多くの日本人が賞賛を送りましたが、その後、この輸血が元で輸血後肝炎に罹ってしまいます。
これがきっかけとなって売血による「黄色い血」に対する批判が強まり、同年8月、閣議決定により厚生省は「保存血」は「日本赤十字社」と「地方自治体」のみが行うこととしました。
その後の努力により、1974(昭和49)年に輸血用血液製剤の全てを献血で確保する体制が確立されたのです。
この結果、輸血による肝炎発症率は以下の通り劇的な低下をしています(出典:厚生労働省「令和元年度版血液事業報告」)。

献血者数・献血量の推移を見てみましょう。
平成30年度の献血者数は約474万人、献血量は約200万ℓでした。平成16年度から30年度までの推移がこちら(出典:同)。

献血者が微減とも言える状況で、献血量が維持できているのは、一人あたりの献血量が増加(200ml献血から400ml献血や成分献血など献血の種類が増えたことによります)したためです。
次に、年代別献血者数の推移を見てみましょう。

10代から30代の献血者数は、この10年で約4割も減少しています。もちろん、この年代の人数自体が減少していることが理由の一つではありますが、献血可能人口と献血率(下図)を見ても、20代、30代が40代、50代に比べると低いことが分かります。

さて、献血事業は日本赤十字社が事実上独占していますが、この事業規模はどれくらいなのでしょうか?
日本赤十字社によると、令和元年度で、収入が1,654億円、支出が1,534億円、差し引き120億円のプラスとなっています(出典:日本赤十字社HP)。

収入の9割は輸血用血液製剤を医療機関に届けたことによるものです。
支出の5割は献血の推進・献血を受け入れる際の器具や献血ルーム等の費用です。その他検査、製造、研究、物流などの費用となっています。
→さまざまな経緯があって確立された現在の献血という仕組み。若年層の献血率が低下する中、感染症も加わり安定確保が難しい状況と言える。一方で災害発生時のボランティアの増加などを見ても貢献したいと考える若年層は多いとも言えそうだが、献血を増やすにはどのようなアイディアがあるだろうか?
最後までお読みいただきありがとうございます。
過去の投稿は以下にまとめていますので頭の体操ネタに覗いていただければ幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
