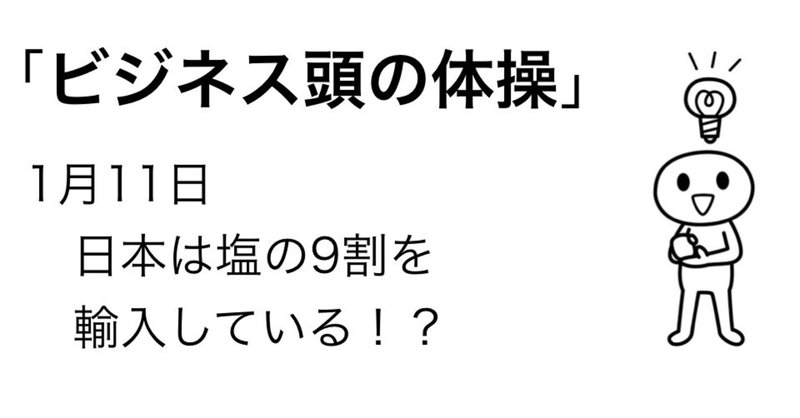
1月11日 日本で消費される塩のうち食用は1割!?
今日は何の日?をビジネス視点で掘り下げ「頭の体操ネタ」にしています。 今日の「頭の体操」用質問例はこちら。
→塩。日本の周りの海から大量に取れるはずだが、なぜ輸入するのだろうか?
1569(永禄11)年、武田信玄と交戦中の上杉謙信が、武田方の領民が今川氏によって塩を絶たれていることを知り、この日、越後の塩を送ったとされている。この話が、「敵に塩を送る」という言葉のもととなったことにちなみ、「塩の日」とされています。
さて、塩。実は、食用に用いられるのは1割に過ぎないことをご存知でしたでしょうか?私は知らずに今回調べて驚きました。
公益財団法人塩事業センターによると、令和2年度(2020年度)の塩の需要量(消費量)は781万トン。
うちいわゆる塩(瓶や袋に入って売られているもの)は13万トン。
漬物や醤油、加工食品などに使われる食品工業用が66万トン。
合計で79万トンですから、全体の10.1%に過ぎません。
では、残りは何に使われているのか?
実は、かせいソーダ、ソーダ灰等の製造に使われるものが604万トンで76.9%を占めているのです。
では、かせいソーダ、ソーダ灰というのは、一体何に使われているのか?
かせいソーダは化学繊維、紙、パルプ、石鹸などに、 ソーダ灰はガラス、瓶、グラスウール、水処理助剤などに、 それぞれ幅広く使われています(以下出典:塩事業センター)。

その他には、融氷雪用に71万トン(9.0%)、家畜用、医療用(生理食塩水等ですね)にも使われています。
そして、塩の自給率ですが、令和元年度(2019年度)で11.2%しかありません。残りは輸入されています。
どこから輸入されているか、というと以下の通りです。

メキシコ?と思ったので調べると、ゲレロネグロ塩田という、東京23区とほぼ同じ5万haの塩田で作られてたものだそうです。
オーストラリア?と思ったので調べると、シャークベイで作られた天日塩だそうです。世界自然遺産に指定された美しい海洋で、ジュゴンやイルカが多数生息しているそうです。写真がこちら。なんかすごいです…

最後に、家庭での塩の消費量の推移をご紹介します。
ご想像の通り健康志向の高まりとともに、塩の消費量は減少傾向にあります。

→塩。日本の周りの海から大量に取れるはずだが、なぜ輸入するのだろうか?
最後までお読みいただきありがとうございます。
過去の投稿は以下にまとめていますので頭の体操ネタに覗いていただければ幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
