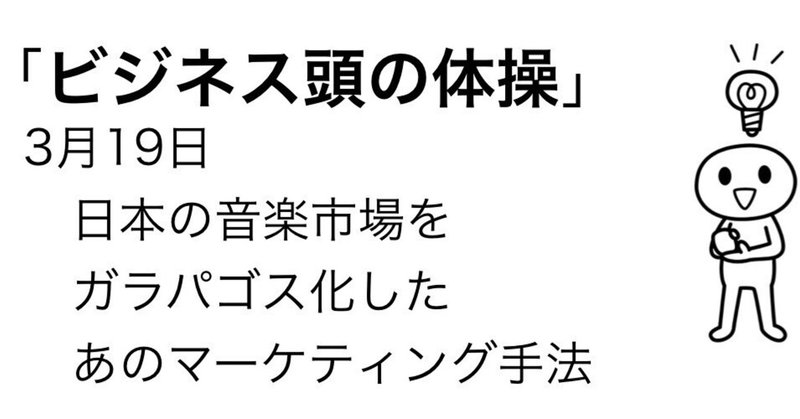
3月19日 日本の音楽市場をガラパゴス化した、あのマーケティング手法
はたらくおとな向け。普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。
普段の仕事を超えて、視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。
考えるための質問例はこちら。
→グローバルではサブスクリプション型での音楽提供が圧倒的シェアを持つのに比較すると、日本ではまだCD販売のシェアが高い。その理由はなんだろうか?
音楽関係者の労働団体・日本音楽家ユニオンが1991(平成3)年に制定した「ミュージックの日」です。
「ミュー(3)ジック(19)」の語呂合せから。
ミュージック。音楽。
そういえば、最近CDとか売れているんでしょうか?そもそもCDなの?ということで音楽の市場について調べてみました。
まず、世界から。
国際レコード産業連盟(IFPI)のGlobal Music Report(以下)によると、

2020年は前年から7.4%成長し、215億ドル(約2兆5,370億円)となりました。
特に、音楽ストリーミングの売上は2割増の134億ドル(約1兆5,812億円)となっています。

中でもSpotifyやApple Music、Amazon Music などのサブスクリプションの利用者の増加が顕著です。サブスクリプション型音楽ストリーミングの有料会員数は全世界で4億4,300万人にもなっています。

一方で、CDなどの物理的な媒体売上は減少を続け、42億ドル(約4,956億円)となっています。
つまり、世界的には、音楽配信、中でもサブスクリプション型が主で、CDなどの売上はその2割程度に留まるのが現状です。
世界の大きな流れは、CD時代から見ると、
CD→iTunseなどのダウンロード型サービス→サブスクリプション型サービス
と変遷しており、購入単位が「アルバム単位」→「1曲単位」→「無制限(音楽を聴くことそのもの)」へと変わっていることが分かります。
次に日本を見てみましょう。
一般社団法人日本レコード協会の「日本のレコード産業2021」によると、2020年の音楽関連売上は前年比9%減の2,727億円となっています。

別の出典になりますが、みずほ銀行の業界レポートに1952年から2013年の長期間のデータもご紹介します。ピーク時は6,000億円市場だったことが分かります。

全世界が伸びている中で、日本が減少している要因はその商品構成にあります。
世界と比べると、いわゆるCDやブルーレイなどの「音楽ソフト」の割合が圧倒的に多いのです。もちろん、サブスクリプションも伸びているのですが、全体に占める割合はまだ少なくなっていることがわかります。
なぜ日本だけ物理的な媒体での音楽ソフトのシェアが高いのでしょうか?
これは、いわゆる、「特典付音楽ソフト」の存在によるものです。握手券とか、同じCDでも特典が異なるものが複数(例えばポスターが付いているもの、特典映像が入ったDVDが付いているもの、グッズが付いているもの、など)あるもの、などで、1種類の音楽ソフトでもファンが複数購入したくなるようなマーケティングをしていることによるものです。
この評価は、マーケティングの努力と評価するか、「おまけ」で売ることが常態化し、音楽そのものの価値を低下させたと評価するか、分かれるところです。
いずれにしても、世界的にみてアメリカに次ぐ2位の大きなマーケットですが、かなり特殊なマーケットなのです。
そうした音楽ソフトの原価構成という資料がありましたのでご紹介ます。これは通常のものですから、先程の特典付であれば、価格が高くなりますので、おそらく収益はさらに高くなると思われます(出典:みずほ銀行「音楽産業」)。

最後に、今後日本でも主流となるであろうストリーミング型サービスの歴史(?)が非常にコンパクトにまとまったものが日本レコード協会の機関紙「THE ROCODE」にありましたのでご紹介します。

→サブスクリプションの普及は、コンテンツを供給するアーティスト(と版権を持つレコード会社)の合意が必要だ。どれだけ聞いても毎月一定額しか支払われないサブスクリプションになぜアーティストは同意したのだろうか?どのようなメリットがあるのだろうか?
最後までお読みいただきありがとうございました。
1年間以上続けていますので、ご興味とお時間があれば過去分もご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
