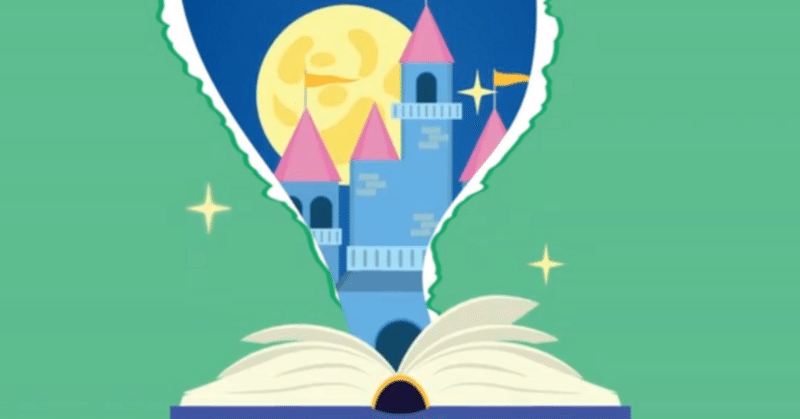
【まずは一つのアイデアを場面にしよう】いろんな角度から着想のヒントを考えるための方法論(2018年3月号特集)
ストーリーが思いつかないとき、どうアイデアを見つけ、それをどのようにストーリーにするかについて考えよう。
アイデアを場面にし、前後を考える
ストーリーにはアイデアが必要
ストーリーを作るには、その前にアイデアが必要になる。このアイデアは真理の発見に近い。
たとえば、めちゃくちゃおいしかったラーメンを3年後に食べたらそうでもなかった。「食べられないでいると、記憶の中でおいしさが増幅する」。
あるいは、社長がごちそうを食わしてやると言ったが、それはカレーライスだった。「ごちそうといっても人それぞれ」。
カッコ内の言葉がアイデアだ。
アイデアだけではお話にならない
思いついたアイデアが万人に共通する思いであればあるほど共感を得やすいが、アイデアのままでは格言にはなっても童話にはならないから、アイデアを場面にする。
では、そのあとは?人気作家の石崎洋司先生に聞いた。
「ストーリー作りの最初の段階では、必ずしも起承転結を考える必要はありません。自分が一番面白いと思うシーン、書きたいシーンを思っままに書いてみる。ひととおり書いたら、今度は冷静になって、キャラクターや舞台について考える。主人公はどんな人(動物)で、ふだんはどんな暮らしをしているのか。主人公はなぜそのシーンにいることになったのか。そのシーンの場所はどんなところなのか。こうしたことを一つ一つたどっていく。つまり、そこに至る経過を自問自答し、書きたかったシーンに至る過程をたどりながら決めていくと、物語の書き出しが見えてくる。同様にこのあとどうなっていくかを考えていく。このときにはもうキャラクターや舞台の設定がある程度できているので、そのあとの展開は比較的楽なはずです」
ここまで中身を詰められていれば、あとは起承転結や序破急などの構成に落とし込むだけ。
具体的に言うと、どこからどう書き出すか、書き出しでどう読者を引き込むか、どう話を自然に運ぶか、どこを山場とするか、最終的な落としどころをどうするか、さらには主人公の目的は何で、伝えたいメッセージは何かを考える。
ストーリーチェックのポイント
テーマが浮かぶか
読後にテーマが立ち上ってくるかを考える。話の筋道が通っていない、話が蛇行しすぎる、複雑すぎる。そんなストーリーだと結末を読んでもピンとこない。あらすじを読んでも、伝えたいことがわかるようになっていること。
削る場面はないか
書くとなると、ついなんでも詰め込んでしまいたくなるが、300枚では大河ドラマは書けず、まして短編では人生のある一瞬しか書けない。その作品のテーマに関係しないもの、結末につながらない場面などは削る。
子供向けか
いいストーリーでも子ども向けでなければならないし、子どもが楽しめる内容でもなければならない。また、文学というのであれば娯楽として楽しませるだけではなく、背後にテーマがほしい(あまり前面に出しすぎないこと)。
ストーリー着想のヒント
格言から考える
実体験からアイデアを発見する逆。すでにある格言、たとえば「覆水盆に返らず」だったらそれをもとに場面を考え、格言がタイトルになるようなストーリーを作る。
絵画を挿絵だと思う
有名な絵画でも子どもが書いた絵でもいいが、それが挿絵だったら文章のほうはどんな物語だろうかと考える。いい絵は背後にストーリーがある。それを想像する。
歌詞をストーリーに
歌詞にはストーリーがあるので、それを借りる……
ストーリー着想のヒントはまだまだある!
特集『童話賞入選への道』
公開全文はこちらから!
※本記事は「公募ガイド2018年3月号」の記事を再掲載したものです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
