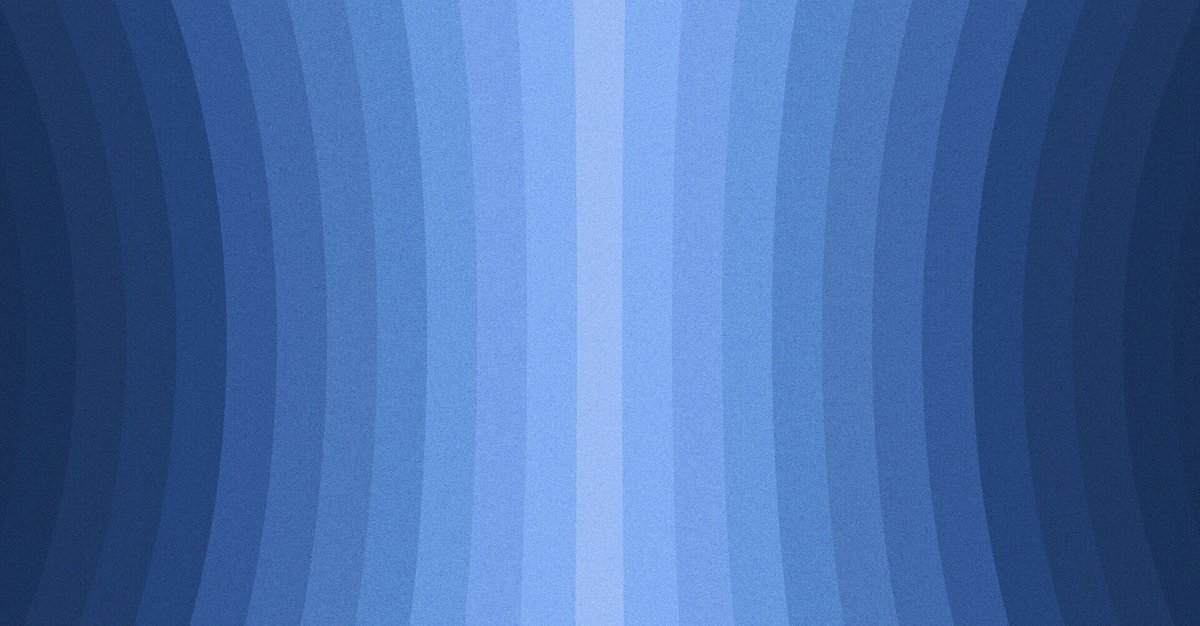
短編小説:絶対S装置(前編)
※ これは、いつものVCや弁護士・薬剤師に関する記事ではなく短編小説になります
短編小説(ショートショート):絶対S装置
2×××年。N国はT大学のS研究室において、革命的なAIが発明された。その名は、絶対S装置。
PCプログラム冒頭にそのネーミングが表示されることに加え、当該AIがインストールされているラップトップハードウェアには、「絶対S装置」と刻印がされていた。金属板プレートを使って。丁寧かつ目立つように。
発明したのは、S氏。ノーベル賞間違いなしの天才と称されていた彼だったが、装置を発明した後、行方不明となった。何でも変わり者として有名だったらしい。
S氏の行方不明に伴い、この残された装置の扱いに困った研究室のメンバーのN氏は、警察に相談をし、かけつけたK氏と会話を始めた。
「はて、この装置は一体何なのでしょうか?」
「絶対S装置と呼ばれております。いわゆるAI装置です」
「ほう、AIというと、データをインプットすると何でも自動的に計算してくれるというアレですか。ディープラーニングだとか、何だとかが関係している。チェスや将棋で人間を打ち負かしたことがあるとかないとか。昔にニュースで聞いたことがあります」
「そうです。大体はそんなところです。この絶対S装置のすごいところは、特定のモデルを使わずに、マルコフニコフ則と呼ばれる、確率論を取り入れ、計算をしてくれるところにあります」
「文系人間の私には、さっぱりよくわかりません」
「わかりました。百聞は一見にしかずでございます。まずは、私のお気に入りの成果物をお見せしましょう」
N氏は、その言葉を自慢気に発すると、さっそく装置をカタカタと操り、デモンストレーションを始めた。
突然流れ出したのは、どこかで聞いたことのあるような音楽だった。だが、どの曲なのか特定はできない。ラジオで流れていたとしても違和感は全くない。しかしながら、誰もその曲名を当てられない、超難問イントロクイズのようだった。
「はて、この音楽は何でしょうか?どこか懐かしい感じがしている一方、まるで新しいニュアンスも含まれているような気がするのですが」
「はい、これは、ブートルズの没後××年後に作られた、新作4枚目のアルバム、Heaven’s Breathに収録されている、Freedom Gameという曲になります」
「新作?」
「はい、新作となります」
「ブートルズとは、、、あの世界的に有名なロックバンドのことですよね?メンバー全員が亡くなられてからだいぶ時間が経つと思うのですが」
「はい、仰る通りです。オリジナルメンバーは全員亡くなられております。これまた、寿命は人間の宿命であります。いやはや、悲しい悲しい」
「となりますと、この装置は、イタコのようなもので、死者をこの世に呼び戻せる機械ということでしょうか」
「ははは、それは違います。この装置は、アーティストの死後の新作も作ることが可能なのです。ブートルズの新作であってもデレクジャクソンの新作であってもです。さらには、現役のアーティストの新作も作成することが可能です。一定の属性グループの曲は、どれを組み合わせても似たような新曲になるなど、作りがいのないアーティストも、もちろんいらっしゃいますがね」
「一体どうやったらそんなことが?」
「先ほどお伝えした通り、確率論的アプローチです。人の過去の挙動や作品から、そのらしさを抽出し、予想し、作成してくれるAIがこの絶対S装置なのです。過去の傾向から具体的な未来を予測してくれる装置だと評価しても良いでしょう」
N氏の説明によれば、アーティストの過去の作品を絶対S装置に読み込ませることにより、将来、そのアーティストが作りそうな新曲を、演奏とともに作詞までしてくれるという。さらに、作り出した新曲を組み合わせることでほぼ無限大に新曲が作れることが可能で、別のアーティスト同士を掛け合わせることもできるとのことであった。
「素晴らしいじゃないですか」
興奮するK氏を前に、N氏はバツが悪そうにちょうど頬をかいた。とても儀式的に。そうして演説するように言った。
「倫理的な問題は残るでしょう。果たして、死者の作品から新しいものを創作し続けて良いのでしょうか?」
「ほほう、そんなものですか」
「はい、そんなものです」
「でしたら、止めたらいいではないですか?」
「いえ、そういうわけにはいかないのです」
「はい?」
K氏は、困った顔でN氏を見つめた。まるで、自作自演のオペラを見せられているようだった。仕方がないのでK氏もその自作自演に付き合うことにした。
「となりますと、倫理的な問題があったとしても、やはりこの絶対S装置をお使いになるということでしょうか?」
「はい、科学者のはしくれとしては、表面上は倫理を気にしますが。原爆や薬害を見ていただければわかるように、実は、科学者はほとんど倫理に配慮しません。常に好奇心が抑えられない生き物なのです。一度発明してしまったものは、必ず使いたくなるのが科学者の性(さが)というやつです。もちろん、副作用には配慮いたしますがね。科学というものは、大変に恐ろしく。素晴らしい発明をしたとしても、使い方を間違えるのが人類の歴史なのであります」
「ほほう、そんなものですか」
「問題は、音楽著作権に代表される知的財産権です。音楽関係は、関係会社が真夏のクマゼミの鳴き声よりはるかにうるさくって。これで商売しようものなら、我々研究室は途端に世界中から訴訟を起こされてしまいます。科学者は、裁判に弱いのです。結局は、世の中は金と権力なのであります。よろしければ、この装置を持っていってくださって結構です。私はもう十分に多くのアーティストの新作を楽しみましたから。ちなみに、私のお薦めは、モーペンターズの新作22枚目のアルバム、Greatest Worldです。懐かしさと新しさとで溢れております。ファイルに保存しておきましたので、どうぞ個人的に鑑賞なさってください」
「ほほう、そんなものですか」
「はい、科学者は、裁判に代表されるまどろっこしいものが大嫌いなのであります」
「ところで、この絶対S装置のSとは何を指すのでしょうか?」
「開発者であるS氏の名前から取ったという説もありますが、我々の間では、正解から取った、つまりは絶対正解装置という意味だろうと考えております」
「なるほど、そのように説明すれば良さそうですね。了解いたしました」
:::::
納得したK氏は、さっそく警察本部にこれを持ち帰り、組織内部でこれを会議にかけた。
「これは、素晴らしい装置だ。商業用に使うのが無理なら、我々で使おうじゃないか。例えば、裁判所とかで使うのはどうだろう?これで裁判も楽になるし、裁判官のミスも減るんじゃないか?」
恰幅がよく、鳥獣戯画のカエルとそっくりなW長官の言葉を受け、絶対S装置は、裁判所での運用が開始されることとなった。
W長官は、すぐに最高裁判所まで出向き、事情を説明すると、まずは東京裁判所を中心に運用を開始し、徐々に全国展開をしていく方針で決まった。
::::
運用を開始して、3日目。成果は途端に現れた。裁判所を統括する調査官であるD氏は、満足気に言った。
「いやー、絶対S装置は大活躍ですな」
全国の裁判所を裏で統括するD氏は、大層ご機嫌だった。働き方改革をどの職種にも進めようとする流れの中、それでも激務に晒され続けていたのが裁判官だった。
この絶対S装置が登場してからというものの、裁判の原告と被告の提出資料を電子化し、読み込ませ、法令に照らし合わせれば、瞬時に判決を書いてくれるのであり、裁判官のワークライフバランスは、劇的に改善されたのだった。
「まさに、仰る通りです」
裁判所職員であるA氏は、D氏に続けて言った。
「この絶対S装置があれば、裁判官同士の能力差、つまりは、どの裁判所で裁判をするかによって結果が変わりうる、不公正さまで解消される。違うかね?」
「まさに、仰る通りです」
「さらに、人間である裁判官が判断するよりも正確な裁判が期待できる。違うかね?」
「まさに、仰る通りです」
「これで、裁判所は安泰だな。がはは」
「まさに、仰る通りです」
:::::
それは、裁判所での運用開始6日目のことだった。
「大変です、大変です、D調査官」
「むむ、どうしたんだね、A君」
慌てて入ってきた、A氏は、走ってきたのか、大粒の汗をかき、襟足部分に汗が垂れていた。ぜーぜー言いながら、A氏は言葉を振り絞った。
「最近の裁判に関して、抗議のメールや電話が止まりません」
「何故だ?絶対S装置は、正しい判決を書いてきているだろう?人が判断するよりも正確な判断をしてきているはずだが」
「それが、こちらをご覧ください」
目の前に出されたメールや抗議文章の束には、概ね、次のようなことが記載されていた。
『薬の副作用で苦しむ人間や生活に苦しむ人間たちを敗訴させるな、昔の裁判所は、人情味あふれ、被害者救済の心に溢れていたはずだ。被害者に寄り添わない裁判など、全く意味がない』
「ふーむ。絶対S装置が出す結論は、正しかったはずなのだが。。。」
「はい。科学的に正しすぎる結論は、多くの国民は受け入れられないのかもしれません」
「そんなものかね?」
「はい。裁判所は、今まで科学をねじ曲げた判決をたくさん書いてきましたから。DNA鑑定に関する裁判とか、医療事故に関する裁判とか。数えられないほど冤罪事件も起こしてきたじゃありませんか?」
「こら、口を慎みたまえ!」
「はい、すいません」
「それでは、裁判所や科学者の意見だけではなく、広く国民感情を踏まえるというのはどうだろうか。絶対S装置に、国民の嘆願書など、国民の情報も読み込ませてみようじゃないか」
「さすが長官!いいアイディアです。さっそくやってみましょう」
A氏は、絶対S装置に、国民の裁判に対する不満や過去の裁判所の前例情報を入力し、再度分析をかけた。解析結果が出てくるまで、わずか数分だった。
「やりました、やりました」
「どうしたんだね、A君」
「絶対S装置が素晴らしい結果を出してくれました」
「ほう、どんな結果かね?」
「裁判所への信頼を維持するため、これまでの判決を踏襲し、科学的に間違っていたとしても国民感情に配慮した判決を新たに書き出しているようです」
「こら、表現に気を付けたまえ!」
「はい、すいません」
「しかしながら、これで裁判所への信頼は強固なものになるだろう。裁判は、前例踏襲が一番だということだな。がはは」
こうして裁判所では、絶対S装置に、原告と被告の提出資料のみならず、世論とも言えるような社会情勢や被害者感情のような資料も読み込ませる運用が開始された。すると、白黒はっきりさせる判決ではなく、どちらかというと両者痛み分けの判決、もしくは和解勧告(裁判で白黒はっきり決着をつけるのではなく、話合いでお互いに譲歩して解決策を探る手段)が、以前にも増して頻発するようになった。
例えば、医療事故裁判においては、医者側が負けることが増え、患者側に多少の金銭を払うよう判断がされることが多くなった。
特に象徴的だったのは、あるウイルスに対抗するためのワクチンの副作用に関する裁判だった。世界的にも科学的にも、問題ないことが証明されていたワクチンであったにも関わらず、接種により体調が悪くなる人が出てくると、国や製薬会社が一定の責任を負わせるような判断が続いた。かくして、N国ではそのワクチンを広く国民に接種しなくなってしまった。国や製薬会社は、以後、すっかり委縮してしまうこととなった。
一方で、裁判所への苦情は激減し続けた。
(後編へ続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
