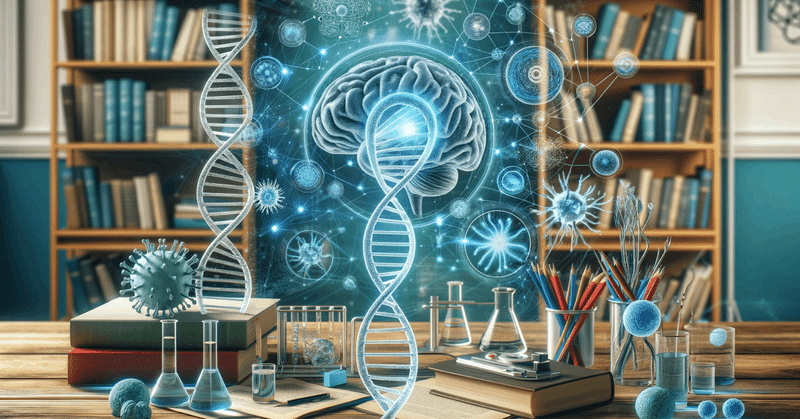
偉大な科学者の晩年の意外な挑戦:クリックの意識研究
前回の続きです。
偉大な貢献をした大科学者の意外な晩年について触れました。
特に、エディントンが晩年に自然に潜む法則を数の一致から見出そうとしたエピソードをお届けしました。
もう一人だけ、晩年に意外な研究に没頭した偉人を触れておきます。
フランシス・クリックです。
こちらも大科学者と呼ぶにふさわしいです。
一番知られているのが、DNAらせん構造を同僚のジェームズ・ワトソンとともに示しました。この功績で1962年にノーベル賞も受賞しています。
実は、もともとは物理学者としてのキャリアを歩みました。
それが生物学に転向するきっかけとなったのは、とある先達の影響です。
ジョン・ランドールという物理学者→生物学者に転向した方で、レーダーの研究に貢献した方です。
ちなみに、ランドール以外にもこの時期にこぞって物理学者が生物学に転向しており、その背景にはシュレディンガーの影響が大きいようです。
特に、彼が執筆した「生命とはなにか」は、今でも名著とされています。何がすごいかというと、従来分類的な手法が常識だった生物に、物理学的(要は還元的)な手法を導入したことです。
さて、無事DNAの構造を解き明かしたクリックですが、転向後わずか6年後の偉業です。余談ですが、その伝説となった論文はわずか2ページでした。
そしてクリックはその後また転向し、これが最後の研究テーマとなります。
「意識の研究」です。
このあたりの背景はまたどこかで調べてみたいと思いますが、おそらくは生命科学はある程度自分のやりかったことが出来たのでしょう。一方で、意識の分野ではまだ物理学的な手法が確立されておらず、同じようなチャレンジを行いたかったのでしょう。
これは孤高ではなく、クリストフ・コッホという神経科学の専門家との共同研究でした。
最後となる著作が1994年に発表され、タイトルは「Astonishing Hypothesis(驚くべき仮説)」です。
ざっくりとその要旨が下記に公開されているので紹介します。
ようは、意識をつかさどる細胞がどこかにある(1つとは限らない)、という仮説です。
ただ、それ以上研究を深めることはできず、現在においても意識のメカニズムは解明されていません。この話題は過去にも触れたので投稿記事を載せておきます。
こちらも万物の理論同様、果たして到達できるのかは誰にもわかりません。
ただ、決して不遇だったわけではなく、少なくとも自身の信念に従って人生を貫き通しただけでも幸せだったのだろうと思います。
むしろ危惧するのは、こういった成果が出るのが難しい野心的なテーマにチャレンジしなくなることだと思います。
これは個々の精神論だけではいかんともしがたいので、無理な挑戦とはいえ最低限の生活が出来る制度を温めてほしいと思う今日この頃です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
