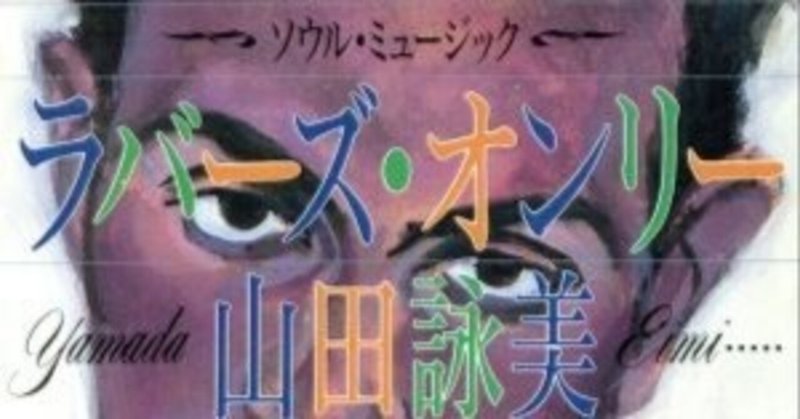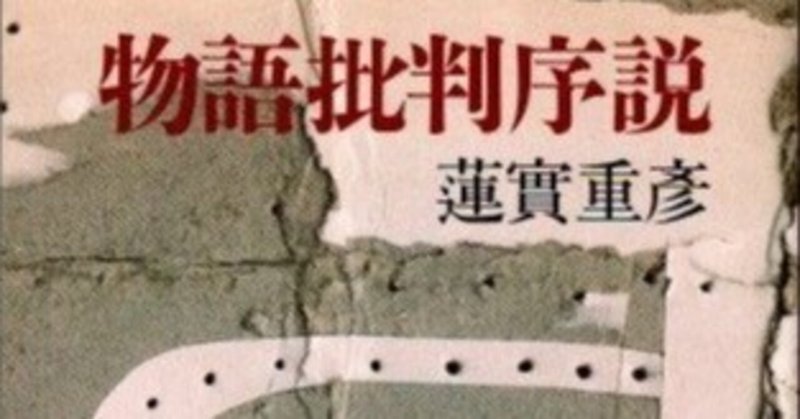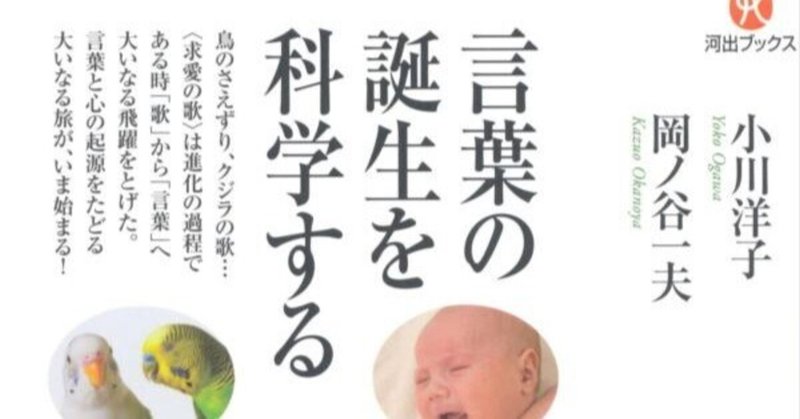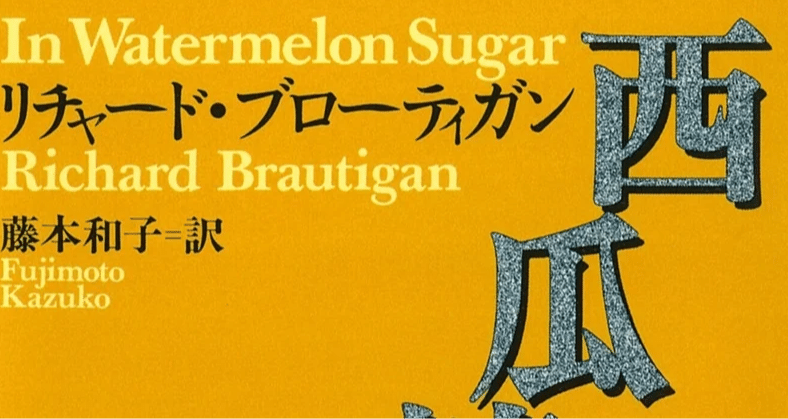
- 運営しているクリエイター
#小川洋子
小川洋子「言葉が存在しない場所で生まれるのが小説」。そこは言葉以前にあったはずの自分の居場所。
(講演「小説の生まれる場所」の続き)
「言葉」はウソをつくために進化した
小川洋子さんは小説づくりの取り組みの中で、「言葉」というものの限界に深い思いを寄せていました。
真理に近づこうと言葉で格闘するとき、ますます真理から遠ざかってしまう。
なぜこんなにも、言葉というのは使い勝手が悪いのか。
その時、言葉の発生について語る進化生物学の岡ノ谷一夫教授のこんな考察に、小川さんは目を開か