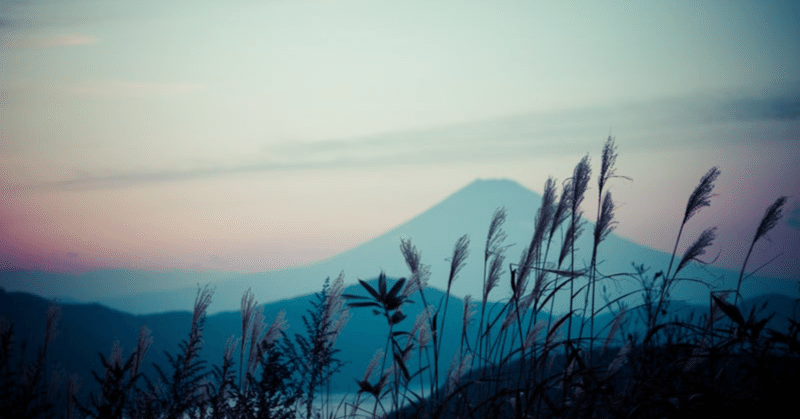記事一覧
イーロン・マスクがオープンAIに、倫理上の観点なども鑑みてCHATgptの開発を、半年停止してはほしいという要請は、もしかすると彼がそれを言わなくても、反対する人がいたかもしれないが、彼がいうことでイノベーションに対して倫理の圧力が中和されたという可能性もある。
健康寿命にインセンティブをつける
一昔前、特養とヘルパーは措置制度で使い勝手が悪かったと言われていた。しかし、2000年から現在までの介護保険と措置制度の介護サービスを比べ、介護保険を今後も続けていくのかという疑問が私にはある。
当時はの特養とヘルパーは措置制度で、しかも応能負担だったため、利用条件は重度の認知症や体の不自由な人、且つ低所得者(その限りではないが)という厳しい条件だった。また措置とはいえ、市町村が委託できる施設自
失敗本質を読んで思ったこと。〜ひきこもりと鎖国は日本の病理?〜
失敗の本質と言う本を読んでいてふと思ったことがある。戦後の公職追放で、各企業は抜擢人事を強制的に強いられたのであったが、日本人がもつ特性を生かし戦後復興してきたと言うようなことがおおよそ書かれていた。
私はここで1つ思ったことがある。日本人は窮地に立たされるとすごい頑張るが、それが安定すると全く変化しなくなるということだ。
この安定に固執する様は、江戸時代の「鎖国」や現代の「ひきこもり」や「失
仕事における評価は自分から発信する必要がある。あいまいなままでは組織の論理が薄くなり、声の大きいものが有利になる、そこには論理はない。故に責任感がないという状態に組織は気が付きにくくなる。335
永井孝尚さんの本にあった、顧客を人物でなく役割で見ることが必要と言う考えは、大久保幸夫さんのボスマネジメントの本にある、上司は便利なツールであり顧客でもあるという概念に近い気がする、
営業マンは断られてからが勝負とよく言われる。つまりニーズがゼロのお客様はいないと考え話を引き出さねばならないということ、そこから問題を解決しものが売れることもあるし、ちょっと本業の路線からは外れるが新たな事業が生まれることもある。
健康寿命を伸ばしたい
下の要介護度別認定者数の推移を見て頂きたい。
これは高齢者人口が増加しているから当然のことだ。しかし要介護度が高くなる程のその増加は緩やかになっている傾向がある。
将来的に医療やデジタル化またはロボット化が進み、今よりも長い時間、社会生活を送れるようになれば、高齢者人口に対する割合のうち要介護度3を中心に下が増え上が減るということも予測できそうだ。
そのような社会になるに連れて特養や宿泊施設