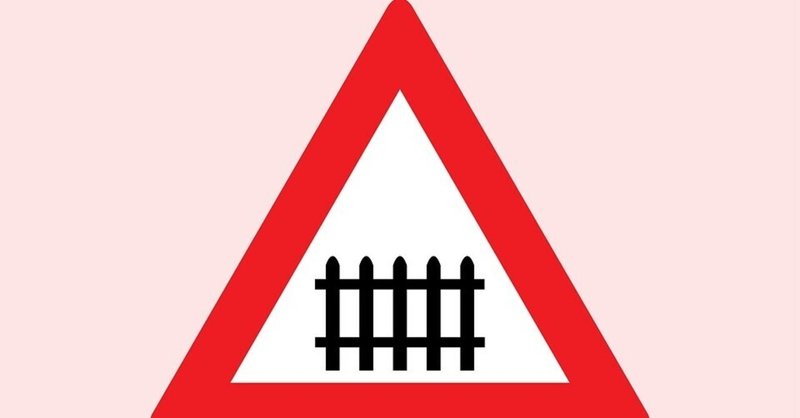
社会的障壁と嫌われる勇気
昨日は社会的障壁がどういった概念なのかについて書きました。
障がい者の社会的生活を阻害するモノだということで、事例を通して一緒に考えていただいたことと思います。
今回は、障がい者という括りを拡大解釈して、社会的障壁について書いてみようと思います。
上記の記事では、かなり乱暴な見解として、健常者という言葉を排除し、人間とは大なり小なり、何らかの障害特性を抱えているという投稿をさせていただきました。
この見解に賛否それぞれあると思いますが、「人間=障がい者」という仮説を元に、社会的障壁の概念を掘り下げたいと思います。
最後までお付き合いいただけると幸いです。

ーーーーーーーーーー
最初に、障がい者だと言われることに嫌悪感を示される方がいるかもしれませんので、少し障害について私なりの考えを述べさせてください。
私は現在、障がい者福祉の世界に入ったばかりの人間です。
多機能型事業所(障がい者支援サービスを複数有している事業所)で、主に重度の知的障害や発達障害を抱える方の支援をさせていただいています。
彼らは、先天的に障害を抱えているために、一般社会で暮らしている人々とは見えているモノ、感じているモノが違います。
言語コミュニケーションが取れない方や、意思伝達そのものが困難な方の支援において必要なのは、五感すべてで相手の意思を感じ取る感覚的コミュニケーションと、どんな些細なことでも共通項を探すことだと感じています。
感覚的コミュニケーションとは、イスを目の前にしてヒザを曲げたり、座る動作を行った場合、そのイスに座ろうとする意思が相手にあることを感じ取り、転倒防止や姿勢の維持のためにイスを支えたり、相手に手添えをし支援する所作を指します。
そして、共通項とは、人間としての構造上の生理現象や条件反射などから始まり、どのような動作がどんな感情表現とリンクしているのかを確かめる行為です。
その際に必要なのは、自分と異なる存在だと思わないことです。
人間は未知に恐怖する生き物です。
ですから、障がい者と対峙した際に怖いと感じるのは、相手を自分と異なる存在だと思っているからです。
共通項は、探すほどに見つかりますし、それが言葉や意思疎通が難しくても、信頼関係を育む手掛かりとなります。
そのような視点で見ると、障がい者と健常者という隔たりの無意味さを感じるとともに、健常者であるという驕り高ぶりも霧散するように思うのです。
ですから、改めて書きますが、私たち一人ひとりが健常者という特権階級であるかのような肩書を捨て、自らにもある何らかの障がいという名の個性を見つめ直してこそ、ノーマライゼーションの精神は浸透すると私は考えています。

ーーーーーーーーーー
さて、社会的障壁の話に進みますが、昨日は障がい者に対して、自分の価値観で支援することは、相手を助ける善行であると同時に、相手のできることを奪う社会的障壁の側面もあるといった投稿をしました。
そして、今は私たち一人ひとりを健常者というステージから個性という障害を抱える者だという前提について書かせていただきました。
これにより、私たちが誰かに施しを与える行為が、必ずしも相手のためにはならず、時には相手の意思や行動を阻害する行為となり、その行為についても社会的障壁という概念が適用されるのではないか…という理屈を通せるようなったのではないかと思います。
この理屈により私が提唱したい仮説は、「情けは人の為ならず」という言葉にもあるように「施しとは善行なのか?」という考えです。
これまで以上に穿った見解になるかもしれないので、そこはご容赦くださいませ。
また、これから述べる考えは、書籍「嫌われる勇気」でも採り上げられた概念に近い意見だと個人的には思っています。
「良かれと思って…」
「必要だと思って…」
「あなたのためを思って…」
これらを含む行為は不要なのではないか?
それが私の考えです。

ーーーーーーーーーー
他人の問題を解決することは、実に良いことだと錯覚しがちですし、なにより自分の存在意義を感じることのできる行為でもあります。
ですが、本当に相手を思うのであれば、何もしない事こそが真の善意なのではないでしょうか?
少しビジネス領域の話になりますが、世の中のサービスの多くは誰かの不便を解消するものと言えます。
最近で言えば、不要不急の外出を禁じられた中で、オンラインサービスの必要性が高まり、多くのサービスが外出を禁じられた私たちの生活を支えました。
「不・未・無・非」といった状態を解消するのが、合理的なビジネスだと私は考えています。
一方で、似て非なるサービスが存在します。
それは、自分の価値観を押し付けるサービスです。
例えば、訪問セールスの常套手段である低価格を売りにする行為を考えてみましょう。
「これだけお安くなるのですから、ぜひ当社のサービスをご利用ください‼」
…安価であることは絶対的な正義ではありません。
「安かろう悪かろう」という言葉もありますし、値段以外の部分で利用するサービスを決める人も多くなっています。
iPhoneなどは好例でしょう。
「良かれと思って…」とは、まさに善意の押し付けなのです。

ーーーーーーーーーー
反対も否定もしませんが、私は「まとめサイト」のようなサービスを好ましく思っていません。
せっかくの知的好奇心を、阻害しているように感じるからです。
一定数の方は、まとめサイトを上手に利用して、自身の疑問や探求したい事案にアプローチします。
ですが、かなりの数の人は、まとめサイトで満足してしまい、それ以上の知識を深める機会を損失していると考えるからです。
もちろん、このような考え自体も、私の価値観に過ぎません。
しかし、押し付けるのではなく、価値観をぶつけることで、もう一度考えてみてほしいのです。
知りたいと思った情報が、すでに整った状態で用意されていることを、気味が悪いと感じたことはないですか?
これが自分の知りたかった情報なのかと疑問に感じたことはありませんか?
時間も労力もムダにするかもしれない探求の旅で得るものは、本当にムダなものでしょうか?
私は違うと思っていますし、そのように知的好奇心を仮想的なゴールに絡めとるものがあるのなら、社会的障壁だと感じます。
改めて書きますが、多くのサービスは私たちに多くの恩恵を与えてくれます。
ですが、だからと言って何でも与えてもらうことに溺れてはいけませんし、何でも施すことは善意でも何でもありません。
難しいニュアンスだと思いますが、線引きを考える機会となれば幸いです。
ーーーーーーーーーー
ということで、最後までお読みいただきありがとうございました。
今回の投稿は以上です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
