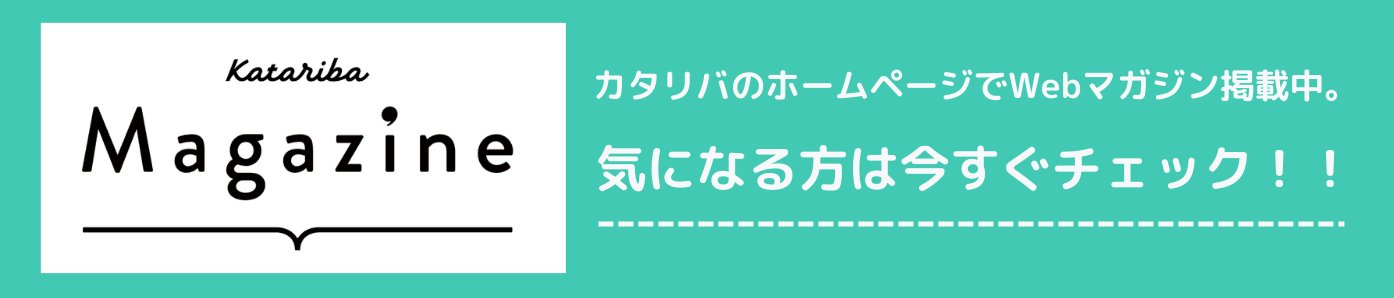放課後の居場所で“みんなで食べるごはん”が中学生たちにもたらした変化とは
家庭でも学校でもない、第3の居心地が良い場所「サードプレイス」。
そこは、子どもたちが親や教員、友だちとも違う人たちと出会い、さまざまな価値観や可能性にふれ、世界を広げられる場所でもあります。
カタリバではこれまで20年間、子どもたちのためのサードプレイスと、親や教員(タテ)や同級生の友だち(ヨコ)とは異なる 「一歩先を行く先輩とのナナメの関係」を届けてきました。これまで出会ったたくさんの子たちの中から、特に印象的だったエピソードをご紹介します。
CASE1:食事は菓子パンやエナジードリンク。“食べること”への意欲が低かった女子中学生
カタリバが運営するサードプレイス「放課後の居場所」には、晩ごはんの食事支援「みんなでごはん」という時間があります。土日も含めた毎日、スタッフとボランティアの方が調理をし、スタッフと子どもたち15人ほどで大テーブルを囲んで一緒にご飯を食べます。
食事を通した関わりは子どもたちにどのような影響を与えるのか……「放課後の居場所」で出会った3人のケースをご紹介します。
中学2年生のマユミさんはお父さんと2人暮らし。お父さんは出張が多く、マユミさんが家に1人きりになるのを心配して「放課後の居場所」に連れてきました。
すぐに毎日来館するようになったマユミさん。しかし、いつまでたっても夕食を食べようとはしませんでした。
「放課後の居場所」のスタッフで、「みんなでごはん」を取りまとめているアキノさんが、マユミさんの体を心配して声をかけると、「好き嫌いが多くて、それを人に見られるのがイヤ」と理由を話してくれました。
「野菜全般が嫌いで、学校の給食もほとんど食べず、夜に家で菓子パンやエナジードリンクをとるだけと聞いて驚きました。
『みんなでごはん』の目的の1つは、バランスの良い食事の大切さを知って、自分の体のことを考えた食事をとれるようになってもらうことです。でも、マユミさんは食への意欲が低く、『食は大切』という意識もないようでした」(アキノさん)
マユミさんに根気よく「食べ物は体を作る素だからとても大切」と説明し続けたアキノさん。マユミさんも自分を気にかけてくれるアキノさんを慕うようになり、アキノさんが調理をしているとキッチンに入ってきて、学校や自分のことなどを話すようになりました。
ある日、調理していたアキノさんが「味見してくれる?」と声をかけると、「シチューは野菜が多いから……」と困った顔をしたマユミさん。「何なら食べたい?」と聞くと「おにぎり」と答えたので、「特別だからね」とおにぎりを握って渡しました。
すると、うれしそうにおにぎりをペロリと食べたマユミさん。そして「シチューも食べてみようかな」と、ほんの少しですが食べたのです。
「もしかするとマユミさんは、お母さんとこういうことをしたかったのかもしれません。でも、ご両親は離婚していて、それができない状況にあります。ここでその雰囲気を楽しんでいるんだと感じました」(アキノさん)
そういうことが何回か続いた後、突然「私もごはん食べようかな」と言い出したマユミさん。仲の良い友だちやアキノさんの横に座り、一緒に食べる日が週に1日、2日と少しずつ増えて行ったのです。
「メニューによっては食べない日もありますが、菓子パンやエナジードリンクはやめて、おにぎりや野菜が少ないお弁当を買って帰ると話してくれました。最初の頃を考えるとすごい進歩です!
大人数で食べる経験を通して食の楽しさや大切さを感じてもらい、社会に出てからも自分の体を考えて食事が取れるようになってくれたらうれしいです」(アキノさん)
CASE2:ケンカから不登校。人嫌いになった女子中学生が調理をきっかけに人の輪へ
エナさんは中学校に入ってすぐにクラスの女の子とケンカし、頻繁に学校を休むようになりました。中3の現在は週に1回行ければいい方で、学習の遅れを心配した担任の先生に「放課後の居場所」をすすめられ、来館するようになりました。
「学校での経験からか同年代の女の子が苦手みたいで、近寄ってくる子がいても避けていました。夕食は週に3日ほど参加していましたが、会話には入らず、早食いしてすぐ席を立ち、どこかへ行ってしまう感じでした」(アキノさん)
そんな状態が2カ月くらい続いたある日、調理をしていたアキノさんはエナさんが暇そうにしているのを見て、「一緒にごはん作ろうよ」と声をかけました。エナさんは「お菓子ぐらいしか作ったことない」と言いながらも、興味深そうにキッチンに入って来たそうです。
「野菜を切ったり肉の下味をつけたりするのを、教えながらやってもらいました。食事のときに『今日はエナさんも一緒に作ったんだよ』と伝えると、皆が『美味しいよ!』と言ってくれて、エナさんが照れながらもすごく喜んでいたのが印象的でした」(アキノさん)
以来、お手伝いを自分から申し出るようになったエナさん。避けていた同学年の女の子たちに「今日の献立、何がいい?」と自分から声をかけることもありました。
「今年の春に入館した1つ下の女の子たちにも『皆で食べるのって緊張するよね。でも、何を話してもいいし、残しても大丈夫だよ』と声をかけるなど、お姉さん役を買って出てくれました。今ではその子たちと仲良しグループになり、並んでワイワイ食事をしています」(アキノさん)
人と話すことを避けていたエナさんが、食事を通してコミュニケーションや気遣いがきるようになって、彼女の心の成長をすごく感じるとアキノさんは言います。
「高校生になったらお弁当を食べる時間もあり、グループ作りなどでまた悩むこともあるでしょう。でも、ここでの経験が彼女の力になってくれると思います」(アキノさん)
CASE3:「恩返しにごはんを作りたい」受験のために来ていた男子中学生からの食の贈り物
「放課後の居場所」では学習支援も行っており、受験のサポートを求めて来館する子も少なくありません。ミキトさんもその1人で、中3の春から来館するようになりました。
ミキトさんの両親は教育熱心で、難関高校への進学を希望。ミキトさんもその期待に応えるべく、学校が終わると「放課後の居場所」に来て、授業を受けたり自習をしたりして頑張っていました。
夕食にも初日から、ほぼ毎日参加したミキトさん。ところが、2学期になると夕食と勉強のタイミングが合わなくなってしまいました。
「ミキトさんは『放課後の居場所』から塾にも通い、終わると戻って閉館まで自習をしていました。その塾の授業時間が変更となり、『みんなでごはん』の時間と重なってしまったんです。塾の前は時間が早過ぎて食べる気にならず、夕食抜きの状態になったんです」(アキノさん)
塾から戻り、おなかをグーグー鳴らしながら自習していたミキトさん。見かねたアキノさんが「ササっと食べられるものでいいならとっておくよ」と提案し、ミキトさんのための夜食づくりが始まりました。
今まで以上に勉強に集中するようになったミキトさん。希望の難関高にも見事、推薦入試で合格したのです。
「すると、ミキトさんが『皆で一緒に食べると元気が出たし、塾のある日は夜食で応援してもらえてすごく有り難かった。恩返しに僕が皆にごはん作りを手伝いたい』って言ってきてくれたんです。料理は一度もしたことがないと言っていたので、びっくりしました(笑)」(アキノさん)
それから週に1回、アキノさんたちスタッフを手伝う形で調理に参加するようになったミキトさん。それが中学を卒業するまで続きました。
「受験勉強のためにここに来ていた彼が、食を通して『放課後の居場所』を安心できる自分の居場所と感じ、感謝してくれたことがとてもうれしかったです。『恩返し』という言葉を照れずに言い、その思いを行動に表すことができるのは、大きく成長した証だと思います」(アキノさん)
「放課後の居場所」では、皆で一緒に食事をする「共食」を大切にしています。しかし、子どもたちに絶対参加してほしいとは考えていないとアキノさんは言います。
「『放課後の居場所』に来る子たちの家庭環境はさまざまで、ここでの食事に対する感じ方もいろいろです。バランスのいい食事の大切さに気づく子もいれば、皆でごはんを食べると気持ちが明るくなると言う子もいます。逆に大人数は苦手と感じたり、『家族と食べたい』と家に帰るようになる子もいます。それら全てが正解だと思うんです。
食事を通した関わりが子どもたちにとって、家族や友達との食事の仕方や自分の健康を考えるきっかけになること。そして自分を大切にしながら生きていけるようになってもらえたら、とてもうれしいです」(アキノさん)
※個人の特定を避けるため、一部フィクションが含まれています
-文:かきの木のりみ