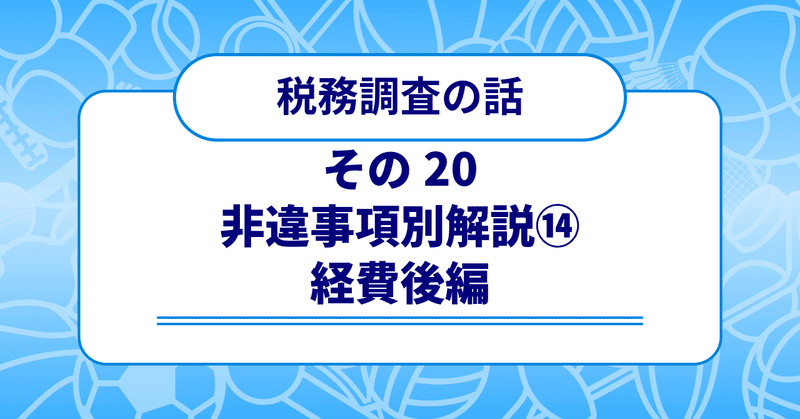
税務調査の話 その20 〜非違事項別解説⑭ 経費後編〜
元国税職員による税務調査のあれこれ。前回に引き続き非違事項(誤りや不正による要是正項目)別の解説をしていきます。今回は誤りやすい経費について取り上げます。
これまでの記事(税務調査の話その○)
調査官からすると申告是認(何も指摘できないこと)は是非とも避けたいところです。そのため、過去の経験から誤りやすいと思われる処理を丹念に調べることが多いです。
本稿では、筆者がよくチェックしていたものをいくつかご紹介します。なお、これら以外にもたくさんあると思いますが、網羅性は意識していません。
税法上の繰延資産
簿記を勉強された方はご存知と思います。既に支出済みでその効果が1年以上の長期に及ぶ場合は、支出時の費用にするのではなく、将来の収益に対応させるために資産計上せよという理屈ですね。しかし、これを広範に認めてしまうと、換金価値のない資産が多額になってしまうおそれがあるため、企業会計上は保守主義の観点から資産計上できるものを限定しています。
一方、税務上は課税の公平…というかできるだけ課税所得が多くなるように、広範に資産計上しろという考え方をとっています。
そして、このような企業会計と税法の差異を意識せずに、税法上の繰延資産を費用計上してしまうと、過少申告となってしまうというわけです。ちなみにGAAPがガチガチに強制される上場会社では、税法上の繰延資産は長期前払費用として資産計上します。
さて、この税法上の繰延資産ですが、どの会社にも関係があるものとしては、賃借している事務所の更新料がありますね。これは、建物を賃借するための権利金等に該当し、資産計上した上で5年又は契約上の賃借期間のいずれか短い年数で償却しなさいとなっています。
税法上の繰延資産といえど、20万円未満の少額なものなら一時の費用としてよいという規定がありますが、そこそこの規模の会社なら更新料が20万円以上ということも多く、筆者はこの規定のおかげで何件か申告是認を免れたことがあります。
このほかの税法上の繰延資産については、こちらをご参照ください。
固定資産の取得価額
基本的に付随費用は取得価額に算入しますが、一部算入しなくても良いものがあり、こちらに例示されています。
不動産取得税や登記費用なんて書いてあるからか、土地・建物を購入した際の付随費用は費用計上でOKという勘違いを起こす人がいます。このため、不動産業者に支払う仲介手数料まで費用計上してしまう誤りが結構見つかります。
固定資産の減価償却費
色々と細かい取扱いが多く、経理経験が長い人でも全て正確に把握していないこともあります。このため、誤りの多い項目となっています。
「建物」と「建物附属設備」
賃借建物に内部造作(内装工事)を行った場合、これを資産計上することを間違えてしまうことはほとんどありませんが、耐用年数を誤るケースが結構多いです。というのも、「建物」で処理すべき内部造作を「建物附属設備」と処理してしまう人が多いんですね。法定耐用年数は「建物」の方が「建物附属設備」よりもかなり長いので、償却費を過大に計上してしまうというわけです。
事業供用日
減価償却を開始するのは、事業の用に供した日からです(実務上はその日が属する月)。例えば、車両の購入の契約日が8月30日、納車日が9月1日の場合、9月から減価償却を開始することになりますが、固定資産台帳に償却基礎情報を登録する際に契約日付しか見ていないと、8月から減価償却を開始してしまうといった誤りが起こります。たった1か月分の償却費ですが、是認回避のためなら調査官も頑張って粗探しをしてきますよ(笑)
ちなみに、筆者は備品の納品日を仮装している不正を見つけたことがあります。納入業者に反面調査を実施したところ、配送日が翌事業年度となっており、減価償却費だけでなく、消費税の課税仕入も否認して重加算税を賦課決定しました。
おわりに
繰り返しになりますが、上記は筆者がよくチェックしていたものの中から、汎用的なものを取り上げたものです。この連載の趣旨は税法の解説ではないので、網羅性は意識していません。ほんのさわりとしてご紹介したことをご理解ください。
それでは次回もお楽しみに!
お仕事のご依頼はこちらまで
最後までお読みいただきありがとうございます😊少しでもお役に立ったらスキ(❤️)していただけると嬉しいです。note会員でなくても押せます。
