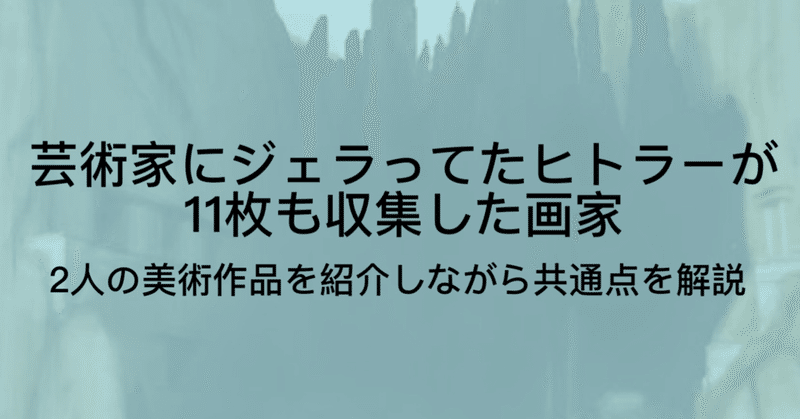
アルノルト・ベックリンはなぜヒトラーに愛された?死の島など代表作で考えてみる
アドルフ・ヒトラー。彼に「人の感性を持たない独裁者」というイメージを持つ方も多いのではないだろうか。そんなヒトラー、実は絵画への造詣が深かった。自身も若いころは美術家志望で、建築画や風景画などを描いている。
ヒトラーの作品は「西洋絵画の巨匠たちの影響を総合的に取り入れている」と評価される。簡単に言うと「オリジナリティ皆無だなおい」という意見だが、ポジティブに捉えると、彼は絵画オタクだったということが分かる。
なかでもヒトラーはアルノルト・ベックリンという画家を特に愛していた。今回はヒトラーが愛した画家、アルノルト・ベックリンについて紹介していこう。ヒトラーとベックリンの関係性を探っていき「なぜヒトラーはベックリンの作品を好んだのか」について見ていく。
ドイツでユダヤ人大量虐殺を行った悪名高きカリスマ、ヒトラーについて

アドルフ・ヒトラーといえば1933年にドイツの首相に就任し、一党独裁のナチスドイツを率いてホロコーストを実行した「非情な独裁者」というイメージがある。まずは彼の画家から政治家への転身について見てみよう。
少年期のヒトラーは父のアロイス・ヒトラーとよく対立しており、父が無理に進学させた学校は休みがち。12歳のころには、いよいよ勉強についていけなくなり、2つの学校で退学・退校処分を受けている。落ちこぼれヤンキーだった。
その後も別に職には就かず、16歳ごろから画家になる夢を持ち、母のクララに打ち明けていた。それで18歳で野心のままにウィーンの美術アカデミーの入学試験を受けるが、残念ながら落ちる。不合格の理由は「頭部デッサン課題の未提出」だ。人物画を好んでおらず建築物に興味があったヒトラーは、課題を放棄した。とにかくアナーキーで気まぐれな性分だったのである。
また当時からヒトラーの作品は「独創性が低く、古典的だ」との評価も受けている。その背景として彼は「古典主義者」を自負していた。古典主義とは、ギリシャ・ローマ時代の学芸や文化を模範として仰ぐこと。つまり「古き良き教育こそ至高」という懐古厨だったのである。
21歳ごろには路上画家として水彩画の絵葉書などを売りながら生計を立てていた。その際もオリジナル手法を試すことなく、既存の作品の模写ばかりである。さらに、そのころのヒトラーはさらに古典主義者に磨きをかけている。図書館で歴史書や科学書を借りて読み、古典・古代の知識を蓄積していた。当時描いていたヒトラーの作品はこんな感じ。たしかに写実性としてもいまいちだし、オリジナリティもない。




その後、ヒトラーは第一次世界大戦でドイツ兵として出兵する。これが彼の人生を逆転させる。戦場で功績を挙げ、政治家に転身するわけだ。
その後は首相に就任し、独裁国家のナチスドイツを作り上げる。しかしその際も「自分の本質は政治家ではなく芸術家である」と信じているなど、芸術家としての信念は捨ててはいなかった。またインタビューには「第一次世界大戦がなかったらドイツいち……はさすがに無理だけど、そこそこ有名な建築家になったと思う」と答えている。まだ芸術に未練たらたらだった。
ヒトラーが徹底して規制した「退廃芸術」とは

すると彼はナチスドイツ下において1933年から本格的に芸術統制を実行し始めた。芸術家として「真の芸術」を勝手に判断して切り捨てたのだ。具体的にいうと「退廃芸術」と「ドイツ的芸術」を分けた。ではこの両者の違いを説明しよう。
20世紀はじめ、当時のヨーロッパは特に芸術運動が盛んになっていた。フォーヴィスム、キュビスム、ダダ、シュルレアリスム、象徴主義、後期印象派などが誕生。芸術が多様的になり始めた「西洋美術史でもめちゃめちゃ面白い時期」だったのだ。
しかしこれらの表現は「古典とかもういいから新しいことしようぜ!」というもの。ヒトラーはこのような、写実的な古典的芸術を根本から覆すような芸術作品を嫌い「退廃主義」と名付けた。また「退廃芸術展」と名付けた展示会を開催し「おいなんだよこれ(笑)基本がなってねぇわ基本が(笑)」と押収した作品を嘲った文章とともに群衆に見せたのだ。
「退廃芸術」とされた芸術家にはダダイズムのラウル・ハウスマンやシュルレアリスムのマックス・エルンスト、キュビスム・シュルレアリスムのマルク・シャガール、表現主義のパウル・クレーなどがいる。
彼らは教職を終われたり、迫害されたりして、満足な芸術表現ができなくなってしまった。では退廃芸術を観ていこう。本当に当時のカルチャーを象徴する、今見ても面白い作品たちだ。

ラウルハウスマン「ABCD」

マックス・エルンスト「森」

マルク・シャガール「誕生日」

パウル・クレー「パルナッソス山へ」
ここまでの力を注いで芸術を排除したのは、ヒトラーが芸術肌だったからに違いない。芸術には人を変える力があることを自覚していたのだろう。そう考えると、画家になる夢を捨てざるを得なかったヒトラーのただならぬコンプレックスも感じ取れる。
ヒトラーが許した「ドイツ的芸術」とは

一方、ヒトラーが是とした「ドイツ的芸術」とは、古典主義を思わせる写実的な絵画のことを指す。もう完全にヒトラーの好みである。独裁というか、もはやわがままだ。
そして「退廃芸術展」と対をなす「大ドイツ芸術展」を開催。こちらは指揮をとったアドルフ・ツィーグラーをはじめとして写実的で理解しやすい絵画が並んだ。
こうした写実的な絵画を良しとした背景にはヒトラーが古代からの格式を重んじる古典主義であったこともあるが、ギリシャ彫刻のような健全な肉体をアピールすることも兼ねていたともいわれる。「健全な人間の”形”」に着眼したのは、建築家を目指していたヒトラーらしい発想ともいえるだろう。ハード面を重視していた。

アドルフ・ツィーグラー「裸婦」
ヒトラーが飾っていた「ベックリンの絵」
そんななかヒトラーは特に2人の画家に傾倒していた。1人はバロック期の巨人、ヨハネス・フェルメール。写実的な作風を見ると、ヒトラーが愛していた理由が分かる。

ヨハネス・フェルメール「牛乳を注ぐ女」
そしてもう1人が今回紹介したいアルノルト・ベックリンだ。ヒトラーは「フェルメールとベックリンの作品だけを収めた美術館を造りたかった」というほど、2人に心酔していた。本当にやりかねんところが怖い。こんなの今の日本の政治家が発言したら森喜朗とか霞むレベルのスキャンダルだ。
特にベックリンの作品は11点も持っていた。ではアルノルト・ベックリンとはどんな画家なのだろう。また彼のどのような作風がヒトラーを惹きつけたのかを見ていく。
ベックリンとはどんな画家なのか

ベックリンはスイスのバーゼルで生まれた。その後、ドイツのデュッセルドルフ大学に入学し、画家のヨハン・ウィルヘルム・シルマーのもとで絵を学ぶ。
シルマーは写実派の画家であり、ベックリンにも絵画の作品の模写訓練をさせていた。ここでベックリンは基本である写実的デッサンを学ぶ。ちなみに師匠の絵はこちらのスーパーリアリズムだ。

ヨハン・ヴィルヘルム・シルマー「遠い船と海の波」
その後、ベックリンはルーブル美術館で巨匠の美術を模写するなど訓練を積み、また、さまざまな風景画を描いた。その後、兵役を終えたのち、1850年3月に絵を描くためにローマへ向かう。
ローマでの色鮮やかな風景、またローマ神話の物語はベックリンにとって鮮烈なものだった。このあたりから彼の作品には神話的な要素や寓意的な手法が含まれる。この寓意性とは古典主義的手法のキーワードでもある。
ベックリンは1853年に結婚。ローマ滞在時の影響が最も色濃く現れており、ベックリンの作品にはたびたび神話の生き物や、ローマ建築の建造物が描かれることになった。

「海辺の城」

「海辺の邸宅」

「海賊の攻撃」
なかでも海辺の邸宅を良く描いている。これらの建造物は「イタリア式のバロック建築」であると評された。ベックリン自身が学生時代に古典的作品の模写を好んでいたことから、オリジナリティ溢れる作品というよりは、古典的な芸術を好んでいたのである。
またベックリンの作品に共通するテーマとしては「死を連想させる物憂げな雰囲気」もある。ベックリンはビッグダディで子どもを14人ももうけたが、そのうちの8人を亡くしている。たび重なる我が子の喪失体験が彼の作品に影を落としているのかもしれない
ベックリンの代表作「死の島」について
そんな彼が53歳のときに描いた代表作であり、ヒトラーが執務室に飾っていたのが「死の島」だ。

アルノルドベックリン「死の島」
岩でできた孤島に船が向かっていく様を描いており、タイトルからも色使いからも、憂鬱で悲しげな雰囲気が伝わってくるのが特徴だ。ベックリンは幼い娘のマリアが亡くなったことに寄せて「死の島」を描いたといわれる。ヒトラーの推しもあって、当時のドイツで絵葉書としても人気を博した。精神学者のジークムント・フロイトや作家のヘルマン・ヘッセなども部屋に飾っていたらしい。まさに一世を風靡した超人気作だ。
絵の解釈としてはベックリンが大好きだった「ギリシャ神話」の影響がよく引き合いに出される。船のこぎ手は死者の魂を冥府へと案内する渡し守「カローン」、また白い布で覆われた船客は、死後の世界に連れて行かれる亡くなったばかりの亡霊だ。我が子のマリアをはじめ、亡くなった子どもたちの葬儀と関わりが深いといわれている。
「死の島」は1880年~1886年までに色合いを変えながら5作描かれており、それぞれ画商や夫を亡くした未亡人からの依頼などで描かれている。ベックリン自身がハマって描いていた。ちなみにベックリン自身がタイトルを付けたわけではなく、名付け親は画商だ。


ベックリンは死の島を描く前まではあまり世間から知られていない遅咲きの画家だった。しかしこの作品がヒットしたことで、収入を得るチャンスを得たので、同じモチーフの絵を描いたのである。
ではベックリンの何が、いったいヒトラーをここまで惹きつけたのだろうか。ここまでを振り返りながら考察していこう。
ヒトラーがベックリンを愛した理由その1「バロック建築」「ギリシャ神話」という古典主義
ヒトラーとベックリンの作品に共通することに「バロック調の建築」がある。ヒトラーがもともと、建築家志望だったのは先述した通りだ。一方、ベックリンの絵画にもよくローマ式の古典的な建築が描かれており、ヒトラーはその写実的な絵に惚れこんだのだろう。
また「ギリシャ神話」も大きな共通点だ。ヒトラーは古代ギリシャの歴史を深く学んでおり、ベックリンもまたギリシャ神話のモチーフを登場させている。
古典主義絵画にはこうしたギリシャ神話のモチーフがよく登場する。2人には芸術家として同じバックグラウンドがあるのだ。
ヒトラーがベックリンを愛した理由その2「軍国主義の象徴としたから」
またベックリンの「死」をモチーフにした絵画は、まさしくヒトラーが目指すナチスドイツのあり方に当てはまる世界観だったともいえる。軍国主義のドイツをつくるうえでヒトラーは「戦争=悪」というイメージを払拭し、戦争は自然に起きるものだと国民に理解させようとした。
第一次世界大戦の敗戦を「美しいもの」としてイメージさせたのだ。そのため戦死者を美化するとともに「この世はそもそも悲惨なものだ」と国民を説得する。これを「ペシミズム(悲観主義)」という。そのうえでベックリンが作り出す「死の空気」はヒトラーにとって都合がよかった。
絵画的なモチーフや技法と、人格そのものの両方に共感し、ヒトラーはベックリンの絵画を集めていたのかもしれない。
ヒトラーにとってベックリンは自己投影の対象だったのかもしれない

今回はヒトラーが愛した画家「ベックリン」についてご紹介しました。ヒトラー自身も少年期から青年期にいたるまで何度も挫折を繰り返しており、そもそも悲観的な面もあったのは間違いないだろう。
そのうえで最も大きなコンプレックスが「絵画」だ。そもそもの感性が芸術家であり「絵で大成できなかったこと」はヒトラーをメンヘラ化させた。その結果。前衛表現に対するジェラシーもあったのだろう。
そして自分とのバックグラウンドが近いベックリンの作品に自身を投影していたともいえる。さらにいうと、その結果「ナチスドイツ」という悲惨な国家ができたのだとも、考えられる。
こんな感じで歴史の背景には常に芸術がある。今回のようにアートに着目することで、当時の世相がより色濃く見えてくるのは非常におもしろい。
また世相を知ることで、アートの楽しみ方もより広がるので、ぜひこれからより絵画作品を楽しみたいとお考えの方は以下の記事を参考に、西洋美術史を観てみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
