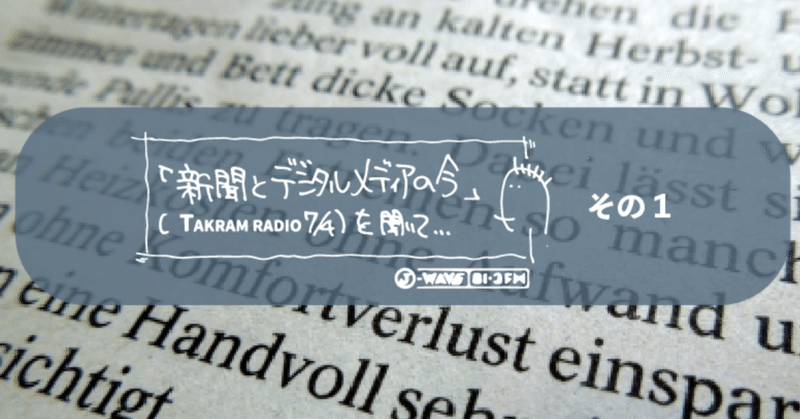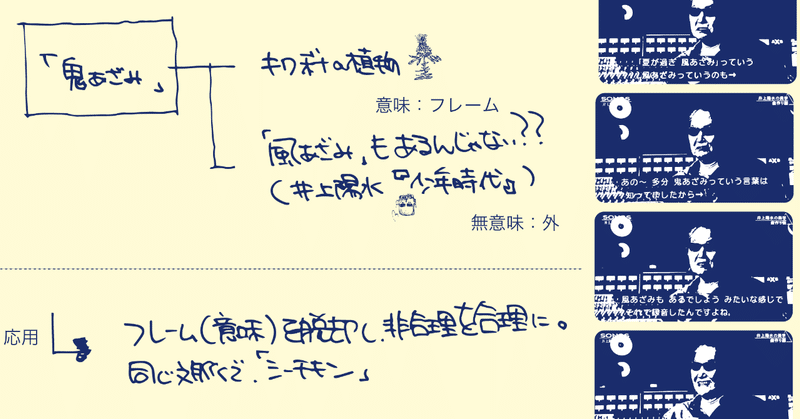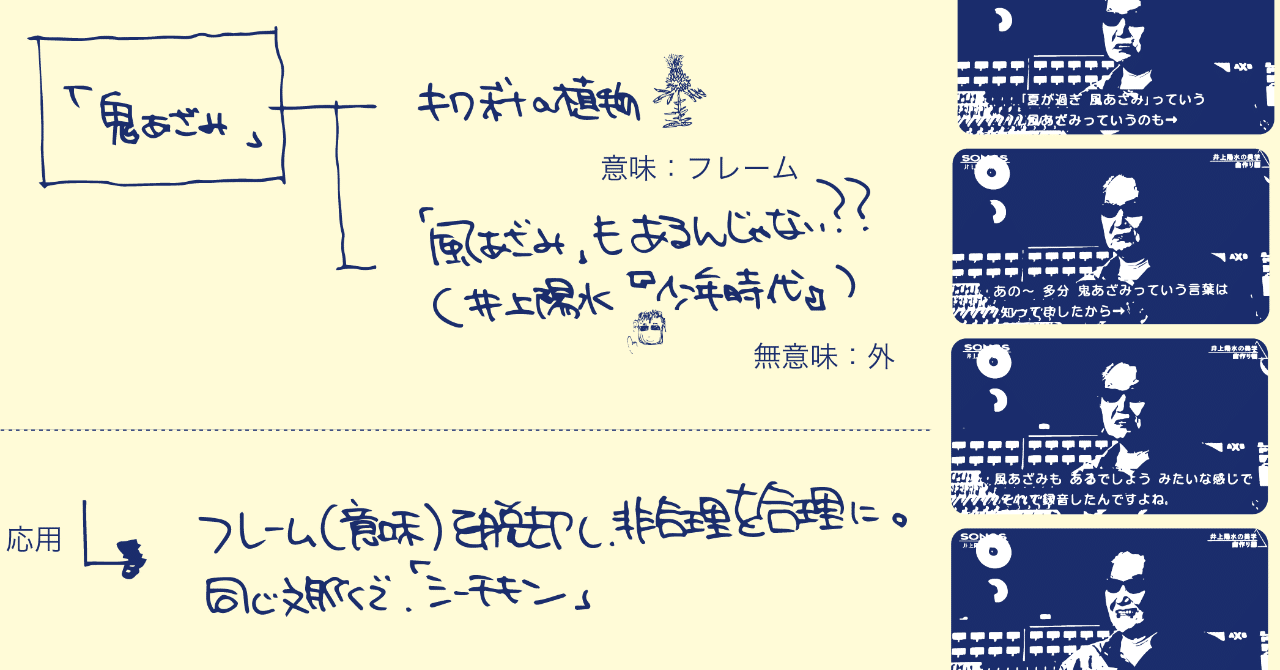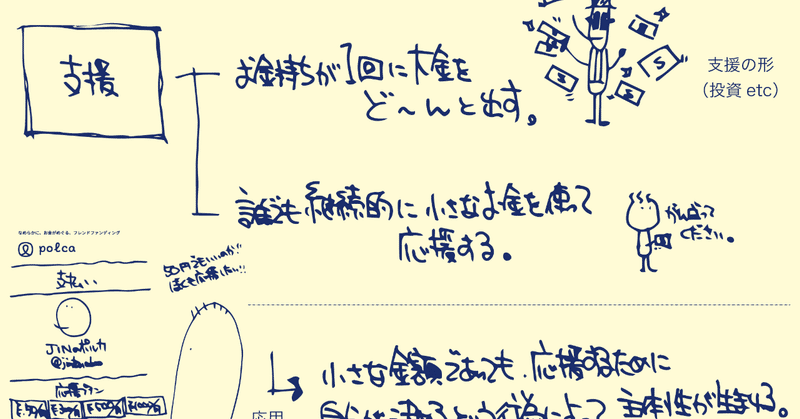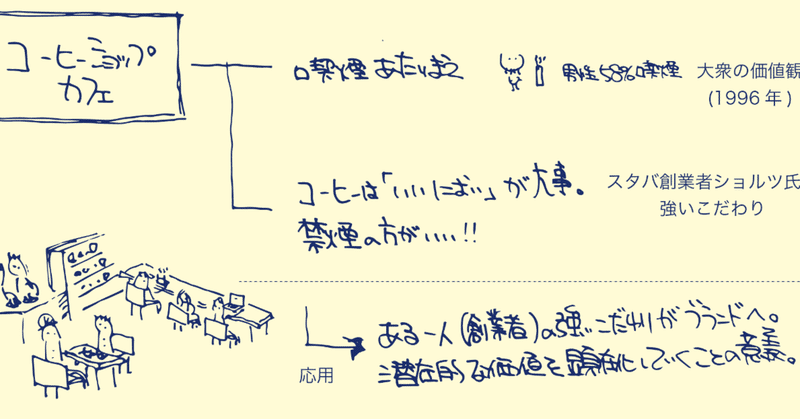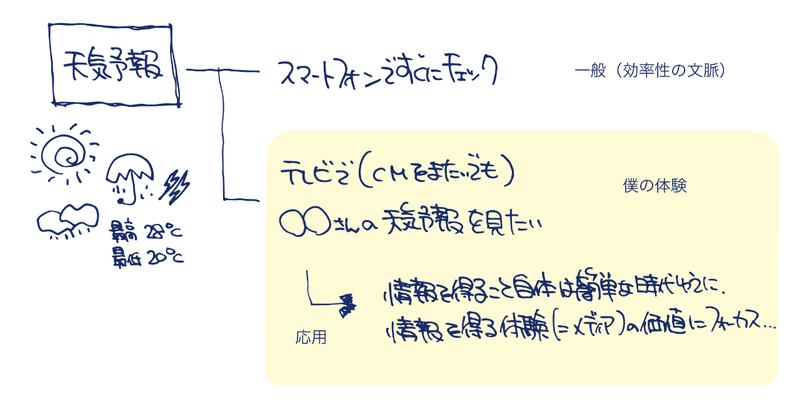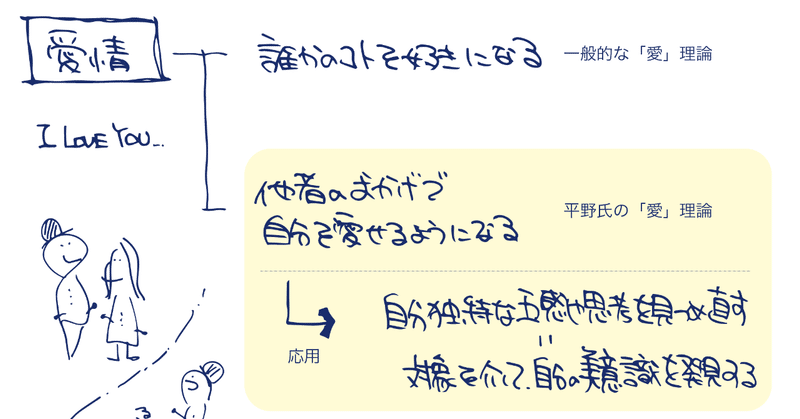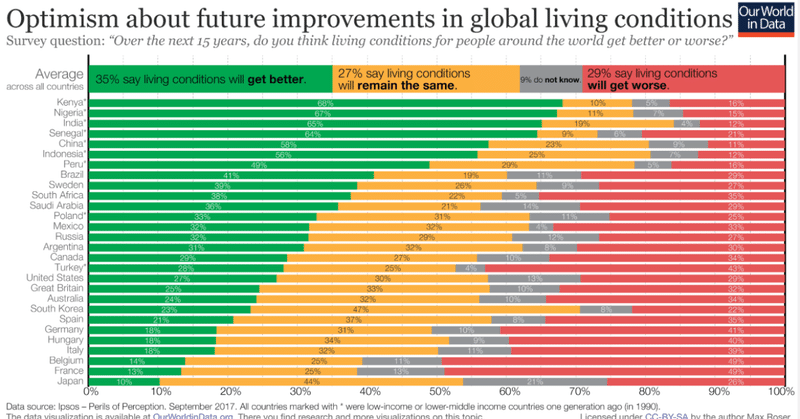最近の記事
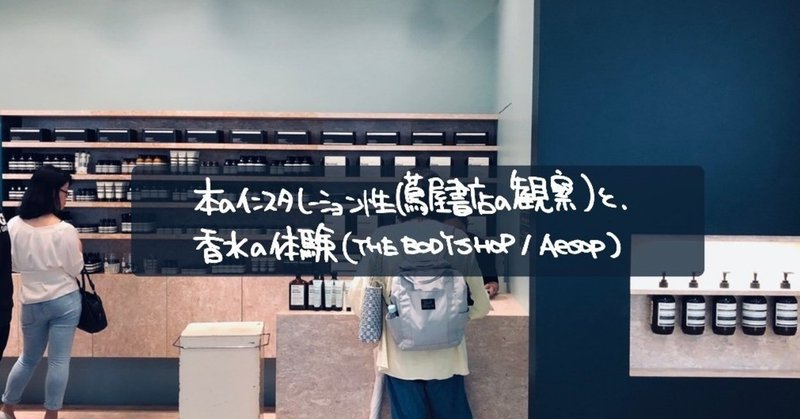
【コンテクストリサーチ6】本のインスターレーション性(蔦屋書店の観察) と香水の体験(THE BODY SHOP / Aesop)
#蔦屋書店による「本」のインスタレーション的空間代官山蔦屋に足を運んだとき、本が美術館の批評文のようなテキストとセットで置かれている風景に出会う。情報を売る(配る)のはウェブに任せ、本は徐々にインスタレーション的体験を重視しているように思えた。軽い情報は、短期視点でPVなるKPIを目指すスキッパブル設計のウェブが担当し、細切れでない重層的な体験としての物語は、本が担当している。本には目の前の対象と堅実に向き合いたくなる「閉じられた」態度が必要で、アートのインスタレーション