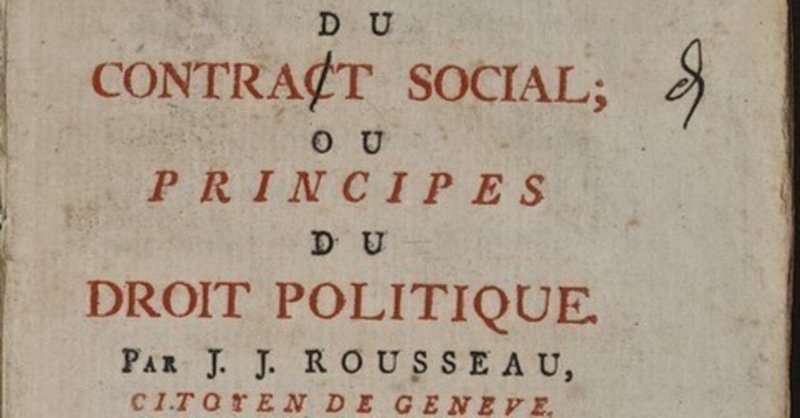
ルソー『社会契約論』を読む(7)
今回の記事では、第二篇第八章以降を扱います。この第八章、次の第九章、そしてさらに第十章は、いずれも「人民について」という同じ章立てで構成されています。まず、ルソーはこんな風に言います。
人民について
建築家は、大建造物を建てるまえに、地所を測り、地質を調べて、土地が重みに耐えられるかどうかを見る。〔注1〕
というのも、建築家と同様、法律を制定する際にも、それ自体として申し分ない完璧な法律を編纂することから始めるのではなく、あらかじめそれを与えようとしている人民が、それを支えるに相応しいかどうか吟味する必要がある、とルソーは考えているのです。しかし、これはルソーの勝手な考えではありません。プラトンも、アルカディア人とキュレネ人に法律を与えるのを断ったし、この地上には、光彩を放ちながら、しかもよい法律に耐えられなかった国民が多数存在しているではないか、とルソーは言います。
国家の規模
そして、もう一つ、ルソーは別の議論を始めます。人間の身長には、自然が定めた均整の限度というものが存在しており、それを越えると、もはや巨人か小人になってしまう、と言うのです(p.153)。これは、国家の構造の大小について説明するためにルソーが持ち出した喩えです。ルソーは、社会の絆は「長くなってゆくと、それだけゆるむ」(p.153)と言います。
恋愛を思い浮かべてみましょう。付き合いたての頃は、相手の一挙手一投足すべてが新鮮で、心を動かし、相手のことで頭がいっぱいなはず。しかし、付き合いがだんだん長くなってくると、相手の嫌なところが見えてケンカになったり、しまいには相手に一切関心がなくなってしまう、なんてことも・・・。「倦怠期」とでも言うべきこんな体験をした読者の方も、きっといるのではないでしょうか。社会の絆は「長くなってゆくと、それだけゆるむ」(p.153)のです。
こういうところがルソーの面白さだと私は思っています。というのは、ルソーはどこまでも具体的に議論をしてくれている。「哲学者」と言われる人々の本を読んだことがある方ならお分かりいただけると思うのですが、彼らはとことん抽象的に、観念の上だけを辿っているかのような書き方をする人が多い(『純粋理性批判』とか、とにかく「難しい」ことで評判ですよね)。もちろん、具体的なことが「良い」とは必ずしも思いませんが、ルソーのように、「我が事として実感を持って」考えたことを、再吟味の末に本に著す、という姿勢は、なかなか真似できるものではありません。そして、それが真理を得ているように見えることが、ルソーのとても面白いところなのです。カントもルソーに影響を受けたというなら、もう少しルソーを見習ってくれても良いのに、と思います・・・。ただ、カントの『人間学」は、例外的に読みやすい本だと思います。閑話休題。
さて、こういうわけで(どういうわけやねん)、社会の絆は「長くなってゆくと、それだけゆるむ」ので、国家は「大規模」であるよりも「小規模」である方が望ましい、とルソーは考えます。なぜでしょうか。より詳しく、こんな理由を挙げています。
①梃子の長さが長いほど、先端に置かれた重量の手応えが増してゆくのと同じで、行政は、距離が大きくなるほど、それだけ困難になり、行政はその段階の数が増すにつれて、高くつくようになる。
②政府が、人民に対して法律を守らせたり、迫害を禁じたり、悪弊をただしたり、遠隔の地で起こりがちな反乱の企てを予防したりするために持つはずの力強さと敏速さが大規模だと劣ってしまう。
③人民は、見たこともない自分たちの首長や、彼らの眼には広すぎて世界にも等しい広さを持つ祖国や、大部分が彼らにとってなじみのない同胞に対しては、抱く愛も乏しくなる。
(p.153-154の要約)
だからこそ、人間の体が、脂肪が多すぎると様々な病魔の住みかになってしまうのと同じで、国家の構造も、その骨格に比べてあまりにも大きすぎる政治体だと、「自分自身の重みで弱り、それに押しつぶされて滅びる」(p.154)ことになってしまうのです。
「膨張」の末路
さて、この国家の規模の議論は、現代の政治学にも、あるいは私たちの日常生活にも、示唆に富んだ議論だと思います。と私が言う理由は、次のようなルソーの指摘を見ると徐々に明らかになってきます。
この結構な必要(=膨張の必要)をみずからおおいに祝福していたであろうが、この必要は膨張の限界をともなっているので、没落の避けられない時期を彼らに示してもいた。(p.155)
いま、ウクライナをめぐって不穏な動きが起こっていますよね。かつては今以上に各地で戦争が多発していた時代があって、その時代の政治は「帝国主義」というのだ、と学校で勉強してきたはずです。
帝国主義の本質は、「膨張」にあります。限りなく自分の勢力を拡大することを目指す。膨張が目的化していたかつての政治が、最終的に行き着いたのが、「全体主義」でした。全体主義は、私たちの住む家を、仕事を、人権を、あらゆるものを奪いました。このことをハンナ・アーレントという政治哲学者は『全体主義の起源』で詳しく説明しています。
帝国主義は、「膨張」が限界を有する点で、いつか没落せざるを得ない。そりゃ、地球全部を支配したら、それ以上膨張できないわけですからね、その時点で「次どうするんだ」って話になります。実際の歴史はどうなったかと言うと、膨張の理念が限界を迎えたとき、「人々の破壊」に行き着いたわけですよね。強制収容所がその最たる例です。
・・・「こんなことが起こってはならなかった。」と皆が言います。でも、その原因だった「膨張」は、過去の話なのでしょうか?決してそうではありません。
「とにかくたくさん働いて儲けるんだ!」と何時間も違法スレスレ(あるいは違法)に残業しているサラリーマンが一定数ですが現在でも存在します。長時間働いた方が、何となく「偉い」風潮が未だに社会には存在します。これを「膨張」と言わずして、なんと言いましょう?
あるいは、前回のテストよりも今回のテストの方が、得点アップしていなければ「ダメ」だ、と思うことも、立派な「膨張」です。そして、「膨張」しなければならない、と追い込んでいるときに、そうではない結果を突き付けられたから、「もう自分はダメなんだ」と思って、東大での刺傷事件が起こってしまったのではないでしょうか?
もちろん、その被害者の方の心身の傷を考えれば、絶対に彼が犯したことは許されないことです。まさに強制収容所と同じく、「こんなことが起こってはならなかった」のです。だから、事件を起こしてしまった彼は、猛省して、罪を償って、もう一度、自分の力で立ち上がらなければなりません。ですが、その原因だった「膨張」は、お咎めなしでよいのでしょうか。彼を追い込んだのは、社会から押し付けられた「膨張という名のプレッシャー」だったのではないでしょうか?彼もまた、被害者なのではないでしょうか?
何度も言う通り、私は彼を擁護するつもりは毛頭ありません。我が身にあのような事件が起こる、と考えると、気が気ではない。しかし、彼自身のような已むに已まれない感情に、誰しもが苛まれてしまう可能性はあるわけです。「膨張」に呪われ、極端な行動に打開策を求める。かつての全体主義と同様、これは決して「他人事ではない」という危機感を、私は覚えるのです。
立法に適した人民
さて、少し話が脱線したようにも感じますが、今回のこれに関しては、脱線ではないように思います。ルソーが提唱した「一般意志」の概念を、全体主義だ、と批判する論者も存在するくらいですから。
ただ、この議論をこれ以上続けるのは、このnoteの意図する読者層を置いてけぼりにする可能性が極めて高いので、「いかなる人民が立法に適しているか」という、この記事の最初に提起した問題の解答を示して、終わりにしましょう。
それは、起源、利害、あるいは約束のなんらかの一致によってすでに結ばれてはいるが、まだ法の真の軛をつけたことのない人民、根強い慣習も迷信も持たない人民、突然の侵入を受けても押し倒されるおそれがなく、また、隣国間の抗争には立ち入らないが、そのどれに対しても抵抗するだけの、あるいは、一方と助け合って他方を撃退するだけの力を持つ人民、各構成員一人一人の事情が全員に了解でき、一人の人にはにないきれないほどの大きい重荷を、その人だけに負わす必要のない人民、他のいくつかの人民に頼らないでやってゆくことができ、他のいかなる人民にも当てにされないですますことができる人民、富裕でも貧困でもなく、自給自足できる人民、最後に、年を経た人民のかたくなさと、新興の人民の馴らしやすさとをあわせ持つ人民(p.157)
だと言います。そして、次の議論へとルソーは進んでいくのです。
ーーーーーーーーーー
本文中に〔 〕で示した脚注を、以下に列挙します。
〔注1〕『ルソー全集 第五巻』作田啓一訳、白水社、1979年、150頁。以下、本記事において、特に断りなく頁数だけが示されている場合は、ここにあげた白水社版『ルソー全集 第五巻』の頁数を示しているものとします。また、( )の補足は記事執筆者によるものです。
ーーーーーーーーーー
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
