
【写真は真を写すもの】
他の女子がどうだったかは知らないが、私は中学生の頃、せっせと子供の名前を考えていた。
将来の自分の子供につける名前だ。
子供を持つ願望というよりも、自分の好みの名前を見つけたいという願望が強かったように思う。なのでそれが例えばペットの名付けであっても興奮しただろう。
私のメモ帳には、連連とアルファベットが並んだ。私の考える名前は外国名だった。
ナイジェル、クレッグ、アシュリー、クロエ……。なぜかそこに日本名が混ざることはなかった。当たり前のように、ごくごく自然に、私の妄想の中の子供達はアルファベットの名前を与えられていった。
青森の田舎の、赤いまん丸ほっぺの中学生は夢見ていたのだ。いつかこの町を飛び去って、新たな地で新たな人生を歩むことを。
丨
丨
noteで投稿を楽しみにしているクリエイターがいる。彼女は写真を投稿する。主に文章を読み書きする私は大抵文章のクリエイターをフォローするのだが、彼女の写真は特別だった。
彼女は、彼女の住む町を撮る。何枚も、何枚も。
その町とは、とっくにあっさり私が捨てたあの町だ。
風景や建物、動物や家族。それらは、彼女の眼球の角膜を通り、カメラのフィルターを通り、私のスマホの液晶を通り、私の眼球から入り、私の心臓に触れる。心臓はいつも、少しだけきゅっと縮む。
十八の春、新幹線に乗り込む私は前だけを見て、一度も振り返らなかった。
あの日、私の生まれ育ったあの町が、どんな色をしていたかなんて覚えてもいなければ、考えたこともない。
「こんな色をしていたんだよ」
「変わらず今も、こんな色をしているよ」
そう彼女の写真が私に囁くから、いつも、いつも、私の心臓は少し痛む。
丨
丨
そこにあるものにカメラを向けてパシャッとシャッターを押すだけ。誰にでもできる簡単な行為だと、目の前の物体がそのまま記録されるシンプルな現象だと、思っていた。
それが、なぜ「表現」や「芸術」と呼ばれているのか理解し難かった。
違ったのだ。
私には出来ない表現方法だったから、私は理解できなかったのだと気づいた。
彼女の写真にかかっているのは彼女の愛情だった。まるで高精度のフィルターのように、彼女の愛情は写真一枚一枚にふんわりとかかる。
それがこんなにも豊かで鮮やかな色味を生み出しているのだ。きっと彼女の観ている風景を私が観ても、同じ色には輝かないだろう。
色を失ったあの町のように。
カメラのレンズで撮影しているようで、きっと彼女は眼球の角膜で撮影している。溢れ出る愛情を目一杯反射させて。だから芸術なのだ。これは彼女にしか撮れない写真なのだ。
丨
丨
今日も、彼女は何でもない木を撮る。
少し前、彼女は孫の縄跳びを撮った。
ただそこにある日常を、
ただそこにある時間を、
平凡とか淡々とかそんな言葉が似合う毎日を撮っている。
まるでそれらが終わる瞬間を知っているかのように。
まるで永遠は来ないと知っているかのように。
刻々と変化するこの世の仕組みを分かり切っているかのように。
今しかないのだと悟っているかのように。
こんなに尊いものは無いと言い切るかのように。
ありったけの愛情を乗せて染み込ませて。
欠落していたのはあの町ではなくて、周りではなくて、自分自身だった。遠くを見てばかりの、形無いものに憧れるばかりの、浮つく足元に気づかぬふりをしてばかりの、そんな私に、色鮮やかな彼女の写真は語りかける。
写真は、真を写すもの。
シャッターを押す人間の真が写し出され、
それを観る人間の真をも映し出すんだよ、と。
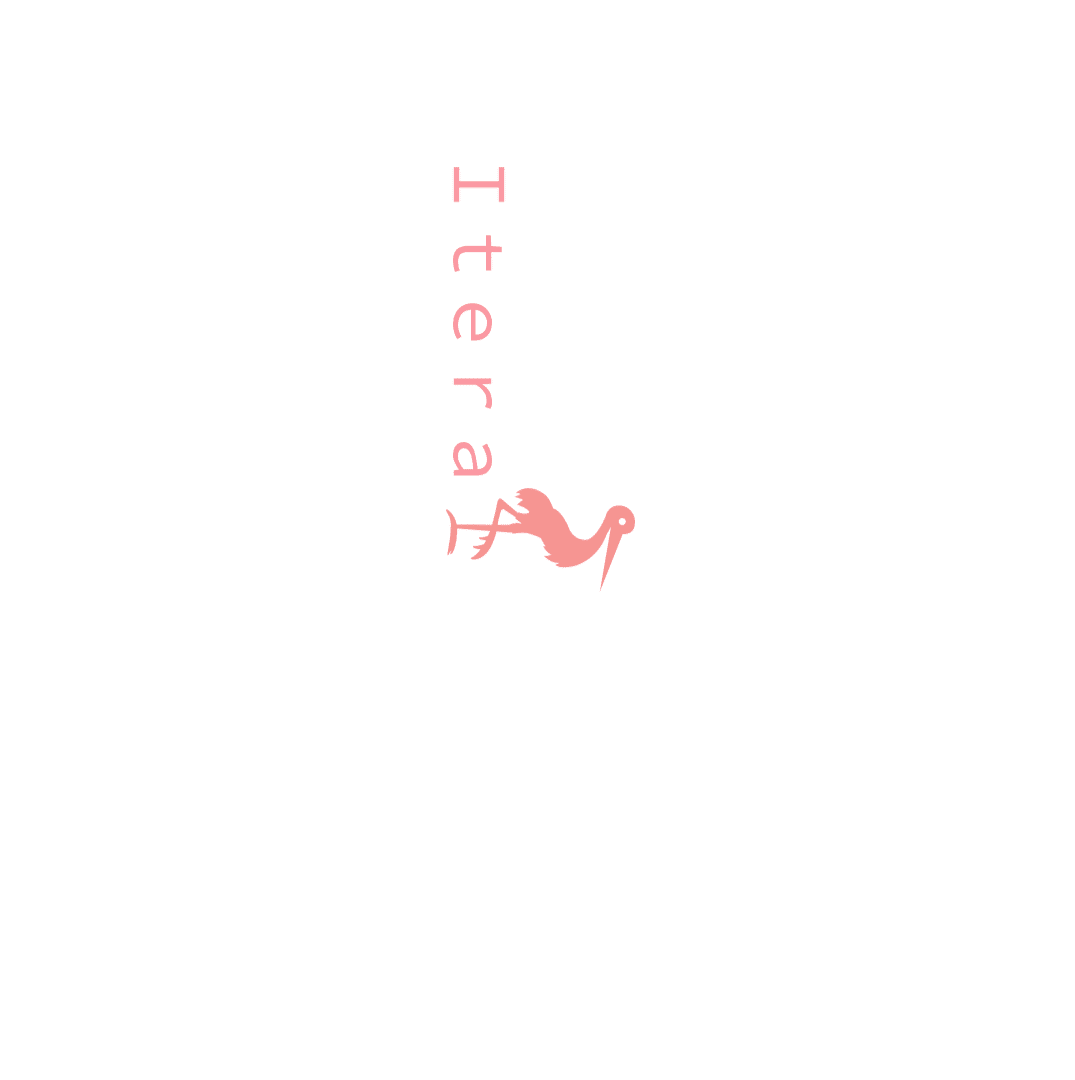
ぇえ…! 最後まで読んでくれたんですか! あれまぁ! ありがとうございます!
