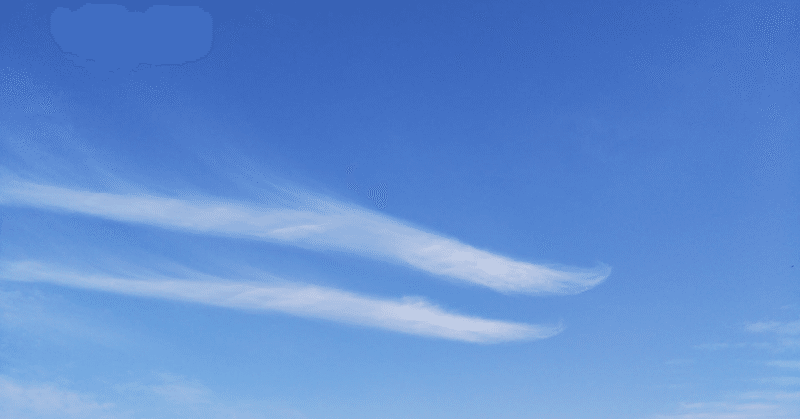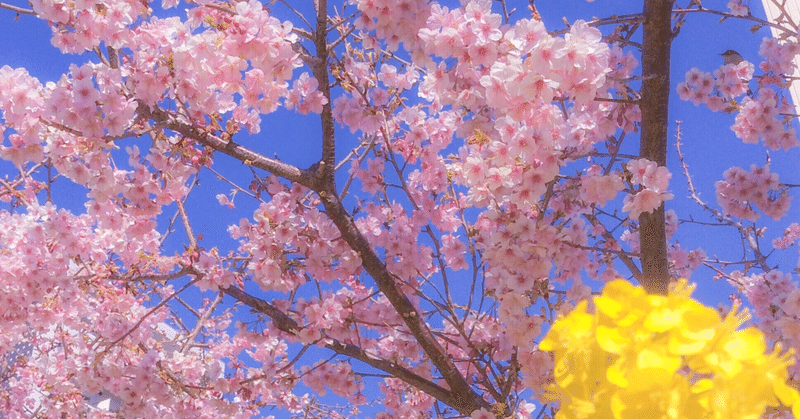#メンタルヘルス
4/29 幸運に納得できる心当たりを作ること
ようやく心と体が落ち着いてきたので、久々に記事を。
最近よく思うのは、良い人間関係の形成のためにできることは本当に少ないということです。
積極的に動こうにも、相手がこちらをどうとらえるかはわかりようがないし、それは相手との距離が遠ければ遠いほどなおさらです。
外出しづらい現状ではとりわけ人とのつながりを感じづらいとも思います。
では何ができるか。
それは自分が人に受け入れられる準備をしておく
2/25 積極的に否定しない習慣
Twitterを見ていると、
「こんなにいい人がいた」という内容、あるいは「こんな嫌な奴がいる」という内容で盛り上がることが多いように思えます。
両者の比率はわかりませんが、前者を賛美し後者を拒絶する。
その源は同じ良心に思えますが、意図というか言葉にしたい感情は異なるように感じられます。
たぶん両者の良し悪しは人工的なものなので、測りませんし測れません。
ただ闘病中の人間としては、後者、要は誰
2/22 自分の内側は自分では変えられない
私の症状は慢性痛です。
時間帯や気分によって痛みの強さや質は変わります。
灼熱感だったり、冷感だったり、チクチクする痛みだったり、痺れに近かったり。
鎮痛剤が効かないため、耐えるしかない。その中で得てきたことを書いていくつもりです。
まず、考え方や意識を変えることで痛みをコントロールすることはできないと思うこと、その必要性について。
自分の内側を自分で変えることはできない。
これが私の前提で