
自分のこれまでを振り返ることは、未来への発射台を確認すること(2024年5月 自分史 4.8万字)
こんにちは、家田佳明です。
40代も中盤に差し掛かるということで、人生の喜怒哀楽を振り返ることで、自分を客観的に眺めてみることにしました。
多様性、グローバル、イノベーション、突き詰める探求心など、小さなころから自分を突き動かしてきたテーマに、改めて気が付くことができました。人生折り返し地点。ここを発射台に、思いっきり飛距離を伸ばしていきたいと思います!
基本情報
家田佳明 1980 年 名古屋市生まれ、名古屋育ち。2004年から東京、2011年からシンガポール、2017年から再び東京。現在に至る
父親 名古屋市出身 東京大学教育学部体育学健康教育学科卒業、イリノイ大学・東京大学修士課程修了、東京大学博士課程単位取得退学。中京大学教授(2023年3月退官)
母親 名古屋市出身 武蔵野美術大学日本画科卒業 専業主婦
妹 7歳年下 マンガ家
0~3歳:東京都三鷹市の都営住宅で過ごす
1980年、名古屋市大須観音近くの病院で生まれました。父親がまだ東京大学の大学院博士課程に在籍中で、両親は東京三鷹市の都営住宅に住んでいたため、生まれてしばらくしたら、私も三鷹に引っ越しました。
その後、3歳まで三鷹で暮らします。さすがにこの頃の記憶はほとんどありませんが、都営住宅の階段やドアの風景、団地の子供が投げた石が頭にぶつかりオレンジ色の薬を塗っていたことなんかが薄っすらと記憶に残っています。
また、保育園の記憶で、ある朝の登園時に、母親と離れるのが嫌で、大泣き。先生に尋ねたところ、おそらくお昼までの登園日だったのでしょう、「お弁当を食べたらお母さんに会えるよ」と言われました。私はクラスから抜け出し、玄関口で、泣きながらお弁当を食べていたところに、先生が探しに来たのを覚えています。「お弁当を食べたらお母さんに会える」と条件付けされたので、「お弁当を食べた」んでしょう。大人は子供にかける言葉に責任を持ってほしいものです(笑)
また、延長保育で母親のお迎えが遅くなり、先生と一緒に職員室で母親のお迎えを待っていたところ、「ケーキ食べる?」と言われ、ご機嫌でケーキが出させるのを待っていたところに、タイミング悪く母親が迎えに来て、とても残念な気持ちになったことを覚えています(笑)
20代後半で初めて東京に住み始めた時、ふと当時の都営住宅が気になって、三鷹までバイクで走り、都営住宅を訪ねてみました。「こんな感じだったかなぁ」と「この階段見覚えがある」(当時の記憶なのかアルバムの写真の記憶なのかはあいまいですが)というノスタルジーを感じました。
幼少期:父親の就職で名古屋に引越
その後、父親が大学の教職に就くことになり、4歳のころに愛知県名古屋市内のマンションに引っ越し、ここから名古屋市周辺で暮らすことになります。こちらでも保育園は楽しく過ごしていて、仏教系の保育園だったのですが、なぜか毎週水曜日にお茶の時間があり、抹茶と和菓子をいただく機会があり、とても楽しみにしていました。
また、年に一回、花まつり・灌仏会(かんぶつえ)という行事があり、お釈迦様の像にひしゃくを使って甘茶を注ぐという経験もしました。このころから、なんとなく宗教や信仰という概念をぼんやりと理解し始めたように思います。
スパルタ将棋始動開始・・・
5歳になったころから、父親から将棋を教わるようになります。これがなかなかのスパルタ教育で、わからないことは怒られないのですが、うっかりミスは激怒されるということで、恐怖におびえながら将棋を指していました。
これがまた、父親が毎日晩ご飯の時間までには帰ってくるので、毎日必ず将棋を指さなくてはならず、マンションの駐車場に車が止まる度に、父親が帰宅したんじゃないか、と心が苦しむ思いをしていました。実際に、小学校5年生で受験勉強を始めるまでは、週に4~5日は将棋を指さなくてはいけず、なかなかに辛い日々でした。
とは言いつつ、自分でも積極的に将棋の本や詰め将棋の本を読んで勉強したりしていましたし、駒落ちと呼ばれるハンデ戦などで父親に勝つとお小遣いがもらえる、などと言った飴も用意されており、それなりに楽しんでいた面もありました。
父親から思えば、「考える力」を養うことを目的にしていたのかもしれません。実際に、将棋は今でも続けていますし、物事を長く考えられる力は、将棋から養われたような気もします。
大好きなおじいちゃん!
ちょうど、この頃、私の人生に大きく影響を与えることが続きます。私には大好きな祖父がいました。東京にいる頃にも遊びに来てくれたり、名古屋に戻ってからは、母親の実家が近かったこともあり、毎週のように遊んでもらっていた大好きなおじいちゃんでした。
晩ご飯では晩酌にビールをよく飲み、イスの上にあぐらをかきながら、オナラをプッ!とすると、「ガハハハ!」と笑う陽気な人でした。おじいちゃんの作る味噌汁は格別においしくて、ナスやらジャガイモやら、適当な野菜をいっぱい入れて作るトン汁のような味噌汁は今でも覚えています。私もたまに料理をしますが、味噌汁なんか何でも入れておけばうまい、と今でも思っています(笑)
おじいちゃんとのお別れ、「死」の理解
そんな大好きな祖父が5歳5ヵ月くらいの頃に他界しました。60代前半だったので、今思えば、だいぶ若くして亡くなったようです。私は、とにかくおじいちゃんが死んでしまったことが悲しくて、悲しくて、悲しくて、お葬式から火葬場までずっと泣いていました。
参列した親族には、お父さんに怒られて泣いてる、と思っていた人もいたようです。この時に、好きな人がいなくなる「死」というものがなんなのか、よくよく理解したように思います。
妹と過ごした暖かい思い出
私が5歳になった頃に、妹が生まれました。妹は生まれた時から病気がちで入退院を繰り返していて、自宅で一緒にいられる時間が限られていました。ある日、入院していた妹が帰宅してきました。両親から、しばらく「一緒に居られるよ」と言われ、「わあ、やっと妹と一緒に過ごせるんだ」と思った記憶があります。
家の近くの公園に、母親と3人で散歩に行きました。大きな池のある公園で、池の水面に、夕日のきらめきがとてもきれいで、暖かく、幸せな気持ちでいっぱいになりました。「母親と妹と、こうして一緒に居られて、なんて幸せなんだろう」と思ったことを覚えています。
人生の方向付けとなった悲しい衝撃
そんなことを思った矢先、ある朝、起きると家に妹がいません。母親に聞くと、「昨晩、亡くなったんだよ」と伝えられました。夜中に息をしておらず、救急車を呼んだが助からなかったそうです。小さい私は、起こすのもかわいそうだと思われ、寝ている間に家から救急車で運ばれていったようです。
祖父の死の経験もあり、死ぬことの意味は理解ができました。「死んでしまうのであれば、家から出る時に見送りたかった。なんで起こしてくれなかったのか」という悔やまれる気持ちでいっぱいになりました。
小学生になって、妹は先天性の遺伝子の病気で、生まれてくる前から長く生きられなかったと説明されました。何万分の1くらいの病気で、普通であれば生まれてくる前に亡くなってしまうような確率であったようです。当時は小さくて説明してもわからないだろうとの配慮で、「風邪で病院にいるんだよ」などと伝えられていました。
祖父が亡くなったのが1985年11月、妹が亡くなったのが1986年2月ということで、短い期間で近しい人の死を経験し、人の死に関する漠然とした悲しさ、というのが刻まれたのかもしれません。
名古屋市郊外で小学校生活開始、片道徒歩45分
ちょうど保育園の年長組の12月頃に、名古屋市の隣町、日進町に引っ越して、最後の4ヶ月間を保育園で過ごした後、そのまま小学校に進学しました。短い期間でしたが、地元の保育園から地元の小学校にそのまま行ったことで、保育園からの同級生がたくさんいて、それなりに友達がいる状態から小学校生活を始められたのは良かったです。
家から小学校がとても遠く、約2.5キロ離れており、徒歩で片道45分かかました。毎日、往復で約90分を歩いて通学するのは、とても遠く感じられました。夏は、帰りに水筒の水が少ないと、帰宅前でに死ぬんじゃないかなどと感じることもありました。そのため、帰り道にあるスーパーで冷やしてある魚の氷を盗んで舐めて帰ったことがあります。今思えば、なんて不衛生なのかと思いますが。
45分も歩いていると、通学や帰宅の途中で便意を催すことがあり、家に帰れない時や登校する時に、間に合わなくて漏らしたこともあります。また、道の外れで隠れて用を足すようなこともありました。
7歳の時に、母親とお風呂に入る時に「妹か弟が欲しいな~」と話していたことがあり、そのお風呂上りに母と父が「妹か弟が欲しいんだって」という会話をしていた記憶があります。それから1年後に妹が生まれ、「自分がリクエストしたからだ!」と思ったことがあります。
短気でケンカの多い小学生
小学校1年生から4年生くらいまでは、あまり大きなイベントはなかったですが、小学校3年生の時に担任の先生が好きだったことを覚えています。それを初恋とは言わないかもしれませんが、そんな気持ちがあったことを覚えています。
小学校4年生の時には、良い担任の先生に出会いました。授業中にうるさいので、毎日のように先生に注意されてましたが、理解のある先生で、カラッと注意してくれるので、自然と受け入れられました。
母親の観察によると、自分がうるさかった・落ち着きがなかった原因は、集団登校の人間関係にストレスあったのではないか、ということでした。行きも帰りも集団登校する小学校だったんですが、自分の学年には一人しかおらず、その一つ上の学年に4人、その4人の弟が僕の一つ下の学年に4人いるという構図になっていました。
その兄弟と一緒に通学していて、地元で遊びに行く時もその兄弟たちと遊ぶことが多かったのですが、遊んでいればたまにケンカになることもあります。ただ、弟たちと遊んで、ケンカになった翌日に、兄たちから集団で仕返しをされたりすることが結構ありました。
自分の学年は一人しかいないんですが、上に4人、下にも4人という状況で、結構複雑な関係の中で立ち回りながら生活していました。自分も力が強かったし、負けん気が強かったので、ケンカになったら、普通にやりあってました。
そういう乱暴な生活をしていましたが、それも含めて楽しい思い出かなと思います。ただ、集団登校の友達以外でも、日常的にケンカが多く、短気でケンカっぱやい自分に、なんとなくいい感じはしていませんでした。
このあたりは1つの事象に理由を求めるのが難しいですが、厳しい父親との関係がすごくストレスで、それが外に悪い形で発露していたのかもしれません。
好きなことは徹底的に調べる
小学校4~5年生くらいに、横山光輝の三国志をきっかけに三国志にすごくハマりました。三国志演戯・正史を読んで、登場人物の名前とかキャラクターとか、歴史とかをたくさん調べ、覚えて喜ぶみたいなことをやっていました。
一番好きだったキャラクターは諸葛亮孔明でした。思慮深く、知略や戦略に長け、自軍を勝利に導く天才軍師の孔明はとてもカッコイイ存在でした。諸葛亮孔明みたいになりたかったです(笑)
それから、日本史の勉強をしていく中で幕末時代が好きになって、もともとは小山ゆうの「お~い、竜馬!」のマンガの影響で、新選組がすごく好きになって、新選組のこともたくさん調べたり本を買ったりとかするようになっていました。母親にお願いして、京都の太秦映画村にも何度も行きました。
あと、自分を象徴的に表してるなぁと思うのは、この頃に缶のお茶を飲んで調べることにハマっていて、自分なりに5つの軸でレーダーチャートを作って評価をしていました。お出かけして、自販機を見るたびに、見たことがない缶のお茶がないかなということを探し、味を確かめて、レーダーチャートでスコアを記入して、自分の評価を書くみたいなことをやっていました。
そのリストが30缶ぐらいになっていて、当時は自分が日本で一番お茶の缶に詳しいんじゃないかと思ったりしていました。新しいお茶を見つけて、自分の感覚をデータで可視化して、比較評価をするプロセスはとてもおもしろかったです!ちなみに当時一番美味しいと思ってたのはサントリーの烏龍茶でした。最近見かけないですね。
中学校受験開始
小学校での成績はまあ良くて、だいたいオール3段階ほかのオール3みたいな感じでしたが、落ち着きがない、授業中に騒がしい、ということを書かれるような通信簿でした。
小学校5年生の夏頃から中学受験のために塾に通い始めました。最初に通い始めたのはなんとなく親の勧めでぼんやりと通い始めたような気がしています。塾は塾で友達ができて、みんな中学受験をするんだっていう目的意識を持って参加をしているので、それはそれでコミュニティができて、なんか目標に向かっているところもあって楽しく過ごしてました。通い始めた頃は真ん中ぐらいの成績だったんですけど、6年生に入ったら一番の上のクラスで安定していました。
小学校では、6年生の頃に、4年生の頃と同じ担任の先生についていただいて、相変わらず私が授業中に騒がしいので、忍耐の「忍」という文字を紙に書いて机の上に貼られ、授業中に雑談したりして話していると、「家田くん、忍耐。忍、忍。」と言うことを、毎日のように言われてました。
この頃は、塾で一番上のクラスに行ったこともあって、小学校の勉強は全部知っているみたいな感じで、実際に小学校6年生のテストは全部100点満点でした。学校の勉強はめちゃくちゃ簡単。塾で勉強して、小学校で遊ぶ、みたいな生活になってました。
家庭環境が学業に与える影響を考える
この頃に思ったことがあるのですが、自分には100点を取って簡単すぎるテストなんですけど、隣の席の友達が同じテストで0点とか取っていって、なんでそういうことになってしまうのかってところをちょっと理解ができませんでした。「0点ってどうやって取るの??」という感覚です。
ただ、そういう友達って家庭環境もなんか荒れてるというか、なんかそういう雰囲気がある家庭が多く、例えば、いわゆる母子家庭だったりで、お母さんは稼ぎを得るためにスナックで働いてますみたいな。なんかちょっとそういう不安定な家庭環境や、親の影響や生活環境とそういった成績みたいなものは、一定の関係が出てしまうのかなぁと思いました。
あと、0点って、本当に何もわからないという状態だなと思うんですけど、当然それは積み重ねというか、わからないことが雪だるま式に積み重なっているんだろうなと思ったんですけど、こんなに差が出ちゃうのかなというふうなことは思ったことを覚えています。
自分が育つ環境と自分の進路を考える
家庭や受験のストレスなのか、大なり小なり毎日ケンカをしていて、学年が上の先輩でも構わず結構ケンカをしてました。小学生では身体が少し大きい方で、力も強かったので、あんまり負ける気もしてないし、負けん気の強さもありました。
6年生のある日、登園時間に遅れてしまい、1人で小学校へ通っている時に、一つ上の学年の中学生の先輩に、道でばったり出会いました。その人は小学校で顔見知りで、ケンカしたこともある少し小柄の人だったんですけど、久しぶりに会って、声をかけられて「お前覚えてるぞ。お前中学に来たら絶対にいじめてやるからな」みたいなことを言われました。
なんかこのまま地元の中学校に行くと、毎日ケンカしちゃうような関係が、中学生に入って上下関係とかを厳しくなりもっとエスカレートしてしまうんじゃないかなあっていう印象を強く受けました。
それで、どうやら地元の中学校にこのまま行くとあまりいい環境ではなさそうだなぁと思われて、これは何が何でも第一志望の私立中学に行く方が良さそうだと強く思いました。
めちゃくちゃ厳しい父親の影響
家庭のことに話を戻すと、幼少期から小学校時代を通じて父親がすごく厳しかったのは、自分に大きな影響を与えているなと思っています。父親が論理的思考力が強く、研究者であることもあって、怒るにしても根拠に基づいて怒りました。
かなり短期で怒るときは激高することも多く、理屈で説明されつつも激怒されるみたいな感じでした。ちゃんとしてなくちゃいけないみたいな価値観が生まれたんじゃないかなと思います。
例えば、小学校低学年の頃に、家族旅行でお城を見に行ったんですけど、金色のお城に温度計がついているような小さな土産物がありました。その時に祖母と一緒に旅行に行っていて、祖母から「何でも買っていいよ」と言われていたので土産物を買おうと思ったら、いきなり後ろから頭を叩かれて、父親から「そんな物、家に持って帰っても無駄になるだけなので買わなくていい」って怒られるみたいな話がありました。
ゲームボーイ事件
あとは、4年生ぐらいの頃だと思うんですけど、「ながら」で色々やるなと言われていて、例えば、ゲームボーイをしながらテレビを見ちゃいけないと言われてました。まあそうは言っても、ついついやってしまっていて、見つかって、怒られるというのを何回か経験してました。何回目かに怒られた頃に、これまたやってると怒られるなと思い始めて、父親は車で家に帰ってくるんですけど、父親の帰宅に気がついたら、ゲームボーイを切るということをしていました。
ある時、電源を切ったゲームボーイを自分の手元に持って、テレビを見ていて、父親からまた怒られたので、自分では意識して電源を切ったこともあって、「電源、電源切ってるわ!」と思わず強めの口調で言ったんですけど、もう即座に「親にどういう口の利き方をしてるんだ!」と激怒され、思いっきり叩かれました。
それだけだったら良かったんですけど、その日の夜、9時か10時頃に布団に入っていたら、階段をすごい勢いであがってくる音がして、父親の怒りがまだ残ってて、布団の上から蹴られるみたいなことがありました。そんなことが日常だったなぁという記憶です。
受験勉強も父親の指導がめちゃくちゃ厳しい
受験勉強でも父親の影響がだいぶあって、うっかりミスをするなという方針がすごく強かったです。父親曰く、受験というのは成績の分布がベル曲線になるので、合格点の前後の受験生が一番のボリュームゾーンになる。実際の合否というのは本当に1点が合格を受けるということでした。
なので、例えば計算間違いや漢字の書き間違いみたいなものをとにかくしないという指導を受けました。計算間違いをしないためには、全部の答案を早く解いて見直しをすることが大事です。算数のテストは必ず最後の10分間で、すべての問題を見直すように指導されました。
それから見直す時に、筆算の検算をするんですが、その検算の確認をスピーディーに正確にやるために数字をはっきり、見やすく書くことを徹底するといった方針がありました。テストがあると、父親に全部の答案をに見せなくちゃいけないんです。回答用紙だけじゃなくて、問題用紙も、全部見せなくちゃいけなくて、筆算をどういう風に書いたかも全部見せなくちゃいけません。
計算ミスが無いことを祈るテスト結果
仮に正解をしていても、数字が綺麗に書かれていないと、怒られたり、計算間違いがあったりすると激怒されました。塾の模試でも何でも、テストをが返ってくる時に一番願うのは「計算間違いをしていないで欲しい」ということでした。回答がわからないのは仕方がないんですけど、うっかりミスをするなというのは結構徹底的に言われました。結果的には、それ自体は正しいなと思ってました。
また、塾の先生からは受験前日はしっかり休んで、本番に備えるようにと言われてました。受験勉強の追い込みで猛勉強していたので、ようやく前日になって、「これで明日に向けて休める」と思っていたのですが、朝起きてきた父親に、「算数や国語は明日、成績は急に伸びないけど、理科や社会は覚えればいいんだから、何なら今日覚えたことは明日役に立つんだ」と言われ、比較的苦手だった社会を朝から夜までかかって問題集1冊全部解きました。
初恋&失恋
小学校の同級生で同じ塾に通っていた女の子に初恋をして、小学校6年生くらいの頃からだったと思います。でも、塾の中では半分男友達みたいな感じで、今更告白すると言う雰囲気でもなかったんですが、小学校卒業して学校も変わってしまうので、なんかそういう思いを伝えたくて。
思い切って、塾の近くの公衆電話から電話をしたんです。好きだとは伝えたんですが、「まあ、ありがとう」みたいな感じで、その先があるような雰囲気じゃなかったです。めちゃくちゃ緊張して、好きだと伝えるのに精一杯という感じの甘酸っぱい小学生時代の思い出です。今思い返すと、お茶か映画でも行こうよみたいなところから始めればよかったんじゃないかと思いますが(苦笑)
中学・高校:刺激の多い中高一貫の男子校
1993年に私立中学校に入ります。中高6年一貫の男子校で、入ってすぐに小学校と比べると、周りの人たちが一変して、自分自身が短気で起こるような反応をしなくなったので、喧嘩がまったくなくなって、これは本当に良い選択をしたなと思いました。
僕は中日ドラゴンズが大好きだったので、野球部に入りました。ちょうどJリーグ元年とスラムダンクがすごかった年で、一学年400人の学校で、野球部に入部した部員が40人だったんですが、サッカー部とバスケ部は60人ずつみたいなすごい時でした。
文化祭:新選組のクラス発表
中学校入ってからは結構本も読んでいて、シャーロック・ホームズがすごく好きになって、シリーズを全巻読破したり、新選組は引き続き好きでした。古本屋なども含めて探すみたいに、関連書籍を40冊近く集めました。例えば、1番隊から10番隊までの隊長から隊員の登場人物やその特徴を調べていました。
極めつけは中学校2年生の文化祭で、自分のエゴを出しまくりのテーマをゴリ押しして、「新選組」をクラス発表のテーマに採用してもらいました。幕末好きが高じてテレビの時代劇が好きだんたんですが、「文化祭でチャンバラ激をやったらおもしろそう」ということで、新選組にまつわる重要なエピソードをチャンバラで発表するというコンセプトを考えました。クラスで劇を披露するというアイディアが新しく、文化祭で特別賞も取りました。
ギターとバンドを始める
中学校に合格して以降、父親からは勉強しろということを一切言われることがなくなりました。父親が趣味でバンドのボーカルをやっていたんですが、家にアコースティックギターとエレクトリックギターがありました。小学校でピアノを習っていたんですが、ピアノはもうやめて、ギターをやってみたい、かっこいいなと思って、中学校1年生からギターの練習を始めました。
中2から何度か文化祭でバンドの演奏をしました。中学校2年生の頃に、バンドでドラムをやっているメンバーと同じクラスで、すごく仲良くなって、お互いに家に泊まりに行ったりして、僕はその友達のことがすごく好きで、学校でも話し、家に帰ったら電話で話すみたいな関係でした。
すごく話も聞いてくれるし信頼している友達だったんですが、ある時、そのドラムの友達が裏で、「あいつ、うぜえ、しつこい」と言っているっていうことを聞いて、裏切られたというか、「うーん、そんな風に裏で言われちゃうのか」みたいな感じになった覚えがあります。
中2から合コン
男子校だったので、普段のつながりではあまり出会いとかないんですけど、受験勉強の塾の友達が、男子校に行ったり、女子校に行ったりすることもあって、塾の知り合いつながりで女子校とつながって、中2から合コンを始めました。2つ3つくらいの女子校と繋がりを作って、カラオケ行ったり、出かけたりしてました。麻雀とか競馬を覚えたのも中2くらいだったかなと思います。
全体的には野球部中心で、勉強も大してせず過ごしていました。野球の素振りを毎日欠かさずやっていて、それこそ元旦から大晦日まで毎日最低100回は素振りするぞって、取り組んでました。
先生に挑戦状
中3になってくると、なんかもう学校にも慣れちゃって、男子校で勢いもあるし、頭の回転が早い同級生の集まりだというのもあって、小バカにしてる先生もいました(苦笑)中3の時の木曜か金曜日だったと思うんですが、5~6時間目は2つとも先生甘かったので、授業中に後ろの席ではカードゲームをしたり、古今東西とかしたりして、負けた人が学校の外に飲み物を買いに行く、みたいなことをしてました。
それから、ムカつく先生に反抗するみたいなことを結構やってて、男子校なんでそういうノリがあるんですが。当たり前っちゃ当たり前なんですけど、学校にマンガを持ってきちゃいけない校則があって、私立で越境で通ってる人がほとんどなんで、まあいわゆる週刊漫画、週刊誌ジャンプとかマガジンとか通学中に買って読むってのも普通でした。
僕はお小遣いがもったいなかったんで、自分では買ってなかったんですけど、持ってきている友達がいるので、回し読みとかさせてもらったりしてました。そういうのを当然先生も知ってて、ある特定の先生がたまに抜き打ちで「持ち物検査だぞ」と言ってマンガを没収していくみたいなことをやってたんです。
それに結構ムカついてて、ある時仕返してやろうと思ったんですが、ある物理の先生の授業の前に、少年ジャンプを自分の教室の中に3冊隠したんですね。それで、黒板に「この教室にジャンプが3冊隠されてる。この時間内に探してろ」、みたいな挑戦状を書きました。結局、その先生は挑発に乗って、授業をせずに、1時間ずっとジャンプを探してました。どっちかというと、なんかやり返したかったというよりは授業を潰す口実になるびで、それが面白いからやっちゃうみたいな感じでした。
それから日本史の先生。まあ日本史っていう科目自体、あまり重要視されたいかもっていうのがあるかもしれませんけど、先生が学期の中で授業のコントロールを上手くやっていて。その先生が釣りが好きなんで、授業の開始の時に「先生、週末の釣りどうだったんですか?」って聞くと、「いやー、それがよく釣れてさ」という感じで釣りの話が始まって、日によっては1時間釣りの話をして終わるみたいなこともありました。うまいことどうやって釣りの話を引き出すか、みたいなことを考えてました。
成績は低迷の中学・高校時代
当時、ビジュアル系バンドが全盛期で、GrayのTeruのストレートヘアが流行ってました。ストレートの長髪みたいな髪型が流行っていて、もともと結構天然パーマなんですけど、僕も爽やかになりたいなと思って、ストレートパーマをかけたんですが、髪の毛ペッターンって感じで大失敗。この時に爽やかさというものとは縁がない人生だと悟りました(苦笑)ちょうどこの頃にポケベルなんかも持ち始めました。
そんな感じで中学生は健やかに過ごしつつ高校にエスカレーターで進学します。入学した時は真ん中ぐらいの成績だったんですけど、勉強をしてなかったので、順調にどんどん下がっていきました。中学は400人なんですが、高校から外部受験で50人入ってくるんですが、もともと下の方だった成績がきっちり50番下がって、450人中400番台という安定の定位置になりました。
唯一英語だけは少し自信があたんですが、高1のテストで英語のテスト6点を取って、いよいよやばいなと思いましたが、あんまり勉強する気もなくて、変わらない生活をしてました。この頃は、特に何向かってるっていう感じじゃなくて、学校の同級生とワイワイガヤガヤやったり、その間の狭い世界でイケてるイケてないとか、イケてないと思われたくないみたいなことをやってました。
うまく行かなくても「とりあえずやってみる」と意識でがんばる
野球部でそのまま中学の野球部から高校の野球部に行って外野手をやったんですけど、何式野球か硬式野球に変わったタイミングで、なんかこう打球の飛んでいく感覚がちょっとわからなくなってしまって。野球って、打者が打った瞬間に、ボールの着地点を予想して、ボールが着地するゾーンに一歩目のスタートを切るのが大切なんです。
それが、ボールが軟式から硬式に変わったことで、その打った瞬間の飛んでいく距離の予測みたいなのがうまくできなくなってしまったんです。進学校だったので、もともと大してで野球が強いわけでもないんですけど、自分なりにできたものができなくなってしまたこと、やる気がなんかちょっと減ってきて。なんだったら野球やめて別のことしようかなと、冬休みに当時K-1が流行ってたんで、極真カラテの道場に見学しに行ったりしました。
そうこうしてるうちに、練習中に、2つ上のキャプテンにぶち切れられて、「上手にできないとか、うまくいかないとか、始めたばっかりのくせしてそんなこと言ってんじゃねぇ。一生懸命やれよ!」と言われて。それで気持ちを切り替えて一生懸命やってみようかなと思ったら、また上達してきて、感覚を掴め直したら、そこから昔のようなパフォーマンスが出せるようになって、また野球に打ち込み始めるみたいなことがありました。
男子校育ちで女の子との付き合い方が下手くそだった高校時代
この頃からポケベルからPHSに変わり、友達とか女の子とかと連絡が取りやすくなりました。高2の時に初めて地元友達の紹介で彼女ができて、でもなんか1ヶ月ぐらいでうまくいかなくなっちゃって。自分が経験なさ過ぎて、振られた感じです。それから、友達の紹介で会った女子高の女の子が可愛いなあと思って、良い感じになるといいなと思っていました。同じ通学路の人で、電車が一緒になるといいなとか思ってたんです。
初めて会った1~2週間後くらいに、通学途中に女の子に会ったんです。たまたまその時に自分の同じクラスの友達で結構モテる友達がいて、その彼も同じ通学の方向だったんで、その日の朝は待ち合わせをして一緒に通学をしてたんです。それで、イケメンなモテる友達と一緒に通っていたので、その知り合った女の子とすれ違って目線があったんですけど、後ろにいる友達を紹介しちゃうと、そっちの方の友達に気が行っちゃうんじゃないかなと思って、目線があったんだけど気づかないふりをしちゃったんですよね。
それで、向こうは目が合ったことに気づいていて、無視された、気づいたのにシカトしたっていう風に受け取られてしまって。そこで一気に印象が悪くなり、その後何も起こらないみたいなことがあって、まあそれも今思い返すとは淡い思い出というか、やっぱり男子校で6年間、女の子と日常的に話す機会が無かったから、女の子との接し方・付き合い方とか上手じゃなかったなって思います。
偏差値42からの大学受験
高3になって、流石にそろそろ受験勉強みたいなことを意識するようになったんですけど、河合塾の模試を3月か4月に受けたら、偏差値が42しかなくて、さすがにこれはやばいと感じました。1学期に三者面談があって、その際の担任の先生からは、「二流大学か浪人だからまずは全力でやれ」と言われ、「まあ、そうだよなー」と思って、野球がんばろうと決めました。
幸い、進学校だったので、高2までで全ての授業が終わっていて、高3から授業の総復習が始まりました。論理的には、これから全ての授業を理解すれば、現役でも間に合うという考えで、中学に入って以来初めて授業を聞こうという気持ちがわきました。高3は、とにかく学校にいる間は授業を一生懸命聞くということをやりました。
一方で野球をずっとやってきて、最後の夏でもあったので、一学期中は一生懸命練習をしてました。やっぱり練習で疲れちゃって勉強もできないので、家に帰ったら毎日1時間だけ英語の勉強をするというふうに決めて、英語の勉強をしていました。まあ、それだけ情熱を持った野球だったんですけど、最後の甲子園予選は第1試合でいきなり負けてしまいました。夏休みが始まって7月下旬が終わり。翌日に部活の同級生全員と集まって最後の打ち上げをして、翌日からはもう受験準備をするという風に切り替えました。
毎日勉強する時間管理をした方がいいなと思って、主要5教科のうち3教科を3時間、2教科を2時間勉強する、具体的には英語と数学を3時間ずつ、国語と理科、社会はローテーションで、毎日13時間勉強するという形にしました。1教科3時間の最大パフォーマンスを保つために、3時間集中すると何ページ問題集を解くことができるのか、っていうのを測って、その最大限集中が続くページ数を毎日こなすっていう感じでノルマを設定して、ひたすらそれをこなし続けるってことをやっていました。
で、ある時13時間いけるんだったら一体何時間くらいまで勉強できるんだろうと思って、勉強の時間数を15時間まで拡張したことがあって、その時はちょっとさすがに3時間かける5教科は精神が崩壊しそうになって、持続するには13時間ぐらいが適正だという風に調整をしました。
それくらい勉強を一生懸命やってたんですけど、現役でどこまでいけるかは分からないと思ってました。自分が受験した中学校が偏差値68だったので、偏差値68ぐらいまでであればたどり着ける領域にあるんじゃないかと。
一方で、小学校の時に理科だけちょっと偏差値が神がかっていて、偏差値が78とか80ぐらいあったんですけど、その領域になるとやっぱり相当深く勉強しないとたどり着けない領域だなという感覚があり、一旦、現役時代は偏差値68ぐらいを目指せるところにしようというところで、地元の大学の経済学部を目指すということで志望校を設定しました。
私立大学に行くって選択肢もあったんですが、一旦現役時には、高2までは理系で数学も全部やってたこともあり、理科も物理選択で数学みたいな感じで解いて、あんまり抵抗もなかったので、現役時代は5教科で行こうということで、国立をメインに勉強していました。
認知行動科学と学習計画
父がたまたま大学院時代の専門が認知行動科学の領域だったので、ある時、父との雑談で、自分の受験勉強の方法をどういうふうに取り組んだのかということを聞かれました。受験勉強における目標設計や学習計画の取り組み方を説明したのですが、これは認知行動科学の観点からすると、とても良い目標設定の仕方をやっていたようです。
認知行動科学によると、目標設定は、簡単すぎてもダメで、難しそうでもダメ。最大限に努力するとギリギリ達成できるラインに目標設定すると、モチベーションが最大限に引き出されるとのことでした。簡単すぎる目標はできてしまうので、やる気がでない。難しすぎる目標は、目指しても無理なんで諦めてしまう。なので、ギリギリのラインが大事だと。振り返ると、私はいつも自然とそういう目標設定をする傾向があるなと思いました。
大学受験と文化祭のバンド
中高の文化祭で何度かバンドで演奏をしていたんですが、高3の夏休みに友達から、「最後の年だからまたやろうよ」と誘われて、勉強が忙しかったんですが、やりたい気持ちに気が付いて、最後の文化祭でバンドをやることを決めました。2学期が始まってからは帰宅後毎日7時間勉強すると決めて、勉強の後1時間、ベースの練習をして寝るという生活になりました。安請け合いするんじゃなかったと後悔したこともありましたが、同じ学園グループの女子高で演奏させてもらう機会ももらえたり、バンドの仲間と高校生らしい最後の思い出もできてがんばって良かったなと思います。
大学の進路検討
少し話がそれますが、進路や学部選択について、もともとなんとなく理系選択で、将来は建築家とかいいなとぼんやり思っていたことがありました。建築ってかっこいいし、アーティスティックな雰囲気があって、かっこいいイメージがありました。ただ、高校2年生の頃に、大学の進路について父親と雑談していた時に、父親自身がもともと工学部で大学に入ってたんですけど、3年生になるタイミングで教育学部に転部したそうで。
その理由が、毎日実験室で実験する生活が、自分には合ってなかったということで、「お前は、そんな毎日実験、実験みたいな生活は合うのか?」っていう感じで聞かれた、それはちょっとイメージと違うなぁということで、理系に行くのはやめて文系にした経緯があります。
文系に進路を変更して、大して成績も良くないし、将来の仕事を考えたときに、現実的に入れそうな大学と言うことで、教育系の大学で、小学校とか中学校の先生になるのもいいんじゃないかなと思いました。自分が小学校4年生と6年生で担任してもらった先生の印象が良かったので、小学校か中学校のの先生もいいじゃないかなと思ったんです。
でも、実際どういう職業なんだろうかと調べたり、ドキュメンタリーを見たり、近くに小学校の先生をしている人がいたので話を聞いたりしたんですけど、すごく大変な職業ということがわかりました。給料もそんなに高くないし、部活動を引き受けたら業務時間は伸びる。でも、部活動に残業代はつかないとか。
中学校の先生なら、担当している子どもが非行で警察に補導されたら、何時でも警察に行かなきゃいけないとか。そういうリアリティを見てみると、「いや、これは大変な職業だな」と思って、あんまり自分がやるイメージがわきませんでした。
同じ中高・部活で過ごしていて勉強の出来・不出来に差が出るのはなぜなのか?
そんなことを考えながら、同じ野球部の同級生で学年1位とか医学部A判定みたいな友達が何人かいて、中高6年間、同じだけ野球をやっていたはずなのにこんなに成績に差ができるんだろうかということを考えました。結論はすごくシンプルで、友達はちゃんと昔から勉強して、準備をしていて、僕は準備をしていなかったということでした。
その時点で成績が悪く、遅れてことは取り戻せないので、逆に大学の間ではしっかり勉強をして、社会に出る準備をするといいんじゃないかなと思いました。経済系でより実践的な経営学を勉強できることがいいんじゃないかと考えました。それで、自分のレベルで志望校を考えると、名古屋大学経済学部経営学科が一番いいかなというところで、第一志望に決めました。一橋大学とか神戸大学の経営学部はちょっと成績が届かないかなと思い、現役が難しく、浪人に進むなら志望校をあげようと考えてました。
第一志望にギリギリ合格の大学受験
とは言え、名古屋大学だとしても、偏差値が全然届かず、ずっとE判定でしたが、センター試験で初めてC判定が出て、ギリギリ現役で合格できました。また、もともと志望校を一本に絞ってたこともあって、東京の大学は1校も受けず、滑り止め的な感覚で関関同立から、関西大学、関西学院、立命館の3校で、かつ受験会場に名古屋を選択できる学部で選びました。また、試験科目を英語、数学、現代文で受けられるに絞ることで、3校とも全部合格して、結果、現役で受けたところは全部受かって、第一志望の名古屋大学に入りました。
心の琴線に気が付く出来事
高校時代の一つの思い出として、1997年に神戸連続児童殺傷事件という事件がありました。その報道が連日ニュースで出たんですけど、その報道が始まるとすごく悲しい気持ちになって、ニュースを見ていると自然に涙が出てきてしまうので、ちょっと耐えられなくて、番組を切り替えるということが何度もありました。
周りの家族や友人を見ていても、そこまで強い反応を持っている人はなかったんで、この心の動きは何だと、なんで自分はこんなに感情に触れるんだろうとを考えていて、小さな子供が殺されてしまうみたいなことが、5歳の時に体験した妹の不幸と重なっていたんだと気が付きました。5歳の頃の記憶自体はおぼろげなんですが、その影響が自分の心の深いところにとても強く残ってるんだなという自覚が生まれました。
始まりもしなかった大恋愛
少し余談ですが、高3の頃に通っていた自習室みたいなところがあって、女子高に通うの女の子出会いました。その子には彼氏がいることを知っていて、その彼氏とは別に通っていた塾が同じで、お互いに面識ができて、一緒にご飯を食べに行くようなこともありました。とても良い人で、志望校も同じところを目指していたので、大学に行ったら一緒に友達になれるといいなと思うほどでした。
その2人は長く付き合っていてたのですが、受験勉強をしている間は、お互いに受験に集中するために、あまり会ったりしないようにしていました。僕はその彼女と自習室で毎日のように顔を合わせて、同じ教室で勉強をしていたので、自然と仲良くなっていきました。最初のきっかけは、なんだか彼女から好意みたいなものを感じるなと思ったところからでした。
でも、彼女には彼氏がいるし、僕もその彼氏のことが友達として好きで、2人の関係が長く続いて欲しいと思っていたので、この好意みたいに見える発言や行動は自分の思い違いなんだろうと思ってました。自分が彼女の好意の対象になりえるという考えがすっぽり抜けていたのに近いです。ただ、あるとき、自習室の他の友達と話していて、「XXちゃんは、君のこと好きだと思うよ」と言われてから、急に意識してしまいました。
そう思うと、自分も急速に好きな気持ちが高まってしまい、片想いなのか、微妙な両想いなのか、と言う期間がしばらく続きました。結局、彼氏との関係もある中で、やっぱり自分は付き合うことができないなと思って、ある時、「好きだ」ということだけ伝えて、それでおしまいって決めました。
自分の中でを整理したつもりだったんですけど、やっぱりそれがすごくストレスというか、心理的には深かったみたいで、自習室のトイレで過呼吸になるということがありました。その子とは、向こうが気を使ってくれて、その後、急速に疎遠になりました。その子は私立中学で付属の私立大学に行くことがほぼ決まっていたので、受験勉強が本格化する終盤戦の頃にはあまり自習室に来なくなりました。
アメリカンフットボールに打ち込む大学生活
大学に入ったらオシャレなアパレルショップでバイトして、留学して英語の勉強をするなどと思っていたんですが、いざ入学する頃には、なぜかやっぱりなんかスポーツをやりたいと思い、いくつかの部活を考え始めました。高校まで野球をやっていたので、最初に野球部は考えたんですが、たまたま大学の同期入学に愛工大名電という野球の強豪校で、甲子園に出場したエースピッチャーが入ってきていました。
そんなエースプレーヤーがいたら、勝っても負けてもその人のおかげみたいな雰囲気になるだろうなと思ったのと、中高6年間野球をやってたので、大学を卒業してからでもできるかなと思いました。あとはアメフト部の先輩がすごく真剣にスポーツをやってるなというふうな部に見えて、大学でしかできないスポーツということでアメリカンフットボールを選びました。
「大学に入ったら勉強して社会に出る準備をするぞ!」ということを思ってたはずなんですけど、実際大学が始まってみると講義がとても退屈でした。私が行った経済学部はあまり授業の出席を取らず、期末テストだけ点数が取れれば単位が取れるということで、パラダイス経済と呼ばれていて、結果的に授業はほとんど出ず、部活と友達と遊ぶことだ大学生活の中心になっていきました。
学部の同級生と熱く語る
この頃に、同じ学部ですごく仲の良い友達ができました。今でもずっと仲の良い男10人グループで、ほとんど男子校みたいなノリでした。大学に行くと、だいたいその友達の誰かがいるので、講義室には行かず、学生控室みたいな溜まり場に集まって何かだらだら喋ったり、外でフットサルしたりとか、そんな感じで生活をしていました。
その友達との思い出で、いまでも印象的なエピソードが1つあります。商業高校から高校在学中に簿記一級を取って、AO入試みたいな感じで入学してきた友達がいました。彼は、佐賀県出身で、公立の中学校から商業高校に行き国立大学に来ていました。僕も同じ大学に通っていたわけですが、友人は実家がそれほど裕福ではなく、僕はいわゆる中流ちょっと上かなという家庭で、私立の中学高校に行って、という違いがありました。
その友達から、「私立の中高一貫のやつと、田舎の公立で上がってきたやつとは価値観が違う。お前とは一緒に一生親友になれる気がしない。」とか言われたんです。僕はその友人のことをすごく好きだったし、友達だと思っていたので、そんな風に価値観が違って、物の考え方が違うんだなと思いました。自分が好意を持つ人でも、同じように好意が持たれるわけでもなかったり、体験によって価値観が変わったりすることを理解しました。その友達とは今でも仲良くて、親しくしています。
善く生きる(ソクラテスの弁明)
そのグループの中の友達といろんな話をしましたが、その友人の1人からの勧めで哲学の本もよく読んでいて、その中の「ソクラテスの弁明」で、「私たちはどのようにより善く生きることができるのか」という問いがあって、「どうせ生きるからにはよく生きたい、よく生きたと思える人生を歩みたい」という風に考えるようになりました。実は、通っていた中高の校訓の1つに、「平和日本の有要な社会人となりましょう」という言葉があり、それとも重なって、「自分は何のために生きるのか、よりよく生きるために何をするか」という価値観が形成されていったと思います。
また、その価値観に関連して、その友達たちと、「自分の誰かにとって何かをしてあげたいという気持ち」とか、そういった「人の役に立つ」とか、「そういった考えそのもの自体が偽善」なんじゃないかという思いを悩んだりするようになりました。つまり、「誰かの役に立つとか人のためになる」ということは、「周り回ってそのような行為をしている自分というのが周りから評価されたり、そうである自分のことを肯定したい」みたいな、そういう思いから来ているんじゃないかなというふうに考えていました。
言い換えると、「その利他的行為の内側に利己的な思いが存在していないか」ということです。人の役に立ちたいとか、誰かのために何かをしたいという時に、これは偽善なんじゃないか、ということを考えたり悩んだりしていました。
善か偽善の思考実験
頭の中でこんな思考実験もしていました。世界のどこかに2000万人ぐらいの人が飢餓で死にそうになっている。神様が僕のところに来て、「お前が右腕を失えば、その2000万人の命は救われる。ただ、お前が右腕を失ったことで、2000万人の命が救われたということを、その2000万人も、世界の誰も知ることはない。右腕の失うか?」という問をするというものです。
僕が2000万人の命を救う代わりに、生涯を持って過ごすことになるみたいな選択がある時に、自分の右腕と2000万人の命を天秤にかけてどんな決断ができるんだろうか、その時の自分の決断に利他と利己がどう表れるのか、ということをく自問自答して、一人でずっと考えていました。
チーム再建に挑戦したアメフト生活
大学時代に主に取り組んだことは、4年間過ごし、最終学年では主将を務めたアメリカンフットボール部です。本当に全力で取り組んだアメフトでしたが、最初からやる気が100%であったわけではありませんでした。練習は痛いし、体力的にもきつい。終わった後には1時間くらいビデオレビューがあって、拘束時間もとても長い。そもそもルールが難しくてさっぱりわからん。ということで、全然やりたくないと思っていました。

ところが、僕が所属したチームは、私が入部する4年くらい前に東海1部リーグから2部リーグに陥落してしまい、そこで一気に部員が辞めて、すごく部員数が少なくなっていたんです。なので、1年生の秋からもう試合に出なきゃいけないみたいな状況でした。クォーターバックという、野球で言うとエースみたいなポジションをやっていたんですが、1年生が終わって4年生が抜けると、部員数がもう本当に極限まで少なくなり、試合開催最低人数の11人しか在籍していな危機的状況になりました。
そもそもアメリカンフットボールは試合中の先週交代が無制限なので、チームの人数が多いほうが有利です。最低30人ぐらいいて、できればオフェンスとディフェンスでメンバーを入れ替える状態にできれば、試合中の選手の体力やパフォーマンスも持続できるわけです。なので、11人でやるのは相当無謀です。そんな状況かつ、自分は中心的なポジション務めていて、「もはや辞める」と言えない状況になっていました。変な責任感なのか、辞め方が分からない、切り出し方がよく分からないみたいな感じで、なんとなく辞めると言えずに2年生のシーズンが始まってしまいました。
ただ、この新しいシーズンから、自分の人生の大きな影響を与える経験が始まります。シーズン開始の最初のミーティングで、2つ上の4年生のキャプテンが、「今までのような少数精鋭では勝てない。今年は1部リーグ昇格を狙わない。その代わりチームの目標を、シーズンが終わる頃に新入部員が20人残っている状態を作る。」と宣言をして始まりました。
これはすごく大きな決断で、学生スポーツをやっていく中で上位リーグ昇格を目標にするのが当たり前ですが、その先輩は自分の代で1部リーグに上がるのは諦め、代わり人数を増やすことを最大の目標にしました。監督とかコーチもその方針で納得させ、とにかく人数を集めるということにチーム最重要目標に置いたんです。それが自分にはものすごい決断だなと思いました。
その方針をもとに、春の入学シーズンは練習量を減らしてでも勧誘を頑張るということを決めました。私は勧誘の中で中心敵な役割を取りに行って、やると決めたら徹底的にやろうと、システマチックに新入生にたくさん声をかける、連絡先を交換する、連絡先を交換したら名簿でプロフィールを管理して、アメフト部に入る意向の度合いをステータスをチェックし、コミュニケーションをいつ、どういう風にするか、などの進捗管理しながら勧誘活動に取り組みました。
あとは、そもそも練習もきつく、ハードなスポーツなので、練習以外のところで理不尽に後輩に厳しくしてもしょうがないなと思い、部活の雰囲気をフランクに、馴染みやすいものにしていきました。練習の後にバーベキューやったりお花見をやったり、部員同士の交流ができるような仕組みを作って、アメリカンフットボールがやりたいということよりも、同じチームに友達、仲間がいるということの連帯感みたいなものが継続する動機づけになるように部の雰囲気を変えていきました。結果的に、その年は20人の新入部員が獲得できました。
その翌年以降も勧誘はうまく行って、部員数は増えていきました。私が4年生の時は、私の代には2人しか残っていなくて、3年生以下の部員が40人くらいになるいびつな構造になり、年生の時は主将も務めたんですが、自分の同期が少ないのに大きな人数のチームをリードしなくちゃいけないというところで、苦労した思い出があります。
自分の大学は地方の公立大学なので、運動能力が高くない人ばかりが入ってきます。例えば同じ中部地区には中京大学という体育専門大学があって、運動能力抜群の人たちがたくさんいるアメフト部や、名城大学はアメリカンフットボールの推薦をやっていて、アメフト経験者ばかりが入ってくるようなチームがあって、そういうチームと優勝争いをしていくためには、チーム一人ひとりの地力を少しずつ高めるしかないです。
スター選手なんかなかなか取れないので、一人ひとりの地力を人並みよりもちょっと上にするために、基礎をすごく重視した練習やチーム作り行いました。4年生の時には基礎固めということの練習方針をもう一気に振り切って、ぶつかりあいで勝たなきゃテクニックも何もあったもんじゃない、ということで、ぶつかって相手に押し勝つということをとにかく徹底的に繰り返す、ということに取り組みました。
また、アメフトは、低い姿勢で早く動く、という特殊な動作が必要なんですが、それに慣れる体つくりということで、毎日練習のスタートを低い前傾姿勢で走る短いダッシュを100本やるところから始めるみたいなことも取り組みました。
結果的に自分の代では、チーム力が高まりきらず、1部リーグ昇格はできなかったんですけど、私の次の代が人数がすごく多く、学年が低い頃から試合をたくさん経験してきた代というのが出来上がり、私が卒業した1年目の年、社会人1年目の時に、1つ下の代が一部リーグに昇格を果たしました。3年越し、4年越しで努力が実る経験で、昇格が決まったその瞬間は、先輩からつないだバトン、興奮や安堵といったたくさんの感情が一気に押し寄せてきて、その場に座り込んでしまうほどでした。
要領よくテストを乗り切って単位取得
アメリカンフットボールはそんな感じでしたが、授業に全然通っていないかった学業も、テストだけ要領よくやっていてました。テストで点数を取れば単位が取れる学部だったんで、テスト前日になると夜8時くらいから大学の同級生と集まって、最初に自分たちの友達でよく勉強している真面目な友達とか電話をかけまくりました。
「こういうポイントが出るよ」みたいな話や、翌日受けるテストの中でどういう問題が出そうか、どういうところが重要視されそうかみたいなテーマを10個くらい書き出して、10人で分担してまとめを作る。まとめを覚えたりとかいろいろ工夫して、テスト中に回答できるようにするみたいな感じでテストをしのいでました。
要領よく単位を取るエピソードが1つあります。専攻の授業の空いてる時間、つまり専門授業ののコマが空いているところに他学部のコマを入れて、関連単位みたいな感じで取れる仕組みがありました。あるとき、法学部の授業で西洋法制史という西洋の法律の歴史みたいな授業を登録だけして、すっかり忘れていて、1回も授業に行ったことなかったんですが、テスト期間中に明日の西洋法制史があることに気が付きました。
1回も行ったことないしさすがにスキップかなと思ったんですが、シラバスを読むと、「出席不問。教科書持ち込み可」という記載を見つけました。テストにしっかり答えれば単位が取れるかもしれないなと思い、学校の書店に教科書を買いに行ったら3,000円でした。1回のテストのためにお金を使うのはもったいないなと思ったんですが、結論、買ってみるかということで、翌日のテストに教科書を持参して臨みました。
テスト時間は90分くらい、内容は論述問題が2問だけ。「XXXについて述べよ」と書いてあった「XXX」が全くが分からないので、教科書の索引から、キーワードをベースに関連する内容を読んで、「こういうことを言ったらいいのかな」みたいなことを考えて、ほとんど教科書の書き写しだったと思うんですが、文字数をいっぱい書こうと思い、A3の答案用紙に表面裏面びっしり埋まるくらいに自分の答案を書いて提出しました。
90分間書き続けたので、テストが終わる頃には肘が割れるんじゃないかと思うくらい痛くなりました。結果的に一番上の「優」っていう成績が取れて、その単位の取得が大学時代で一番効率が良かったです。
ファイナンシャルプランナーの資格取得
大学の3年生の頃に、授業に行ってもつまらないのと、それであまり授業にも行かないのとで、あまりにも勉強しなさすぎて、「さすがに何か勉強しないと」と思い、資格の取得を考えて、就職活動にも有利だったり、部活をしながらも取り組める想定時間数なども考慮して、ファイナンシャルプランナーの資格を取得しました。
恩師との出会いで、世界の課題と自分がつながる
大学の恩師との良い出会いもありました。僕の大学に5年ほどMBAがあった期間があって、たまたま学部の友人の紹介でMBAの長官と仲良くりました。その方は日本人なんですけど、フランスの国立大学で国際経営のMBAの教官を10年ほどやっていた方で、2001年頃の当時、ヨーロッパの多様な地域における持続的な社会ということに深い思想や知見をお持ちでした。
その恩師から地球や人類という視座・視点で、未来について考えるということを聞いたり、コーポレートソーシャルレスポンシビリティやミレニアムデベロップメントゴールズのような話を聞く中で、なんとなく小さい頃から社会的弱者が虐げられるような世の中が良くないなという思いと、そういった問題が世界にはたくさんあるんだなという認識がつながり、途上国とか貧困問題みたいな国際開発のテーマに興味が高まりました。
とはいえ、当時はまだ英語も大して話せませんでしたし、JICAの青年海外協力隊なんかも考えたんですが、2年間海外派遣されても仕事とかキャリアみたいなことはあまりプラスにならなそうだといことで、普通に就職を目指そうかというような就職活動を始めました。
就職活動で出会いが広がる、経営学への興味が高まる
就職活動は、名古屋の狭い世界が中心だった自分にはとても刺激にあふれた機会になりました。東京や大阪の学生とつながりが増え、刺激が増えていきます。IBMのインターンシップでは、東北~関西から集まる個性あふれる仲間と、IBMの優秀な講師陣からたくさんの勉強をさせていただきました。
特に、アメフトばかりやって、専門の経営学すらサッパリ勉強していなかった自分には、インターンシップの同期が、ビジネスの様々なフレームワークや経営理論、ITやプログラミングについて豊富な知識を持っている人がたくさんおり、高校3年生の時に味わった、「このままではヤバい・・・」という感覚を持ちました。
その後、このインターンシップを境に、ビジネスのおもしろさ、その基礎を学べる経営学や礎となる経済学への興味が湧きあがり、卒業までの期間に大量の経済学、経営学、ビジネス書を読み漁りました。この頃、ちょうど「コーチング」という言葉が世の中に広がり始めた時期ではないかと思い、コーチング関連の書籍を何冊か読んだり、「アクティブ・リスニング」を実践してみたり、など、コーチングの表層を少しかじった記憶があります。
また、このIBMのインターンシップのメンバーから、関西で活動する学生向けの学びの場、「ビジネス道場」の存在について教えてもらいます。当時、P&Gのファイナンス部門で働かれていた方が、学生向けのボランティアで経営学のフレームワークやケーススタディを学ぶ場を開催しており、関西で優秀な学生が集まっているとのことでした。
とても刺激的な学びの場に見えたので、同じ大学の友達を誘い、車を運転し、名古屋から泊りがけで出かけました。ビジネス道場の勉強会では、就職活動を終えた先輩が後輩のアドバイスにも参加したり、ケーススタディやその後のフィードバックを行ったりなど、今振り返っても質の高い学びの場であったなと思います。
当時は、コミュニケーションツールとして、メーリングリストも盛んで、活発に議論がされていました。この時につながりができた人たちとは今でも交流がありますが、のちに、コーチングを学ぶ師匠となる李英俊さんともこのコミュニティを通じて友達になりました。
外資コンサル&金融は全滅
一方、就職活動そのものはどうだったかと言えば、名古屋の大学で情報戦に遅れていたこともあり、マッキンゼー、ボストン・コンサルティング・グループなどの戦略コンサルティング会社は選考が間に合いませんでした。安直な興味があり、外資系銀行にも応募をしていました。ドイツ銀行はインターンシップの最終面接まで行きましたが、応募していた本部が急遽日本撤退となり募集自体が無くなってしまいました。
その後、ゴールドマンサックス、メリルリンチなどの外資系銀行を受けるもことごとく筆記試験落ち。第一志望だったP&Gも書類選考という結果で、第一志望群は散々な結果となりました。それでも、東京海上、IBM、日本総研、電通などから内定をもらい、「多くの人に伝える手法(=マスマーケティング)を学びたい」と思い、電通に入社することを決めました。自分なりに準備や努力ができ、結果も出すことができた就職活動だと思いますが、グローバルトップ企業にはまったく手が届かず、劣等感のようなものが残りました。
ロジカルシンキングやフレームワーク
また、就職活動を通じて勉強していく中で、ロジカル・シンキングやフレームワークなどをかなり広く、深く学んでいきますが、ロジカル・シンキング、フレームワーク、経営理論に偏った思考を生んでしまったような気もします。自分でゼロから考える、という思考プロセスではなく、思考フレームワークを探して、情報整理から始めてしまうようなイメージです。物事を効率的に進めていくには便利ですが、独自の発想や突き抜ける思考が疎外されてしまっているような気もしています。
経営学の歴史をまとめた卒業論文
就職活動を終え、アメリカンフットボール中心の生活になりますが、4年生になり大学の講義も少なくなったので、日中の時間などが空いていたので、この時期に経営学の書籍やビジネス書を大量に読みました。大学の卒論では、「マネジメント・サファリ」と題し、ヘンリー・ミンツバーグの「戦略サファリ」になぞらえ、経営学の発展の歴史、各種理論・学派への考察、まとめとして、西洋思想と東洋思想の比較から、分析的思考と統合的思考、それらのマネジメントへの適用について語りました。
なかなか読み応えのある内容にはまとまったと思いましたが、新しいアイディアを提示したわけではなかったので、ティーチング・アシスタントからは「文学部に持っていくといいね」という厳しいコメントをいただきましたが、卒業単位は暖かくいただくことができました。
電通(2003~2004年):悩みながらキャリアの方向性を模索
2023年4月に電通に入社します。入社後2ヵ月は東京での集合研修があり、この時に、初めて東京に長く滞在することになりました。座学で広告の基礎を学んだり、営業研修で営業現場で業務をしたり、先輩にお誘いただいて会食のマナーを学んだり、同期と交友を深めたりなど、楽しい期間を過ごしました。
研修後、「東京でマーケティング」と配属志望に記載するもの、「名古屋でテレビ担当」という真逆の配属で、かなりの落胆がありましたが、冷静に考えれば、名古屋の体育会アメフト部出身は、名古屋で媒体局の配属にするために採用してると思うのが妥当だったでしょうか。
配属後の仕事が始まってからは、なかなか苦労、苦痛の多い社会人生活のスタートでした。もともと、就職活動で広告業界を目指していなかったのもあり、電通がどういう企業文化を持っているのか、などをよくわからずに入社したのが失敗でした。人事にも、アメフト部だから媒体系が向いているだろう、と思われていたであろうこともミスマッチの要因だったのではないかなと思います。
ウワサ通りのザ・電通のど真ん中で、1年目からハードな社会人生活でした。毎日、終電まで仕事か、取引先のテレビ局と午前2~3時まで飲みに行く生活。どれだけ遅くなっても翌朝は朝8時30分に出社が必須です。先輩からは今でいうところのパワハラのオンパレードで、当時の時代背景的にはようやく「パワハラ」という言葉が少し出始めた程度のころでしたので、それはそれは苦労の多い社会人デビューでした。
通常、テレビ系の配属になると最低7~8年はその辺りのキャリアになります。広告業界で働いていく上で、媒体社との切った張ったの交渉ができる、その経験を有していることはとても力強い武器になると考えられていました。そうは言っても、仕事のメインは、取引先のテレビ局と人間関係を作り、No.1の電通の購買力を武器に、電通に好優遇を引き出すためのタフな交渉をするという世界で、俗にいう「飲ませろ、食わせろ、抱かせろ」を地で行くような仕事でした。
あれだけ経営学やロジカルシンキングを勉強してきたのは何だったのか、という思いは募りました。また、当時の40-50代の部長クラスと飲みに行くことも多かったのですが、名古屋の電通はまだまだ平和だったのか、先輩から聞く話は、ゴルフ、麻雀、女遊びばかりで、20年後にこんな人生になってたら本当に後悔すると思うようになり、1年目の終わりには、この会社で長く働くことはない、という思いを固めていきました。
とは言いつつ、まずは社内でできることを、ということで、名古屋支社のマーケティング局への異動を画策し、媒体局からマーケティング局へ異動した先輩の話や、マーケティング局長に時間をもらって人事異動で引っ張って欲しい旨などを伝えました。
当時は人事異動の仕組みもよくわかっていなかったのですが、マーケティング局へ異動するしないに関わらず、近い未来で経営コンサルティング会社に転職しようという考えが高まっていき、2年目の夏ごろには具体的に転職することを考え始めました。とは言いつつ、具体的な転職先を探し出すまでに、社内のノウハウ集、営業・マーケティングの方々の提案資料などから勉強して、知識獲得には取り組んでいました。
パソナグループ(2004~2006年):新規事業立上の魅力に出会う、自分の在り方とも向き合う
社会人2年目が始まった初夏の頃に、IBMのインターンシップで出会い、大阪のビジネス道場でも親しくさせてもらった友人と久しぶりにキャッチアップをしました。彼は新卒でSONYに勤めていましたが、人材派遣のパソナグループで若手に任せる新会社設立に際して、社長を任せられることになったと言う話を聞きました。
第二新卒に特化した求人媒体を作るという事業案で、立ち上げメンバーとして参画しないか、という誘いでした。第二新卒の事業なので、第二新卒のメンバーを集めて立ち上げたいとのこと。もともと学んできた経営学の方向性で、経営コンサルティング会社に転職したいと思っていましたが、24歳で、実際に会社の立ち上げから事業を作る経験は、いずれ経営コンサルティングの世界に携わるとしても貴重な経験になるだろうと思い、電通を辞めて、転職することを決意しました。
2024年10月から転職、名古屋から東京にも引っ越しました。誘ってくれた友人を含めてほとんど初めてのシステム開発経験で、開発パートナーをうまくコントロールできなかったり、手戻りの多いプロセスで苦労をしながら、なんとかウェブサイトのローンチの1ヵ月前になりました。
サイトオープンに向けて死に物狂いのプロジェクトマネジメント
私は主に、戦略、ブランディング、マーケティング、営業を担当していましたが、ウェブサイトの編集方針や求人広告制作のディレクターをやっていたメンバーから、「求人広告原稿の制作がウェブサイトのローンチに間に合わない」という報告がありました。ローンチに向けて顧客を獲得し、求人募集を集めていたり、マーケティングプランも固め、ローンチのPRイベントも日程を決めたあとでした。
特に企業の求人というのは旬があり、採用をしたいタイミングもあるので、募集の開始が1ヵ月、2ヵ月と遅れることは、新規立ち上げを迎えるウェブサイトとしては信頼を大きく損ねることになりかねません。担当ディレクターに確認しても、全体像が把握できておらず、課題が何かも全くわかっていませんでした。
チームで議論しましたが、やはりローンチタイミングはずらせないという結論になり、急遽、私が制作ディレクターを兼務することになりました。そもそも自分の役割もローンチ直前でかなり業務過多になっていましたが、日中は制作業務の立て直しに専念し、夜からマーケティング業務を行うようにシフトを調整しました。
求人広告制作については、獲得済みの求人募集と顧客から回収済みの求人原稿素材の可視化、求人制作業務フローの把握、各プロセスで必要なリソースと現状リソースのギャップ把握、不足リソースの外部調達などを行い、遅延のリカバリーを開始しました。関係各所で必要な動きが多く、全体が不安になる中で、「絶対になんとかなる!」と気持ちで周りを後押ししながら、プロジェクトを遂行していきました。
大炎上中の制作ディレクターとマーケティング広報計のローンチ企画をやりきるには通常の業務時間では全く足りず、この期間中、平日はオフィスで寝泊まりし、睡眠時間が毎日1時で過ごしました。土日はさすがに長く寝ていましたが、平日はこのサイクルで1か月間過ごし、最終的には、顧客都合でローンチタイミングに求人原稿の準備が間に合わない案件以外は全てローンチ時の公開に間に合いました。

立ち上がりが鈍かったサイトオープン
そんな苦労をしながら、ローンチにこぎつけたわけですが、同時に、私はマーケティング広報の担当もしていまいた。ローンチイベントも成功させ、メディアの獲得も取り、当初の予定通りのプロモーションを開始しました。ただ、そもそも広告予算も大きくなかったので、いきなり求人候補者が集まるわけではなく、ウェブサイトの立ち上がりでは期待するほどの求人応募が発生しませんでした。
オープニングの滑り出しが良くなかったことから、「マーケティングのせいで上手くいかない」と言われ、限られた予算の中で、ベストなプランは作っていたので、実情を知らない人からの低い評価に少しショックを受けました。とは言え、集客計画については社長としっかりコミュニケーションしながら進めていたので、「詳細を知らずに印象だけで評価するのは、理不尽すぎるだろ」などと、心の内では思っていました。
信頼を失い、在り方を見直す
ローンチが少し落ち着いたあと、マーケティング活動はジワジワ改善しつつ、営業チームやシステム開発チームにも、事業を伸ばすために必要だと思うことをバンバン言っていたところ、気が付いたら、いつの間にか古株の友達以外からはめちゃくちゃ嫌われてる状況になっていました。
相手の主張を論破したり、そもそも物の言い方・伝え方が悪かったりと、とにかく、受けたの感情への配慮が足りなかったのだと思います。自分が担当する業務の計画は誰よりも考え抜いていたため、自分がやろうとしていることが正しいはずだ、とは思っていました。
ただ、その正しい戦略や計画が、自分のふるまいのせいで伝わらない、実行されないということでは、ビジネスがうまく行くはずがない、と思い、自らの在り方を7つの信条を作成して、毎朝毎晩、通勤前と通勤後に見直し、反芻するようにしました。当時のメモが無く、7つ全てが思い出せないのですが、下のようなことが一部です。
「相手の存在に感謝をする」
「声をかけられたら、相手の目を見て、笑顔で返事をする」
「意見や批判に反射的に反応しない」
「元気に挨拶をする」
人とのコミュニケーションや、周りの人の感情を読み取ることが得意な人から見ると、「なんだそんなことか」と思うようなことかもしれませんが、いまだに私はこの辺りの機微は得意ではないし、不得手だからこそ、二重にも三重にも意識で、ギャップを埋めに行こうとしているところがあります。
マーケティングを改善しつつも1つの区切りで転職
その後、マーケティング予算を最適化しながら、粛々と応募数などは改善していましたが、メディアビジネスである以上、どこかで大きな投資をして、認知率とユーザー数を獲得しないとジリ貧という状態は続いていました。
競合との認知率調査などで比較を出したり、認知向上施策の立案などもしたりしましたが、親会社が派遣会社で、メディアビジネスへの理解も得られず、事業を大きく成長させることができませんでした。実際には、グループ全体のポートフォリオの中で、若手に任せて立ち上げて、立ち上げがスムースに軌道に乗らなかった新会社をどう位置づけるのか、というもう数段高い議論があったのかもしれませんが、当時はそのあたりのコミュニケーションに入り込むほどの思考は持っていませんでした。
そのような議論をしている中で、本社にて、ターゲットユーザーの層が近い別の子会社と合併が決定され、事業モデルの転換も決定。自分が取り組んだ事業の1つの幕が閉じたと考えて、合併による統合プロセスが一通り落ち着き、自分の業務も他の人渡せるところまで見届けて、転職をすることにしました。
国際開発領域へのつながりと学びを深める
この頃、プライベートでは、東京に来たことで新しい人とのつながりも増え、国際開発への理解を深めるべく、JICA、NGO、CSRコンサルティングの分野で働く人、国際開発のキャリアを志す人などと集まって、国際開発に関する勉強会を開催していました。
また、食を通じて世界とのつながりを深めるというテーマのコミュニティにも所属して、いまでもつながりのある友人をたくさん作り、自分の視野が広がったなと思います。自分の目指していく方向性についても言語化が進み、「Make a better world(より良い世界を作る)」というビジョンができました。
初めてのビジネスコーチとNLPプラクティショナー取得
この頃、友人からの紹介で、ビジネスコーチをつけました。国際コーチ連盟 認定マスター・コーチ、米国NLP(Nuero Linguistic Programing)協会公認NLPトレーナー資格を保有している方で、断続的ですが、合計で1年ほど支援をいただいて、自分のスコトーマが外れたり、短い時間でビリーフシステムが書き変わる体験をしたりと、コーチングの効用をクライアントとして多く実感しました。
また、NLPにも興味が湧き、NLPプラクティショナー資格も取得しました。ラポール、キャリブレーション、サブモダリティー、リフレーミング、8フレームアウトカム、アイ・アクセシング・キュー、VAKモデルと言った基本概念を、自分がコーチングを受けた感覚値を持ちながら、習得していけたことはとても学びになりました。これ以降、ビジネスや日常生活のシーンでもNLPをうまく取り入れるようになりました。
再度、戦略コンサルに不合格
2006年の夏~秋に行った転職活動では、かねてから志望をしていた戦略コンサルティング会社から受けていくことにしました。戦略コンサルの友人に話を聞いたり、コンサル向けの転職活動書籍などを読んで対策などをしつつ、フェルミ推定やケース面接など、特有な面接手法に緊張しつつ、いくつかの会社を受け始めました。結果から行くと、マッキンゼー、BCGは筆記試験落ち。ATカーニーとローランドベルガーは二次面接落ちということで、思考力が足りないのか、向いてないのか、ということで戦略コンサルタントになる、という大学時代からの1つのベンチマークはここであきらめることになりました。
その後、直近の新規事業の立ち上げという仕事の、自分で考え、実行するとすぐに結果を見てたくさんの試行ができる、正解がない中で方向性を決めて進む、という特性が楽しかったなと思い、もう少し新規事業の経験が豊富な会社で力を磨いてみたいと思うようになりました。その後、新規事業に積極的な会社をいくつか受けて、学生時代からの先輩や友人が多く在籍しているリクルートに入社することになりました。
ロンドン留学(2007年1~2 月):世界で働く臨場感を掴む
2006年末ごろにリクルートから内定をもらい、入社タイミングを切りよく2007年4月にさせてもらい、前々から英語の勉強をしたかったので、ロンドンへ短期留学に行くことにしました。いつかはグローバルに活躍するというイメージを持ちながら、大学卒業時のTOEICは500点ほど。海外旅行でブロークンな英語を話すことに抵抗はないものの、話せる内容は中学生英語未満という感じでした。

ロンドン中心地の語学学校へ2ヵ月の留学を始めましたが、語学学校だけでは簡単に上達しないと思っていたため、留学初日にプリペイド式の携帯電話を購入し、ロンドン市内にあるデジタルマーケティングの会社をリストアップし、テレアポで連絡し、インターンシップの募集をしていないかヒアリング。
資料を送って良いと言われたら、事前に準備しておいた英語のレジュメをメールで送りました。結局、日本で仕事をしたことのあった247RealMedia というグローバルメディア企業の日本支社からロンドン支社を紹介してもらい、無償のインターンで採用してもらうことができました。

仕事の内容は営業サポートのような雑務のような仕事で、契約書の更新期限のチェックや社内システムのマニュアル作成など簡単な作業ばかりでしたが、なるべく早めに片付けて、何か他にやることないかな?と社内を聞いてまわりました。
当時、まだウェブマーケティングの仕事というのは世の中に広がっていなかったので、社員の人から、「ここで働きたかったら入れると思うよ」などと、雑談でも言葉をかけてもらえたのは自信につながりました。自分で機会を得ることで、世界でも仕事ができそうだという実感を持てるようになった良い経験でした。
海外で親友ができる
また、語学学校でも良い友達との出会いがありました。語学学校の学生は大学生が中心で、僕のように社会人経験を経て語学留学に来ている人はあまり多くありませんでした。そこで、同じクラスに仲良くなったは、同じく社会人組で在学生していた韓国人の男性でした。年齢は1つ違いで、ソウル大学からマッキンゼー、外資系証券会社と、僕から見たらキラキラの経歴の彼でしたが、人柄も気さくで温和で、何度かカフェに行ったりランチに行ったりしているうちに自然と仲良くなっていきました。
一緒にクラブに行って、深夜のバーガーキングでハンバーガー食べたり、仕事やキャリアの話をしたり、など短い期間でしたが、とても波長の合う親友になりました。彼とは今でも家族ぐるみの交流があって、東京やソウルで何度も交流しています。
リクルート(2007~2011年):新規事業開発の経験を高める。国際開発の課題と自分の在り方を模索
リクルートでの配属はご縁があって新規事業部門に配属になり、クロスメディアや広告技術系の新規事業・新商品立ち上げに携わりました。新商品開発や部門立ち上げなど刺激の多い時間を過ごしました。
一定の成果を出して、楽しく過ごしてはいましたが、どこか満たされない気持ちがありました。そんな時、リクルートの研修で、自分のキャリアプランを考えるキャリア研修に参加しました。研修自体は10~20年の社会変化を想像しながら、自らのライフプランを考えるというもので、それ自体にも発見は多くありましたが、一番大きな取れ高は、研修グループのメンバーで自分の話をして相互にフィードバックをもらう時間でした。
どこか自分の中で「もっと自分はできるはずだ」という思いと、それが十分にやり切れていない自分の焦りというものがありました。グループのメンバーで、プランナーをしている人から、「将来、本当に世界の課題を解決したいと思っているなら、今くらいの小さな課題が解けなくて焦っているのはおかしい。私ならプランナーとして、もっと問題解決する力を磨く。」というコメントをもらって、目からウロコが落ちました。
より大きな課題に取り組むために、たかだかリクルートの1部門内での課題くらいで悩んでいてどうする、という気持ちが定まり、ますます自分の力を磨いていくことに集中していくようになりました。
インドでの社会起業家視察
国際開発への興味関心は引き続き続いていて、一般財団法人国際開発機構(FASID)の社会起業家コースに参加しました。1週間のプログラムでは、Indian Institute of Management Colucatta(インドでトップクラスのMBA)にて、社会起業家関連の教授からインドの社会起業家に関するケーススタディを学びました。

フィールドワークではマイクロファイナンスから支援を受ける女性起業家を訪問しました。例えば、マイクロファイナンスで借りた資金で、小さい機会を購入し、プラスチックの傘の先端部分を加工するような町工場のような場所です。4畳くらいのスペースに機械が2台置かれ、雇われた社員がプラスチックを加工していました。

長らく国際開発や社会起業家という方向性、できれば途上国で社会起業家として事業をするというようなことを妄想していましたが、実際にフィールドワークを通じて、「途上国の課題は途上国の人がもっともリアリティを持って理解できる」、「基本的な社会インフラやインターネットですら簡単には手に入らない状況で、ソリューションを考えるクリエイティビティが必要」など、多くの気づき・発見が得られました。

そのうえで、いきなり現地に飛び込んで大きな変革を生もうとするよりも、自分の得意な領域でイノベーションを作り、そのモデルで国境を超えていくアプローチのほうが合っているのではないか、と考えるようになりました。
28歳で英語の勉強を本格的に始めることを決意
関連して、グローバルな課題を解決できる人間になっていくために、大学時代から海外MBAでリーダーシップを学びたいと思っていました。インドのプログラムでも、英語力の不足を痛感していたので、28 歳の正月から本格的に英語の勉強を始めることを決意しました。
社会人の英語学習は限られた時間との戦いです。大学受験の時には大量の時間数をコミットすることでなんとかしましたが、フルタイムで忙しい仕事をしながら時間をかけることで学習しようとするのは無理があると思いました。まずは、英語の勉強法に関する書籍を10冊ほど読んで、効率的な学習方法について考えました。
またMBA予備校などの情報によると、トップMBAに合格するには最低でも1,000時間の勉強時間の確保が必要ということでした。そのため、平日はできるだけ朝5時に起きて、会社に行く前に2時間の勉強、土日はどちらも7~8時間は英語の勉強に充てるという生活を続けました。
海外でのキャリアを志向
その後、1年半で TOEIC 970 点を取得するものの、MBA出願に必要なTOEFL/GMAT のスコアがなかなかあがらず、トップ校に応募するための準備が揃わない状況が続きました。ここでも、「やはり自分に世界の一流の壁は届かないのか」と劣等感が募りました。
リクルートでは、本当に素晴らしい同僚に囲まれ、新しい新規事業の創出に熱狂し、周囲からの期待や評価ももらいながら、楽しく働いていました。一方で、年齢が30歳を超え、トップMBAへの出願準備が整わない状況など、思い描いていた自分の成長と現実とのギャップに焦りもありました。将来のキャリアについても、仮にトップMBAに入れたとしても、英語がノンネイティブの日本人が現地での就業機会を獲得することはかなり難しそうだ、という現実も理解も深まりました。
そもそも就労VISAの問題も大きいです。そんな中で、ちょうどリクルートがグローバル化に力を入れ始めたところだったので、海外MBAに行って、リクルートのグローバル推進をする、というのが本筋かなと考えるようになってきました。
P&Gシンガポール(2011~2013年):グローバルキャリアの実現。自己肯定感の向上と劣等感のはざま
学習を続けているうちに英語の力もそれなりについて来ていたので、第2志望群のMBAに応募をしてみようかと考えている頃に、人材紹介会社から連絡があり、P&Gのシンガポール法人がマーケティング部門で日本人を積極的に採用してることを紹介されました。P&Gは経営学の教科書でも度々登場するグローバル企業で、新卒の頃にもP&Gのマーケティング部門で働きたい、と思っていた会社でもありました。
特に、P&Gはマーケティングがリーダーシップを発揮するように組織がデザインされており、P&Gのシンガポール(アジア統括本社)で働くことができれば、グローバル観点でのマーケティングとリーダーシップを獲得することができるだろうと考えました。
現実問題として、海外MBAに私費留学で行くには、仕事を1~2年休職し、MBAの高い学費と生活費を自己資金でまかなう必要があります。働いていればもらえているであろう給料との差額を考慮すると数千万円の差が生まれます。また、海外MBAで国際色豊かな環境でリーダーシップを学べるとしても、やはりケーススタディやインターンシップなど、実務・実践との差はあると思います。
そのあたりを考慮し、MBAで高いお金を払うより、給料をもらいながらグローバル・トップ企業でリーダーシップ経験を積む、という選択肢が魅力的でこの機会を掴みたい、という気持ちで応募しました。私の英語力で、いきなりシンガポールの現地法人で働くのはかなりのチャレンジだったと思いますが、サバイバル能力や突破力のようなところを買ってもらい採用されました。
初めての海外生活、外資系企業、英語の仕事
2011年6月から、初めての海外生活、初めての外資系企業、初めての英語の仕事が始まりました。配属は高級化粧品SK-II のマーケティングで、日本市場担当からスタートしました。SK-IIは日本初のアジアブランドであるため、グローバルのヘッドクォーターがシンガポールにありました。
洗剤やシャンプーのようなグローバルブランドだと、本社機能がアメリカで、シンガポールは地域本社機能という組織構成になるため、配属自体は地域本社機能への配属でしたが、グローバル本社機能が同じフロアで働いているブランドで働けたのは幸運でした。

日本市場へのマーケティング戦略立案、キャンペーンの広告開発、担当カテゴリーの損益管理に加え、本社機能と連携して商品開発やブランド再構築プロジェクトにも関わるなど、ビジネスやマーケティングの観点でも多くの学びがありました。もちろん、多国籍なメンバーと共にビジネスを作っていく過程もグローバルリーダーシップを磨く経験も積むことができました。
20ヵ国以上のメンバーと仕事をするグローバルな環境
空港免税店ビジネスのグローバル推進担当に。営業部門と連携し、日本、香港、シンガポール、ヨーロッパ、中東領域のマーケティングプランをリードしました。ロンドンでヨーロッパ初の店舗、ドバイで中東初の店舗ローンチに携わりました。ローンチにあたりドバイ出張も行い、現地のプロジェクトメンバーと関係性を構築をしたり、計画の詰めを行ったり、ユーザーインタビューを行って消費者理解を深めたり、など、新しい国の市場理解や計画立案についても学ぶことができました。
また、チーム構成として、私の上司はイギリス人、その上司はインド人。シンガポールとグローバルで20ヵ国籍以上のメンバーが関わり、日本人は私1人という環境は他では得難い経験でした。
自己肯定感と劣等感が同時に押し寄せる
P&Gシンガポールには、アジア中からエリート中のエリートが集まってきます。同期入社で 22~23 歳の新入社員と肩を並べつつ仕事をしましたが、英語のビハインドもあって、最初の1年は本当に苦労しました。
また、エグゼクティブ層になると、戦略コンサル並みの思考力と、圧倒的なリーダーシップを兼ね備えてる人がこれでもかというくらい居て、ここで昇進してくのは相当難しいな、とも感じました。もちろん、日本人でエグゼクティブクラスまで昇進している人もいるので、可能性がないわけではないですが、基本的な能力の部分で差を感じぜらるをえず、ここでも世界との壁というか劣等感を募らせることになりました。
日本を飛び出して、グローバルに挑戦したら、とてつもなく頭の良い人材に出会いまくって、「頭の良さ」について、世界とのギャップも思い知りました。「頭の良さ」という、得体のしれないものを追い求め、比較し、自分には足りないことがコンプレックスで、日本で限界までがんばってみたら、世界の壁はもっと高かったというオチです。笑えない笑い話です(笑)
シンガポールでのスタートアップ起業(Job Forward社)(2014~2016年):自己資本での挑戦
P&Gシンガポールで充実した仕事はしていましたが、グローバルでトップクラスのマーケティング会社とは言え、マーケティング自体はテレビ CM 中心のマス・マーケティングが多く、当時、デジタル施策はようやく少し重要度があがってきたというところで、リクルートでデジタルマーケティングの新規事業開発に取り組んでいた自分にはかなり遅れていると感じる環境でした。
丸2年ほど経って、仕事にもなれ、グローバルビジネスを推進する自信もついてきたあたりから、インターネットビジネスのつながりが薄くなることに危機感を感じ始め、転職を考えるようになりました。
まずは、シンガポールで大手 IT 系企業の仕事を探してみましたが、Google、Facebook、Amazonというような企業だと、アジアの販売拠点であるため、基本的にはほとんどのポジションが営業職か一部のエンジニア職が募集のメインで、これはやりたい、と思う仕事がなかなか見当たりませんでした。
それで、今後のキャリアについて、キャリアパスのようなものを想像し、自分の未来の満足度を計ってみるというシミュレーションを行います。具体的には、ロケーション、業界、職種という軸でいくつかのパターンのシナリオを作り、それぞれの最高到達点と思われる未来が訪れるとすると、自分の満足度はどれくらいだろうか、という評価を行いました。
シナリオの中でたくさんの分岐を作っていったのですが、どの方向に進んでも、どこかで「自分で起業する」というパターンが出てきました。自分で客観的に見てみて気が付いたのですが、20代から新規事業に取り組んで、いまはグローバルに働くことを挑戦しているけれど、心のどこかで起業にチャレンジしてみたいという思いがありました。
起業のプランをまとめる
そこからは、P&Gでの仕事もしながら、起業のアイディアについても考え始めました。いろいろと考えはありましが、伸びる東南アジア市場でSNS集客型の求人メディアを作る、という事業コンセプトが固まってきました。
東南アジアの求人広告市場は一定の市場ができあがっているものの、成熟市場よりは一歩手前。メジャープレイヤーはいるものの、どれも使い勝手はいまいちで、比較的歴史の長い古い企業が多いので、テクノロジーを活用した新しいアプローチを取り入れていけば、市場の5%を獲得していく可能性はあるだろうと見込んでいました。
また、そのようなポジションを取れれば、日本のHR系企業が東南アジア進出のきっかけとして買収を検討してくれる可能性も高いだろうと、イグジットのシナリオもM&Aを第一候補で考えていました。幸いにも、僕がこのビジネスを起業するなら最初の資金を支援するというエンジェル投資家も見つかりました。
怖かった起業の決断
それでも、ここまでそれなりのキャリアを築いてきて、傍から見れば順調なキャリアを歩んでいて、会社員のキャリアでもそれなりの成功は作っていけるんじゃないかと思っていたところから、一旦、全部を捨てて、自分の力で勝負をする、ということはめちゃくちゃ怖くて、なかなか決断ができませんでした。
もちろん、エンジェル投資家からのバックアップや、多少の貯金も含めて、失敗したからと言って、生きて行けないというセーフティネットはありました。ただ、キャリア(レジュメ)的にはイマイチな感じには見えるだろう、と。やってみたい、でも怖い、という中で、長らく逡巡していました。
いつまで迷っていてもしょうがないと思っていたある夜、仕事が終わった後に、ふと思い立ち、英語の勉強の時に自分で教材として選び何度も聞いていたスティーブ・ジョブズの米スタンフォード大学の卒業式で行ったスピーチを見返し、その中の一説に私は心を揺さぶられました。
「永遠の希望やプライド、失敗する不安…これらはほとんどすべて、死の前には何の意味もなさなくなるからです。本当に大切なことしか残らない。自分は死ぬのだと思い出すことが、敗北する不安にとらわれない最良の方法です。我々はみんな最初から裸です。自分の心に従わない理由はないのです。」
私は起業の挑戦をしたかった。でも、怖くて決断できなかった。そんな私の心にこの一説は深く、深く突き刺さりました。「このまま留まって、死ぬ前に後悔したらどうする・・・!?」 怖いけれど、やりたいことがある。例え、どんな悪いシナリオになっても、やらない後悔より、やった後悔のほうが良い。それなりの年齢だけど、まだ独身。結婚したり、子どもができれば、もっとリスクが取りにくくなるかもしれない。
可能性を感じる市場もビジネスプランも、重ねてきた経験もある。「やるなら、いま。」 スティーブ・ジョブスの言葉に突き動かされ、起業の決断をした時、怖さを許容したこと、前に進むことを決められた安堵などから、自然と涙があふれてきました。
シンガポールで登記、就労ビザの獲得
その後、シンガポールに会社を登記し、就労VISAの申請を行い、無事に就労許可の確認ができたところで退職の手続きを進めました。同時に、プロトタイプの作成やテストを始め、ビジネスモデルのコア部分の検証を始めました。手続き関係は順調で、退職、就労VISA発行、お約束していただいていたエンジェル投資家からの入金など、ひとまず6~9ヵ月くらいはMVP開発に向けて活動できる準備が整いました。
とは言え、会社の資金も少ないため、当面は自分への給与は無し。自分は貯金でつなぎながら、必要最低限の出費に抑え、会社の資金はベトナムのシステム会社に発注するシステム開発費に充てました。
東南アジアでスタートアップのチャレンジをする数少ない日本人やベンチャーキャピタリストとのネットワークを作り、スタートアップイベントの情報を仕入れたり、ベンチャーキャピタルとのつながりを広げたりしました。ちょうどこの時、のちに、シナモンAIで共同創業者として一緒に働くことになる平野さん・堀田さんとも起業家仲間として親交を深めました。
ベンチャーキャピタルからの資金調達
MVPが完成して、シンガポールの登竜門的なスタートアップイベントの決勝ラウンドに登壇するなど、順調にステップを進みながら、いよいよベンチャーキャピタルからの資金調達も開始しました。ご縁があって、私の経歴や事業プランを気に入っていただける投資家に出会うことができ、数千万円の出資をいただきました。
システム開発体制の拡充やわずかながらに自分の給与を払うことができるようになり、当面は資金が底をつく心配が遠くになり、少し落ち着きました。リモートでチーム構成を拡大し、シンガポール、マレーシア、ベトナム、インド、ネパールの開発チームができあがりました。
ミニマルな生活に幸せの基準を感じる
この頃、日々の生活は、毎週、市場で鶏むね肉を 4kg 買って、冷凍庫に保存して、自炊をしてました。週4~5回ジムで筋トレして大学時代と同じくらいのパフォーマンスを出してました。
幸いシンガポールは年中暑く、Tシャツと半ズボンで過ごしていたので、頻繁に服を買う必要が無かったのも助かりました。お金が無いのでミニマルな生活にならざるをえませんでしたが、鶏肉が食べられて、筋トレができれば、だいたい幸せだなと思うようになりました。
また、シンガポールは、国自体が多様性に富み、ワークライフバランスもとても優れています。会社員として働いていたころは、周りのメンバーは午後6時くらいになるとほぼ全員帰宅しており、残業しているのは日本人だけ、年末年始も上司はクリスマス前になると長期休暇で2~3週間いない、など当たり前でした。
日本の当たり前ではない文化に触れてきたことと、自分自身が今の自分にOKが出せるようになったここと、日常にある幸せに気が付けることも相まって、人生の目的は、いつ変えられる幸せの最高到達点ではなく、幸せに感じられる時間の総量だと考えるようになりました。
インドネシアの市場開拓に挑戦
立ち上げから1年ほど、シンガポールでプロダクトを磨いていましたが、トラクションが作れなかったため、シンガポールより経済成長率が高く、テストマーケティングの結果が良かったインドネシアをターゲット市場を変更しました。
単身、ジャカルタに移動し、英語が堪能なアシスタントを採用。コワーキングスペースも交渉して格安にしてもらい、コワーキングスペース近くに月3万円のアパート(それでもジャカルタ市内では中級より少し上のクラス)を借りて、コストも抑制しながら。セールス、マーケティングの現地社員も採用して、初期ユーザーの獲得に向けてトライをしました。
ジャカルタにあるローカル企業と採用の状況やプロダクトへの意見をたくさんもらいました。プロダクトコンセプトを複数試しましたが、トラクションが生まれる前に資金が無くなり、結果として、SNS上での拡散型の採用メディアは東南アジアでは市場が無い、またはタイミングがいまではない、という結論に至りました。
資金が完全に無くなる前に、最後の給料をメンバーに払ってチームを解散しました。この時のメンバーとは、解散から8年経った今でも交流があり、起業家としては苦しい経験にはなりましたが、今でも慕ってくれる仲間ができたことは良かったなと思っています。
プチブレーク(2016年5~6月):自分の目指す方向性の再認識
シンガポールで起業をして、エンジェル投資家とベンチャーキャピタルからも資金調達をして、3年ほど新しいビジネスをチャレンジしたが、事業の成長の兆しを作ることができず、会社の存続が難しくなり、解散を決断。最後まで残ってくれた4人のメンバーに、転職期間用に1ヶ月分の給与を支払って辞めていただくのが、経営者として最後にできたことでした。
30代前半で会社員を辞めて、起業にチャレンジ。3年間全力をつぎ込みました。最初の1年間は自分への給与はゼロで、資金調達後も必要最低限の生活費を給与として得るだけ。シンガポールという国で、貯金がどんどん無くなり、事業の兆しも作れない。
その時点でやるべきことは全部やったつもりですが、実力が無かったのか、市場の選択が悪かったのか、タイミングが悪かったのか、心血を注いで取り組んだ努力は結果につなげることはできませんでした。
自分への無力感、投資家への責任感、大きなゴールを一緒に達成することができなかったメンバーへの申し訳無さ。この無力感は大きく、20歳くらいから、心の底からなりたいと目指していた「世界を変えるグローバルリーダーになる」という目標も、なんでそんなことを思っていたのかも全く思い出せないほど、人生の目的を失ってしまいました。
これ以上、生きる意味が無いんじゃないかという失望感の中、次のキャリアで何をしようか、ということも全く思い描けない毎日を過ごしてました。
自分を取り戻したバリのナシゴレン
3年間本当に全力疾走だったので、少しの間、休息を取ろうと思い、2ヶ月間、全く何もしない期間を取ることにしました。2ヶ月目の中頃に、リフレッシュのつもりで、シンガポールから2時間くらいのフライトでいけるバリへ数日間の旅行へ行きました。南国の素晴らしいビーチを目の間にしても、心ここにあらずという感じで、全く楽しむことができていませんでした。
バリに滞在して数日したある夕方、ビーチ際のレストランへ、晩ご飯を食べに行きました。いつもどおり、ナシゴレンを注文し、ビールを飲みながら料理を待ちました。
しばらくして、ナシゴレンが運ばれてきました。なんの変哲もない普通のナシゴレン。いつもどおり、スプーンですくって、一口目を口にいれた瞬間に衝撃が走りました。
「なんて、おいしいんだ!?」
何も変わったところはない普通のナシゴレンだけど、スパイスの効きも良く、素材の味がよく出てる。あまりの美味しさに、ナシゴレンを口いっぱいにほおばって、目をつぶり、ゆっくりと味わいました。インドネシア料理独特のスパイスの刺激、鶏肉とお米の旨味をこれでもかというほど味わいました。最高の幸福感が頭の中をかけめぐります。
そして、目を開けると、さらに驚きました。目の前にある夕日の美しさに。神々しい太陽の光がビーチに反射し、辺りは黄金に包まれているかのようです。とても心地の良い海風が吹いていることにも気が付きました。
それまで、まったく白黒の世界の中にいたような感覚から、生き生きとした活力と美しい色や音楽に包まれた世界に、突然放り込まれたような衝撃でした。この世のものとは思えないような幸せに包まれてました。
その時に、気がついたんです。
こんなにどん底の底にいても、最高の幸せを感じられるのかと。
自分の周りの環境と、自分が日々感じる幸せとは、大した関係が無いと。
普通のご飯を食べられることが、幸せだし、感動だし、ありがたいじゃないかと。
なんてことのない、小さな幸せを実感することができたことをきっかけに、自分自身の感覚が取り戻されて行き、次のステージに進んでいく心の準備が整いました。
少しずつ、自分よりも大きな成功を果たしている起業家の友達と話をして、「1回目の起業でしょ?そんないきなり上手く行く人ばっかじゃないよ。気にすることはないよ。」と言ってもらったり、もしイーロン・マスクやスティーブ・ジョブスと話したとしたら、自分の挑戦なんて小さすぎて、「失敗した」とか恥ずかしくて言えないなと思い、起業家としてもう少し挑戦を続けようと思えるようになりました。
Fuckup Nights での起業の失敗体験共有
2016年6月頃には少し自分を取り戻しつつあり、友人伝いに依頼された Fuckup Nights という世界中80カ国、250都市以上で開催されるグローバルイベントのシンガポール大会で、起業の失敗体験を共有させてもらいました。
「生身の失敗談からの学びの方に価値がある」というコンセプトに共感して、登壇をしましたが、このタイミングではまだまだ現在進行形で悩んでいる際中でした。
いろんな国の友人ができたシンガポール生活
初めての海外生活、外資系企業勤務、起業など、いろんな経験をしたシンガポール生活ですが、7年弱の生活で、いろんな国の友人ができたことは僕の人生にとってかけがえのない財産になりました。シンガポールはシングルルームのアパートメントが少ないため、独身者だと2ベッドルーム、3ベッドルームをハウスシェアすることが一般的です。
ハウスメイトの中では、いまでもつながりを持っている友達もできました。フラッグフットボールのコミュニティに所属していたので、世界中から集まるアメフト好きの友人と、毎週のようにフラッグフットボールを楽しみ、スーパーボウルの日は有休を取って朝から観戦など、今でも東京、シンガポール、アメリカなど、タイミングが合えば再開する友達ができました。

シナモン AI(2016年~現在):最先端テクノロジーへの挑戦。経営を通じた自己成長
起業家として新しいチャレンジをしようと決めてから、1回目の起業について振り返り、「良い共同創業者」と「伸びる市場」が足りなかったなと思いました。フリーランスとしていくつかプロジェクトを引き受けながら次のアイディアを考えている時に、起業家仲間であった平野さん・堀田さんから、「人工知能で事業を創りたいので手伝ってくれないか」というお誘いをいただきました。
もともと、一緒にチームを組んだら相性が良さそうだなと思っていたので、テーマとしてのAIもとてもおもしろそうだったので、最初は50%コミットで東京で営業活動をしていた平野さんの後方支援をするところから一緒に働き始めました。
半年ほどしたころ、東京で一人で営業活動をしていた平野さんから、突然、出産間近ということを聞いて、他に営業ができる人がいないので、翌週からスーツケース1つに荷物を詰めて東京で営業活動を開始しました。
引継ぎは比較的スムースに行き、途中、荷物の追加やシンガポールに残している部屋を片付けるために一週間だけシンガポールに戻り、スーツケースの荷物を1つ追加して、東京に戻りました。その後、猛烈な忙しさが訪れ、1年半ほどシンガポールに戻る余裕が無く、シンガポールの部屋を残したままスタートアップのジェットコースターに突入するのでした。
ジェットコースターの始まり
2017年春頃、出産明けの平野さんが登壇したスタートアップのイベントで、私たちが発表したAIソリューションが大きな注目を浴びました。大企業とスタートアップを接続するイベントでしたが、イベント終了後、名刺交換に150人ほどの行列ができ、名刺交換が終了するのに1時間ほどかかかりました。
そこから、名刺をいただいた全ての方々にフォローアップと、営業機会の提案をするところから始まりました。平野さんがまだ全快ではなかったため、最初の頃はほとんど1人で営業活動をこなしていました。
まだまだ開発チームを存続させるのが精一杯で、自分たちへの給料は払えず、新しい人の採用もできなかったので、オペレーション関連の全てのことを回していました。具体的には、営業活動、提案資料作成、経理・支払い、契約書対応を一人で担当。
平日の日中は営業の打ち合わせを20-25本こなし、アポが終わった夕方から提案書の作成、深夜から経理・支払い、契約書対応、朝方に帰宅して、翌日朝イチから営業打ち合わせというサイクルでした。平日だけでは時間が足らず、土日もどちらも8-12時間は仕事をするという状況でした。
2017年いっぱいまでその状況は続いていましたが、当然働きすぎで、12月中頃にはさすがに倒れそうになりましたが、なんとか踏みとどまりました。ちょうどその頃、スタートしたAI事業をテーマに資金調達をすることができ、アシスタントの採用をする余裕ができて、異常な業務量について少しずつ解消していくことができました。
また、それらの過程の中で、平野さん、堀田さん、私のチームビルディングも仕上がり、私も正式に共同創業者として加わり、シナモンAIの事業を共に推進していくことになりました。
ベトナムにAI研究所を立ち上げ
AIソリューションへの強い需要へ応えるため、資金調達を行い組織作りを始めました。研究開発拠点をベトナムのハノイとホーチミンに持ち、優秀なAI研究者を採用・育成していく仕組みを作っていきました。
トップのAI研究者は数学とコンピューターサイエンスの天才が集まっているのですが、「AIは研究室にこもって研究するのではなく、実務適用して意味がある」という実践的な研究開発組織を作り、苦労しながら研究者が育つ仕組みを作ったことで、ベトナムのIT企業の就職志望ランキングでTop10入りをするようになりました。
また、トップ国際学会の論文採択も積極的に取り組むことで、ベトナム国内でも有数のAI企業と言う認識が高まり、さらに優秀な人材が集まるようになりました。この頃、日本とベトナムの社員数が100人を超える計画になっており、ミッション、ビジョン、バリューの言語化、バリューを体現する人事評価制度の導入などを推進しました。
アメリカ進出に挑戦
自分自身も毎日毎日猛烈なタスクに追われながら、組織もどんどん拡大していくなかで、さらなる成長シナリオを追い求めアメリカ進出に挑戦することを決めました。2018年に、ジェトロ(日本貿易振興機構)とNEDO (新エネルギー・産業技術総合開発機構)のプログラムを利用し、シリコンバレーの調査に行き、アメリカにも日本と似たような顧客ニーズがあり、競合環境もこれから、という市場のステージを確認しました。
2019年から本格的に東京とアメリカを頻繁に行き来する生活を始め、テキサス州オースティンで本格的にチーム作りを始めました。その間も、日本の仕事とアメリカの仕事の両方を兼務する体制が続いており、日本時間とアメリカ時間の両方で仕事をするような生活が1年間ほど続きました。

マーケティング活動と営業活動の成果がようやく出始め、最初の受注案件がそろそろ得られそうだ、という頃に、新型コロナウイルスの流行が始まりました。オースティンでニュースを見ながら、中国、日本と広まり始めた最初の頃は、対岸の火事のような感覚がありましたが、圧倒言う間にヨーロッパにも広がり始め、その後すぐにアメリカ全土にも広がり始めました。
アメリカの企業活動も一気に停滞し、やりとりをしていた全ての顧客がシステム投資を停止。経済回復の見通しもまったく立たない状態になり、アメリカ進出を断念せざるを得ませんでした。大きな投資をしたが、リターンがゼロだった新規事業に対し、取締役会では責任を取ることと、今後の新規事業時の注意点や対策の報告を行いました。
結婚(2018年)
私生活では、このアメリカ進出をチャレンジしている間に、妻と結婚をしました。知人の紹介で会った時の第一印象は「疲れたオジサン」だったそうです(苦笑)2017年ほどの激しさではなかったですが、引き続き忙しく働いている間に出会ったので、満身創痍の状態ではあったと思います。
海外経験や考え方が似ているなと思えたことや、最初から取り繕わず、良いところも悪いところも自分らしくいることを受け入れてもらえたことが、この人と長く一緒にいたい、と思えたポイントでした。
組織のバリュー再構築と経営の難しさを痛感
2020年春ごろから、日本の事業に専念するようになりますが、経営チームの意識が日本とアメリカなどに分散しているうちに、いつの間にか、経営チームと現場のメンバーとの間に意識の乖離が起こっていました。特に営業部門が一部のメンバーを中心に部門内での結束が強くなっており、営業現場との接点の多かった私を批判するようになりました。
そこから会社のバリューや企業文化の再浸透や共有認知を高める活動を行い、同時に会社のバリューや価値観について対話する時間を増やし、折り合いがつかないメンバーは自然と退職し、営業部門のメンバーが入れ替わっていきました。
プロコーチへの学び
このような組織運営の難しさを痛感する中で、共同創業者の堀田さんから、マインドセット・コーチング・アカデミーのお勧めをされました。人工知能の出自は主に情報処理で、認知科学は出自は主に心理学ですが、ともに1956年のダートマス会議が人工知能と認知科学の発祥と言われています。本業で人工知能についての理解を深めていたので、隣接する認知科学についての理解を深めることに興味もありましたし、より良い組織づくりをするために、人の認知や心理についての洞察を深めることはとても需要だと思いました。
また、それ以上に、現状の外側を求めることで、自らのエフィカシー(自己効力感)を高めていくというコーチングを体系自体が、起業家としてずっと持ち続けていきたい枠組みであると強く共感をしました。
実は、マインドセット・コーチング・アカデミーの学校長で、母体となるマインドセット社の代表取締役である李英俊さんと、学生時代からの20年来の友人であることもあり、すぐに入学を決めました。スクール期間中の学びは圧倒的で、人の認知や心の動きについての解像度が高まることは、自分自身の理解を深めることに直結しました。
起業家としてもともと持っていたゴールから、圧倒的に抽象度の高いゴールを設定することで、エフィカシーと安定感が高まりました。特に、事業に取り組んでいると、日々、様々な困難が押し寄せてきます。そんな時に、焦って対処をしようとすると、抽象度が下がり、思考力が低下します。
困難が大きければ大きいほど、自分が設定したゴールの臨場感を思い浮かべ、未来から現状を見ることで、クリエイティブな解決策を生んでいくことができ、これに再現性を持てるようになりました。
第一子誕生(2021年)
このコーチング・アカデミーを卒業後、第一子となる娘が生まれました。妻もフルタイムで働いているため、家事育児の分担もできるだけ半々、それ以上は取り組めるように自ら積極的に取り組むようにしています。
また、コーチングを通じて、家族のゴールを設定できていることもあり、妻と娘を一人の人として存在を認めながら、自分の人生に包摂する考えを持つことができ、良い関係を築けています。もちろん、日々の家事育児が思い通りに進むことばかりではありませんが、1つひとつの迷いや悩みが自分の成長につながる貴重な機会だと捉えています。
シンギュラリティ・ユニバーシティ エグゼクティブプログラム参加(2022年)
本業のAIベンチャーでは、最先端のAI技術についてキャッチアップをしながら、日本の大手企業向けにデジタル・トラスフォーメーションを実現するために、企業のパーパスやテクノロジーに関するビジョンや企業文化のレベルから議論をしながら、AI戦略の立案や導入を行っています。
自分自身の継続的なアップデートやテクノロジーへの理解を世界的な視点で広げたいと考えて、2022年5月に、シリコンバレーで開催されたシンギュラリティ大学のエグゼクティブ・プログラムにも参加しました。
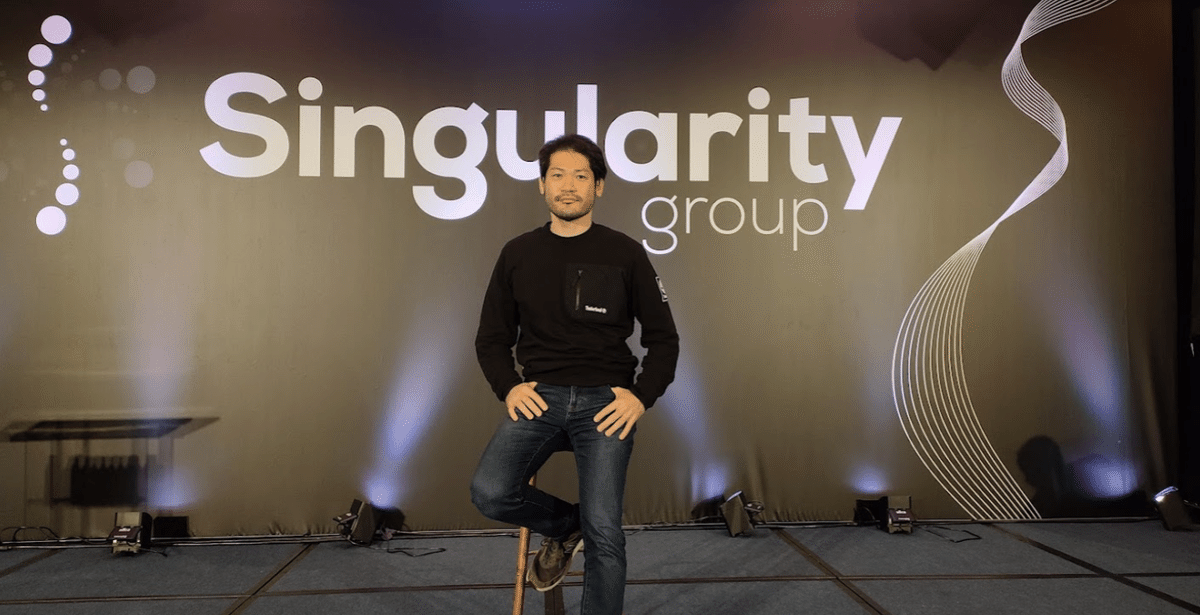
世界に変革をもたらすような野心的な変革目標である Massive Transformative Purpose(MTP、個人や組織が最低30年以上先に実現する、現状とは全く異なるような世界観)や、変革の基盤や推進力となるテクノロジー領域の知見を深め、また世界中から集まるエグゼクティブと、未来志向で交流を深めることはとても刺激になり、ますます本業のおもしろさを再認識する機会になりました。
ChatGPTの登場とAIの民主化
翌年の2023年には大規模言語モデル(Large Language Model, LLM)やChatGPTが登場し、日常的に使えるAIが一気に広まり、AIでできることの範囲も圧倒的に増えました2020年頃には既に市場には登場していたのですが、性能面ではオモチャのような感覚でしたが、専門家の間では、この技術がどこかで急速に成長するであろうことはその頃から当たり前とされていました。
ただ、それが2023年に一気に起こると予想していた人は少なかったのではないかなと思います。AI業界の技術の発展は、これまでのインターネットの歴史から見ても、まさに指数関数的な変化を生み出しており、市場環境・競争環境も劇的な変化を起こしています。私たちの事業環境・ビジネスモデルも良い意味での変化が生まれ、ビジネスや組織が新たな変化を創っていく局面を迎えていますが、コーチング・マインドでゴールの臨場感高く、変化の波に乗っていきます。
趣味の将棋
コーチングではオール・ライフでゴールデザインを行いますが、趣味の領域では、2020年から将棋の勉強を再開しました。定跡の勉強、詰将棋の練習、実践と振り返りなど、小学生の頃のように感覚では上達のできないので、勉強の仕方から工夫して取り組んでいます。
将棋は完全情報ゲームと言って、自分と相手の手が全て見えているゲームです。読み抜けやウッカリミスなど、いろいろあり、級位・段位上は格下の相手に負けることも多々ありますが、詰まるところ、「自分の方が弱い」ということに尽きます。また、どう考えても勝ちの局面から、逆転負けをしてしまったりすると、次の対局で勝ちを急いで、視野が狭くなり、負けが込んだりしてしまいます。
定跡という一定のセオリーを学びながら、変化する局面の中で、自分の思考を研ぎ澄ませながらベストな選択をし続ける、という将棋と向き合う姿勢が、ビジネスや人生との向き合いにも似ていると感じ、将棋への取り組みが人生の研鑽になるのではないかと思い、勉強を続けています。2022年4月初段昇段、2024年1月に二段昇段と、ゆっくりなペースながら、結果につながっています。
美容・健康の領域
また、美容・健康の領域について、筋トレを意識して、マクロ栄養素と呼ばれるタンパク質・脂質・炭水化物については知識を深めていましたが、妻の妊娠をきっかけに、家族の食生活の栄養バランスに気を配れるようスポーツ・フード・スペシャリストの資格を取りました。これまでタンパク質・脂質・炭水化物だけに注目をしていましたが、ビタミンやミネラルも意識した食生活を取り入れるようにしてまいす。
一方、2021年に第一子が生まれて以来、それまで週3~4回通っていたジムへの時間を減らし、家事育児にかける時間も多くしており、運動量は少なくなっています。それに伴って、食生活も少しゆるんでいるところがあり、2年ほど、理想の体型より少し体重が多い期間が続いていました。
トレーニングを継続していた頃は、食生活にもかなりこだわっていたので、体重・体脂肪率を良く管理できていましたが、その頃は、「大きな筋肉と引き締まった身体」ことを目的に置いていました。そのため、トレーニングの頻度を上げられない状態だと、目的の1つである「大きな筋肉」が進捗しないため、そちらの影響から「引き締まった身体」についても意識を上げられず、とは言え、自分の身体の状態にほんのり「ベストではないな」という感覚が張り付いていました。
そこで、2023年10月に、健康美容のゴールの臨場感を高め、自分の身体に違和感を感じ「らしくない」のを止めようと決めました。そこから自分の持っているノウハウを実践に移し、4か月間で体重6.2kg、体脂肪率7.2%減らしました。その間、過剰なダイエットは一切行っておらず、自然な食生活を心がけて、体質改善を実現しました。いまは、自分らしく感じられる体重67kg、体脂肪率13-14%程度を維持しています。
私のMassive Transformative Purose
私は自分のMassive Transformative Purposeを「持続可能な世界」と設定しています。人類として、第一優先の目的を「種の保存」と考えていますが、人類という種が保存できるための大前提が、地球(他の惑星への移住の可能性を除けば)自体が持続可能であることです。
そのためには、生物多様性が地球レベルで実現されており、気候変動に対し世界の国々が積極的に参加をしていることが必要でしょう。天然資源は重要なリソースであり続けますし、非連続な変化を生むための技術革新が欠かせません。先進国と発展途上国は1つの地球のうえで、循環していることを理解し、経済格差の是正に向けてますますのアクションを取ることでしょう。
このような大きな課題を、私自身が解決する、または解決された状態を見届けることは難しいかもしれません。一方で、それらが実現した世界に想いをはせ、行動を取ることが、世代を越えた未来につながっていくと考えていることはとても重要です。
これからしていくこと
私がMTPに向けて取り組んでいることは2つです。1つは自身のAIベンチャーで、世界最先端のイノベーションを提供し、世界の変革を推し進めること。もう1つはプロコーチとして、個人や企業の変革を後押しすることで、未来へのフィードフォワードをすることです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
