
【いま、何も言わずにおくために】#003:「門はあるけど城はない」世界を生き延びる 前編|九段理江・森脇透青
※こちらのnoteは森脇透青さんの不定期連載「いま、何も言わずにおくために」第三回の前編です。他の記事はこちらから。
ゲスト:九段理江さん

1990年生まれの小説家。ザハ・ハディドによる新国立競技場が完成したもう一つの東京で、著名な建築家・牧名の目を通した社会を描く『東京都同情塔』が第170回芥川賞を受賞。生成AIを用いた執筆方法にも注目が集まった。
その他の作品に、『悪い音楽』(第126回文學界新人賞受賞)、『Schoolgirl』(第166回芥川龍之介賞候補、第35回三島由紀夫賞候補、芸術選奨新人賞受賞)、『しをかくうま』(第45回野間文芸新人賞受賞)等がある。
「悪い小説家」
森脇
今日は九段理江さんとお話させていただきます。まずは賞受賞後のゴタゴタでお忙しいところ、お越しいただいてありがとうございます【注1】。
おそらく九段さんの名前を初めて認識したのは、『Schoolgirl』が『文學界』に載ったときだったと思います。今回対談にお呼びした直接のきっかけは、『文學界』(2024年3月号)に掲載された「九段理江」というエッセイで、たいへん面白く読ませていただきました。
九段
ありがとうございます。
森脇
このエッセイは、芥川賞受賞後の一連のお祭りを俯瞰して、一種のメタフィクションのような構造で、少々皮肉っぽく、やや悪意を込めて書かれている。これを読んで——いきなり語弊を招くかもしれないですけど——この人は「悪い人」、というか、「悪い小説家」なんじゃないかと思ったんですよね。
九段
面白いですね。最初、デビューで私は「悪い音楽」という作品を書いているから。私はその主人公を悪い音楽教師だと思って書いてないんですよ。タイトルは「悪い音楽」でしたけど、音楽って本当はいいも悪いもないはずなのに、それを評価する人が良い悪いという評価を下すから、ヒップホップは一応悪い音楽にされている。そういう状況を象徴するものとして「悪い音楽」というタイトルにしました。でも、悪い小説家っていうのは……(笑)
森脇
その点はのちほど言い訳させていただくつもりですが、もちろんいい意味で言っております(笑)
さて、九段さんの小説を読み直してみて感じたことですが、九段さんの書かれる文章でまず独特なのは、文体というか、世界との距離の取り方のような気がするんですね。自分が巻き込まれてる状況をつねに俯瞰しているような、状況にべったり張り付かず、不即不離の距離感から言葉にしていくような、独特の感覚があると思っています。
九段
つい最近、企業の研修に呼んでいただいて、今井翔太さんというAI研究者と一緒にお話したんです。ただ、今井さんは私との対談が決まったときにエッセイ「九段理江」を読んで、「こんな怖い人と対談できるのか」と思ったらしいんです。私は本当にナチュラルに怖い印象を抱かせてしまっているんだなと反省しました(笑)
怖がらせようと思っているわけでは全然ないんですよ。マウント取ってやろうとか、文句を言ってやろうとか、世の中の状況を馬鹿にしてやろうとか、全然そういうこと考えてなくて、なにか楽しんでもらえることを書きたいといつも思ってて、一生懸命考えた結果、あのエッセイが出てきたという。
森脇
なるほど。そこは、僕もよく他人から勝手に怖がられるので何となく共感します。
九段
人にそういう印象を与えて後悔することも多いので、自分では自分の使う言葉に対して距離は取れていないように思います。
芥川賞を受賞するとどうなるか
森脇
すこし迂回しましょう。置かれた状況に対する距離感でいうと、「芥川賞を獲るコツ、わかりました」という、好書好日のインタビューを読ませていただきました。ちょっと顰蹙を買いかねないタイトルだけど(笑)、面白かったのは芥川賞をとるのに必要なのはとにかく枚数の調整だ、とおっしゃっていたことで、これはかなりフォルマリスティックな答え方ですよね。先ほど挙げたエッセイもそうですけど、賞に対して冷徹な目があるような気がする。
九段
やっぱりそれはそうですよ。芥川賞みたいな純文学の賞では、新規性が求められてはいるものの、作品を評価する基準が全然明確でないし、一般の読者からすると中で何が行われてるかわからないわけです。しかも、いざ本屋さんに並べられた作品を読んでも、大抵の人には芸術性がどこにあるのか伝わらない。それはすごくもったいないことだと私は思っているんです。芥川賞はニュースでも大きく報道されますし、せっかくなら本屋さんで手に取ってもらって、興味を持つ人が増えてほしい。
最近は講演に呼ばれたりもしますけど、それは別に私の話を聞きたいわけじゃなくて、「芥川賞を獲った人」の話を聞きたいわけです。強制参加の学生もいるんですね。場合によっては単位のために聴きに来ると。
その状況で、最近私は芥川賞と直木賞の違いから説明するようにしてるんです。野暮だけど、そういう一般の読者がいかに興味を持つかによって、読み方が変わってくると思う。結局書いてる方と読んでる方のコミュニケーションが、どんどん小説をより良くしていくというか、進化させていくなっていうことを、最近はすごく感じます。」
森脇
僭越ながら、たいへん誠実な態度だと思います。そもそも、受賞者が芸能人扱いされている状況もありますよね。一昔前、蓮實重彥が三島賞を獲ったときには、記者会見で「誰か私の小説を読んでくれた人はいないのでしょうか」と言い放ったことがありました。ちなみに蓮實の場合も、蓮實の實が旧字じゃないと郵便物を受け取らない、なんて噂もある。
九段
私、めちゃくちゃやっていることが一緒だな(笑)。
森脇
まあ昔からではありますが、賞が文芸の中のお祭り騒ぎみたいになっちゃっている状況はありますよね。
九段さんにはすでに多くのインタビュー記事があるわりに、本の話、内容の話に突っ込んだものは少ない。九段さんの普段の生活やAIの話が多く、やはり多くの読者はそれに興味があるのかもしれないけれど、インタビュアーの人たちはほんとうに九段さんの小説を読んでいるのだろうか、と疑ってしまう部分は否めない。AIの話についてはたしかにセンセーショナルなんで話題になる第一段階はそうでしょうけど、別に『東京都同情塔』という色んな要素がある小説のなかで、中心的に話題にすべき問題でもないのではないか。もうそろそろ作品をちゃんと読む段階に入るべきで、そのきっかけの一つになれば嬉しいと思います。
九段
ありがとうございます。
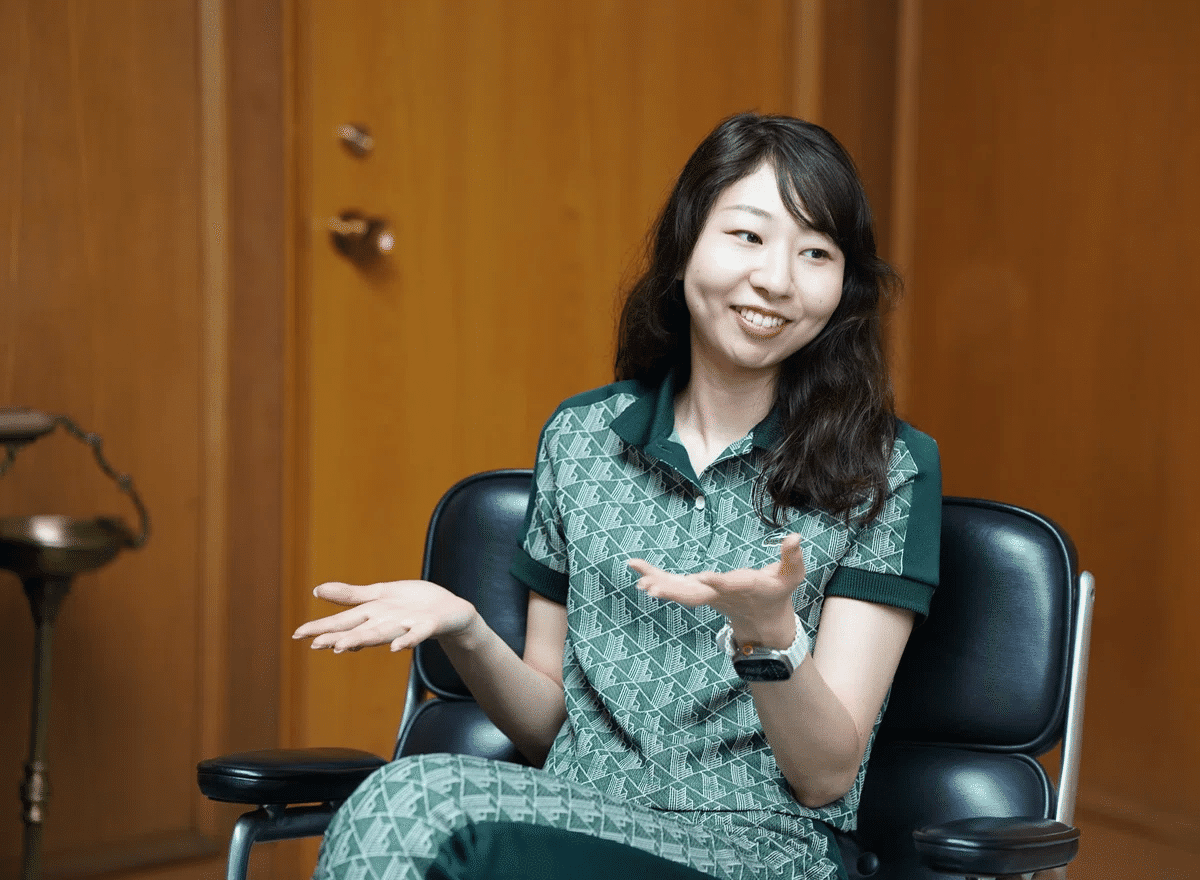
言葉の物質性
森脇
先ほど、九段さんは自分の置かれた状況や言葉の使い方に対して「距離を取っている」と表現しましたけど、それは言い過ぎだったかもしれませんね。むしろこう言ったほうがいいかもしれませんが、九段さんは文字に対してデザイン的な感覚がありますよね。
単純に言って、九段さんはゴシック太字をたくさん使う小説家です。極端なところだと『しをかくうま』で、人名がほとんどゴシック太字になっていますし、『東京都同情塔』でも明らかにAIが記述しているところのフォントは変えている。デザイン的・形式的な目で言語を見ているということは、まさに意味や物語との馴れ合いの手前で一度立ち止まるということです。
さきほど挙げたエッセイ「九段理江」でも、海外メディアが連絡で「Qudan Rie」の綴りを「Kudan Rie」と間違えていたという失礼なエピソードをかなり皮肉っぽく書かれています。こういう文字の視覚的なかたちや綴りへのこだわりが強いということがまず言えると思う。それは九段さんのヒップホップへの傾倒とも関係があるのかもしれません——まさに音韻を揃えていくような目線が言葉に対してある。もちろん、そうした形式だけでは小説になりえないわけですけれど。
九段
そうですね。それは重視しています。物質的に見てるっていうのはそうかもしれないな。物質としてどうしたら言葉が美しくなるだろうみたいなことに、子供のころから興味があったような気がしますね。
森脇
『しをかくうま』は固有名が重要な要素になっているわけですけど、とくに固有名を大量に列挙するパートは、まず視覚的に驚かされましたね。

九段
これは大変でした。夏のすごい暑いときに、部屋の中で汗かきながら名前がカタカナで10文字の人を探して、結局99人集めたんです。紙面いっぱいに並んで、遠目から見ると、紙面にちゃんと白い線が入っているのが美しい。
森脇
なるほど。
九段
文字を物質的に見ているという話でいうと、サインをかっこいいと言ってもらえることが多くて嬉しいです。他の人のサインを考えたこともあったんですが、考えてる時間が楽しくて、私はもともと文章じゃなくて、単純に文字が好きなんじゃないかという気がします。
森脇
あとで僕のサインも考えてください(笑)。とくに『しをかくうま』はその感じが強く出ていますよね。
九段
文字に対するこだわりみたいなものが大きいんじゃないかな。それが自分の特徴のような気がします。
森脇
この連載の一番初めに書いたステートメントの中で、僕自身、現代人はあまりにも言葉の内容やスローガン性に依存しすぎてるんじゃないか、と問題提起しました。なんでもいいから動員・連帯・共感できる空虚な「箱」を用意することに注力していて、そこにどういうコンセンサスやディセンサスが生まれるのか、ということについてはきわめて放ったらかしになっている。それをもう少し、いったんは形式主義的に見て、どのようにして文字から──言ってしまえば単なる物質的な形象から──意味が生まれてくるのか、みたいなことを見ていくことに興味があるんです。さっき九段さんの態度について「距離感がある」っていう言い方を僕はしたのは、その点がこの連載のコンセプトに合うなと感じたのも大きかったからですね。
九段
ありがとうございます。今回森脇さんとお話するにあたって、事前の資料を読ませていただいて。その文章を読んだときに、森脇さんが私に関心を持ってくださったのがすごく納得できました。というのは、『東京都同情塔』に登場する牧名さんと喋りたいんじゃないかなと思ったんです(笑)
森脇
ああ、なるほど。たしかにあの主人公に共感するところもあります。でもそれ以上に、そういうテーマは九段さんの作品に通底していると思ってますよ。
九段
私の中では森脇さんと、自分の作品に登場する牧名さんがイコールになっているというか。最初の方で牧名さんは、“SNSで逐一自分の態度を社会に表明せずにはいられない人たちと自分は人種が違う。でも、人種って言い方は差別になるんだっけ?”みたいな独り言を言っています。そのあたりは森脇さんも書いてらっしゃることです。
「目覚めた」言葉をいかにずらすか
森脇
なるほど、なるほど、たしかにそうしたタイプの悩みは持っているし、僕は牧名沙羅なのかもしれない(笑)
とくに牧名沙羅が語るカタカナ語への抵抗感には共感して読みました。この目線は『しをかくうま』にもありますが、輸入されてきた英語の新概念を訳さずそのままカタカナにして用いるという最近の傾向に対する斜めの目線がありますね。全部が全部悪いわけではありませんが、ああいうカタカナ表記は原語に忠実なふりをしているだけの翻訳の放棄にほかならないし、暗黙のうちに日本語に吸収する同化にすぎないと僕は思います。
今回、九段さんの作品を改めて全部読み直して、実はどの作品の中にも同じテーマがある気がしています。例えば『しをかくうま』では、同じ言葉のスローガン的な反復は言葉を硬直させ、詩が生まれるための「空白」を埋めてしまう、という記述がありました。実際、一方的に「正しい」言葉の形式的な繰り返しは新たな言葉の発明の余地を減らしてしまう——いわゆるポリティカル・コレクトネスを安易に批判しているわけではないのですが。それに対して、そういう正しさは一旦カッコに入れて、あなた自身の言葉で話してみようよ、というような場面や台詞が多いように思います。
九段
ああ、なるほど、そうですね。「作品によって全然違うことを書きますよね」とよく言われますけど、実は全部言ってることはほとんど一緒というか。
森脇
もちろん、九段さんの扱うモチーフや展開の多様さを見逃すべきではないですけどね。
あと九段さんの作品に通底する部分でいうと、登場人物がよく寝ますね。
九段
寝ますよね。
森脇
『Schoolgirl』は目覚めるところから始まるし、『悪い音楽』も瞑想してるところに人がやってくるシーンで始まって、最後は目を閉じるところで終わる。
九段
たしかに!
森脇
『東京都同情塔』でも、牧名沙羅が眠るシーンが最後のほうにある。神経過敏・ワーカホリック的な性格の牧名沙羅が外界を一旦切断して一人になり、唯一リラックスできる時間として睡眠の時間が扱われているわけです。
そこから接続するならば、とりわけ「目覚め・覚醒」と「眠り」の対比が現れているのは『Schoolgirl』でしょうか。その「目覚め」のほうには、きわめて明瞭に「Awakenings」という言葉があてられています。語り手の母と「目覚めちゃった」「リベラルな」娘の対立が主眼なわけですが、この娘の「Awakenings」は、最近で言う「ウォーク(woke)」と訳すこともできると思うんです。つまり一般に「意識高い系」とか「お目覚め系」と揶揄されている勢力ですね【注2】。言葉の背景からして、「woke」を「意識高い系」と揶揄的に翻訳することに、僕は批判的ですが。
しかし『Schoolgirl』はその「目覚めた」言葉を粗雑に批判することのほうに向かっているわけではない。むしろ、それと違う言葉をいかに語りうるか、という問題設定に繊細に向かい合おうとする。最終的には目覚めなきゃいけないわけだから、寝逃げ・不貞寝で終わり、ではない。善悪を決めるというよりも、その対立軸をずらすというか、どうやったらそこに言葉が介入できるかということを考えている。それは、『しをかくうま』で「詩」や「名前」と呼ばれているもののなかでも問題になっているんです。

文学でAIをどう考える?
森脇
九段さんの小説は、定型的で陳腐化している言葉をどう変化させるか、ということに本当に繊細に向き合っておられる。それは現実的にも重要な話で、例えば「AIは心を持ちうるのか」とか、そういう話も正面から論じてもあんまりうまいこと話が転がっていかないわけですよね。「人間のほうが自由なんだ」とか、「いやすべて機械化できるんだ」とか、そういう陳腐な定型ばかりを話すようになって袋小路になっちゃうのは、そもそも言葉や表現というものに向き合ってないからだと思うんです。
九段
『東京都同情塔』のAI表現については、今反省してるんですよ。途中で実際にAIと対話するというシーンがあって、そこではやっぱり痛みを感じる人間と、そうでないAI、というように、両者を対立的に扱ってしまっているんです。これ書いてる去年の9月ぐらいは本当にこういう回答をChatGPTはしていたんで、それを踏襲するようにしてここの文章を書いたんだけど、実は1ヶ月ぐらい前に同じ質問したら、全然違う回答返ってくるようになっていて。
だからこの小説の舞台である2030年には、おそらくAIはもっと進化していて、もっと人間っぽく語るようになっていると思う。こんなにAIに関する質問をインタビューで受けると思ってなかったし、研究者の方と話すとも思ってなかったんで、その辺の設定はすごい雑にやってしまったかなあと思っているんです。だから『東京都同情塔』が芥川賞とったのって本当に奇跡的な巡り合わせというか、この2024年の第170回芥川賞じゃないと取れなかった。これが半年後の171回で候補になったとしても、2030年のAI、という点については全然リアリティがなくなっちゃってたと思う。
たぶん機械が人間の仕事を奪うとか、機械対人間みたいな話も、もう5年10年経ったら全然古くなってしまって、どちらも見分けられないような状況が来ると思うんです。たとえば私の小説も、どこにAI使ってるんですか、とか頻繁に聞かれるので、初めの頃は律儀にここはAIでここは私で、と答えていたんですけど、なんだかそこを区別して答えて、読者がそれを元に小説を読んでいくというのが、文学の鑑賞方法のあり方として全然本質的じゃないなっていうふうに思うんですよ。
森脇
まあたしかに、これからは、文学でAIを使うというのは全然センセーショナルなことではなくなっていくでしょうね。普通のツールの一部になる。そもそも九段さんの小説についても、どこがAIなのかなんて全く気にならない。ある意味、どうでもいいと思う。
九段
そもそも、私が書いた部分だって全部自分の言葉ってオリジナルでできてるわけじゃないから。他人から教えてもらった言葉でできてる。例えば、「ここは何とかしなければならない」という沙羅さんの口癖がありますけど、あれは元々三島由紀夫の『金閣寺』の「金閣を焼かなければならぬ」から来てるわけです。そういうことを一つ一つ確認しながらやってたら「何%が自分の言葉」って言えないわけですよ。
強いていうなら、『東京都同情塔』というタイトルはちょっとオリジナルな感じがする。「同情」という言葉と「塔」という言葉をくっつけたのが最低限のクリエイティビティかなあ、って。
【後編に続く】
【注1】対談収録日は2024年5月20日。
【注2】この点については、以下を参照。森脇透青「はたして私たちは目覚めているか——「真の弱者」争いが持つナンセンスさ」『週刊読書人』「論潮」三月、2023年3月10日。
