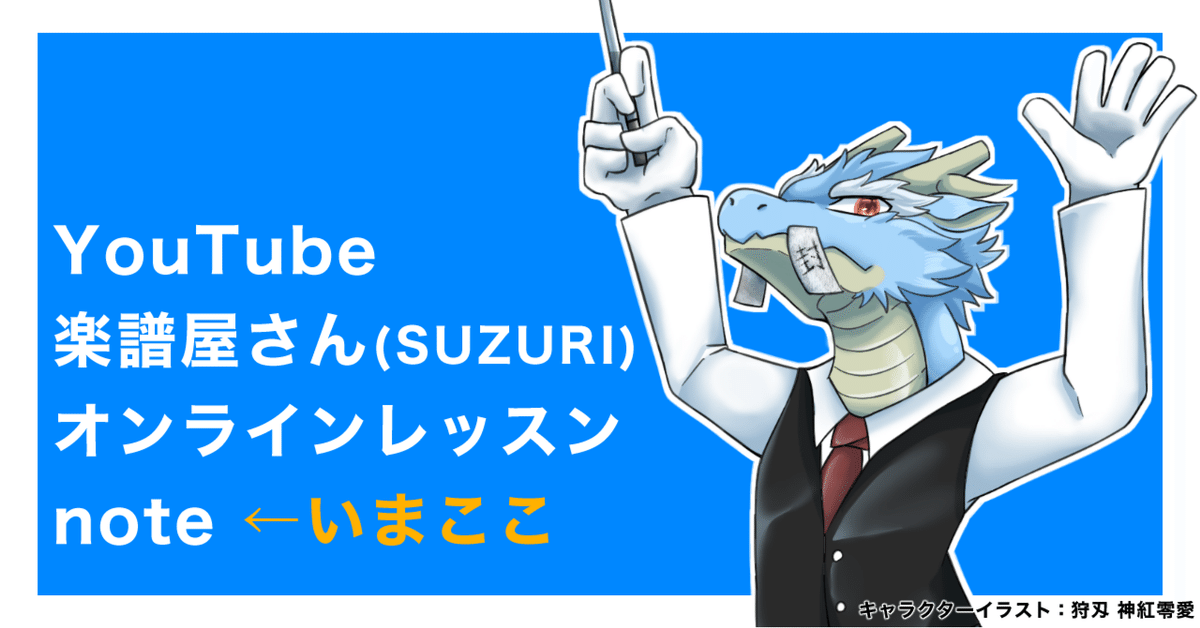
「ドミナント」とは、”何”に名付けられた名なのか?
本記事は、問題提起です。
普段の記事と違って、最後まで読んでも解答編はありませんので、ご了承ください。
(調査できる環境にある方は、どうぞ私の代わりに調査して下さい。)
◆
皆さんの大半は、既に「トニック」「ドミナント」「サブドミナント」という「調性音楽に於いて、和音が持つとされる機能の3分類」を、当たり前のものであると受け止めていることでしょう。
私は最近、方々で語っている通り、この「TDS機能」というもの(の導入の有用性)を懐疑視しています。どう最近?
その過程で、最近ふと疑問に思ったことを綴ります。
"TDS" のフィニシエ
まず喩え話から入りますが、我々は「赤色」を認識するとき、「波長が625-780nm の電磁波だ」という観念で以てキャッチしてはいません。
我々は🍎の赤い色を見るものの、その内部的正体である「リンゴの表面が吸収せず反射した電磁波」の波長……その ”長さ” など、見ることはできないのであって、
まず初めに脳内に出現する観念こそが、「"赤" という色(クオリア)」であるはずです。
同様に我々は、「赤」と「黄」と「青」を、「3つのもの」として分節化して認識し、決して黄色を見て「赤と青の中間(くらいの波長)だな~」とは感じて・考えていないはずです。
考えるとしたら、経験や学習によって得た後天的知識です。
この3つの色は、科学的・内部的には「電磁波の波長の長短」の違いのみに由来するものであって、その特徴は、一次元的(長い↔長くない)かつ、完全に連続的(analog)です。
つまり「赤」と「青」の中間に「黄」という ”独立した色種” を見出す…
”分割” するのは、人間もしくは生物独特の作用であると言えるでしょう。
◆
喩えが長くなりましたが、
じゃあ「T、D、Sってのは、提唱者が ”何(どこ)” を見た(感じた)結果、見出されたものなのか」
「”何” に名付けられた名で、”何” を3つに分節化した概念だったのか?」

「レインボーフラッグ」の6色のデザインが示唆する通り、
「虹は7色」という観念は現在、世界の多数派ではない。
虹の色を「2色」だとする文化圏も実在するが、そこでは恐らくだが、
概念的に「色相」というよりか、「明暗」や「濃淡」が注目されているのだろう。
(その地域の言語における「色」に相当するワードのニュアンスや範囲が、
日本語のそれとは異なる可能性なども考え始めると、問題は簡単ではない。)
寄り添って考えること・汲み取ろうと努めることをしないと、
「虹が2色なわけないじゃん」という諍いが起こる。
この真相の如何により、「三度堆積和音をより積む(13thとか)行為は、その和音の Tなり Dなり Sなりの機能を、濃くするものなのか・逆に薄めるものなのか」、話が全然 違ってくるぞ、と思ったのです。

F△ と F△7(9, #11, 13)、
”よりサブドミナントである” のはどちらか?
◆
※以降、コードネームを書いたら、全部が「Cメジャーキー上の話」だと思って下さい。あとドイツ語音名は出て来ません。英語音名です。
”薄める” 派の主張
なぜなら、C△7 って、主和音のはずなのに「導音(B音)が未解決のまま残っちゃってる感じ」とも思えるじゃないですか。
(古典派~ロマン派 中期 頃の時代だったら「その解釈しかあり得ない」と言ってしまって良いと思う)

(実際は2小節目頭を G7/C の形にする方が、より "良い感じ" で普通。)
C△9 まで積めばもっと明示的です。ドミナント機能であるはずの G△ の和音が、完全に内包されています。これは「トニック機能とドミナント機能の合体和音」と表現しても、幾分かの真実を言い当てていることでしょう。
(そこの受け止め方の違いは、「流派」の違い。単純な正誤ではない。)
その極論の話が、↑の動画の話です。メンバー限定ですまんな。
◆
🍎△7が、「トニック機能を体現する落ち着いた響き」であるとする観念は、ジャズの系譜に特有の、音楽史上では相当に後発のイデオロギーです。
その心は「ひねくれた響きで終わりたい」、すなわち「円満の終止感を避ける」意図で選択
されていると、普通なら受け止めるべき場面。(無論 個人の感性のことなど、一概には言えない)

(具体的に特定のプレイヤーを真似たわけではないので、理解度が低い印象かもしれない。)
和声法的な観点からは「刺繍和音」もとい「解決の延引」を拡張し・多用していると着目できる
……というのが上の方の小さいコードネーム。
――Ⅰ△7 を「多少華やかさが増すものの、これも落ち着いたサウンドになると思います。(p51)」と思うのは、当たり前の感覚じゃないんですよ。
それはジャズの文化の思考回路で「〇7ではないから」という相対化の上で「相対的に ”トニック感” を体現した響きである」という手順を踏まえて説明しなければ、ジャズ界隈の外でまで「当たり前」とはできません。――
◆
ジャズの話をし過ぎたので話を戻します。”薄める” 派の主張の話です。
こちらの思考回路を採るならば、「最も混じりけの無いトニック」であるのは、シンプルな三和音である C△ …という考え方も可能なはずです。
元はと言えば tonic は単音の主音のことを指しているし、dominant も同じく単音の属音、subdominant も同じく単音の下属音の呼称であって、それを「その音を根音とした三度堆積和音にも、同様の役割が宿ると "見なす"」、という発想こそが、「調性システム」というコンセプト・もしくは西欧音楽の作曲アプローチの一つです。
”濃くする” 派の主張
こっちはまぁ、最近のジャズに関する記事のあちこちで触れて来た通りの方の話です。さっきのがクラシック的で、こっちのはジャズ的な思考回路・感性なのかもしれません。
――一方で、13th音 まで積んでやれば、積むだけで C.Q. は一応 7種7様 に分化することも分かります。―(中略)―逆に考えれば、「その和音が(特定のキーの)ダイアトニック・コードであると仮定する」という条件付きならば、コードってテンションマシマシにする行為のみで、その機能は(消去法的に)特定可能へ近づいていきます。――
――Em7/A という情報量(手がかり)の多いコードは、もしもこれがダイアトニック・コードであるならば、D:Ⅴ上の和音 か、G:Ⅱ上の和音 か、C: Ⅵ上の和音、3択まで絞られます。――
◆
これらの話は全て「和音にテンションを積めば積むほど、その ”機能” は濃くなる」という主張を、前提としないと成立しないお話でした。
では ”TDS機能” の方、についてはどうなのか?
比例して同じく濃くなっていく性質のものなのか(であったのか)。
補足が遅れましたが、先程の ”機能” というのは、実際は「ディグリー(和音の音度)」の意味合いです。
ただ実際、それは ”TDS機能” の方とも連動することが当たり前…と思われていると思う(多分)ので、曖昧に、単に「機能」とだけ表記してしまっていました。
今回の記事のトピックを踏まえると、これまでの「機能」という書き方には、問題があり兼ねない、ということになります。
◆
これというのはやはり、TDS機能の提唱者が元来、何のクオリアを指して「トニック」だの「サブドミナント」だのを ”感得して” いたのか、によって左右される話となってきます。(恐らく「人工的な概念」でFAだもの。)
このような観点自体が、私を含む我々には抜け落ちてしまっていたのではないか?という問題提起です。
より詰めていくなら、「TDS機能、その ”T”感、”D”感、”S”感 という3つの観念は、元はと言えば ”何” に由来していた観念だったのか」ということになります。
「”何(どこ)” を見ていたのか」でしょうか。

虹は「色」という(日常的には離散的な)概念に注目すれば、6つや7つに分割し得る。
一方、電磁波の「波長」要は「長さ」という連続的量には、(便宜的に分割するのでなければ)
そもそも分割(すべき)点が無い。1nm と 2nm の隙間には、1.1nm も 1.00…1nm も存在する。
今回の話は、もしあなたが音楽学者や歴史学者だと言うなら、頭を抱えるべき、あるいは究明・解決すべき話題であるかもしれませんが、
あなたが「作曲家」であるならば、今回の話は朗報のはずですよ。
「(共に有効そうな)ものの捉え方・考え方が2種類ある」ということですから。
◆◆◆
記事は終わりです
関係ないけどYouTubeに各方面への配慮が神経質すぎて伸びてない音楽の動画をあげています。(1本の編集に1か月~半年かかります)
チャンネルは作品がメインです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
