
第八回「北の国から恋は始まる!?」
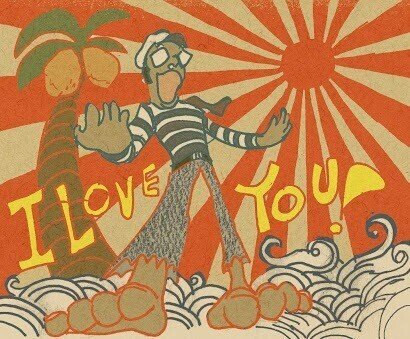
◆一九九三年 大冷夏 獨協
「三強の対決」はいいものだ。僕は昔から三角形というものにも惹かれていて、テストでそれを扱った証明問題とか見つけると好んで解いたりしたものだ。三という数字はバランスをもたらす。また「三度目の正直」と言う様にカタチとして現れる原理数とも云われ、しばしば歴史の事象にもその類型が多く見られる。中国の三国時代における「天下三分の計」もその一つであるし、競馬界においても語り継がれるのは「テンポイント・トウショウボーイ・グリーングラス」などの名馬を筆
頭に、いつだって三つ巴の体をなすのが常だった。
「やっぱ三強で決まりだろ」
「弥生賞のチケットとタイシンの鬼脚は凄かったもんな」
「あれ、武豊は本番に向けて脚を測ってたんだろ」
「でも、自在性ならビワっしょ」
高校時代からの競馬仲間である「スピード指数の三枝」はダービーではチケット推しなようだが、弘樹はビワを軸にしようと決めていた。いずれにしても、三頭全てを買ったら馬券にはならないのだ。
結果、春のクラシックレースはその脚をカミソリと称されたナリタタイシンが皐月賞を制し、ナタの切れ味・ウイニングチケットが日本優駿を勝った。鞍上の柴田政人の悲願のダービー制覇という、些か仰々しいドラマも伴って新旧の競馬ファンを大いに沸かせた。これで残る三冠目の菊花賞をビワハヤヒデが勝てば、三強世代のシナリオは完成に至る。(そして少し後に、実際にそうなる訳なのだが…。)オグリキャップ、メジロマックイーン、トウカイテイオー、ミホノブルボンと立て続けにスターホースが躍り出てきた近年の日本競馬界は、今この三強世代をもって更なる興奮が渦巻いていた。何しろ有馬記念という年末のグランプリレースの約二分三十秒で、およそ八〇〇億円を売り上げる程なのである。(1レースでの最高売上額は九七年の八七五億とされている)
当の弘樹も仲間うちで競馬狂集団「馬なり」という団体を作っていた位だから、まさに競馬に狂っていたといっていいだろう。そして、競馬のフィーバーというものは、「世相と密接にリンクしている」ものでもある。その競馬熱は時代を取り巻く、特にマイナスの空気感と反比例するかのように、ぐんぐんと高まっていく。これについては競馬に対して偏見を持っている人も多く、知らない人が多いだろうから、少し説明が必要かもしれない。実は競馬の歴史は、災害や復興と深い関係性を持っているのだ。まず競馬法第一章第一条にはこう記されている。「競馬を開催できるのは、著しく災害を受けた市町村に限る」と。戦後の日本の復興、震災からの復興ということが、競馬の成り立ちにおいての前提条件であり、だからこそ全国に公営の競馬場が広がったといえる。まさに負からの脱却への潜在意識が競売熱をあげる、そう宿命づけられていると言えるのだ。
葦毛の怪物オグリキャップが国民的アイドルホースとして活躍していた頃。それは弘樹が将来についてぼんやりと考え始めた中学高校時代なのだが、そういえば何かと暗いニュースが多かったように思う。僕らが未来に対して希望を持とうが持つまいが、当時の日本丸という船は、日々ずぶずぶと沈んでいっているような嫌な感覚が蔓延していた。国内で初めての消費税導入があり、次いでバブルの崩壊、佐川急便事件、自民党五十五年体制が終焉を迎え、更に自然災害が頻発するようになっていた。得体のしれない何かの怒りが発動し、スサノオまでもが暴れ出したのかもしれなかった。
そして今年は一月の釧路沖地震に始まり、二月の能登沖地震、テレビでは国営放送のヤラセ事件が連日報道され、八月に入っても雨はしとしとと降り続き、ずっと止むことがなかった。一度は梅雨明け宣言した気象庁も、沖縄以外全ての地域でその宣言を撤回するという異常事態が起きていた。
「夏がない夏」であった。とはいえ学生たちにとって夏休みであることに変わりはない。何もしないで過ごす事も出来るし、何か一大イベントを引き起こす事も出来るバケーションなのである。そういう点で弘樹の大学一年目の夏はというと、どちらともいえない宙ぶらりん感は否めなかった。とはいえ休みに入ると弘樹は、バイトの合間をぬって同期のミライがつくる長編映画のロケに参加することに決めてはいた。サークルの先輩たちは、映画をつくることより、楽しい思い出づくりを優先させていてるようで、弘樹はどこか物足りなさを感じていたからだ。「早く映画づくりを覚えたい」そんな時にまるでナンパするように軽く誘ってきたのがミライだった。
「弘樹、一緒に映画をつくらない?」
断る要素などある筈もないだろうという、彼の爽やかさというか、育ちの良さみたいなものが弘樹を一瞬戸惑わせた。大人しそうでいて随分と直球な奴だな~という印象は、その後もずっと変わることはなかった。
「仲間もいるからさ。そしてもう脚本も出来ているんだ。前期のテストが終わったらすぐ撮影に入ろう!」
同じサークルのノリやイセアサミも参加するというから、気持ちは楽だった。聞けば、ミライは高校時代から映画を何本も撮っていて、自ら自主映画の団体を主宰しているらしい。また最新鋭のVX1というカメラを三台、ガンマイクや編集機、照明など撮影に必要なものも全て持っているのだという。凄い!何ということだろうか。まさか同世代で既に映画創りをしている奴がいるなんて思いもよらなかった。弘樹の周りには毎週コンパして遊んでいる仲間か、もしくは「将来俺たちはいい思いしちゃうからな」とガリ勉に励む奴らしか今までいなかったのだ。
さて、釧路の友人Jからの手紙は、相変わらず気まぐれなタイミングで届いていた。手紙が届くと、僕はいつもどこかの喫茶店でそれを読む。読んだ後、何度かぼんやりとそれを眺めてから、その場で返事を書くことにしている。その日は、草加のコロラドという店でJから昨日届いたばかりの手紙を開いていた。最近R女史がその店でバイトを始めたと聞いて、冷やかしがてらに来てみたというわけだ。
「ヒロキくん、あと三十分で終わるから」
R女史は小声でそう囁くと、僕の前に頼んでもないドリンクを置いた。
「これがアイス・アーモンドオレよ」
(僕は甘いものは頼まないのだが)彼女の最近のお気に入りの飲み物らしい。すぐさま「それ飲んでいい子にしてなさい」というような手振りをして仕事に戻っていった。
Jの状態は掴みやすかった。意中のミカちゃんと何か事件があれば長文の手紙になり、そうでなければ「いつ北海道へ来るのだ君は!」という督促めいた文言が、中島みゆきの詩と共に記されているのが特徴であった。どのみち酒を飲みながら書いたのであろうことは分かっていたのだが、それにしてはまるで純文学のようになかなか読ませるものでもあった。Jという名前だけに、それらの手紙を「J文学」と僕は命名し、ファイルしていた。
「なんか、Jくんてオトナって感じ~」
「えっ、どこが?」
仕事を終えたR女史が、自分で作ったアイス・アーモンドオレを片手に呟く。例の如く勝手に人の友人の手紙を読むなよな~とも思ったが、彼女の思わぬ感想に僕はうっかり反応してしまった。
「本を読んでる人って、言葉に色があるから凄いなぁって。感じてることを素直に書けるって素敵だと思う」
呑んだくれの与太話だと笑い飛ばして読むかと思いきや、素敵とか言ってるし…。
「ふ~ん、言葉に色ねぇ」
「わたしもさ、いつか文章を書ける人になりたいと思っているの。会ってみたいなぁ、Jくんて面白そうな人ね」
「まあ会ったらがっかりするかもよ」
そう言うと彼女はクスクスと笑いながら、再び手元に視線を落とした。そして真剣に読み耽る彼女の姿を眺めていて気がついた。どうやら僕は嫉妬しているようだった。
R女史とは、サークルに入って以来毎日のように会っていた。バイトが忙しかったからそれ程長い時間という訳ではないが、なぜか気がつくと傍らに彼女は居た。サークルの飲み会で終電を逃した時などは、決まって彼女の家に泊まらせてもらうのが通例にまでなっていた。
「ところで弘樹くん、あれぜーんぶ観ちゃったわよ。で、いつ行くの?北の国へ」
「八月のお盆過ぎてからだな。夏期講習があるから、出来れば八月後半から。一週間は最低必要だけど、本当に行く気?」
「うんっ」
言葉より先に、弾ける笑みが返ってきた。
梅雨があけない夏だったが、ヒットナンバーチャートの1位はユーミンの「真夏の夜の夢」。熱い夏を歌い上げる曲が売れに売れていた。そして気がつけば、ミライの長編映画「THE IDENTITY」もクランク・インを迎える。アンドロイドのような戦闘人間たちと戦う主人公。彼もまた実はアンドロイドの初号機だったという設定らしいが、CIAやFBIも出てくるし、弘樹には一体どんな映画になるのか想像もつかなかった。タイトルの意味する「自我をこえ、自分とは何なのか?」を問いかけるヒューマンラブストーリー、というのがこの作品のテーマなんだとミライは自信満々に語っていた。彼はこの映画にかけている様で、家族のサポートも相当に厚く感じられた。家でご飯をご馳走になれば、歌声サークルをやっているお父さんがギター片手に現れ、「林くん人生はさ、表現することだよ」なぁんて語りかけてきた。そして終まいには決まって「さあ、みんなで歌おう」と、梅原司平の「愛ある街で」の合唱となるのだった。映画で食っていこうなどと言うものなら、勘当されるであろう弘樹の家のアイデンティティとは根本から違っていた。
ロケの最中、ミライはいつもclassの「夏の日の1993」を口ずさんでいた。そして「監督をしながら主演もこなす俺ってコビン・ケスナーみたいだろ」と言っては「どこがじゃー、しかもケビンだし」と記録係のイセアサミとふざけあう姿がよく見られた。そんなイセだが少し距離をとってミライを見ている時には、ふと普段見せない表情を覗かせることがあった。
カメラマンのノリは、初の映画制作のはずなのに斬新なアイデアを出しては、せっせと画コンテを書いていた。その画がまた上手い。そして数々の名作のカットワークにも詳しかった。更にノリは撮影しながら名脇役をも務めるという、マルチな才能ぶりをも開花させていった。日を追うごとにボルテージも上がり,ある日のロケの終わりには、なんと夕陽に向かって「○子ちゃん、好きだー」とクラスの帰国子女の子へ愛を叫ぶまでに到る始末だった。
そして弘樹はといえば、とにかく初めての長編ロケに夢中だった。複数のバイトの掛け持ちで全ての撮影に参加することは叶わない。それでもBカメの撮影を担当させてもらった。最新型のカメラの扱いを覚えながら、言われるがままにカメラを据える。移動撮影では、ぶれないように中腰で走る。クリエイティブな真剣勝負というものに触れた気がした。何度も脚がつったけれど、実に楽しかった。一つ難点をいえば、自分の演技力だったろう。友人役やスナイパー役など、撮影したラッシュを観ると鳥肌が立つようなひどい代物だったと思う。弘樹が「今後一切演技はやらない」と心に誓ったのは、たぶんこの時だったはずだ。(実はその後、弘樹が主演を演じる宮沢賢治原作の映画を撮ることになるのだが、結局その作品はお蔵入りとなるのである)
雨が降ればノリのアパートで撮影し、たまの晴れ間が見えれば八国山で銃撃戦を撮った。日本中で米騒動といわれる程に、どこにもお米がなかったから「いっそ国の米倉庫を襲っちゃうか」とマシンガン片手に語り合う夜もあった。(でも、初めてタイ米を食べたらこれが意外に美味しかった)
メンバー各々の夢は違っていたし、いつか誰かが認めてくれるかなんて検討もつかない。でも、ノリの勧めで映画「冒険者たち」を観れば、俺たちこそ冒険者なのだと気持ちは高ぶった。噂で映画の大手五社の一つである日活がとうとう倒産したことも知らされた。しかし暗いニュースには慣れっこになっていた僕らは「希望はまだ、ある」と信じていた。何はなくても僕らには映画があった。若者にありがちな熱病のようなものだと言われても、仕方がないことは分かってはいた。だからどうなんだ、大人はどうなんだとすぐに言い返すことは出来ないが、けれどせめて僕らの映画が完成するまでは待ってもらいたかった。
八月三十日。R女史とは夜八時に上野で待ち合わせた。十時半、急行八甲田は、赤い電気機関車に牽かれ上野駅を出発する。僕らはビールと、乾燥ホタテの貝柱をつまみに買いこんで、早々に飲み始める。これから北海道に行くとのに上野でホタテを買うなんて可笑しいよと彼女は言ったが、いやこれが美味いんだよと笑いあった。
出発して三十分ほどで大宮駅を過ぎる。夜行列車に乗って自宅の前を通過するというのは、不思議な気持ちになるものだった。隣のR女史は出発前から飲み始めて酔いが回ったのか、早くも寝息を立て始めていた。
宇都宮を過ぎるともう乗り込んでくる人もいなくなった。車内の照明も落とされ、弘樹は読んでいた渡辺淳一の文庫「阿寒に果つ」を閉じる。車窓からたまに見える幻想的な光を眺めながら。弘樹は考えていた。厳格な父のことを、そしてこれからのことを考えていた。父にはまだ「映画をやりたい」と面と向かって言えてはいなかった。言えば反対されることは分かっていたから、現状は執行猶予みたいなものだった。だから今は必死に掛け持ちのバイトでお金を貯めているのだ。あと百万円くらいあれば足りるだろうか。生活資金と学費、そして映画制作の資金と、まだ過剰なバイト生活は辞められなかった。
「弘樹くん、ここどこ?」
寝ぼけているのだろうか、R女史は僕に寄りかかったまま聞いてきた。
「福島あたりだから、まだ大丈夫」
「そう…か、弘樹くん、君も少しは眠りなさい」
言い終わると、再び一定なリズムですうすうという寝息が聞こえてきた。仙台には着くのは夜明け頃になるだろうか。何も考えずこのままどこまでも走っていきたいなと思った。
「自立しよう、年が明けたら家を出よう」
そう決めたのは夢なのか、現だったのか、もう弘樹には判断出来なかった。
二0一七年 ヴェネチア に続く
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
