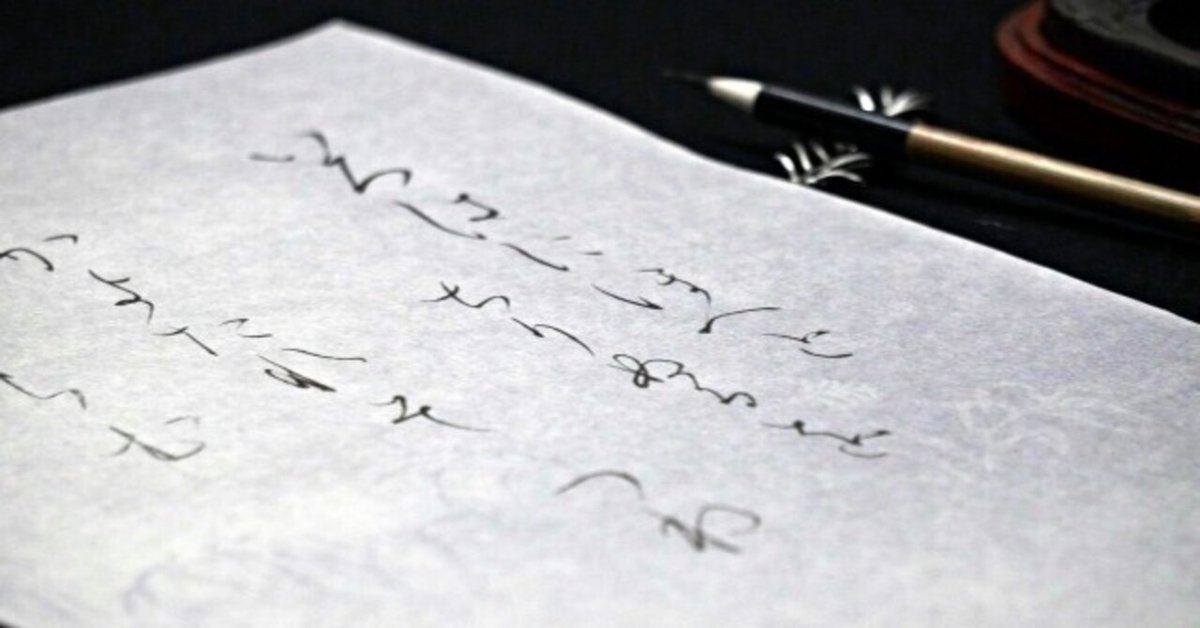
つれづれなる恋バナ 第六章 移りゆく季節【歴史長編恋愛小説】
第六章 めぐる季節
春から初夏へと移ろいゆく季節。ほかほかとした風がそよぎ、京の都は心地いい陽気に包まれている。
四月中酉(中旬)の日、賀茂祭が色鮮やかに都大路を彩る。御所から、例祭が催される下鴨神社と上賀茂神社までを、華やかな行列が練り歩く
いま花園帝は二条富小路内裏に居している。そこから衣冠などに飾りをつけた勅使、供奉者らが行列をなして富小路を北上し、下鴨神社を経由し上賀茂神社に参向する。その行列自体が「路頭の儀」と呼ばれる儀式の一環で、洛中を颯爽と進んでいく。
「兼好、良い場所を確保したな」
牛車の中で、堀川具守は上機嫌である。堀川家の牛車は、路頭の儀をはっきりと眺められる地点に停車している。牛車の先導役を務め、いち早く通りに到着し絶好の場所を確保した卜部兼好の貢献によるところが大きい。
「兼好様、どうもありがとう」
兼好にねぎらいの言葉をかけたのは、唐橋咲子である。咲子は胡坐をかく具守の横に寄り添うように座っている。二人の手は、固く結ばれている。
牛車の中には今、兼好、具守、咲子の三人が乗っている。
「若葉の梢が涼しそうに茂るこの季節になると、春のみずみずしさがむしろ寂しさを誘い、人恋しくなり心がそぞろになる」
ぽつりと具守がつぶやく。どういうことだろうと兼好が首をかしげていると、
「だからこそ、一条よ。お前がここにいてくれることが、無上の喜びなのだ。こっちを向いてくれ、一条」
うっすらと笑みを浮かべた咲子がそっと振り向く。具守はゆっくりと顔を咲子に向けると、左手で優しく彼女の頭を撫で、そのまま唇を寄せる。二人は目を閉じ、舌を絡め合う。流石に居心地が悪くなった兼好は、
「では私は外に出ますゆえ、あとはお二人で」
と言い、行列が見渡せるよう牛車の物見窓を開けると、そそくさと一人牛車の外に出た。気まずくなったのは、主人とその愛人の接吻姿を見ただけでなく、思い続けてきた女が目の前で唇を奪われたからであることを、自分自身痛感していた。
牛車の外では従者たちが待機しているが、気まずさに支配された兼好を見て、みなせせら笑っている。もうすでに牛車担当のこの者たちには具守と咲子の密会のことはばれている。無論、彼らも秘密を厳守している。共に同じ隠し事を共有する者が増えて、兼好は少しばかり気が楽になってはいた。
間もなくして路頭の儀の行列が始まった。装飾が施された牛車や風流傘を目の当たりにした見物人からはさかんに歓声が上がる。具守の牛車の前で行列を眺める兼好の周りにも、見物人が寄って来ていた。
ざわつく周囲を気にすることなく行列に注目していた兼好に、若い男が声をかけた
「おや、卜部どのではございませんか」
兼好はその声の方を振り向く。
「ああ、二階堂どのではないか」
立っていたのは、二階堂貞宗という、二十二歳の若者だ。一役人として朝廷に勤務している。
「歌会以外の席でお会いするのは、初めてですな」
「確かに」
この男、兼好と同じく、歌壇の大家・二条為世の門下で学ぶ歌人仲間である。
「祭りを拝しながら、互いに歌でも詠みますか」
この場で簡易な歌会を提案した貞宗。彼は若手門下生の中でもその才は群を抜いている。
「いやいや、私は今日は遠慮する。それにしても、そなたは根っからの和歌好きだな。いつでもどこでも詠めるのだから」
「藤大納言様もおっしゃってたじゃないですか。森羅万象あらゆる物事に心を寄せ、感じ、思いを発することが大事だと」
藤大納言とは、権大納言である二条為世のことだ。
「ああ、私も常に心がけている。それが『もののあはれ』であると」
「では、あれを見てどう思われますか?」
貞宗が指さした先にあるのは、行列の中にあってゆっくりと進む御所車の、御簾に飾られた葵の葉だ。
「あの鮮やかな葵を、祭りが終わってしまえばもういらないからと、すぐに捨ててしまうのはもったいないと私は思います」
貞宗が思いの丈を率直にこぼすと、兼好も我が意を得たりといった感じで、
「さっさと捨てると私に言った人もいたなあ、そういえば」
と応じた。そして、
「枯れてしまうまで、そのままにしておくのも風流なものだと思う。周防内侍という女性がまさに、御簾にかけた葵が枯れるのを歌に詠んでいる。『枕草子』には枯れてしまった葵に郷愁を感じるというくだりがあるし、鴨長明も『四季物語』で祭が終わっても葵が懸かったままの様子を綴っている。葵はただ自然に枯れていくだけ。なのに名残惜しむことなくさっさと捨ててしまうのは、罪深く感じる」
「さすが卜部どの。見事な所感でござる。和歌に親しみ、書物に造詣が深いあなたらしい」
年下の秀才に褒められ、兼好は照れ隠しに少しばかりうつむく。
「見たまま感じたままの思いを表に表す。歌を詠むことは実に面白く奥深いというのに、歌壇は醜い争いごとで揺れている」
「そうだな……」
「まあ、その話は、ここではやめておきましょう」
二人の胸の内には、ここのところ気がかりで仕方ない歌の世界の現状がある。だが、華やかな行列を前に、それをここで話題にするのは避けた。
やがて行列は過ぎていった。ごったがいしていた見物人も、ぞろぞろとその場を後にしていく。そして二階堂貞宗も兼好に暇を告げ、具守の牛車に深々と会釈をしてから立ち去った。
貞宗を見送った兼好は、ゆっくりと御簾を開く。屋形の中には、肩を寄せ合ったままの具守と咲子がいた。見物の最中も、ずっとそうしていたのであろう。
「行列は去りました。そろそろ、ここを発ちましょう」
落ち着いた口調を装い、兼好はそう告げた。具守は物見窓の外に目を移し、そっと声を発した。
「見物人が足早に去り、桟敷の簾や畳も片づけられておる。祭りのあとは寂しいものよのう。人の世の移り変わりを、見せられているかのようだ」
外の風景を覗きながら、六十二歳の貴人はしみじみと語った。そして、兼好の方を向く。
「兼好よ。行列を見ながら、わしは一条に、近々左大将を辞して年内には大納言を辞す旨を伝えた。一条はそっと頷いておった」
具守は咲子の身をさらに寄せる。
「その後は私は、岩倉の別邸を居として余生を過ごす。景子はまだ若い具親を後見せねばならぬゆえ、堀川邸に残ることとする。だから一条とは四六時中共に暮らせるようになる。別邸には彼女に一室を与えるつもりじゃ。のう、一条」
「ええ……」
具守に促され、ゆっくりと頷いた咲子。だが、その視線はまっすぐ具守に向かわず、すこしばかり斜めのあたりに置き、うろうろと瞳を動かしていた。その姿は、兼好にはかわいらしく見えた。やはり、いつになっても、この女のしぐさのすべてが、かわいい。
「では、一条の家まで送るとしよう。兼好、車を進めよ」
「ははっ」
兼好は車を降り、従者たちに出発を告げた。牛車は富小路をゆっくりと北へと進み、咲子の住む唐橋邸を目指す。
さきほどまでの煌びやかさとは一転、あれほど溢れていた人混みがすっかり消えて、通りはいつもの日常よりも寂しげである。同じ場所が、ほんの一瞬でこんなにも虚しくなる。そんな中、具守は咲子を抱きながら、希望に満ちた余生に思いをはせていた。時の流れに逆らえず身を引く自らの境遇に抗う精一杯の強がりのように、兼好には思えた。
山に囲まれた盆地である京都の夏は暑い。
七月に入り、暑さはまさに盛りだ。ぎらぎらに照りつける日差し浴びながら兼好がやって来たのは、歌の師である二条為世の屋敷だった。今日は二条邸で歌会が開かれたのだ。
「籐大納言」こと二条為世を総帥とする二条派の門弟が集い、御題に合わせて歌を詠み競った。今回の参加者は若手中心の構成だったためか、和歌師範の為世が盛んに感嘆するほど、活気のある歌会となった。
歌会が終了し、門弟たちが続々二条邸を後にしたが、卜部兼好と二階堂貞宗のみ屋敷に残るよう通告された。他の出席者が全員退出したのち、二人は為世の書斎に赴いた。
為世は参加者が和歌を自筆した紙に一枚一枚目を通していた。兼好と貞宗が着座すると、手を止めて前方を向き、二人に視線を移した。
「本日二人が詠んだ和歌は見事なものであった。成長の跡が感じられる。今日参会した若い衆の中では、群を抜いているといってよい出来じゃった」
普段は厳しい指導で鳴らしている為世は、嬉々とした面持ちで兼好と貞宗を称えた。師範から高い評価を得て、二人は深く礼をした。
「もったいないお言葉、痛み入ります」
兼好が会釈すると、為世の口から思いがけぬ言葉が飛び出した。
「私が次なる勅撰集の選者になれば、お前たちの和歌を撰集するとしよう」
「本当ですか」
兼好と貞宗は顔を見合わせた。これを伝えるために、為世は二人を屋敷に残したのだ。勅撰集の入選は、一人前の歌人として認められた何よりの証になる。為世は去る嘉元元年(一三〇三)に後宇多院の院宣により『新後撰和歌集』を撰進している。今回選者となれば、自ら率いる二条派の歌人の歌を多数選抜する構想を持っていた。二〇代の若手二人の歌が選ばれるとなると、大抜擢といえる。
(これで一人前の歌人と認められる。名を売ることで将来の任官にもつながる)
兼好は為世の言葉を素直に喜んだ。無官に陥ってもう二年近くになる。長いこと曇り空に覆われた中で、ようやく希望の光が差し込む感覚がした。
一方で、二十二歳の貞宗は極めて冷静だった。
「藤大納言様が選者になるかは、京極様との訴訟次第。私は決して楽観できませぬ」
若い弟子の鋭い一言で、為世は即座に真顔になり、室内に緊張感が走る。
「京極為兼は我が従弟であるが、勅撰集の選者には全くもって不適格な人物である。彼が選者に選ばれるなど、決してあり得ん」
二条為世と京極為兼は血縁が近いにもかかわらず、二条派と京極派に別れ、歌壇の主導権を争っている。二人の曽祖父は『新古今和歌集』を撰進し『小倉百人一首』を編纂したことで名高い藤原定家である。この定家の系統、いわゆる「御子左家(みこひだりけ)」が和歌の名家として君臨していたが、為世、為兼の父の代に相続争いから二条、京極の二派に分裂した。
この両者が勅撰和歌集の栄誉ある選者の座を巡り、訴訟合戦を繰り広げている。この年、すなわち延慶三年一月に為世が訴状を提出、為兼も受けて立ち申し立てを行い、朝廷を巻き込んだ歌壇の主導権争いは激しさを増していた。
「私は二条家の嫡流で祖先に親しく学び、代々の歌書を相伝し保守本流を守ってきた。だが為兼は分家の身でありあくまで庶流。 庶子で選者になった先例は無く、思い上がりも甚だしい。 また為兼は以前に不祥事で佐渡に配流されたことがある。かつての罪人を栄えある勅撰集の選者とするのは不吉である。この訴訟、間違いなく我々が勝訴するであろう」
為世は自信をのぞかせる。二条派こそ歌壇の本流という認識は世間でも強く、その総帥が当世の勅撰集の選者から漏れるとは、常識的には考えにくい。それに為世は軍事権を握り実質的に国政を動かしている鎌倉幕府の将軍、執権の歌道師範をも務めている。まさに歌壇の権威である。
ただ、為世の主張はいささか感情的であった。保守的な歌風を遵守する二条派に対し、破格・清新な歌風を提唱する京極派は革新的と言え、確かに対立構造は明確だ。だがそれよりも、為世が個人的に為兼のことを大いに嫌っているのが、言葉の節々から伝わってくる。それに対し、貞宗が落ち着いた口調で言葉を発した。
「しかし、選集を計画しておられる伏見院に、京極殿は近習として長く仕えておいででした。この関係を利用して単独で選者になろうと目論んでいると聞き及んでおります。京極派隆盛の千載一遇の好機とみて、どんな汚い手でも打ちかねません」
歯に衣着せぬ貞宗は師匠に対しても決して物怖じしない。その上で時局をあくまで冷静に観察している。いくら朝廷内での訴訟であっても、「勅撰集」であるから最終的には伏見院の裁定に委ねられる。「身内びいき」の結論に至る可能性は全く否定できないのだ。
「貞宗、お前の言うことはよくわかる。確かに、為兼は伏見院との関係は近い。実際に為兼本人が伏見院に勅撰和歌集撰集を進言したようだ。だが、後世にまで残る和歌集である。肝となる選者に誰を起用するかは、慎重な判断が求められるはずだ。伏見院もそのあたりはよくわかっておられるだろう」
為世はあくまで強気だが、話をじっと聞いていた兼好は、「伏見院は京極殿に選者を任せたいのが本音ではないか」と思えてならない。
(ここでも、政治の権力争いが絡むのか)
兼好は愕然とした気分になる。二条派は後宇多院が率いる大覚寺統と結んでいるし、京極派は伏見院が支配する持明院統と強固につながっている。筋論では二条派が優位のはずだが、今は伏見院の皇子である花園帝の御世。京極派が成り上がる素地はできている。
(歌壇が政界の動向に左右されることは、本来はあってはならぬ)
兼好のみならず、歌壇に属する皆が思っている本心だろう。だが実際は、時の政権の意向が歌集にも反映されるのは紛れもない事実。和歌に限らず、文化を奨励するのは時の為政者である。文芸の世界に身を置くなら、あの手この手を使って政権にすり寄り甘い蜜を吸おうとするのは、いつの世も同じことだ。
(私は歌道に邁進したいだけなのに)
二条派総帥と若手天才歌人のやりとりを傍らで聞きながら、朝廷内の権力争いと同時進行で歌壇の覇権争いがこれからも展開されると思うと、暗澹とした心持ちになる。
(だが己自身も、勅撰集入選をきっかけに出世を掴もうと目論んでいる。人のことは言えない。歌と政治を絡めようとしているのは、私だって同じだ)
人はみな思惑を秘めて生きている。誰しもが欲望から逃げられず、欲望に縛られるがゆえに、姑息な手段に手を染めることもある。人間のやることなんて、大差はないのであろう。「清廉潔白な人間などいるのだろうか」と、不毛な問いに頭を巡らせる兼好であった。
光陰矢の如し。一年が過ぎるのは早い。延慶三年ももう大晦日である。
ところがそんな慌ただしい中、二条為世邸に二条派の歌人たちが集められた。若手の兼好や二階堂貞宗も参じた。
大広間に集合した二条派門弟たちはみな表情が固い。大晦日にわざわざ呼び出しを受けたのだ。これから為世が重大な報告をするのが明らかだったからだ。
「今日は年の瀬にもかかわらず集まってもらい、誠にすまない。だが、どうしても大事な話をせねばならぬので、ここに来てもらった」
為世の第一声が、静まり返った大広間に響く。
「このたび、朝廷より内示を受けた。京極為兼が次なる勅撰集の選者になると」
広間を占めた門弟たちから騒めきの声があがる。自分が選者でないといけないと固く信じていた為世にとって、これは痛恨の報告であった。
次期勅撰和歌集をめぐる主導権争いは、京極派が勝ち、二条派は敗北した。
(やはり、そうか)
後方に正座していた兼好も、がっくりと肩を落とす。
去る十二月二十八日、くしくも堀川具守が大納言を辞したのと全く同じ日、京極為兼が権大納言に叙された。配流先から帰京後初めての任官であり、政府中枢に躍り出たことで、勅撰集選者の座も射止めるだろうと歌壇では推測されていたのだ。
「改元直後にも、伏見院から正式に院宣が下るであろう。誠に無念じゃ」
実はこのごろ疫病が流行傾向にあった。そのため、来年前半に改元することが朝廷内では既定路線となっている。新時代の幕開けに乗じ、満を持して国家の重大事業を天下に宣する狙いがあるのだろう。持明院統政権の権勢を世間に示すことにもなる。
「伏見院との関係を活かして朝廷内でしたたかに根回しをし、鎌倉幕府からも了解を取り付けたようだ。相手が一枚上手であったか」
やはり歌壇といっても政治とは密接につながっている。為兼の巧みな政治工作にしてやられたという感じで、為世は呆然と天井を見つめた。
師範の報告が終わり、門弟たちは足取り重く二条邸を後にする。
兼好も、二階堂貞宗とともにうつむき加減のまま正門を出た。
「これで、このたびの勅撰集入選の夢は露と消えたか。次は何年後、何十年後になるのか」
兼好がぼやくと、貞宗も、
「覚悟はしておりましたが、いざ報告を賜ると、悔しさが増してきます」
冷静な男もまた、悔しさをにじませた。
「主人の堀川大納言様も辞され、これで任官の道は潰えたかもしれん」
二条派歌人として頭角を現し始めた時機だっただけに、兼好の胸に絶望が広がる。
「期待しすぎていたゆえに、喪失感も大きい。はあ、情けない」
「それは仕方のないこと。この世は実に無常です。我々の執着をはるかに超越して、時代は残酷に変化する。世の中の変化に抗うことの、なんと愚かで惨めなことか。だが、抗いたくなるのも、また人間なのでしょう」
貞宗は実に達観した思いを淡々と述べた。秀才ゆえに、勅撰集入集の機を逸したのは相当無念であったはずだが、理性的に胸の衝動を抑制しているのか。少し間を置くと、貞宗は思いつめた表情で口を開いた。
「実は私は役人を辞し、出家するつもりです」
「え、出家?」
貞宗は思わぬことを告白した。
「比叡山に入り、僧侶として本格的に修行することになるでしょう。政治の世界は気疲れが多く、時の政情に歌壇が振り回される実情に辟易しており、隠遁生活を送りながら静かに和歌を詠みたいのです」
「そうか」
若く優秀な後輩歌人の悲壮な決意が、兼好の心に重く響く。
「私も、いずれ俗世を離れるのも、ひとつの選択肢かもしれぬ」
兼好がぽつりとつぶやく。
くしくも、父の兼顕は体調の衰えを理由に来年の吉田神社の正月行事の参加を見送った。事実上の引退表明だ。同時に自らも参加を遠慮し、弟の兼雄のみが任務を果たすことになる。これにより、卜部家の後継者は兼雄であることが公に示される。今後朝廷の祭儀に携わることもなければ、神事のため鎌倉に下向することもない。兼好が神官として生きる道は閉ざされた。
それに伴い、兼好は来年一月から神楽岡の実家をついに離れ、東山の白川通に近い卜部家別宅の小さな庵で暮らすことにしている。
こうなると、隠遁の道を選ぶのは決して不自然なことではない。
「しかし卜部どのには、堀川様がいらしゃるではありませんか」
「ああ、そうであったな」
兼好は具守の姿を思い出す。そしてその横にそっと寄り添う咲子の姿も。具守が引退後も、兼好は引き続き堀川家家司の職を務める。東山に移るのは、具守が余生を過ごすことになる岩倉には、白川通を直進すれば通いやすいためだ。職がある限り、与えられた業務に邁進せねばならない。それがあの二人の愛を深める仕事であってもだ。
(二人が幸せに過ごすために、私はこれからも全力を注ぐ。今はそれが第一の仕事だ)
役人、勅撰歌人、神官、どの道も絶たれた兼好は、もはや堀川具守に尽くすほかない。主人が最も望むことのために最大限献身せねばならない。その一方、自分の中のとある意識が揺らぎつつあるのに、まだ兼好は気づいていなかった。
貞宗とも別れ、都大路をひとり進む兼好の前に現れたのは、帝が住まう御所、二条富小路内裏だ。
先帝後二条院も住んでいたこの内裏は、五年前に火災に見舞われ御所機能は移転したが、花園帝の御世になり少しずつ再建が始まり、現在は仮御所が建つに至っている。鎌倉幕府から造内裏費用が献上されたことによるもので、翌々年にはかつての平安京内裏を限りなく模した豪華な本内裏が完成する予定になっている。
この仮御所において、来年、延慶四年(一三一一)正月三日、十五歳となる花園帝の元服の儀が行われる。そのため、式典の設営に多くの役人が年末年始を返上して駆り出されていた。
御所の正門を多くの役人が行き交っている。その様子を卜部兼好は二条大路に立ち眺めていた。
(今も出仕していたら、私は喜び勇んで儀式設営の現場に参加していただろうな)
天皇の周辺で仕える蔵人職を経験した男である。本来ならあの場にいないといけないはずである。無官の兼好は、忙しく働く後輩たちを羨ましそうに見つめた。
とはいえ、眼前の風景をただ見つめていても、何か起きるわけではない。長居しても無駄なだけである。兼好は御所を横目に、さっと歩き出した。
あたりが暗くなりつつある。大晦日の日が暮れようとしている。明日になると、世の中の空気ががらりと変わる。いつも通りの新年の訪れだ。大晦日と元日はわずか一日の差なのに、人々の心は清浄され、澄み切った風に運ばれるように新たな一年が開ける。
この夕暮れから夜となり、年を越し日の出を迎えたとき、兼好にとって人生の分岐点となる一年が幕を開けることになる。
各章リンク
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
