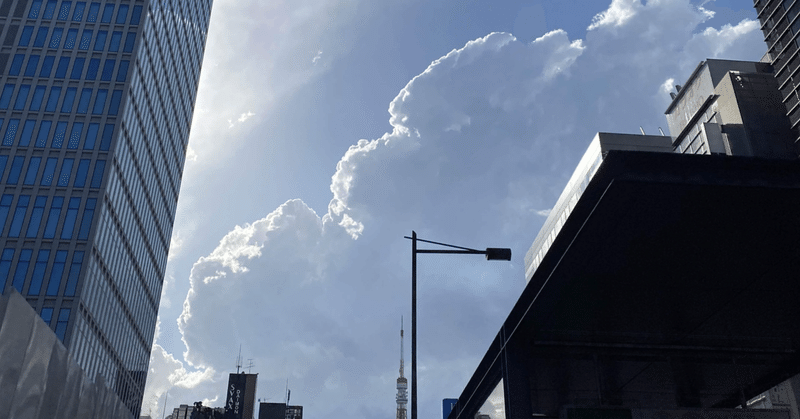
「孤独」から考える「コミュニティ」の必要性
「子どもと大人が夢を共有できる居場所」をつくるために、こつこつ活動を続けています。
先日は、スタッフ総出でヤスリがけを行いました。
興味のある方は、共に活動しましょう!
さて、僕たちが地域コミュニティづくりに乗り出したのは、
「学校で窮屈な思いをしている子どもの居場所をつくりたい」
という僕の思いと、
「地域の人が気軽に集まる居場所をつくりたい!」
という地域の方の思いが合致したため。
先日は、地元のロータリークラブで活動をプレゼンさせていただく機会に恵まれました。
じわじわと認知が広がっている訳ですがプレゼンをするにあたり、そもそも「コミュニティの価値ってなんだっけ?」という根本的な部分をもう一度考え直しました。
結論は、「つながりやすくなった社会で起きる孤独の解消」だと思うのです。ということで、現代社会が抱える問題の一つである「孤独」とコミュニティの価値についてさくっとまとめました。
ぜひ、読んでみてくださいね。
▼「孤独」って問題点と勘違い
そもそもの部分から少しずつ深掘っていきましょう。
気になるのは、「孤独って何が問題なの?」ということ。
コミュニティを率先して作っている僕ですが、そもそも集団が苦手。一人で本の世界に没頭している時間が最高の幸せと思ってしまっている。そんなやつがコミュニティとか…と思いますよね。
しかし、これは「孤独」の捉え方が間違っているのです。
話が込み合ってしまうので、問題点から解決していきましょう。「孤独」の問題点は、単純に健康被害が出るということ。
カリフォルニア大学バークレー校での研究では、「良好な人間関係は寿命を10年延ばす」ことが分かっています。
細かく書いていけばきりがないので割愛しますが、「孤独」がもたらす健康被害は、数えきれないほどあるのです。
「だったら一人暮らしはしない方がいいのかな。」と不安になる人がいるかもしれませんが、ここが「孤独」の捉え方の勘違いなのです。
簡単に言えば、「孤独=一人でいること」ではありません。大切なのは、「人間関係の質」なのです。もっといえば「孤独かどうかということは、その人の感じ方による」ということ。
僕が「一人で本を読む時間が最高の幸せ」と感じているだけで、その一人の時間を「孤独」と感じていなければよしなのです。
そして、逆もあり得ます。周囲から見ればたくさんの友達に囲まれて充実しているように見えていても、精神的に充実した”つながり”を感じていないとむしろ孤独感を深めてしまうかもしれません。
研究者のカシオッポさん曰く、
「他者と過ごす時間の量や交流の頻度は、孤独感の予測にあまり寄与しない。」
と報告しています。さらに、
「孤独とは質の問題であり、他者との触れ合いの意義、あるいは無意味さに対する個人の評価である。」
としています。
#残酷すぎる人間法則
学校でも親御さんとの面談で「うちの子は、一人ぼっちでいませんか?」と相談されることは多いもの。そこには何となく「友達は多い方がいい。」という価値観があるのでしょう。
過去にこんな記事を書きました。
確かに孤独感はおすすめできません。かといって、無理やり人間関係を築こうとしてもうまくいかない。
大切なのは、友達の人数ではなく、自分という存在を受け止めてくれるよりよい人間関係を築くこと。そのためには、コミュニティに所属することは一つの方法です。
だからこそ、「同じ地域に住んでいる」という共通点がある集まりというのはそれだけで人間関係を深める”きっかけ”をつくりやすいのです。
▼まとめ
本記事では、「同じ地域の集まりが人生の幸福度を上げる!」という内容をまとめました。
ぜひとも、ご自身の地域の活動に興味をもち、無理なく参加してみましょう。もしかすると、その地域に住んでいることが、さらに楽しくなるかもしれません!
📙「不登校の教科書」もうすぐ出ます
「不登校はチャンスである!」という理念をもとに不登校の生かし方をまとめました。

5月の終わりに出版予定ですので、ぜひぜひダウンロードしていただけると嬉しいです(^^♪
いただいたサポートは、地域の「居場所」へ寄付させていただきます!
