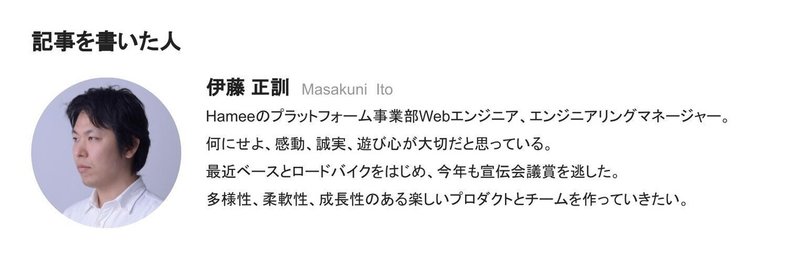中途採用者に大切なことは、環境を変えられると信じていること
こんにちは。Hameeでエンジニアリングマネージャーをしております正訓(まさくに)と申します。最近、自転車のチューブを交換できるようになりました。
さて、先日、新卒内定者の方々向けに「過度に力みすぎない方がいいっすよ」という内容で記事を書かせていただいたのですが、
そもそも僕自身、Hameeに入社したのが2020年4月、その時から状況は良くも悪くも完全にリモートワーク下、力みもゼロではなかったでしょうし、ここまで(今もそうですが)余裕しゃくしゃくで過ごしてきたかというとそんなわけありません。
そこで今回は中途採用者として大切だと思っていることをまとめてみたいと思います。「中途採用者の活躍」について、まぁまぁ役に立つ内容を書けると……いいですよね。(不確か)
前提として、すべて僕の勝手な考えです。
どうすれば転職成功になるのか
個人的に最近友人からよく聞くので「どうすれば転職って成功なんだろうね?」を考えた話を最初にします。よく転職の成功項目として並べられるのは以下でしょうか。
・年収や社会的ステータスが上がった。
・労働時間や福利厚生が最適化した。
・やりたい仕事、成長できる仕事ができるようになった。
・会社が求めるバリューを発揮できた。
・人間関係のストレスが減少した。
最近ではこのHameeをはじめ、noteなどに社内報を載せているようなオープンな気質の会社も増えたので社内情報も集めやすくなりました。もしかしたら人と企業のシンクロ率は高まっているのかもしれません。
しかしそれでも「どんないい会社があったとしても自分が合うかは分からない」ので、何というか、どんなに手を尽くしても最後の一手は運だと思っています。普段の行いというか、カルマというか。転職ガチャといいますか。
特に上記5つめ。人間関係なんて会社関係ないですからね。ビジョンに共感する仲間というくくり、あるいは会社に敷かれている人間関係をフォローする制度・基準などで、ある程度、「自分に合いそうなグループだなぁ」みたいなのが分かったりするんですけど、最後はそんなの勘ですからね。
なので転職が成功したと思うためには、人事を尽くして天命を待ってから、当然また人事を尽くす必要があると思っています。当然。
その尽くす観点として、自分は「仕事はもちろん環境と向き合う」ことが大切だろうなぁと思いながら、中途採用者として働いています。なぜそう思うのかを続けて書きます。
企業側の採用モチベーションを考える
僕は働くということに関して、企業と自分の健全なギブアンドテイクの関係を築くことも大切だと思っていまして、その関係構築自体が転職成功の一つの要素だとも思っています。
片方からの献身だけでは、いい関係って続かないものです。なので前述の転職の成功条件には「会社が求めるバリューを発揮できた」を入れさせてもらいました。
このため、ちょっとここで逆に企業にとっての採用成功とは、ということを考えてみたいと思います。
基本的に企業の採用目的は下記の図、上の青い帯に書いたことくらいかなと思っています。人員補充、事業拡大、転換、活性化、ブランディングなど。よく転職サイトで見かける文言ですね。

そして目的の下には組織課題があります。この課題は裏返すと、採用の条件になります。人員が不足していれば既存メンバーと同程度以上のスキルセットの人を採用したいし、影響力が不足していれば社内外に影響力が高い人を招き入れたい、企業文化は当然継承したいからビジョンマッチは必ずチェックしたい、とかです。
このため、ここを頑張ると仕事で成果が出たりします。コーディングをしたり、ドキュメント作ったり、リリースをしたり適切な成果が出せると、採用目的に沿っているので「この人採用して良かったなぁ」となります。
ただ、実はその下の黒い帯のところ、企業には恒常的なモチベーションがあると思っていて、それは「ミッション達成のために環境を進化させたい」という欲求です。そのためにあの手この手で自分に刺激を与えるんです。
環境とは、ある要素の周囲に存在して、それと相互作用を及ぼす関係のものを指しています。中途採用者をその要素としたとき、同僚、上司という人間関係はもちろん、カルチャー、フロー、制度などの抽象的なもの、バイアス、歴史、背景といった暗黙的なものまで含みます。
ミッションを達成するために、これをいい感じにして欲しい、リソース不足をもっと効率的に補って欲しい、もっと人を刺激してパフォーマンスが100%以上発揮できるようにして欲しい、もっとビジョンに足る会社風土にして欲しい、ということをだいたいいつも考えています。
これは会社側のニーズ、あるいはインサイトに近いものなんじゃないかと思っているので、これを雇用される側が意識しているのと、意識していないのでは全く働き方が変わってくると思いませんか。
このため、中途採用者は「仕事というよりは環境と向き合う」と、結果、会社が求めるバリューに近づきやすく、ひいては転職成功につながるのでは、と僕は考えています。
仕事というよりは環境と向き合うために
本当は「指示待ち人間」という代名詞自体があまり好きではありません。指示をハイパフォーマンスで遂行できるんだったら、それはそれですごいバリューですし。
ただ一定の枠組みの中で仕事を待っている分、上長の能力にまず依存しますし、ロスタイム多いですし、主体性のある二者でなければシナジー出ないですし、雇用という長期的なスパンで見ると、パフォーマンスが出にくい体質なのだと思います。
この「指示待ち人間」を脱却するために、世の中にはさまざまな療治があると思うのですが、そのどれもがやる気や情熱に傾倒するか、仕事術や手法論で心を殺すかのどちらかに見えます。
もちろんどちらも正しいとは思うんです。ですが、本当はもっとシンプルなことかもしれないとも思っています。指示を待つ姿勢になってしまうのは、もっとシンプルに「環境って自分で変えられるんだよ?」と気づいているか、気づいていないか、ではないでしょうか。
環境に対して自己効力感があるか否かとも言えます。
そしてこれは「指示待ち人間」に限った話ではありません。自身の周囲の環境を変えられると気づき、信じているのと、そうではないのとは可動域の次元が違ってきます。
仕事は慣例的にフィールドに立たされてサッカーボールとサッカーのルールブックを一応渡されますが、実はサッカーをやれとは言われていないのです。実は。ずるいよね。
何か今のところ効率的に見えるからサッカーをやってみる、でも本当にサッカーをやり続けるのが効率的なのか否かはずっと内省して、これでいいんだっけと周囲に働きかける。その活動が環境を変動させ、うまくいけば、会社の求めるバリューとなっていくのだと思います。
ずっと中途採用者には、という文脈で話してきましたが、お気付きのとおり、これは実は中途採用者に限った話ではありません。ですが、前環境と現環境を比較できるため、中途採用者には少しアドバンテージがあると考えます。
つまり「仕事というよりは環境と向き合う」ためには、「成果を出す方法を常に洞察しながら働き、必要とみたら自分が環境を変えられると信じて行動に起こす」というマインドが必要になると思っています。
環境を変えるために気をつけていること
環境と向き合うのは分かった、ではどのようなアクションを起こせばいいんだろうということなんですが、僕自身でも暗中模索で、ケースバイケースですし、あんまりはっきりしたことは言えません。(投げた)
ただ、だいたい同じようなフェーズは通るのかなと思っていて、環境への理解、環境への同化、環境への行動が必要になるかとは思っています。そのフェーズごと、対応することは本当に様々だとは思うのですが、下記3つは一貫して大切にしているマインドです。
これらを常に念頭に置いておくと、自然と必要なタイミングでアクションにつながり、人を巻き込み、人に巻き込まれることが多くなっていくと、実体験として感じています。
既存環境の歴史や背景を絶対に尊重する
これは絶対だ、と思ってください。
既存環境と向き合う、手を入れる、意見するににあたって、ありがちなのが、制度や前任者への否定です。環境を再構築するにあたって、批判思考は必要になると思いますが、既存の環境はそのときどきの真摯な判断と努力と状況によって培われています。
そのことを忘れると単に独りよがりな思想になってうまくいきません。このため、常に環境の成り立ちや意味などを傾聴し、理解し、尊敬すること、自己開示をして自分のスタンスを理解してもらうことに力を割くべきだと考えています。
ただし、非常にバランスが難しいのですが、過去には過去の、現在には現在の状況の変化が訪れています。このため、過去を大切にするあまり、現在の環境も変えられないと思ってしまわないような見極めが必要になります。
基本的にどんな環境も良い方向に変えられる
人間関係におけるほとんどの課題は交渉可能です。環境は人間によって作られるので、ほとんどの環境も交渉で変えることができるのではないかと楽観的に考えています。
きっと話せばわかります。役職やロールは関係ありません。そういうとき意識しているのが共通言語です。だいぶ昔に務めていた会社の役員が「全ては費用対効果」と言っていて、彼との交渉テーブルに乗せるものは費用と効果でした。
それはお金であったり、工数であったり、影響であったりしましたが、逆に言うと、費用対効果を示して説明すれば、様々な交渉で対等に話し合うことができました。(だいたい負けましたけれど)
環境の改善にチャレンジして報われなかったとしたら、それは「環境は変わらないんだ」というわけではなく、自分の絶対的な実力不足や、視点不足、交渉力不足、スピード感不足などに起因する失敗なのだと思っています。
環境の改善は局所最適ではなく全体最適を目指す
独善的になると物事はうまくいかないと思っています。この「独」の意味は、もちろん自分一人という意味もあるのですが、自分のチームであったり、部署であったり、局所最適のみを考えたセクショナリズムで動くと失敗しやすいということです。
意見の相違や人間関係でクラスタが作られるのは理解できます。作業分担が生まれるのは自然です。ですがミッションを共有している仲間である以上、何らかの環境が改善されるとき、その主語は局所ではなく全体であるべきだ、と考えています。
このため話し合いを欠かさないようにしています。時間がかかりますし、それでもうまくいかないときの方が多いので難しいところなのですが。あと連携が不要な改善はどんどん局所最適でもいいと思っています。
考え方が違うから環境を変えられる

会社の採用モチベーションを再掲します。
色々書きましたが、この最後の黒い帯、「ミッション達成のために環境を進化させたい」は完全に今の僕の考えで、会社や経営者によっては、もしかしたら別の言い回しや、観点で動いているのかもしれません。
そうです、これまで話したのはすべて自分の場合です。今まで気をつけてきたこと、そう言えばこう考えていたな、ということを言語化しました。
かなり抽象度を上げて、多くの方に当てはまることを書いたつもりですが、これが万人において正しいとは思っていません。将来的に僕も正しいと思えなくなっているかもしれません。
それこそクリエイティブな環境を作るには、様々な考え、スタンスを許容して活かすことが必要であると考えています。中途採用者として成果につながるであろうと思っている働き方は僕の場合はこう。
皆さんはどのようなことを大切だと感じながら働いているのでしょうか。もし一つの視点として、この記事がお役に立てれば幸いです。
それでは、正訓でした。