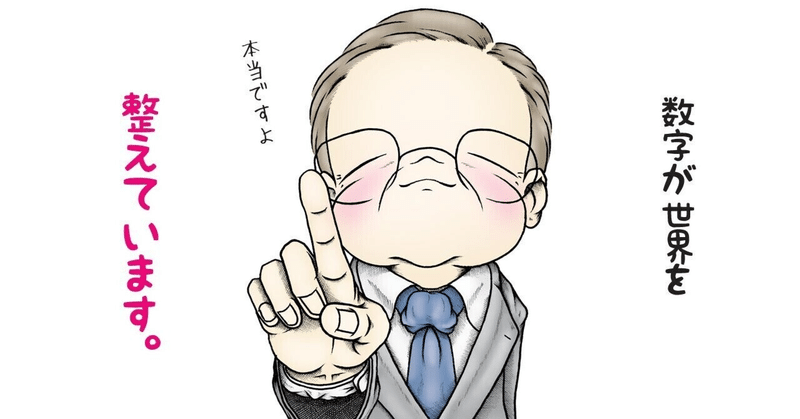
父への手紙 14
スポーツだったら監督派
父は、行動派か理論派なのかどちらかと言われると、理論派なのかもしれない。
自称学者肌だったので、理論派で間違いないだろう。
行動派の面もなくはなかった。
テニスとゴルフがいい例で、運動はウォーキングや登山以外にやっている記憶がないが、テニスは当時流行り始めていたテニススクールに通い、ゴルフは接待ゴルフがあるために、ドライブレンジで練習するなど、定期的に練習に足を運んでいたのは覚えている。
他に覚えていることと言えば、「練習=上達の方程式を覆した」第一人者ということかもしれない。
テニスは教則本を見たり、テニスコーチが教えるテレビ番組を見たり、住んでいたマンションに併設したテニスコートを家族でレンタルして定期的に実践練習を繰り返していたものの、上達はあまり見られなかったかなと、子供心に感じたものである。
私も兄もテニススクールのジュニアクラスを受講していた。
兄は、何をやってもできるタイプなので、期待通りに上手になっていったが、私はフォアハンドもバックハンドもボレーもそれなりのレベルには達したものの、サーブだけが出来なかった。
つまり、試合を開始できないため、選手としては致命的である。
「致命的な欠陥を持つ」という意味では、家族の中で父の遺伝子を限りなく引き継いでいるのは私かもしれない。
もう一つ、「練習=上達の方程式を覆した」下りで話をすると、私は留学時代、クラスが終われば図書館で勉強をする日々だったが、テストで点数が取れなかった。
これも「練習=上達の方程式を覆した」成功事例と言えるだろう。
周りの人間は、「図書館で勉強してもうだつが上がらない」と私の弱みとして語るかもしれないが、私からすれば「練習すれば上達するという常識に囚われない類まれな行動力」がなせる業を強みとして、貼られたレッテルを育んでいった。この礎は小学校の時から始まっていた。
私が通っていた小学校では、5,6年生から特設サッカークラブとバスケットクラブというクラブに希望者は入ることが出来た。
当時、男子はサッカー、女子はバスケと決まっていたので、私はサッカーに入ることになる。
特設サッカークラブには、既に週末外部でサッカーを習っている既存のサッカー少年達と、私のように特設サッカークラブからサッカーを始める将来のドラフト一位指名予備軍としてのルーキーから構成されていた。
入会に試験のようなものはないので、サッカーがやりたいと思った子供は誰でも入会できるが、やはり入る人は、運動が苦手ではないと自負した人達が集まっていた。
私は、単純に足だけが速かった。サッカーはボールを軽くけりながらドリブルをしていくスポーツでもあるが、私が走ればボールはついてこない。
言い換えると、私が先を行き過ぎてボールがついてこられない、現代でいう所のIT富豪の卵のような存在だったということだ。
当時の顧問は、サッカーが非常に上手で、足が速いだけでなくスキルもあり、オーバーヘッドシュートなども何度も見せてくれるような顧問だった。
当時は、「キャプテン翼」というアニメがはやり、ドリブルをすれば、ゴールが地平線の下から徐々に見えてくるし、オーバーヘッドシュートをするなら、ボールへ向かってジャンプしてからシュートまで10秒もかかるほど、滞空時間が長く表現されていた。
「練習=上達という方程式を覆す」ほどの知能を持ち合わせてるだけに、オーバーヘッドシュートをする人は、10秒くらいは空に浮いているものと言うのが私の中でリアルなものだと思っていた。
顧問のオーバーヘッドは一瞬の蹴りなので、「あーこの先生もまだまだなんだな」と思っていた私自身が「まだまだなんだな」と成人を迎えてから反省することになる。
それくらいサッカーのできる顧問の下でサッカーを覚えていくわけだが、右利きで足が速いという所をすぐに見抜いた顧問は、私は練習の時からずっと右のウイングというポジションで起用をしてくれていた。
実際には、右ということしかわからず、ウイングの役割はよく分かっていなかった。顧問はあまり細かく指導はしなかったが、とにかく縦に走らせるようなパスしか出されなかったため、走れということだったんだと思う。
練習試合では、毎回右のウイングとして起用してもらえた。練習では、右側のサイドに行ったボールを死守するよう教え込まれたが、本大会を迎えると、自陣のベンチを死守するよう指示があり、本大会には出ることができなかった。
中学へ行くとバスケ部へ入部することになる。兄とは3つ違いなので、私が入部した時には、既に卒業していたが、兄がそこそこバスケができただけに、残念なくらい比較をされ、モチベーションを保つのもしんどかった。
中学時代のバスケ部は、上の代が強いと次の代は弱くなるというバイオリズムが常だった。
強い代の時は、その代のメンバーを使って試合を勝っていくのに対し、弱い代になると勝てないことを見込み、次の代を育てる1年とするわけである。
その為、下の代が試合慣れをしていき上達をしていく一方で、同じ代は試合に起用されないため実力がどんどんつかないまま引退を迎える。
私は部活を一日も休んだ覚えはなかったが、試合に勝てる程の上達を遂げたとは言い難かった。
そもそもチームスポーツなので、自分だけが上達したとしてもチームとして勝つことは難しいはずだ。
誰を攻めるわけでもなく、たまたま自分が入部した時期が、顧問から見放されてしまう程の実力しかない環境であったというだけだ。
これも「練習=上達の方程式を覆した」成功事例だ。
大学受験を控え、現役失敗をして一浪したが全滅した。
しかし、勉強をしてなかったかと言えばしていたと思う。
クラス以外は自習室で勉強していたし、模試での判定も合格圏内だったが、本番入試は瞬殺。
渡米前の「練習=上達の方程式を覆した」成功事例の中で、最大規模のものが大学受験の顛末だったと思う。
大いに自信を無くしたことに自信を持つことが出来るようになり、自己肯定感は、生まれて以来最高潮を記録した。
振り返ってみると、父の生きざまに限りなく似ているなと思っている。
私の中の広辞苑には、「努力は報われる」という表現はない。
「努力と思うから挫折を感じる」と表現は載っている。
挫折は期待の落差で、傷の深さが決まる。
傷を深く追いたくなければ、期待を大きく持たないことだ。
父の生きざまと私の生きざまは限りなく似ているが、唯一似ていないのが、私は「やってみよう」とすぐに試してみる性格をしているところである。
父は理詰めで試す前に議論をする。
議論の根拠を聞くと決まって「…だと思うよ」と返ってくる。
つまり根拠がない議論なので、人を動かすことが出来ない。
私はとにかくやってみて失敗をするが、やってみることが出来るのは、別に傷を負わないだろうと思っていることだからだ。
傷を負っても対処できる程度のことでしかない。
私も読書が好きなので、様々な理論を勉強するが、学習すればするほど、理論と現場がそのまま当てはまる事例がないことに気が付く。
私が戦場で戦い理論通りにいかなかったことを、傷を負いながら証明するのに対し、父は戦地には赴かず理論で結論を一旦導き、私が戦場では理論とは異なることが起こったことを共有すると、「あっ、そうか…」という反応は1年で366回起きていた。
さすが、自分で学者肌というだけあり、もっともな物言いであることはたしかだが、現実に落とし込めないと空回りに終わってしまう。
父は、それを証明するかのように空回ったが、経験した知識に限っては非常に的確なことに言及する。
だから、学者肌という思い込みが、実践をさせなかった原動力となってしまい、本来前進させるために存在するグロースマインドセットがクローズマインドセットという、ある意味、タイプミスのような形でアルツハイマーまでの人生を過ごしたと言えるだろう。
父への手紙
親父と私の生きざまは非常に似ています。
多くのフラストレーションを抱えながらも、責任を果たすべく最高を求めて生きてきたのだろうとお察しします。
経営者にまで上り詰め、私に留学の選択を用意したことが、それを証明しています。
頑固さや分析力、考察力はあったからこそ、経営する側にまで至ったわけですが、家庭でその性分を発揮できなかったのは、本能寺にいた信長が言った「敵は本能寺にあり」ということを伝えたかったのだと今は理解しています。
敵は、人生の「上り坂」でも「下り坂」にもおらず、「まさか」に存在しているというのは、現代の偉人も皆が言及しています。
親父からすれば、アルツハイマーは「まさか」の出来事だったでしょうし、その進行のはやさも「まさか」で起きています。
私がテニスで「サーブができない」致命傷を負ったのも「まさか」で起きましたし、高校大学受験と滑り止めで、滑りを止められなかったのは、「まさかの中のまさか」だったと言えるでしょう。
恐らく、次男坊をこのまま前進させたら、自分の生きざまの二の舞になると感じた親父は、留学という良い「まさか」で軌道を修正しようと試み、無事に親父がなりたかったグローバル人材にはなったものの、親父が一つの会社を勤め上げたのとは真逆で「まさか」の8社目を終えたところにおります。
人生、思うようにはいかないものの、少しは軌道を修正して前進させていくことが出来ると思います。
私にも娘が二人おりますが、いい大学もいい成績も期待はしないようにしています。
ただ、二人には「数学」「英語」「IT」だけは身に着け「どんな会社で働くんだ」とは聞かず「どんな会社を作ってみたいんだ」と聞くようにしています。
これで少しでも、未知を切り開ける人材に育てば、それで親父からの教えを後世に伝えるのに役立てることができたと思えるものです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
