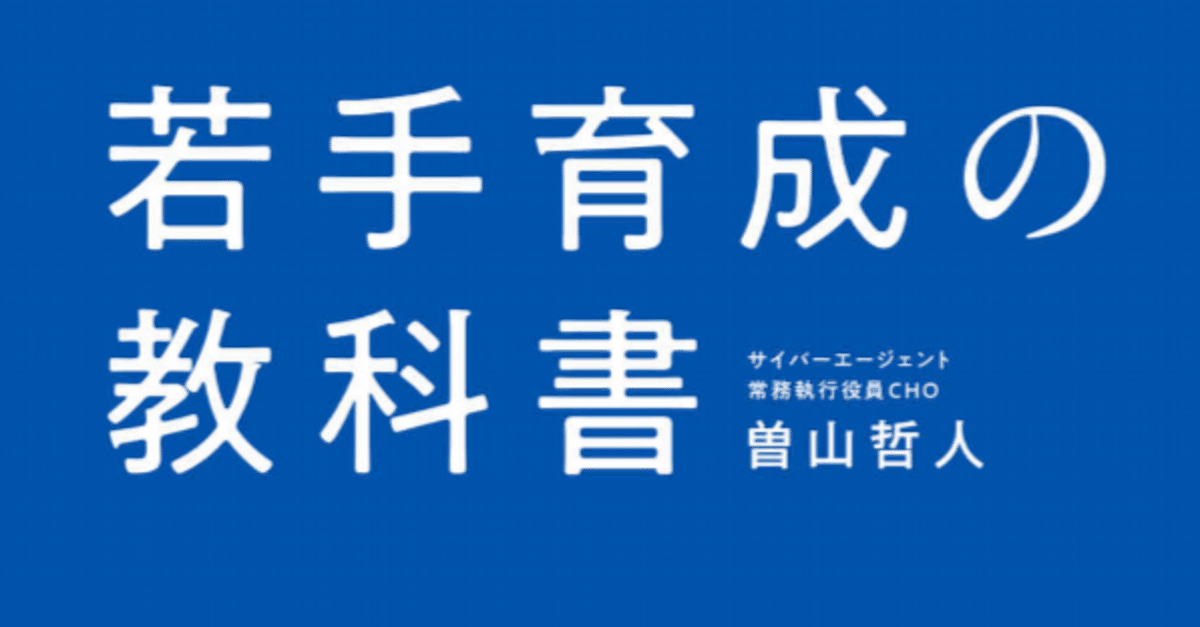
【読書感想】『若手育成の教科書』
(このNOTEは3分で読めます。約2,900文字)
『若手育成の教科書』がMARUZEN & ジュンク堂書店 渋谷店の新刊コーナーに陳列されていました。著者であるサイバーエージェントCHO(最高人事責任者)の曽山さんはYoutubeで動画を拝見したことがあったので、この書籍に興味を持ちました。
このNOTEでは、曽山哲人さんの『若手育成の教科書』についての読書感想を書きます。内容の要約でなく、あくまで私の感想ですのでご了承ください。主観的な感想も多くございますので皆さまの広いお心で読んでいただけますと幸いです。
【総評】
オススメ度:★★★☆☆
読みやすさ:★★★★★
【対象とされる読者層】
・中小企業の人事責任者
→後述しますが、失敗回避が根強い大企業ではハマらない内容です。
読了までの時間を計ったところおよそ70分でした。スラスラとページをめくって読み進めることができる読みやすい本でした。
✅1、印象に残った内容と感想
1ー1、全体感
一人一人手取り足取り指導して成長させるやり方は、組織の規模が大きくなればなるほど難しくなります。構造的にみると、マネージャーに対するメンバー層の割合が大きくなればなるほど難しくなるということです。マネージャー層とメンバー層がきれいなピラミッドになっていない場合、マネージャーはマイクロマネジメントに徹している時間はありません。
『若手育成の教科書』ではその問題の解決方法として、『若手が勝手に育つ「自走サイクル」』を紹介しています。
1、抜擢
2、決断
3、失敗
4、学習
1~4のサイクルを回していくことによって若手が自走して育っていく環境を構築することが重要だと指摘しています。
『第1部 抜擢前』では、『若手が勝手に育つ「自走サイクル」』に入る前の下準備の内容です。『第2部 抜擢』は『若手が勝手に育つ「自走サイクル」』の『1、抜擢』の内容です。『第3部 抜擢後』は『2、決断』『3、失敗』『4、学習』の内容です。
1ー2、第1部 抜擢前
組織の上からの命令でポジションに抜擢したとしても意味がありません。仕事を完遂する可能性を高めるには、本人に『やりたいです。』と言わせ、内発的動機付けをすることが必要です。
第1部では、どのように本人に『やりたいです。』と言わせるかその具体的テクニックが記載されています。
キーワードは『言わせて、やらせる。』です。まずはどんなことでもいいので本人の口から言わせることが大切。そして、言わせるためには『どういうふうに解釈した?』や『次は何をすればいいと思った?』など、詰めるのではなく、問いかけをすることが重要だと書かれています。
第1部では、『心理的安全性』をどのように創出し、どのように本人の口から『やりたいです』と言わせるのかというサイバーエージェントの方法を学べます。
1ー3、第2部 抜擢
第2部では、『抜擢』の具体的内容が記載されています。『抜擢』とは、『期待をかけること』と定義されていました。
『抜擢』は、
①期待を伝える
②本人に『やりたいです。』と宣言させる
③承認する
の3つのプロセスがあると説明されています。
『抜擢』するさいの具体的なフレーズが印象的でした。
1ー4、第3部 抜擢後
第3部は、『決断』『失敗』『学習』と大きく3つの章に分かれています。
『決断』に関する部分で出てきた、『抜擢後の人材は「決断経験」で大きく成長する』や『「決断サイクル」を回せば質が上がる』などは実体験とも重なって共感できる内容でした。
個人としての能力はほとんど変わらないはずの大学の同期と久しぶりに会って話をすると『あれ?』と思うことがあります。無理難題の案件に放り込まれて試行錯誤している自分と、大企業に就職して先輩の後ろについて行き言われたことをやるだけの同期を比べると明らかにレベルの差を感じるのです。これは決断量の違いなのだと思いました。
✅2、総評
2ー1、サイバーエージェントだからできる
本書冒頭に『サイバーエージェントだからできるんでしょ』と言われた曽山さんのエピソードが書かれています。『サイバーエージェントだからできるのではなく、どの会社でも採用できる仕組みとして紹介すること』が本書で伝えたいことだという曽山さんの思いはよく分かりました。
実は、『サイバーエージェントだからできるんでしょ』と言いたくなる側の気持ちもなんとなく理解できます。私は本書を読み終えて『サイバーエージェントだからできるんでしょ』と思いました。これは感覚的なものではなく理由があります。それは、制度として失敗が許容されるかどうかという点です。
『第3部 抜擢後』には、抜擢して結果が失敗に終わった場合の対処法についても記載されています。その中には、組織的に失敗を許容することも含まれています。
サイバーエージェントの行動指針『Mission Statement』の1つに『挑戦した敗者にはセカンドチャンスを。』という言葉があります。これがあるからこそ、組織的に失敗を許容することができるようになっています。
つまり、『サイバーエージェントの行動指針『Mission Statement』の1つに『挑戦した敗者にはセカンドチャンスを。』があるからこそ組織的に失敗が許容される。失敗が許容されるからこそ、若手を抜擢できるようになる。』ということです。
抜擢できるためには、失敗のリスクを組織的に許容できるミッションステイトメントのような”法”がなければなりません。失敗が許容される”法”がなければ、誰も失敗をしたがらないでしょう。
その意味で、この書籍は組織自体を変えることができる権力を持った人が読んだ方がいいなと思いました。
2ー2、スタートアップ企業は抜擢せざるを得ない
スタートアップ企業の人事担当者に本書はまだ必要ないと思いました。抜擢することが中心的内容の本書は、そもそも人が足りておらず抜擢せざるを得ない環境であるベンチャー企業には不要だと考えるからです。
2-3、巻末にまとめがついている
巻末には、書籍の中で紹介されていた内容がイラスト付きで要約されています。書籍を頭から読むのではなく、巻末のまとめを始めに読んで要点を理解してから本編を読むという読み方もできます。本編を読んだ後に復習として巻末のまとめを読むことでより理解を深めることもできます。
書籍の構成として読みやすさが増しているのはこの巻末の要点まとめの存在が大きいと思いました。
✅3、書籍紹介
全体的に読みやすい書籍です。本書と併せて曽山さんが自ら『若手育成の教科書』を解説しているYoutubeを見るとより理解が深まるのかなと思います。
✅雑感
プルデンシャルっぽい方やリクルートっぽい方など、その企業で働くイメージ像を私たちは無意識のうちに創り出しています。サイバーエージェントに関しても、なんとなく『サイバーっぽい方』のイメージがあります。
それが良いとか悪いとかではなく、『その企業っぽい方のイメージ』が作られている企業って人気と知名度が抜群です。ふと、そういったイメージはどのように創られていくのかが気になりました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
よろしければサポートお願いします。いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます。
