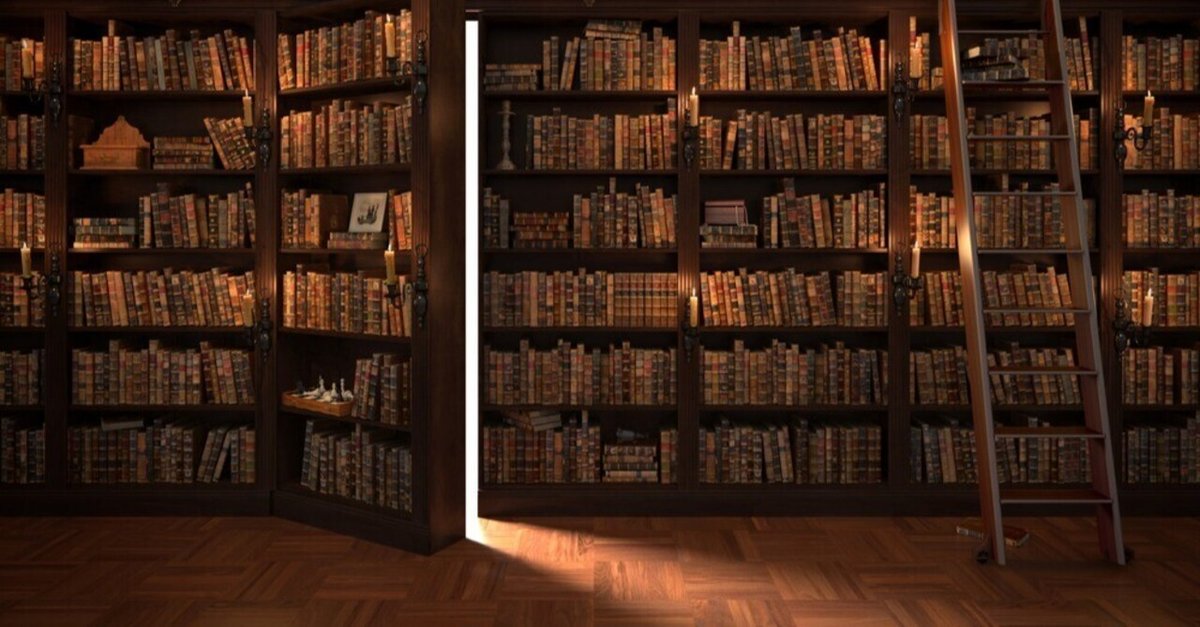
本づくりに人生をかけている人たちの話
はじめまして。
このたびフォレスト出版編集部の一員となりました、美馬幸子と申します。
入社してまだ2週目ですが、こうして記事を書く機会をいただけたこと、本当にうれしく思っています。
前職の仕事は、実は出版社とは縁の遠いものでした。
ずっと憧れていた編集者になるという夢があきらめきれず、モヤモヤとした毎日を過ごしていた末に、一念発起し転職活動をスタート。
来る日も来る日もあらゆる出版社に応募し続けたところ、弊社フォレスト出版に拾っていただけました。
運を使い果たした気がします。
何を伝えたいのかといいますと……、
やはり夢はあきらめなければ、叶うということです。
もちろん、人によって努力の大きさや時間に相当な違いはあれども、人生の全てを投げ打って行動してみたら、意外に夢は叶うものなのだと感じています。
編集者の仕事とは?
さて、そんな私が、内定の電話をもらった日に購入した一冊がこちら。
『「本をつくる」という仕事』(稲泉連/ちくま文庫)です。
著者の稲泉連さんは、取材を通して社会問題をリアルに我々読者に伝える、いわゆる「ノンフィクション作家」と呼ばれる仕事をされている方です。
同書では、本づくりに携わるさまざまな職業の第一人者らに取材をし、本づくりにかかわる熱い舞台裏を綴っています。書体、製本、印刷、校閲、製紙、装幀、海外版権、作家……。
ここに“編集者”というワードが並ばなかったのは少しばかり残念ではありますが、以前、弊社編集長の森上が
「編集者は決して1人で成り立つ仕事ではない。いろいろな職業人に支えられてはじめて成り立つ仕事だ」
と、話してくれたのを思い出しました。
企画が通ったら原稿は著者が、書籍のデザインはデザイナーやイラストレーターが、そのほか校閲者や印刷所など関係各所を経て書店に本が並びます。実際に本を作っているのは、我々編集者から依頼を受けた関係者の方々です。
編集者は最高の一冊を生み出すために働くマネージャーのようなものでしょうか。
プランナーでなければならない、と述べている方もいらっしゃいますね。
ゼロから企画を考え、より良い本になるように原稿やデザインなどのやりとりをし、校了日まで全力を注ぎます。
編集者は、あくまでも裏方に徹することで実力を発揮できるものなのでしょう。
同書に“編集者”の文字がないのも、妙に納得しました。
宝石みたいな本をつくる
装幀家の日下潤一さんは書籍のデザインについて次のように述べています。
「その世界が好きやったら、自ずといろいろ考えるし、分からなければ人に聞きたくなる。そういうもんやないですか。ブックデザインいうんは淡々と作業としてこなしていくこともできる。でも、やっぱりそれは僕にとっても一つの運動なんやね。そして、そうであるが故のやり方や楽しみ方がある。そんな仕事やと思うんです」
例えば、ヨーロッパの教会に行くと、何百年も前の紙の本が飾ってあるように、「美しい本」への憧憬は人間が持ち続けるものであるはずだ、と日下さんは言った。そう信じているからこそ本が好きだし、本をデザインする仕事への熱意もわいてくるのだ、と。
「たとえお金をかけなくても、宝石みたいな本はつくり手たちが必死に手間と時間をかけて工夫すれば、つくれるはずなんや。それを見て「こんな本をつくりたい」と思う人がいる限り本は残っていくやろ。そのためにはやっぱり紙の本が美しくなければあかんのですよ」
“宝石みたいな本”……、
すごく素敵な言葉ですね。
電子書籍を専門に取り扱う出版社も増えてきている中、私が転職活動をする上で譲れなかった条件(選り好みできる立場ではなかったのですが)は、紙の書籍を取り扱っているかどうかでした。
書店の棚に並ぶ書籍を眺めるのが好きなのです。
液晶画面上ではわからない、カバーの触り心地や、におい、ページをめくる音など生で一冊の本を感じることではじめて心が満たされるものです。
そういった意味では、2020年、弊社刊行の『マインド・プロファイリング豪華書籍版【DVD付】』(苫米地英人)はまさに、“宝石みたいな本”の代表ではないのでしょうか。
残念ながら現物を見たことはないのですが、革張りのハードカバー、金の箔押しと空押し、香り付きというまるで聖書のような本だと聞いています。
編集者として、読者の方に“宝石みたいな本”だと思っていただけることほどうれしいことはおそらくありません。
原稿を最初に読むということ
以下、校閲者の矢彦孝彦さんを取り上げた一節です。
編集者と同時に校閲部員もまた、作家の原稿を最初に読む読者であり、重い責任がある。しかも世の中に原稿を送り出す側にいる編集者に対して、校閲部員は読者の側に立って原稿を読むという重大な役割を担っているのだ、と。
「これは物事を知っていないと書き手に負けるな、と感じました。ゲラを通した闘いというのかな。あの人たちが分からないようなことを、こっちから指摘してやろう。そんな思いが湧いてきたんです」
誰もが真剣に作品を世に送り出そうとしていた。
作家が書き、編集者と校閲者が読み、そこで生まれる疑問に作家が答える。
それは著者のためであると同時に、何よりも読者のための仕事である。
彼は校閲を仕事とする者として、そのように自負するようになっていったのだ。
以来、四〇年以上にわたるキャリアのなかで、彼は『週刊新潮』や単行本、文庫と担当部署を渡り歩き、最後は新潮社校閲部の部長を務めた。
そして、いまもなお外部の校閲者として仕事を続ける彼は、その日々を振り返って言うのだった。
「出版業界には、非生産部門である校閲部門を縮小しようという流れがあります。でもね、僕は校閲部こそが出版社の良心だと思っています。ネットがあって、あらゆる人が文章を書くようになったからこそ、その社会的な意味は増しているのではないでしょうか」
校閲は出版社の価値であり、良心である——。
矢彦さんはそう言うと、酒の入ったグラスに口を付けた。
校閲一筋、四〇年——それが彼のたどり着いた結論である。
石原さとみさん主演で校閲部を舞台にドラマ化もされましたし、本をあまり読まない方にとっても、校閲は馴染みのある仕事ではないでしょうか。
入社1日目に私に与えられた編集者としての仕事は、弊社6月刊行『売れる「ライブコマース」入門』のゲラの素読み、校正作業(見よう見まねの校正もどき)でした。
校正、校閲のチェックポイントしかり、校正記号の資料に目を通して挑みましたが、これがまたルールがたくさんあるもので……。
以下、『標準編集必携第2版』(日本エディタースクール)に記載されている校正のチェックポイントの抜粋です。
⒈ 書名,予定ページ,刊行計画など,その本の刊行にかかわる基本的な事項を確認する.
⒉ 著訳者の経歴はどうか,既刊書があるか,既刊書があった場合,校正の 参考になる本はあるか,また,どのような点が参考になるかを確認する.
⒊ 著訳者が漢字・仮名遣い・送り仮名に特異な使い方をしていないか,著者に校正についての希望があるかどうか確認する.
校正作業を開始する前、準備段階として確認するべき項目をほんの一部挙げてみました。
準備の段階でここまでするのか!というのが率直な感想です。
ただ、誤植を見つけるだけでいいのなら、このような準備は不要なのでしょう。
完璧な書籍をつくるためにわずかな言葉の違和感を拾い上げていく、決して派手とは言えない作業ですが、並大抵の覚悟では務まりません。
とはいっても、人間ですので100%誤植がないとも言い切れませんが。
そのために、著者、編集者、校閲者と何度も原稿のやりとりを行い、誤植がないことはもとより、より良い内容になるように書籍づくりに邁進しています。
入社して半月も経ちませんが、言葉の難しさを痛感するとともに、日本語の美しさを再認識する毎日です。
ここまで本づくりについてわかったような雰囲気を出してしまいましたが、私はまだ編集者の「へ」の字も知らない新人です。
編集部の先輩方をはじめ、本づくりに携わるさまざまな職業の方たち、
そして読者の皆さまとの出会いを大切に……。
これから、少しずつ自分が担当した書籍をこの場で紹介できることを楽しみにしています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
