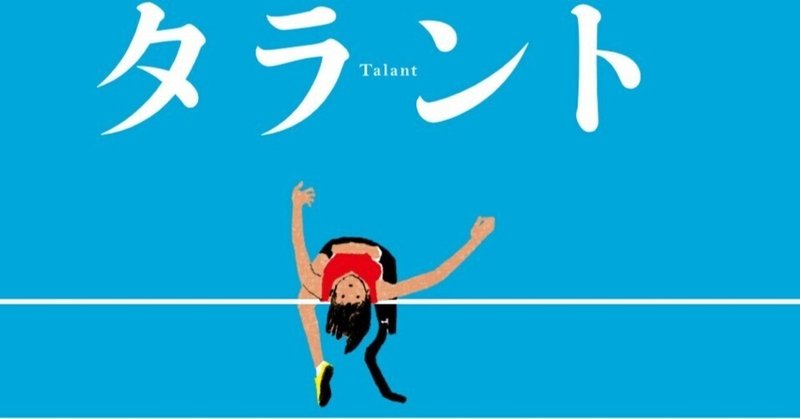
角田光代『タラント』(毎日読書メモ(492))
遅ればせながら、角田光代『タラント』(中央公論新社)を読んだ。2020年7月~2021年7月にかけて読売新聞に連載され、改稿のうえ、2022年2月に単行本が出た長編小説。
まず、タイトルの「タラント」の意味がわからない。そして、義足をつけたアスリートが高跳びをしているイラストの表紙なのに、読み始めるといっこうに義足のアスリートの話は出てこない。
(この先ストーリーに踏み込みます。未読の方注意)
物語は1999年と2019年を行ったり来たりする。
高松で、同族経営のさぬきうどんの店の一族の中で育ち、東京の大学に進学することになった多田みのり。狭くて緊密な人間関係でがんじがらめになった故郷から、自由な世界に出ていく解放感。空の色も違う気がする。この本の表紙の青は、みのりが見た新世界の空の色だったのかもしれない。
しかし、女子学生会館に住み、誰一人知る人のいない大学に行ったみのりは、情報弱者になり、大学でどう暮らしていけばいいかわからなくなる。この辺の感じは、自宅通学だったけれど、知り合いのあまりいないマンモス私大に進学したわたしも似た経験をしているので、みのりの途方に暮れた感じに親近感を覚えた。そんなみのりの突破口となったのは、同じ学生会館に住んでいるが違う大学に通っている市子が所属している、色んな大学の学生が参加しているボランティアサークルだった。
並行して、祖父清美の上京が語られる。友達に会う、という名目でやってきた祖父、学生会館には泊められないので、近くのホテルをとって、どこかに行っているようだが、寡黙な祖父にどんなに語りかけても祖父から言葉が返ってくることはあまりない。第2次世界大戦に従軍し、その際に左脚を失った祖父が、どんな体験をしてきたのか、家族の殆ど誰も知らない。しかし序章、そして各章の最後の部分、そして終章のモノローグが清美のものであることが読者にはすぐわかってくる。
麦の会というサークルで、他の大学の玲や翔太、そして後輩の睦美と親しくなる1999-2000年のみのり。バイト代を貯めてネパールのスタディツアーに参加して、そこで見た光景に感銘を受け、自分に出来ることを考えるみのりと、2019年のみのりは別の人になっている。麦の会のことを知りもしない寿士と結婚し、東京で共働きをして暮らしているが、責任ある仕事を任されそうになると逃げる。みのりは何を直視したくないのか? 仕事が込み入ってきそうなタイミングで、何かを任されることを避けるために長期休暇をとって帰った高松で、甥の陸の不登校について聞く。そして祖父に来ている「涼花」という差出人の手紙。この2つのファクターからみのりの人生が動き出す。
2002年のスタディツアーは同時多発テロの影響で中止になり、みのりと玲と睦美は自分たちで旅程を組んで、ネパールに行き、深い共感をもった結びつきが出来る。サークルの中でもボランティア活動より、写真を撮ることに力を入れていた翔太は、同時多発テロの際にたまたまニューヨークにいて、その時に撮影した写真が話題になったことからフォトジャーナリストを目指すようになり、大学卒業後の玲は、海外に軸足を置いてルポルタージュを書くようになっていく。ボランティアは何のためにするのか。ボランティアをするのはいい人意識の高い人なのか、何のために海外に行き、国内にいる人が知らないことを伝えようとするのか。取材の途中でゲリラに捕まる人は無鉄砲でひと迷惑な人なのか。玲と翔太それぞれの活動と並行して、様々な問いが湧いてくる。玲が長期滞在しているヨルダンにスタディツアーでやっていたみのりは、自分がしたことが誰かの運命を変えたかもしれないような事件に関与することとなる。玲とも気持ちのすれ違いが生じ、みのりは自分の視野の狭さに自己嫌悪になる。
不登校になった陸が一時東京に来て、みのりの家で暮らしたりしたことをきっかけに、二人は祖父が東京で何をしていたかを知る。織田フィールド(わたしもランニングの練習会で何回も使ったことのある、代々木公園の一角の陸上競技場)で、義足の人の陸上競技練習会に参加していたのだ。
それをきっかけに、みのりはそれまで全く知らなかったパラリンピックのことや、義足の開発について知る。
それと並行して、タイトルになっている「タラント」という、聖書を出典とすることばがみのりの生活の中にじわじわと浸透していく。タラント(Talant)とは、タレント(Talent)の語源で、才能のことであると同時に、「使えば使うほど豊かになるもの」「神から恵まれた天賦」を意味している。自分が何かをしたいと思ったこと、それ自体が一つのタラントである、ということを、傷つき何にも真剣に取り組みたくないという気持ちになっていたみのりは少しずつ認識していく。そして、陸も、自分が不登校になったきっかけと向き合う。
義足の高跳び選手の涼花は、2020年のパラリンピックの選手に選ばれ、陸とみのりは清美と観戦に行く、と意気込むが、そこにパンデミックがやってきて、パラリンピックは順延される。その時に、寡黙な清美がどうしても東京に行く、と言いだして語った言葉がわたしたちを震撼させる。
そして終章、清美のモノローグの力強さで慟哭する。もう20年以上、角田光代の小説を読み続け、それぞれの小説が問いかける問題意識に胸を締め付け有れる体験をしてきたが、声を出して泣くほどの結末と向き合ったのは初めてかもしれない。最後の3ページは、電車の中とかで読んではいけない。う、う、とうめきながら泣いた。
玲が海外で活動するきっかけとなった、大学時代のトルコ旅行の際に知り合ったクルド人の話が、そんなに深くは出てこないが通奏低音のように、わたしに響いた。
中島京子『やさしい猫』(感想ここ)の中でも、主たるテーマであるミユキさんとクマさんの物語より、マヤが親しくなったクルド人少年ハヤトのエピソードの方が、読んで1年以上たった今、じわじわと辛く思い出されるのだが、忘れないでいようと思うことだけでなく、もっと出来ることはあるんだろうか、と、時々考える。
たぶん、この本を読むと、読者それぞれが、自分の心の琴線に触れる、何かの問題意識を自覚することになるのではないかと思う。
何かを厳しく問うている小説ではないけれど、静かにナッジしてくれる、そんな小説だった。
#読書 #読書感想文 #角田光代 #タラント #中央公論新社 #ボランティア #ネパール #ヨルダン #クルド人 #高松 #さぬきうどん #パラリンピック #義足
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
