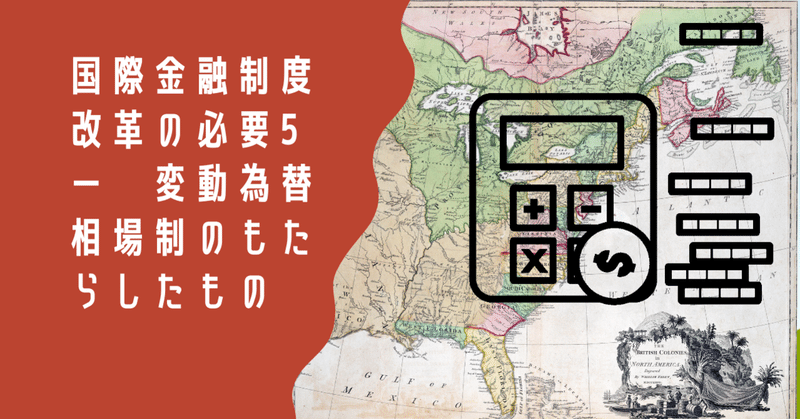#国際経済
国際金融制度改革の必要性6 ー オイルショックの構造と帰結
2. デリバティブの急拡大こうした背景を踏まえた上で、最も注目を集めた世界貿易センタービルへのテロをどう考えるか、と言うことであるが、これはやはりグローバル経済制度に対する不満の顕在化だと考えるべきなのだろう。
テロ事件後の原油価格急騰話は少し飛ぶが、同時多発テロに前後して、国際的な原油価格がこれまでに例を見ないほどに急騰しだした。これまでも二度のオイルショックがあり、それによって世界経
国際金融制度改革の必要性4 ー 変動相場制と為替先物
戦後通貨体制の確立さて、戦後通貨体制についての構想は、シカゴ大学のジェイコブ・ヴァイナーを中心に1939年、まさに第二次世界大戦が始まった頃から動き出しており、まだ太平洋戦争の始まっていなかったその時期には、東南アジアの情勢は考慮の外であった。太平洋戦争が始まった1週間後には財務長官モーゲンソーは指揮下のアメリカ財務省で働いていたホワイトに戦後通貨体制についての草案づくりを命じ、ヴァイナーは翌年1
もっとみる国際金融制度改革の必要性3 ブレトンウッズ以前の通貨体制
それに対して、ワシントンD.C.という政治の中心へのテロと見られるものをどう解釈するか、と言うことであるが、このテロ事件の前から、ワシントン・コンセンサスという考え方で、アジア通貨危機の起こった国々に対してかなり強硬な構造改革を押しつける、という事が起こっていた。これは、IMF・GATT体制という第二次世界大戦後の国際経済秩序を規定する仕組が、その価値観に基づいて自由貿易・金融体制をあまねく広めよ
もっとみる