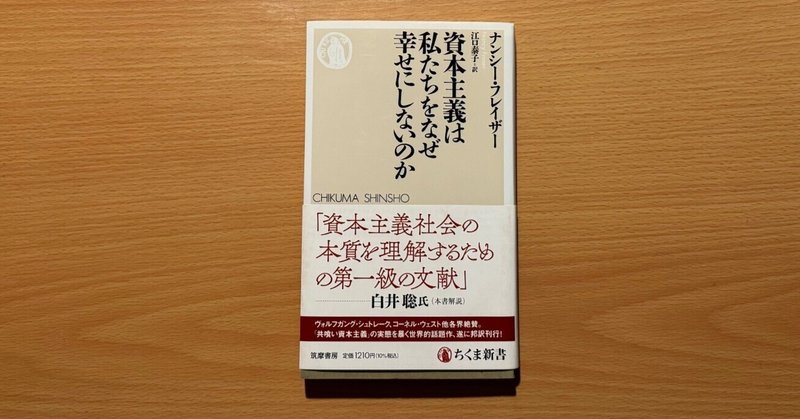
『資本主義は私たちをなぜ幸せにしないのか』を読んで④完結〜本当の教育無償化とは〜
前回のおさらい
資本主義社会は発展のために、労働者が得るべき対価を「搾取」することによって利潤を生み出してきました。そうしてこの本では更に「収奪」にも焦点が当てられています。この「収奪」とは、対価を一切支払われないというもので、自然(資源)や家庭で家事や子育てを強いられてきた女性などは、対価を一切支払われずに資本主義社会を支えてきました。
現在では、少しずつそれらが是正されようとしています。自然は環境活動などによって、対価を支払われるまでには及んでいませんが、自然環境の保護の動きは当たり前になっています。
教育はいまだに女性が家庭で担っている状況は変わりませんが、数十年前に比べると、女性の社会進出によってしつけなどが学校で行われるようになっています。
そして学校では対価はそのままで、家庭で行われなくなった分のしつけなどを担うことになり、それに耐えきれなくなった学校の先生方は「働き方改革」の重要性を訴えるようになりました。
このような次々に連鎖する教育という負担は誰がどのように担えばいいのでしょうか?そもそも本当に「教育」は必要なのでしょうか。
「教育」の必要性①:人間だから
人間と「教育」は、人間が二足歩行を始めたときに切ってもきれない関係になってしましました。他の生き物は生まれてすぐに、もしくは数時間も経てば自立して自分で移動することができます。人間にそれができないのは未熟な状態で生まれてくるからです。人間が未熟な状態で生まれてくるのは、二足歩行にともなって両手で複雑な作業をこなすようになり、脳の容量が増え、頭が大きくなったために、産道を通過できるギリギリまでしか母体の中にいることができなくなったためです。人間は人間になった瞬間に、未熟で不完全にしか生まれることができなくなくなってしまったのです。そのため人間は本能だけでなく、生きるために必要な事柄を外部か(周囲の人間)から学ばざるを得なくなったのです。
「教育」の必要性②:「資本主義」の担い手
このシリーズでも以前書きましたが、資本主義が「収奪」の対象とするものは「自然(資源)」など、私たちの生活に欠かせないものばかりです。そしてこれまで女性が家庭で無償で強いられてきた「教育」こそ、資本主義社会を支える担い手づくりそのものだったのです。
常に発展を追求する資本主義社会では、人それぞれの能力が重要になっています。しかし、その重要な構成要素である「教育」が家庭から学校へ移行し、そしてその「学校」負担に耐えきれなくなっています。
「教育」を直接的な対価の対象にしない
教育と経済とは、前回の学校の先生方の給特法でも書いたように相性の悪い分野です。なぜなら学校教育サービスは業務の対象が利益の対象にならないからです。しかし、この(資本主義)社会を支えるため、人間として生まれてきてしまったために我々人類にとって「教育」は不可欠なものであることは間違いありません。
そこで、「教育を収入源としての職業にしない」というのが私が行き着いた考えです。職業にしてしまうと現在の学校の先生方に起こっているような、教育に収入の枠、待遇の枠という際限を設けてしまいます。際限ない教育を提供をすることでしか、際限のない資本主義社会を支えることはできません。
一方的な利益集中を避ける
「収奪」によって利益を享受しているのは一部の資本家だけです。多く人々は一部の資本家の利益のために納得のいかない「収奪」を受けています。しかし、今後の資本の増大を目指すなら「教育」への負担は必要経費なのです。現状では税金によって教育の大部分が担われています。しかし、これは結局は全員で教育を負担しているため、本来担わなければならない資本家の負担を軽減させてしまうことになっています。
教育の無償化
教育の無償化が叫ばれています。それを政治活動の中心にしている人たちもいます。教育の無償化は誰かに負担の皺寄せが行きます。教育の無償化は増税の言い訳になりかねません。そして教育の無償化によって学校の先生方は収入が増える可能性も奪われてしまいます。自分の収入は減らさずに政治を使って更なる資本家の利益を生み出そうとする政治家に言いたいのは、他人のことはいいからまずは自分で無償の教育を提供してみろよ、ということです。
私はそのような政治家と一線を隠すために、無料の学習サポートを提供してみることにしました。本当の無償の教育サービスは時間と体力以外の際限はありません。家庭の経済状況に関わらずに大人から子どもまで「教育」を受ける機会を作っています。先週から無料の学習サポートを始めてまだ利用がありません。ぜひご利用ください。
『資本主義は私たちをなぜ幸せにしないのか』シリーズはこれで終了です。次回はまた別の本と自分の考えを混ぜて書いていこうと思います。読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
