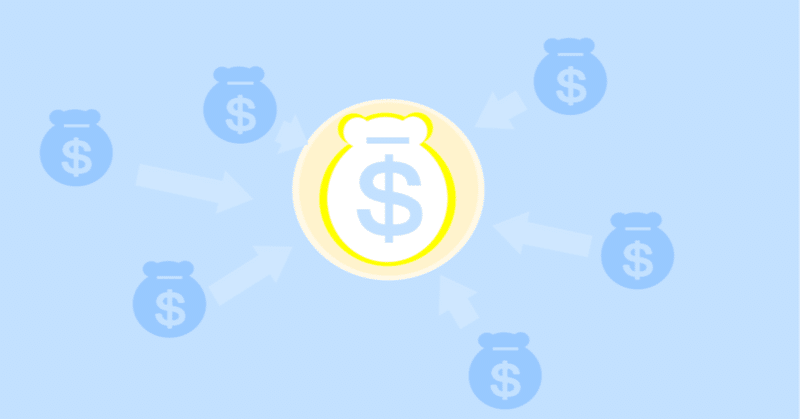
儲かることと儲けること
儲かることと儲けること。
ある大手の住宅メーカーでは〇〇円以下は請け負わないと言われています。一時期よりも多少原価が下がっているのか、上限が少し下がった気がしますが、それでもハッキリしています。つまり、原価割れを起こす案件は、最初からNOなわけです。まぁ大手の場合は、お客様よりも株主を気にする傾向があるので、何とも言えませんけど。。。
ただ会社には「損益分岐点」という経費を差し引いた、実益となる黒字・赤字となる指標があります。役員クラスになれば税引きとなる経常利益等まで責任の所在を明確にして行き、場合によっては戦略的な赤字という手法も用いますが、営業部門で言えば原則的に営業利益という指標を持つことによって、単純に営業部門単体で儲かっているかいないかの指標を持って、年間含め半期、四半期、単月と目標値を計画して行きます。
故人になってしまいましたが、アメーバ経営を提唱されていた稲森さんもおっしゃっています。どんな小さなセクション(部門、部署等)であれ、組織として機能させており人材を抱えているのであれば、独立採算制を考慮すべきだと。もちろん完全な間接部門であれ、定性評価という評価制度も行える事と事務経費の削減では主流になるので損益を算出し、目標を設定することは可能です(むしろ積極的に行って欲しいが、、、)そして、その成果以外にも営業部門や製造部門への支援は可能なのです。この後方支援という目に見えない成果を見える化するマネジメントも必要と思われます。
事業部を率いるという事は、基幹事業を率いるという事は、数字の責任が必要です。そのリーダー的には最低の条件でしかないのですが、マネジメント無くしては成果を上げることは困難であろう。また、マネジメントするにも人徳・人望が不可欠です。個人の魅力というか「この人のためなら、、、」など、カリスマ性と言わないまでも、休日等の返上を辞さないまでもとことん突き詰めようとするモチベーション、部署全体含め士気を上げることです。間違っても士気を低下させたり、また士気を感じられないような責任者では到達することは難しいかも知れません。
適正利益という基準を制定したならば、これらを逸脱するような決済は行わないことです。万が一にも決済を出す場合は、これらの現場によって生み出される相乗効果など、広報面やマーケティング目線を考察すべきです。
また、数字というのは「頑張りましょう」という掛け声だけでは絶対に生まれません。仮に達成することが出来ても、再現性が極めて低いでしょう。つまり、安定しないのです。安定させるためというわけではないですが、数字というのはあくまでも計画的に作る(生み出す)ものです。戦略的に達成できるしくみを構築するだけでは無いということです。顧客ごとに攻略するポイントをベタであってもマネジメントできなければならないのです。
月目標(又は四半期目標等)が達成出来なければ、半期含め年間達成は難しいでしょう。仮に追い込みを掛ける時に必ず問題になるのが、先に書いている利益を割っての受注なのです。そりゃー売上が上がったとしても、利益を得ることはできないでしょう。よく決算月の翌月は数字を落とす企業も多く見られます。大体の企業が、この数字の計画が出来ていない証拠です。自社が決算月の翌月であるなら、競合他社は決算月の追い込み月かも知れません。安易な計画で安堵感を出して入れば、コテンパンに叩きのめされるでしょう。少なくとも業績を担うマネージャーは、休んでいる暇など無いでしょう。今ではパワハラや過重労働などで訴えられるかも知れませんが、自分が責任を負っている業績なのに訴え出る心が理解できないのは、昭和の考え方なのでしょうかね。だったら、そのポジションを降りれば良いだけのことだと思いますが。。。
仮に売上が落ち込んだとしても、利益が確保できて入れば、存続は可能ですし、次へのステップを生み出すことができます。儲かっているのは会社のお陰様です。でも、儲けるかどうかは、自分の行動次第です。活動、行動の積み重ねです。
企業は利益を生み出さなければ、存続できないのです。衰退の一途の始まりです。いざとなった時にはわが身を守ることに、家族を守ることに懸命になるものです。誰も経営者を助けることはしないでしょう。
組織には「勝つ戦略」と「負けない戦略」があります。勝つことは華々しく輝かしいもので評価も脚光を浴びることになるでしょうが、負けないという事を実践するのは困難です。
負けない事というのは地味かも知れませんが、とても重要なことなのです。
どうやったら負けないか、考えてみましょう。
