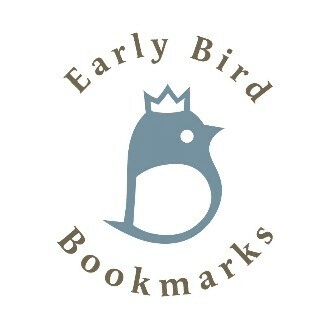読書感想文: 悪童日記・ふたりの証拠・第三の嘘
中 2 の頃だろうか。
地元に図書館がオープンした。
その時仲良かった友人と、学校帰りに片道 2km の距離を毎週かよった。
1 週間に 10 冊借りて返すから、1 日に 1.4 冊読むスピードだ。
もう読み終って週をまたがずに行くときもあった。
私はこのとき以上のスピードで本を読んでいたことは、後にも先にも (今のところ) ない。
当時大好きだった赤川次郎はもちろん、海外小説や海外文学に興味を持っていたので、単純だが作者がカタカナで書いてあって、タイトルが面白そうなら片っ端から借りていった。
『ニール・サイモン戯曲集』がお気に入りだったように思う。
その中で、アゴタ・クリストフ著の三部作
悪童日記
ふたりの証拠
第三の嘘
を借りた。
これは 「自分で見つけた」 のではなく、当時流行って & ハマっていた『花より男子』の作者、神尾葉子が作中のコラムに 「面白い」 と書いていたので興味を持ったのだ。
当時は特に、欧州に関する戦争のことなど知らなかった。
フランス語で書かれたということから、作者はフランス人だと思っていた (実際はハンガリー人)。
戦争だから、というのはもちろんなのだが、それだけが理由とは思えない、胸が悪くなるようなエピソードが多く、あまり 「面白い」 と思って読んでいなかった。
後になって意図的な表現だったことを知ったが、「~~だった」 とか 「~~した」 とかの 「〇〇 だ」 の連続に食傷気味になりながら読んだのを覚えている。
あまり書くとネタバレになるので書けないのだが、『悪童日記』→『ふたりの証拠』と続けて読んで、いよいよ最後である『第三の嘘』を読みはじめた時、「え?」 と思った。
この作品は、人によって評価が分かれるのかもしれない。
当時の私はとにかく、『第三の嘘』に納得がいかなかった。
なぜ、中 2 のときに読んだ話に関して今書いているのかというと、Audible で再読 (?) したからである。
思春期のあの頃の記憶というものは (特に衝撃的なものは) かなり深く刻まれているらしく、聴いているうちに 「あぁ、そうだった」 と思い出すことが多々あった。
しかし、『第三の嘘』では 「え、そんなエピソードだったっけ?」 と、しきりに首をかしげていた。
思うに、中 2 の私は『第三の嘘』を読み始めて、「え?」 となって、途中で読むのをやめたのではないか。
解説を聴きながら、ほかの著書『怪物』・『伝染病』・『昨日』も読んだことも思い出した。
が、内容はまったく憶えていない。
しかし、『第三の嘘』の話の軸はかなり衝撃的なものだ。
普通なら忘れるはずがないし、最後まで読んでいたのなら、「え?」 という感覚はかなり和らいだのではないだろうか。
全体をとおして、悲しい、悲しい物語だと思う。
戦争がすべてを壊しもしたが、それだけではない。
そもそも、すべての歯車が軋むように廻っていたような印象を受ける。
私は浦沢直樹の『MONSTER』が大好きだ。一番好きな漫画を挙げるとしたら、これだろう。
この作品を読んで、プラハとドレスデンに行ってみたいと思うようになった (念願叶えた)。
『MONSTER』を読んでいるときにはまったく思わなかったが、この『悪童日記』・『ふたりの証拠』・『第三の嘘』を読んでいるときの虚しさのようなものは、『MONSTER』を読んでいるときと同じものではないか、と思った。
戦争に引き裂かれたきょうだい。
愛されない子ども。
名前のない、誰でもない自分。
ただただ、戦争に蹂躙され大人たちに翻弄され続ける、純粋で美しい子どもたちの悲哀と苦悩。
その中でしたたかに、残酷にならざるを得ない悲しさ。
ただただ、目の前で起こる悲惨なできごとを非力ゆえ受け止めることができず、少しずつゆがんでいく感情。吐き続ける嘘。
誰も守ってくれない。だから自分たちで強くなるしかない。
子ども時代を 「子どもらしく」 生きられなかった子どもたちの物語。
読んでいて胸が悪くなったのはそのせいかもしれない。
アゴタ・クリストフの上述三部作に関しては、ちょっと 「面白い」 と手放しで言えない感があるのだ。
『MONSTER』とは異なり、著者本人が亡命経験者だからなのだろうか。
『MONSTER』はフィクションだ。ヨハンなどいやしない。テンマも同様だ。
手塚治虫ファンなら、登場するヒゲオヤジ似の医師や下田警部似の元刑事などにニヤリとしてしまう要素も含んでいる。
テンマはヨハンを追い詰めてどうするのか?
そこが一番気になって読み進めてしまう。
しかし『悪童日記』ほかの三部作は、フィクションとは思えないほど、現代にも起こっている事象のやるせなさ、哀しみが根底を流れている。
私はこの三部作を読んで、作者の強い憤りを感じた気がした。
徹底的に蹂躙されたと。
過去に自分に起こった出来事を、あんなに淡々とした書き方をしながらも、俯瞰して眺めているような気がしないのだ。
だから伝わってくるものが生々しく、読んだときに同じ傷を覚えるような気がする。
「僕たちはこういうことに傷ついた」
などとは一切書かれていない分余計に、「努めて感情を排除しようとしている」 ような気がして、幼い子どもの心を思うとつらいのだと思う。
『悪童日記』では、感情のない、それこそ悪魔のようにも思える双子が、実はとんでもなく傷ついていたのではないか、と思えるエピソードが、あの 「司祭館の女中のパン」 だ。
あのエピソードがあるのとないのとでは、あの双子の印象がまったく別のものになる。
あれ以降、とても悲しい物語としてしか、私には読めなくなるのだ。
『MONSTER』が好きな方はこの三部作を、この三部作が好きな方は『MONSTER』を読んでみるのもおすすめだ。
もっとも、私はこの三部作をもう読み返すことはないような気がする。
あの中 2 のときに 「え?」 と思ったのははたして、中学生だから理解できなかったからなのか、本当に物語が 「え?」 というものだったからなのか知りたくて再読してみたのだ。
答えは前者でもあるし、(おそらく) 途中で読むのをやめたからでもあろう。
もったいないことをした。
また、『MONSTER』以外にも思い出したものがあった。
『香水』だ。
こちらは戦争の話ではなく、カテゴライズするなら 「孤高の天才」 系の話だが、彼にもまたアイデンティティがなく、愛に飢えている。
純粋がゆえに人を殺めてしまうし、天才がゆえに人を操ることもできる。
それでも満たされない。
かな~りグロテスクな話で、アゴタ・クリストフの上記三部作より断然 「胸が悪く」 なる話かもしれない。
ただ、「香り」 をメインにした主人公というのは非常に珍しいと思うし、「香り」 というものがどんな役目を与えているのか、という視点は自分ではまったく思いつかないものであったため、とても面白く読んだ。
映画も観たが、どちらかというと 「天才の苦悩」 というよりは、恋愛話のように片付けられてしまっていて、ラストの乱痴気騒ぎ? にスポットが強く当てられているような印象を受けた。
主人公ジャン・バティスト・グルヌイユは、恋心のために殺人を犯したのではなく、純粋に香りを追求した結果が殺人になってしまった (殺さずにその香りを入手できたなら、特に殺す必要はなかった) というだけで、映画よりももっと天才的な人物として読んだ。
映画では 「グルヌイユが穴蔵にこもっていた後にしたとんでもない発明」 というエピソードが抜け落ちている。
これがグルヌイユを 「天才」 と言わしめ、かつこの物語のキモでもあると私は思っているため、映画を観て OK だった方にはぜひ原作も読んでいただきたいと思っている。
なんだかまとまりがなくなってきてしまったのでこのへんにしたいと思う。
印象に残っていた本たちも、日々起こる出来事も、いつか忘れてしまうことだとは思うが、それでもできるかぎり憶えていることが大事。
アイデンティティとはすなわち、記憶でもあると思う。
突然すべての記憶をなくしたなら、私は一体何なのだろうか。
ここに記載した小説はいずれも、胸が悪くなる内容のものがある。
しかし、内容はどうあれ 「記憶や印象に残る」 ものを書けるというのは凄いことなのだと思う。
お読みくださりありがとうございました (^^)
いいなと思ったら応援しよう!