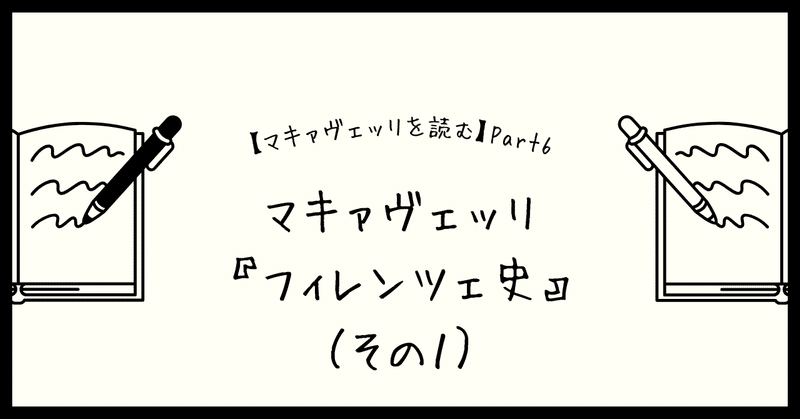
マキァヴェッリ『フィレンツェ史』(その1・イントロダクション)〜【マキァヴェッリを読む】Part6
『フィレンツェ史』の面白さ
『君主論』の次にマキァヴェッリを読むのなら…
マキァヴェッリの『君主論』を読んだ人が、もし彼の書いた他のものをもう1冊読んでみたいと思ったのなら、私は『フィレンツェ史』をおすすめします。
『フィレンツェ史』は、題名のとおり、マキァヴェッリが自身の祖国フィレンツェの歴史を描いた本です。
歴史上の出来事をただ書き連ねたわけではなく、マキァヴェッリが過去の出来事を評価する理論的なコメントを入れたり、登場人物の演説を創作して挿入していたりします。
いわば、司馬遼太郎や塩野七生の歴史物語エッセイの遠いご先祖のようなものです。
また、「失うことへの恐れは、それが近くに迫らなければ実感できないが、手に入れることへの望みは、まだ遠くに離れていても夢見ることができる」(第4巻18章)といったような、気の利いたフレーズなども散見されます。
『君主論』の箴言を面白く思った方なら、『フィレンツェ史』も楽しめるのではないかと思います。
このマキァヴェッリの『フィレンツェ史』について、自分なりの整理を3回に分けて記事に書いてみようかと思います。
今回は、私が1番物語として面白いと思った箇所の紹介、全体の概要、そしてフィレンツェ史の外枠になるイタリア史へのマキァヴェッリの言及を見ていきたいと思います。
次の記事(【マキァヴェッリを読む】Part7)では、マキァヴェッリがフィレンツェをどのように描いていたのかを取り上げます。
そのあと(【マキァヴェッリを読む】Part8)では、『フィレンツェ史』のなかで述べられているマキァヴェッリの政治思想を扱う予定です。
マキァヴェッリ創作演説(これぞマキャベリズム!)
『フィレンツェ史』の面白さをプレゼンするには、言葉を尽くして説明するより実際に読んでもらった方が早い気もするので、
『フィレンツェ史』の中にあるマキァヴェッリ創作演説を1ヶ所丸々引用してみようかと思います。
紹介する演説は、「チオンピの乱」と呼ばれる騒動、参政権のない下層労働者による一時的な政権奪取劇の最初期の一幕(第3巻13章)。
下層民による暴動が生じた後、処罰を恐れた暴動参加者たちを奮起させるために行われた「勇敢で経験豊かなある者」(つまりマキァヴェッリの創作人物)による演説です。
私が1番面白いと思った箇所でもあります。
『君主論』を読んだ方なら、どこかで読んだことがある印象を持つのではないでしょうか。
権力の獲得というテーマが『君主論』と共通しているからかもしれません。
一般に抱かれている「マキャベリズム」のイメージにピッタリな内容になっていています。
「もしもおれ達が、今これから武器を取るべきかどうかとか、市民の家に放火して略奪すべきかどうかとか、教会を荒らすべきかどうかを決定しなければならないのだとすれば、おれだって、それはよく考えてからにした方がいいぜ、と言うだろう。
そしてたぶん、やばいことをして稼ぐよりも、たとえ貧しくとも静かに暮らすほうを選ぶべきだという意見に同意するだろう。
しかし、おれ達はすでに武器を取ってしまったし、たくさんの悪事を働いてしまったのだ。
だからおれは、どうすれば武器を離さずにすむか、またどうすれば犯した悪事から身を守れるかを論じるべきだと思う。
おれは他人が教えてくれなくても、必然の成り行きがきっとおれ達に思い知らせてくれるはずだ、と思っている。
お前たちは町中の奴らがおれ達を恨み、憎んでいるのが分かるだろう。
市民どもは団結していて、執政府はいつも役人どもと一緒だ。
つまりおれ達を縛り首にするために縄をなっているんだよ。
おれ達の首を刎ねるための新しい軍隊を準備しているんだよ。
だからおれ達は二つの事がらをねらって、二つの目標のために、方針を決めなければなるまい。
一つは、おれ達がやったことのために近日中に罰せられないようにすること。
もう一つは、過去の暮らしよりも、もっと自由に、もっとおれ達が満足して暮らせるようにすること。
だから、おれが考えるには、新しい過ちを犯すことによって、悪事を二倍にし、放火や略奪を何倍も繰り返して、またそのための仲間をたくさん持つように工夫して、古い過ちを許されるように望むべきなのだ。
なぜなら大勢なら過ちを犯しても、誰も罰せられないからだ。
小さな過失は罰せられるが、大きくて重大な罪は賞をもらえる。
多くの人が苦しんでいれば、復讐しようとする者などほとんどいない。
全員に対する侮辱は、特定の人への侮辱よりも、ずっと忍耐強く耐えられるのだ。
だから、悪事も何倍かに増やしたほうが、ずっと赦免を受けやすい。
しかも、おれ達の自由のために、おれ達が得たいと望んでいる代物を手に入れる手段をも、与えてくれることだろう。
おれには、確かにうまくいきそうだと思えるのだ。
なぜなら邪魔をしそうな連中は、ばらばらでしかも金持ちだからだ。
奴らが分裂していることは、おれ達に勝利をもたらし、奴らの富がおれ達のものとなったとき、おれ達を支えてくれるだろう。
それがないために奴らがおれ達を馬鹿にする、血統などにびくびくするな。
人間なんて元は一つだから、同じように古くて、自然によってまったく同じように作られているのだ。
みんな服を脱いで裸になれば、まったく同じに見えるだろう。
もしおれ達が奴らの服を着て、奴らがおれ達の服を着たら、おれ達は疑いなく貴族に見え、奴らは賤民に見えるだろう。
なぜなら貧富の差だけが、おれ達に差をつけているからだ。
お前たちの多くが、やったことについてどれほど良心の痛みを感じていて、またなるべくなら新しい罪を避けたいと思っているのを知って、おれは残念だ。
たしかに、もしそれが本当だとすれば、お前たちが良心にも恥辱にもたじろぐことがないように、お前たちはそうであってほしいとおれが考えていたような人間ではないようだ。
なぜなら勝利を得る者は、どんな手を使ってでも勝利を得て、決して恥ずかしいなどとは思わないからだ。
おれ達は良心などを問題にしてはならない。
なぜなら、おれ達のように、飢えと牢獄の恐怖のあるところでは、地獄の恐怖などがあるはずもなく、またあるべきではないからだ。
しかし、もしお前たちが人間の振るまい方に注目するならば、巨万の富や大きな権力に達した人物はすべて、欺瞞か暴力を使ってそれに到達したことが分かるだろう。
ところが彼らは、詐欺や暴力によって簒奪した代物を、後にそれを獲得した汚いやり方を隠そうとして、その手口を偽り、別の名目で手に入れたことにして飾りたてているのだ。
知恵が乏しいか、愚かすぎるため、こうした方法が使えない者は、常に隷従か貧困の中で溺れてしまう。
なぜなら忠実な下男は、常に下男のままで止まり、善良な人は常に貧乏のままで止まるからだ。
不忠で大胆でなければ、決して隷従からは抜け出せない。
また強欲で詐欺師のようでないと、貧困からは抜け出せない。
なぜなら神と自然は、人間のあらゆる富を彼らの真ん中に置いて、勤労よりも略奪によって、また善良な技能よりは邪悪な技能によって取りやすくしているからだ。
そこから人びとがお互いに共食いし、弱者が常に貧乏くじを引くことになるのだ。
だからチャンスが与えられたら、暴力を振るわねばならないし、まだ市民たちが分裂していて、執政府の態度もあやふやで、役職者連中も呆然自失の態にある今以上に、運命の大きなチャンスはあり得ないだろう。
つまり奴らが団結し、度胸を決める前なら、簡単に押え込むことができるわけだ。
そうすれば、おれ達は完全にこの市の主人の地位に収まるか、それともその重要部分を押えて、過去の過ちが許されるだけではなくて、新しい侮辱によって奴らを脅せる権利まで得るだろう。
この作戦が大胆で危険なものだとは、おれも認めよう。
しかし必要に迫られた時は、大胆こそ賢明だとみなされる。
大事に際しては、勇気ある人間は、危険など問題にしない。
なぜなら危険で始まる企ては、常に褒美とともに終わることになっているのだ。
またある危険からは、危険を冒さずには抜け出せない。
つまりおれが思うには、牢獄や拷問や死が準備されたのが目に見える時には、身を守ろうと試さないで、じっとしている方がずっと恐ろしいことなのだ。
だって、じっとしていれば不幸は確実だが、何かをやってみた場合、結果は分からないじゃないか。
おれはお前たちが貪欲な上役どもや、役人どもの不正を嘆くのを何度聞かされたことだろう。
いまや奴らから解放されるだけではなく、お前たちがそのまま奴らの上役になって、お前たちが奴らを恐れた以上に、奴らの方が、お前たちのことを嘆いたり、 恐れたりすべき時なのだ。
チャンスがおれ達に持ってきてくれた幸運は、すぐ飛んでいってしまう。
それが逃げ去った後で、また取り戻そうとしても無駄なのだ。
お前たちの敵が準備しているのが見えるだろう。
奴らの魂胆を出し抜いてやろうじゃないか。
おれ達のうちで一番先に武器を取る者が、疑いなく勝利者となって敵を滅ぼし、自分への賞賛を勝ちとれるだろう。
またそれによって、おれ達の多くの者は名誉を得るだろうし、全員が安全だろう。」
邦訳書について
邦訳の種類
アクセスしやすい『フィレンツェ史』の邦訳は、3種類あります。
〈1〉大岩誠[訳]『フィレンツェ史』(上下巻)岩波文庫(旧訳)1954/1960年
〈2〉在里寛司/米山喜晟[共訳]『フィレンツェ史』(上下巻)ちくま学芸文庫2018年
〈3〉齊藤寛海[訳]『フィレンツェ史』(上下巻)岩波文庫(新訳)2012年
〈1〉は、多賀善彦という名義で戦時中に出版された『マキアヴェルリ選集』に収められていた邦訳を改訳したもの。
筑摩書房『マキァヴェッリ全集』月報によれば、フランス語からの重訳のようです。
現在では、Kindleで響林社文庫から復刻版が入手可能です。
古本屋で目にした時は、同じ岩波文庫から出版された〈3〉と間違わないようにしましょう!(経験者談)
〈2〉は、『マキァヴェッリ全集』第3巻として筑摩書房から1999年に出版された邦訳の文庫化。
「文庫化においては、特に訳注の部分で若干の訂正を加え」た、とのこと。(文庫版「解説」)
また、文庫の巻末には、訳者によるフィレンツェ史年表が追加されています。
〈3〉は、イタリア中世史の研究者による最新の邦訳です。
どの邦訳がおすすめできるか
まず、〈1〉はおすすめから外れます。
イタリア都市国家の役職に対して、「主として鎌倉幕府の官職名を中心にして選択し」た訳語を活用しています。(「著者のはしがき」)
政所、執権衆、管領代、都護、旗持衆、身代書……それなんて鎌倉殿?
フランス語からの重訳、古い翻訳年というマイナスポイントも付け加わるため、他の邦訳を最初に読む一手です。
〈2〉と〈3〉は、読む人によって好みが分かれるかと思います。
〈2〉の訳者はイタリア言語学とイタリア文学が専門、一方〈3〉はイタリア中世史が専門。
〈3〉は、(おそらく従属節などを別の一文に分けるような工夫をしたのか)ひとつひとつの文が短めで、文章全体が柔らかく読みやすい印象を受けました。読み比べると、その分だけ〈2〉の文章を少し硬く感じてしまいます。
ただ、〈2〉の邦訳は、文中に多々ある登場人物が語った演説など直接話法の文章になると、かえって読み応えを覚えます。〈3〉の訳者の方も「筆勢のある翻訳」と〈2〉を評されているのも納得です。
また、〈2〉に年表が付録としてあるのはセールスポイントですが、少し細かすぎて、私の場合には、本書を読むのにはあまり役立てることはできませんでした。
私の結論としては、「〈2〉の文を読みにくいと感じない方は〈2〉、そうでない方には〈3〉がおすすめ」です。
ちなみに、上で引用した演説は〈2〉の訳文です。
また、以下でマキァヴェッリ『フィレンツェ史』から引用するとき、私の好みで引用箇所ごとに〈2〉と〈3〉を切り替えて使用しています。
『フィレンツェ史』を読んでみようと思われた方は、読み比べてみて訳本選びの参考にしていただければ幸いです。
『フィレンツェ史』の概容
マキァヴェッリの大部の著述のうち、最後に書かれたのが本書『フィレンツェ史』です。
ジュリオ・デ・メディチ枢機卿、後の教皇クレメンス7世の斡旋で、1520年にフィレンツェ共和国と執筆契約。
25年に現在残っている第8巻までが献呈される。
後続の歴史を著述する用意もあったようで、第9巻の下書きの断片が残っているとのこと。
後続の巻が完成しなかった理由が、著作する意志の消失によるか著者の死によるかは、説が分かれている模様。
実際に読んでみると、各巻ごとにかなり異なる印象を受けます。
国内対立、対外戦争、イタリア全体の情勢など、巻ごとで扱う内容に偏りがあるせいなのでしょうか。
それとも、元ネタにした資料の影響なのでしょうか。
(マキァヴェッリが元ネタにした資料については、ちくま学芸文庫の解説が詳しく取り上げています。
そこに挙げられたもの以外にも、第8巻36章のロレンツォの叙述は、同時代のヴァローリ『ロレンツォ伝』そのままの引き写しという指摘があります。(石黒盛久「マキアヴェッリ政治思想とロレンツォ・デ・メディチ像の創出:『フィレンツェ史』第8巻の分析を中心に」))
『フィレンツェ史』主要トピック
教皇クレメンス7世への献辞
序言
第1巻 ゲルマン民族大移動から1434年までのイタリア史の概観
第2巻 フィレンツェ史(都市の起源-1343)
:フィレンツェ内でのグエルファ党とギベッリーナ党の抗争(1215-)/フィレンツェ内での白派と黒派の抗争(1300-)/アテネ公の領主選出と追放(1342-1343)
第3巻 フィレンツェ史(1343-1414)
:八聖人戦争(1375-78)/チオンピの乱(1378-82)
第4巻 フィレンツェ史(1414-1434)
:ロンバルディア戦争(1422-)/コジモの国外追放と帰還(1433-34)
第5巻 イタリア史(1434-1440)
:メディチ支配の開始(1435)/ロンバルディア戦争(含アンギアーリの戦い)
第6巻 イタリア史(1440-1462)
:ロンバルディア戦争(承前)/ヴィスコンティ家断絶からローディの和平まで(1447-54)
第7巻 フィレンツェ史(1462-1478)
:コジモ・デ・メディチ死去(1464)/反メディチ派追放(1466)/ピエロ・デ・メディチ死去(1469)/ヴォルテッラ掠奪(1472)/ミラノ公暗殺(1476)
第8巻 フィレンツェ史(1478-1492)
:パッツィ家の陰謀とパッツィ戦争(1478-80)/フェルラーラ戦争(1482-84)/ロレンツォ・デ・メディチ死去(1492)
(各巻の下に記載した内容は、分量の多さや印象から私がピックアップしたもので、原書内で選出されているわけではなく、また網羅的でもありません。)
読書ノート(注目ポイントの引用)「イタリア全体関連」
フ国内の党派対立、国家を牛耳る僭主などをめぐるフィレンツェの歴史への言及や、マキァヴェッリの政治思想については、また別の記事をたてて見て行こうかと思っています。
今回は、それ以外のことで気になった点、フィレンツェ外の話題に関連する事柄について記録しておきます。
ローマ教皇庁への評価
教皇は、自分が圧迫されても、没落したこの〔東ローマ〕帝国に保護を求めることができなくなった。
他方、ロンゴバルト族の力が増大したので、新たな保護を求めることが必要になったと考えて、フランク王国に行き、その王たちに保護を求めた。
その結果、これより後にイタリアで蛮族どもがなしたすべての戦争のうち、その大部分は、教皇が原因となって引き起こされた。
また、イタリアに侵入したすべての蛮族は、たいていの場合、教皇によって呼び込まれたのである。
このような事態が、このわれらの時代になっても、まだ引きつづいて起きている。
その結果、イタリアは分裂して弱くなったし、現在でもそうなっている。(第1巻9章)
このように教皇たちは、あるときは宗教的な理由から、またあるときは個人的な野心から、イタリアに新たな挑戦者を呼び込んで、新たな戦争を引き起こすのをやめなかった。
そしてある君主を強力にしてから、そのことを後悔すると、彼の破滅を求めたのである。
教皇たちは、自分が微力なのでイタリアを支配できず、かといって他人が支配することは許さなかった。(第1巻23章)
このような俯瞰的な評価は、別の著作(たとえば『ディスコルシ』第1巻12章)でも見られるものです。
一方、『フィレンツェ史』では、同じプレイヤー目線での教皇庁の評価があるところが目を引きました。
〔一般に高齢で即位する〕教皇の余命の短さ、その継承如何による事態の変化、教会が支配者たちをものともしていないこと、教会が方針を決める際の配慮のなさ、これらのことによって、世俗の支配者は、教皇を全面的に信頼することも、自分の運命を安心して教皇と分かち合うこともできない。
戦争や危険に際して教皇と組む者は、勝てばその成果を分かち合わなければならず、負ければ一人で取り残される。
教皇は、精神的な影響力と名声のおかげで、支えられ、守られるからである。
傭兵制批判の背景
相変わらず、傭兵制への嫌悪感が各所であらわになっています。
好き勝手に悪口を書いていて、かえって面白く感じてしまうくらいです。
「それゆえ私の歴史は、こうした無気力な君主たちや卑劣きわまる軍隊で満ち溢れることになるだろう」(第1巻39章)
「また、これほどの大壊滅においても、二十時間から二十四時間も続いた白兵戦のあいだに、ひとりの兵士のほかは死者はなく、その死者も負傷とか名誉の果し合いのためではなく、落馬し、馬のひづめにかかって落命したのであった」(第5巻33章)〔訳注によれば、この記述が由来する資料はなく、史実とは異なる〕
「ただ一頭の馬が頭を向けるか、背中を向けるかで、一つの合戦の帰趨が決したほどである」(第8巻16章)
それはともかく、『フィレンツェ史』では真面目な傭兵制批判もあります。
純粋に軍事的な有効性の視点から主に非難されていた『戦争の技術』での批判とは少し毛色が異なるものです。
長期間の平和にもとづく平穏な時代が出現することはなかったにせよ、激しい戦争によって危険な状態に陥ることもなかったのである。
なぜなら、諸国が武器を取って互いにしばしば攻撃し合う状態では、それを平和だとは言えないにせよ、人々が殺戮されず、都市が略奪されず、国家が破壊されない状態は、戦争とも呼べないからである。
というのも、これらの戦争は、たいへん軟弱なものに成り下がっており、恐怖もなく開始され、危険のない揉み合いがおこなわれ、損害もなく終結するからである。
マキァヴェッリの傭兵制批判の背景には、相手を徹底的に打ちのめすことを「本来の戦争」とする見方があります。
この「本来の戦争」と比べれば、傭兵の戦争は生ぬるいわけです。
『戦争の技術』にも同様の記述がありました。
そちらでは、このように戦争が堕落してしまったのはキリスト教の影響であると述べています。
そして、戦争が変わったせいで、自分で武装して訓練するより傭兵を採用する、敗北を賠償金で埋め合わせるという悪癖がはびこっているというわけです。
戦争を起こそうとする目的が、自分を富ませ、敵を貧困に陥れることにあるのは、これまで常であったし、またしごく当然だ。
また勝利を追い求め、戦勝による利益を追求するのは、自力を強め、敵の力を弱めるため以外には、いかなる理由もない…(中略)
敵を抹殺し、戦利品と身代金を我がものにできる君主や共和国は、戦争の勝利で富み栄える。
ところが、勝ちはしても敵を抹殺できないで、略奪品や身代金が我がものとはならず、配下の兵士に横取りされる君主は、勝利ゆえに貧困化する…(中略)
昔日の、よく統治された共和国は、戦いに勝ってその国庫を金銀で満たし、人民に贈り物を供給し、臣下の税金を免除し、競技会と壮大な祝祭を催して彼らを楽しませたものだ。
ところが、いま叙述している時代の戦いでは、勝利は、まず最初に国家の金庫を空っぽにし、つぎには人民を貧困にすることを意味し、しかもその勝利は、君の敵から君を守ってはくれない。
このことはすべて、こうした戦いが行われるその無秩序から生じてきた。
倒した敵兵を身ぐるみ剥ぐだけで、彼らを捕虜にもしなければ、かといって殺しもしなかった。
『フィレンツェ史』での傭兵批判には、財政的な視点が登場しています。
マキァヴェッリがいう「本来の戦争」は、掠奪、土地の接収、奴隷の獲得で儲かるものであったと言います。
逆に、傭兵制は儲かるどころか金銭を支出するという理由で非難されます。
さらに、相手を叩きのめさない傭兵の戦争では、再び敵と戦争が起こるのは当然で、またさらに戦費で貧しくなるというわけです。
実際、『フィレンツェ史』では、戦争=傭兵のための費用を捻出するための税金の導入、税負担の分配をめぐる国内対立に幾度も言及されています。
(マキァヴェッリが現実の政治生活で徴兵制を導入できたのは、この傭兵費用の負担をめぐる政治調整が失敗したためであることは皮肉です。
より費用のかからない窮余の策として、彼の徴兵制案は採用されたのでした。)
ジェノヴァのサン・ジョルジォ銀行
ジェノヴァのサン・ジョルジォ銀行に言及している第8巻29章が目を引きました。
その章の最後は、ある予言によって締めくくられています。
いずれにせよ時の経過とともに実現するであろうが、もしサン・ジョルジォがこの都市全体を自己の支配下に置くことになれば、それはヴェネツィア共和国よりもっと記憶に値する共和国となるであろう。
当時ヴェネツィアは、古代ローマを除けば、もっとも優れた国家として名前があがる存在でした。
そのヴェネツィアより評価が高いというのは並大抵ではありません。
さらに、『フィレンツェ史』という書物のなかでこういうことを書くのは異様な気がします。
もっとも、この予言は実現しませんでしたし、おそらくジェノヴァやサン・ジョルジォに対する深い考察が込められているわけではないと思うのですが…
サン・ジョルジォは邦訳文献では銀行と訳されることが多いようですが、その機能はただの債務機関とはとても言えない存在です。
彼ら〔ジェノヴァ人〕の共和国は、多額の金銭を貸し付けてくれた人々に返済できなかったので、彼らに税関からの収入を譲り渡した。
債権者の一人一人が、 この共和国から完全に返済してもらえるまで、自分の貸付け金額に応じて、 主要財源のこの財政収入を分配するようにしたのである。
そして共和国は、彼らがそこで集会を開けるように、税関の上に位置する宮殿を彼らに譲渡した。
そこで、これらの債権者は自分たちの間で一種の統治組織を形成して、公的業務について審議する一〇〇人からなる評議会と、彼ら全員の統括者としてそれを実行する八人の市民からなる執行機関を設置した〔一四一一年〕。
彼らの債権は株式と呼ばれる持ち分に分割され、彼らの団体全体はサン・ジョルジォと名乗った。
このような執行機能を受けもったので、ジェノヴァ共和国に新たな必要が生じたときは、共和国はサン・ジャルジォに新たな援助を求めた。サン・ジョルジォは、富裕でよく管理されていたので、共和国に奉仕することができた。
共和国は、これとは反対に、先にサン・ジョルジォに税関を譲渡したように、新たな債務の担保として、自国の土地を引き渡し始めた。
共和国の必要とサン・ジャルジォの奉仕から生まれたこのような事態が大いに進展した結果、サン・ジョルジォは、ジェノヴァ支配下の集落や都市の大部分を自己の管理下に置いて、どの分野でも共和国の介入を受けることなく、それらを統治し、防衛し、毎年公的に選出した統治者を送り込んだ。
このジェノヴァとサン・ジョルジォについて、マキァヴェッリは以下のように描写しています。
この都市には多数の貴族的な家族があり、それらはたいへんな勢力をもっていたので、役人の命令にはなかなか従おうとしなかった。
そのような家族の中で、フレゴーゾ家とアドールノ家が最も強力であった。
この両家のせいで、この都市の分裂が生じ、 法的秩序が破壊された。
というのも、両家は法的に争うのではなく、多くの場合は武器を取って戦ったので、この都市の統治は常に、一方の側が抑圧され、他方の側が支配するという事態になっていたからである。
そして幾度か、要職を剥奪された側が外国の武力に支援を求めた結果、自分たちが統治できない祖国を一人の外国人に服従させる、という事態を招いた。
ジェノヴァの市民は、共和国を圧政的なものとして、そこへの愛着を断ち切り、サン・ジョルジォを公正によく管理された機構だとして、その愛着をこちらに移し替えた。
そのために、国家の体制が容易にかつ目まぐるしく変化するようになり、ときには一人の市民に従い、またときには一人の外国人に従うありさまとなった。
体制を変えるのはサン・ジョルジォではなく、共和国だったからである。
その結果、支配権をめぐってフレゴーゾ家とアドールノ家が抗争したときは、それが共和国の権力をめぐるものであったから、市民の大部分は、党派からは身を引いて、その支配権は勝者が手にする獲物だとして放っておいた。
サン・ジォルジォの当局は、ある者が〔共和国の〕権力を握ると、彼に自分たちの規約を遵守することを誓約させるほかは何もしなかった。
その規約は、今日にいたるまで変更されていない。
というのは、サン・ジャルジォが武力、経済力、管理機構をもっているので、明らかに危険な反乱でもないかぎり、誰もそれを変更できないからである。
ジェノヴァの例はまったく例外的なものであり、哲人によって空想された、あるいは分析された多くの共和国の中にも見当たらないものである。
同じ市民からなる一つの同じ〔社会の〕枠の中に、自由と圧政が、法にもとづいた生活と腐敗した生活が、正義と放縦が見られる。
というのは、その〔サン・ジャルジォの〕秩序だけが、この都市を古くからの尊敬すべき組織として維持しているからである。
マキァヴェッリの描くジェノヴァの姿が、実際のジェノヴァにどれほど近いかは調べてみないとわかりませんが、興味を引きます。
(根拠はないのですが、もしかしたらマキァヴェッリは、過去のフィレンツェでポポロが統治権限を獲得する姿をサン・ジョルジォに投影しているのかもしれないと思っています)
ちなみに、サン・ジョルジォについては、マックス・ウェーバー『中世商事会社史』(邦訳は『中世合名・合資会社成立史』)、大塚久雄『株式会社発生史論』(楠井敏朗『大塚久雄論』に詳しい解説あり)で取り上げていることくらいしか、私は知りません。
イギリス東インド会社が比較的近い組織になるのでしょうか?
ジェノヴァやサン・ジョルジォについて手頃に知ることができればいいのですが…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
