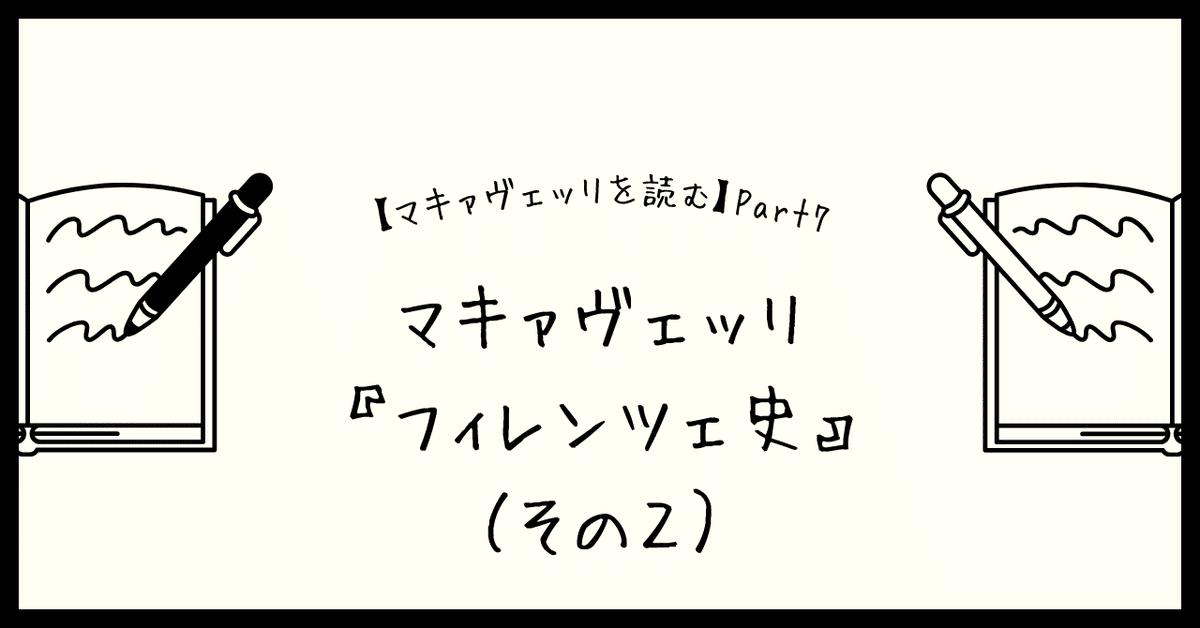
マキァヴェッリ『フィレンツェ史』(その2・マキァヴェッリの描くフィレンツェ像)〜【マキァヴェッリを読む】Part7
イタリア半島の中央、トスカーナ地方の都市の一つでしかなかった都市、フィレンツェ。
わずか300年足らずの間に、かつては同格であった他のトスカーナ北部の諸都市を勢力下に置いていき、遂には、イタリアの五大勢力の一角をしめるまでに成長します。
そんな自身の祖国の歴史について、マキァヴェッリはどのように見ていたのでしょうか。
ローマ教皇庁や当時の戦争についての言及を見た前回(【マキァヴェッリを読む】Part6)に引き続いて、今回はマキァヴェッリが描いたフィレンツェの姿を見ていきたいと思います。
次回の記事では、今回取り上げたフィレンツェの歴史に対するマキァヴェッリの理論的考察、『フィレンツェ史』に現れたマキァヴェッリの政治思想を取り上げる予定です。
マキァヴェッリの見たフィレンツェ史の全体図
まず、『フィレンツェ史』に書かれたマキァヴェッリ自身の手による全体的な総括を見た後、フィレンツェ史の流れや各時代への言及を取り上げてみたいと思います。
マキァヴェッリ自身による『フィレンツェ史』の要約
時の教皇、メディチ家出身のクレメンス7世に宛てた『フィレンツェ史』の献辞で、マキァヴェッリは『フィレンツェ史』の内容をこう要約しています。
これをご覧くださいますと、聖下は、次のことをお目になさいますことでしょう。
まず、ローマ帝国が西方で力を失い始めてから幾世紀もの間、イタリアでは多くの〔国々〕が滅亡し、多くの支配者のもとで国々のあり方が変化したこと。
教皇、ヴェネツィア人たち〔の共和国〕、ナポリ王国、ミラーノ公国が、この地〔イタリア〕の第一等の地位と政治権力を手に入れたこと。
聖下の故国〔フィレンツェ〕は、〔神聖ローマ帝国内部の〕分裂のおかげで皇帝への従属から解放されたとは申しましても、聖下のご実家〔メディチ家の庇護のもとで統治されるようになるまで、〔その内部が〕分裂したままであったこと。
マキァヴェッリが見たフィレンツェ史の特徴
マキァヴェッリがフィレンツェの歴史の最大の特徴を見て取るのは、都市国家内の度重なる党派対立でした。
この「諸々の都市における憎悪や分裂の原因を教えてくれる」党派対立について書くこと、そこから「教訓を手に入れる事で賢明になり、自国の団結を維持することができる」ようにすること、これが『フィレンツェ史』の目的であるとマキァヴェッリは「序言」で述べています。
あらゆる共和国の実例が興味をひくとすれば、われらの共和国の実例について読むことは、それよりもさらに興味がわくし、さらに有益である。
どこかの共和国の内部対立が人目をひくとしても、フィレンツェの対立は特筆大書すべきものである。
なぜなら、なんらかの情報どこかの共和国の内部対立が人目をひくとしても、フィレンツェの対立は特筆大書すべきものである。
なぜなら、なんらかの情報があるほかの共和国の大部分では、対立は一つだけであったからであり、その都市は、事件の展開の仕方に応じて、繁栄することもあれば、破滅することもあった。
しかし、フィレンツェでは、対立は一つでは収まらず、いくつも生まれてきた。
ローマでは、よく知られているように、王が追放されると、貴族と平民との間に反目が生まれ、その対立が〔共和政の〕 ローマの滅亡までつづいた。
アテネも同様であり、当時繁栄していたほかの共和国もすべて同様であった。
しかし、フィレンツェでは、最初は貴族内部で対立が生まれ、ついで貴族と平民が対立し、最後に平民と下層民が対立した。
対立する二つの集団のうち一つが勝ち残り、それが二つに分裂する、ということが何度も起きたのである。
この対立の中から、多くの死者、多くの亡命者、多くの家族の破滅が生じたが、それは記録があるほかのどの都市にも生じなかったほどの規模であった。
実際、わたしの見るところ、偉大できわめて強力な都市のどれをも破滅させてしまうような、この対立の中から生まれてきたわれらの都市の力は、ほかのどこにも例がないようである。
そうであるにもかかわらず、われらの都市は、成長しつづけてきたように見えるのであるから。
(中略)
フィレンツェが皇帝権力から解放された後、団結を維持しうる政体をもつというたいへんな幸運に恵まれていたとしたら、疑いもなくわたしは、最近のものにせよ過去のものにせよ、それを凌ぐような共和国を知ることはなかったであろう。
武力にせよ経済力にせよ、その力量が満ち溢れていたにちがいないので。
この党派対立への言及が、『フィレンツェ史』におけるマキァヴェッリの政治思想の表明の大半を占めています。
マキァヴェッリの描くフィレンツェ史の諸相
フィレンツェ史の起点
今日フィレンツェの歴史が語られるとき、大抵は1115年から始まるようです。
(真偽不明ないくつかの都市の創設伝説を除く)
この年、トスカーナ女伯マティルデが後継者を残さず亡くなり、カノッサ家が断絶しました。
(かの「カノッサの屈辱」の舞台を提供したカノッサの城主としても有名です)
これにより、その領土内の諸都市が領主層の支配から独立する傾向が生じます。
フィレンツェもそのような諸都市の一つでした。
このため、今日ではこの年が都市国家フィレンツェが誕生した年とみなされることもあるようです。
しかし、マキァヴェッリはこのトスカーナ女伯の死には、重きを起いていません。
西暦1215年が、マキァヴェッリが注目するフィレンツェ史の最初の年になります。
この年、とある婚約破棄事件を機に、フィレンツェ内で貴族同士の流血沙汰が発生しました。
この際、イタリア全体のギベッリーニ党(当初は皇帝派)とグェルファ党(当初は教皇派)の対立がこの騒動と結びつき、フィレンツェ内にも党派対立が持ち込まれた、とマキァヴェッリは言っています。
キリスト降誕一二一五年までの間、この都市は、イタリアを支配している人びとと運命をともにした。
この当時フィレンツェ市民たちは、彼らを支配していた人びとの権力のために、記憶に値するほどの成長や活動は何一つできなかった。
それ〔引用註:皇帝と教会の分裂〕にもかかわらず、フィレンツェ市民は一二一五年まで統一を保っていて、我が身を守ること以外にはいかなる目的を追うこともなく、勝利者に服従していた。
その後、1250年に神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世が亡くなった時機に、今日プリーモ・ポポロ(第一次平民)政権と呼ばれる体制が成立します。
この時こそ、体制が「自由を樹立した」=独立したとマキァヴェッリは表現しています。
しかしフェデリーゴ二世〔引用註:神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世〕が死ぬと、フィレンツェで中流階級を占め、人民の間でより大きな信用を得ていた人びとは、分裂したままで都市を滅亡させるよりは、それを統一させるべきだと考えた。
そして彼らは、グェルフ党が屈辱を水に流して帰国し、ギベッリーニ党が疑惑
を棄てて彼らを受け入れるように工作した。
こうして一体となったとき、彼らは新しい皇帝が力を得る前に、自由に生きる政体と自衛するための体制を取ることができる時機が到来したと考えた。(第2巻4章)
市民たちは、こうした軍事的、市民的制度によって彼らの自由を樹立した。
フィレンツェがほんのわずかの時間で、どれほど大きな権威と力を獲得したかは、とても考えられないほどである。
そしてトスカーナの盟主となっただけでなく、イタリア第一流の都市の一つに数えられるにいたった。
もしも、たび重なる新しい分裂がこの町を襲わなければ、いかなる偉大さにでも到達できたことだろう。
フィレンツェ市民は、この政府の下で十年間生きた。
その間にピストイア、 アレッツォシエナの市民たちを強制して、自分たちとの同盟を結ばせた。
シエナから軍隊を戻すとヴォルテルラを占領し、またいくつかの城塞を壊して、その住民たちをフィレンツェに連行した。(第2巻6章)
フィレンツェのもっとも幸福な時期
イタリア全体における戦闘の帰趨により、第一次ポポロ政権は約10年で崩壊。
その後、政権を担当する党派は幾度か入れ替わります。
そして、1290年に今日セコンド・ポポロ(第二次平民)政権と呼ばれる体制が成立します。
この時、この政権を認めなかった貴族は「豪族」と認定され、政権に参加する資格を剥奪する「正義の規定」が成立します。
この政権こそ、マキァヴェッリは最大級の賛辞を送った体制でした。
人材と富と名声に満たされて、われわれの都市がこの時代以上に偉大で、幸福な状態になったことはなかった。
武器を取れる市民は三万人、それに周辺領域部の七万人が加わった。
トスカーナの全土が、そのうちの一部は属領、一部は友邦としてではあったが、フィレンツェに服従していた。
貴族と平民の間には、多少の念憑や疑惑が残ってはいたものの、もはやどんな悪影響ももたらさず、団結して各自が平和に生活していた。
その平和は、もしも内部の新たな敵意によって攪乱されなければ、外部の敵意など疑う余地はありえなかった。
なぜならこの都市は、もはや皇帝権も亡命者も恐れる必要のない状態にあり、また自国の戦力によって、イタリア中のあらゆる国家に対抗することができたからだ。
したがって、この国に対して、外部からの力がもたらせなかった不幸を、内部の力が及ぼすこととなった。
この幸福な時期も、1300年に終わります。
ピストイアの白派と黒派の党派対立がフィレンツェ内に波及して、党派対立が発生したからというのです。
この都市は、一つの対立ではなく、多くの対立によって、混乱に陥った。
そこには平民と豪族、ギベッリーナ党とグエルファ党、白党と黒党の対立があったのである。
だから、都市全体が武器を取って戦いに明け暮れた。
ナポリ王の庇護とアテネ公の追放
14世紀前半、神聖ローマ皇帝ハインリヒのイタリア来訪、ギベッリーニ党のルッカやピサからの外圧を受けて、フィレンツェはナポリ王ロベルト1世などグェルファ党の外部勢力の庇護を求めるようになります。
どのような措置も、敵を押さえ込むのには足りなかった。
そこで、ロベルト王の息子でカラーブリア公のカルロが彼ら〔引用註:フィレンツェ〕の防衛に来てくれるのを望むなら、カルロを自分たちの支配者に選出せざるをえなくなった。
というのも、当時のフィレンツェ人は、自分たちの都市を支配者の手に委ねることに慣れていたので、彼の友情〔対等な立場での同盟〕よりも、むしろ彼に従属するほうを望んだからである。
アテネ公グァルティエーリ(ゴーティエ)も、ナポリ王から派遣されてきた一人でした。
1342年、彼は民衆の支持によってシニョーレ(君主ないし領主)として選出されます。
しかし、シニョーレとなるとすぐに彼は支持を失いました。
結局、翌年には市民が蜂起、わずか10ヶ月の支配ののちに追放されてしまうのでした。
人々が蜂起した日は、聖アンナの日という記念日として現代まで残っています。
チオンピの乱
その後も、アールビッツィ家とリッチ家とが争うなど、ミラノや教皇庁との外交方針や戦争にまで党派対立は影響を与えます。
その対立の間隙をぬって、下層市民が政治参加を要求する「チオンピの乱」が1378年に発生。
党派対立は混沌の坩堝と化して行きます。
(先日の記事で長文引用した演説は、このチオンピの乱で叛乱をあおるものでした。)
勢力圏の拡大
1382年になると混乱は収束し、有力家による寡頭派体制が成立しました。
アールビッツィ家とリッチ家との不和によって生まれ、ついでサルヴェストロ・デ・メディチ殿によって大騒動〔引用註:チオンピの乱〕とともに息を吹き返した党派争いは、消え去ることがなかった。
〔下層民の〕全般から強く支持された党派は、たった三年間だけ支配して、一三八一〔正しくは一三八二〕年には打ち破られた。
それにもかかわらず、その党派感情は、都市の大部分を包み込んでおり、完全に消え去ることはなかった。
この党派の首領たちに対して、一三八一年から一四〇〇年まで、〔彼らに不利な措置を実現するための〕度重なる全市民集会や、切れ目のない迫害がおこなわれた結果、この党派がほとんど消滅したのは事実である。
この党派の首領として追及された主な家は、アルベルテイ、リッチ、メディチの家々であり、それらは、その人員にせよ財産にせよ、失うことを何度も余儀なくされた。
また、この体制のもとでフィレンツェは勢力圏を拡大しました。
この時期の終わり、ミラーノ公フィリッポ〔=マリーア〕との戦争〔引用註:1422年-〕とともに、 〔フィレンツェでは〕党派が復活した。
これらの党派の対立抗争は、この体制が崩壊するまで鎮まらなかった。
この体制とは、一三八一〔現行暦では一三八二年〕から一四三四年までつづき、多くの栄光をもたらした多くの戦争をおこなって、アレッツォ、ピーサ、コルトーナ、リヴォルノ、モンテプルチァーノをフィレンツェの支配下に収めた体制である。
もしこの都市が統一を維持し、内部の古い敵意が再燃することがなかったら、もっと大きなことが成し遂げられたであろう
メディチ家の支配
1420年頃からアールビッツィ家のリナルドに権力が集中するようになります。
この対抗馬として台頭したのがメディチ家のコジモでした。
1433年のルッカ攻略失敗を機に、コジモ・デ・メディチが政争に勝利し、ここからメディチ家の支配が始まります。
陰謀による危機的な状況もありましたが、結局は反メディチ派の排除が進み、メディチ家への権力集中は進行していきました。
イタリアの「破滅」
パッツィ戦争やフェルラーラ戦争など、いくつかの危機はあれど、イタリアは1450年代半ばから1494年まで総じて平和な時期を過ごします。
しかし、1492年のロレンツォ・デ・メディチの死をもって、この状況も終わりを迎えます。
こうして、彼の死をイタリア中の全市民とあらゆる君主が悲しんだ。
そのことについては明白な証拠が残っている。
なぜなら、この重大な出来事から受けた悲しみを、その使者を通して、フィレンツェで表明しなかった人はいなかったからである。
しかし、彼らにそれを悲しむ正当な原因があったことを、彼の死の結果がその後間もなく証明した。
なぜならイタリアは彼の助言を受けることができなくなったため、残された人びとの力では、ミラノ公の後見人であるロドヴィーコ・スフォルツァの野心をなだめることも抑えることもできなくなったからである。
そのためロレンツォの死後間もなく、悪い種子が育ち始め、それをえぐり取ることができる人が生きていないために、それは程なくしてイタリアを破滅させ、さらに今なお破滅させつつある。
ロレンツォ死去の翌年、ナポリ王と対立したロドヴィーコ・スフォルツァが、フランス王シャルル8世へナポリ遠征を勧告。
そして、1494年にシャルル8世がイタリア遠征を実施。
ここからイタリアは激動の30年間に突入することになります。
マキァヴェッリの『フィレンツェ史』も、ロレンツォの死を述べた上の文章で締めくくられるのでした。
余談:「イタリア」史の地理範囲と時代区分について
マキァヴェッリをはじめとして、グイッチァルディーニから現代のイタリア史に至るまで、1494年をルネサンス終焉を象徴する年と見ているようです。
シャルル8世のイタリア侵攻から始まるイタリア戦争で、西欧政治史の中央からイタリアが脱落する、と。
今回、フィレンツェ史を読んで感じたのは、この年で歴史を区切ることへの違和感でした。
イタリアにとって、1494年前後で事情が大きく変わったと見るよりは、
北部の内陸イタリアが政治的な自立性を発揮できた、14世紀から1453年頃までが例外的な時期と考える方が、全体像がスッキリ見えるのかもと思えました。
つまり、周囲の大国がさまざまな事情で身動きが取れない例外的な権力の空白期間に咲いた徒花としてルネサンスを見る、
そして、ナポリ王国をイタリアより地中海世界の地域として見る方が構図がスッキリする気がしたのです。
教皇庁のアヴィニョン捕囚(1309-1377)と大シスマ(1378-1417)と、いわゆる英仏百年戦争(1343-1442)は、イタリアのルネサンスの背景として言及されます。
そこに、ロベルト1世死去からアルフォンソ1世登位までのナポリ王国の混乱を加えた方がいい。
そして、現代でも北部と大きく異なる南部イタリアを「イタリア」と分けて歴史叙述した方がスッキリするように思えた次第です。
フィレンツェに所属するマキァヴェッリやグイッチァルディーニにとって、シャルル8世が侵攻した1494年は、たしかに「フィレンツェ」史にとって大きな転機でした。
長年フィレンツェを差配していたメディチ家が追放されたのですから。
しかし、シャルル8世の侵攻は、ナポリ王国史から見れば恒例の王位争いと言えますし、
そもそも翌年には撃退されてイタリアから撤退しています。
西欧史全体から見れば、ハプスブルク家カルロス1世登壇前の前座のようにしか見えない…
そんなわけで、1494年という区切り、「イタリアの破滅」というレトリックは、イタリア史がフィレンツェ史に引きずられていることの象徴のように思います。
それはきっと、『君主論』の最終章での「夷狄からのイタリア解放」という当時の常套レトリックが、19世紀にイタリア統一への情熱と読み違えられることと呼応しているのでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
