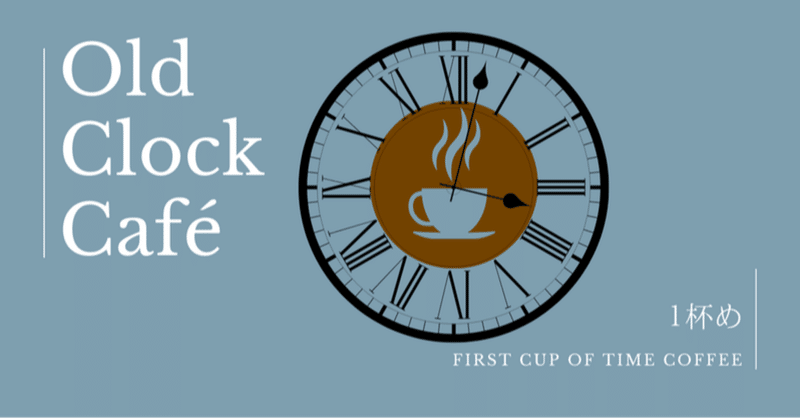
『オールド・クロック・カフェ』1杯め「ピンクの空」 <全文>
その店は東大路から八坂の塔へと続く坂道の途中を右に折れた細い路地にある。町家を必要最低限だけ改装したような店で、入り口の格子戸はいつも開いていた。両脇の板塀の足元は竹矢来で覆われていて、格子戸の向こうには猫の額ほどの表庭があり、春になると山吹が軒先でゆれる。格子戸の前に木製の椅子が置かれ、その背もたれにメニューをいくつか書いた緑の黒板が立て掛けられていなければ、そこをカフェと気づく人はいないだろう。
そのメニューが変わっていて、黒板には、こんなふうに書かれている。
Old Clock Cafe
6時25分のコーヒー ‥‥500円
7時36分のカフェオレ ‥‥550円
10時17分の紅茶 ‥‥500円
14時48分のココア ‥‥550円
15時33分の自家製クロックムッシュ‥‥350円
なぜメニューに時刻がついているのかはわからない。そこにどんな秘密があって、何を意味しているのかも。ときどき、この風変わりな黒板メニューに目を止めて、開け放たれた格子戸から中を訝し気に覗きこむ人がいる。
いらっしゃいませ。ようこそ、オールド・クロック・カフェへ。
あなたが、今日のお客様です。
* welcome *
店舗コーディネーターの亜希は、朝から外回りで足が悲鳴をあげていた。小指がヒールに擦れて、たぶん中で赤く腫れあがっている。おまけにこの辺りはどこもかしこも坂道ばかりで、必然的にヒールの中でつま先へと圧がかかる。ヒールを脱ぎ捨てて裸足で歩きたい衝動に駆られていた。次のアポイントまでは小一時間ほどある。それまでに昼を済ませておきたい。足も限界だ。小指の痛みが頭まで響く。辛うじて背筋は伸ばしているけれど、おそらく体は不自然に左右に揺れているにちがいない。産寧坂まで行けば店はいくらでもある。でも、これ以上、坂道をのぼれる気がしなかった。
左に細い路地がある。ちらりと覗くと、まっすぐ延びている路地の中ほどに椅子がひとつ置かれていて、黒い板のようなものが座面に立て掛けてあるように見えた。黒板メニューはカフェの定番だから、あそこはカフェかもしれない。違っていても、坂をのぼるよりはいい。亜希は路地に入った。
椅子の上に置かれていたのは、思ったとおり黒板だった。
『Old Clock Cafe』とある。良かった。カフェであたりだった。けれど、そこに書かれているメニューには首をかしげた。それに、門の格子戸は開いているけれど暖簾も看板もない。どう見ても、町並みに溶け込み静かに佇んでいる民家にしか見えない。でも、亜希はもう一歩も歩きたくなかった。まちがっていたら、すみませんと謝ればいい。女も27歳ともなれば妙な度胸がつく。門をくぐり、表庭を通り引き戸を開けた。
ガラスの嵌った杉板の格子戸を引くと、からからと乾いた心地よい音がした。扉を開けると、ぼーんぼーんと柱時計が深く沈んだ声で時を打った。
「いらっしゃいませ」
カウンターで眼鏡をかけて本を読んでいた若い女性が、ぴょんと立ちあがる。20代前半ぐらいだろうか。髪をトップでだんごに結っていて、白いスタンドカラーのシャツに黒のカフェエプロンをつけている。眼鏡をはずして微笑むと、えくぼが浮き出て、たちまちあどけない顔になる。古びた店の雰囲気とちぐはぐな印象が、なぜか亜希をほっとさせた。
店は京町家を改装した造りで、床は磨きこまれて黒光りしている土間だ。入口の真向かいに同じ格子戸がある。おそらく戸の向こうは中庭だろう。表庭と中庭に面して窓が切られていて、そこから射しこむ陽光にほんのりと包まれ店内はよい加減に明るい。
丁寧にこしらえられ、丁寧に使われてきた町家だということがわかる。
店に入ってまず驚くのは、壁という壁に所狭しと掛かっている柱時計や振り子時計だった。いったい全部でいくつあるのか。あるものは2時25分を指し、あるものは7時16分を指していて、ばらばらの時刻を刻んでいる。けれど不思議なことに、あのカチッカチッと規則正しく時を刻む音がうるさくも耳障りでもないのだ。それぞれが、めいめいに音を鳴らしているはずなのに不思議と調和してひとつの音楽を奏でていた。
たいていは飴色の鈍い光沢をはなつ木製だが、中には青銅や真鍮製の時計もあった。凝った装飾がついているもの、美しい曲線が印象的な意匠のものや鳩時計もある。まるで時計の森に迷い込んだようだった。
そのみごとさに圧倒され、亜希は口をあんぐりと開けたまま、壁から壁へとゆっくりと嘗めるように首を回す。驚きのあまり声もでない。
「すごいですね」
ようやく深い吐息とともに漏らしたのが、そのひと言だった。我ながらもう少し気の利いたことは言えないのかと思ったけれど、感嘆以外の言葉が見つからなかった。
「そうでしょう。ここは祖父がやってた店なんです。祖父は振り子時計や柱時計が好きで。東寺の弘法市を覗いては、骨董品を集めてたみたいです」
「骨董品いうても、値打ち物はひとつもありません。ガラクタばっかりです。でも、『それがええんや』って祖父は言うんです」
「お好きな席に、どうぞ」
にっこり微笑んで、檸檬を浮かべたピッチャーの水をグラスに注ぎながら、亜希をうながす。
カウンターの他にテーブル席が3つ。表庭の窓際と中庭の窓側にひとつずつ、部屋の中央にひとつある。亜希は中庭の窓側のテーブルに座った。
メニューと水が亜希の前に置かれた途端、柱時計のひとつが鳴った。
「ふふ、気にいられたようですね」
あどけない笑顔をほころばせて、彼女がいう。
「えっ? 何に?」
亜希が思わず見あげる。
「えーっと。今、鳴ったのは12番やから。あの白い時計があなたのことを気にいったみたいです」
「時計が私のことを気にいる? それって、どういうこと?」
女性は盆を胸に抱え、アールヌーヴォー調の優美な植物模様がついた白い柱時計を振り返る。それからゆっくり向きなおると、亜希の目を見つめた。
「信じるかどうかは、お客様しだいなんですけど。時計はいつも鳴るわけではありません。それに、私じしん体験したことがないので、本当かどうかもわからないんです。でも」
「祖父がいうには、時計が、時のはざまに置いてきた忘れ物に気づかせてくれるそうです」
女性店員、いや今は店主なのだろうか。彼女は時計をひとつひとつ確かめるように視線を滑らせる。
「忘れ物‥‥ですか」
「何か心当たりはありますか?」
忘れ物なんて思い返せばいくらでもありそうで、どれが該当するのかがわからない。
「あ、そういえば。祖父は、『本人も気づいていないから、忘れ物なんや』と言ってました。そのうえ『時計は気まぐれやさかい、気にいったお客じゃないとあかん』とも」
「気づいてない忘れ物‥‥ますます、わからないわ。それに、あなたの話だと、時計が客を選ぶっていうこと?」
にわかには信じがたい話に亜希はとまどう。ひょっとして、とんでもない店に入ってしまったのだろうか。でも、目の前の娘の視線はまっすぐに澄んでいて、からかっているようには見えなかった。それに。
これだけアンティークの時計が掛けられていれば、多少なりとも妖しい雰囲気が漂っていてもおかしくない。ところが、どういうわけか、この店にはそうした違和感が微塵もなく、どの時計もそこが本来の居場所であるかのようにしっくりと落ち着いていた。窓辺で踊る陽の光がやわらかく、亜希は格子戸を開けたときから、この静謐な空気感に懐かしさまで覚えていた。
「祖父が入院して、店を継いで3カ月になるんですが。今みたいに、時間でもないのに柱時計が鳴ったのは、お客様でまだやっと3人目です」
「ひとりめのお客様は、バカなことを言うな、と怒って出て行かれました。ふたりめのご夫人はずいぶん悩まれたのですが、『時のコーヒー』をご注文になられました」
「あ、時のコーヒーというのはですね。祖父が時計に番号をつけていまして。カウンターの向こうに小抽斗がたくさんついた箪笥があるんですけど。見えますか? 鳴った時計と同じ番号の抽斗に入っている豆を挽いて作るコーヒーを『時のコーヒー』と呼んでます」
「それって、ふつうのコーヒーとどう違うの?」
「そこ、気になりますよね」
「私も実は気になって。お客様のいないときに、1番から順に試し飲みしてみたんです。けっこうドキドキしながら。私の忘れ物って何だろう?って。32番まで全部試したんですけど。何も起こりませんでした。どれもふつうの美味しい豆のコーヒーとわかっただけ。時計が鳴らないと、奇跡は起きないみたいです」
「せやから、味は保証します。それに、変なものが入っていないことも」
えくぼをきゅっと縮めて、あわてて付け足す。
「ふたりめのご夫人は、時のコーヒーをひと口すすられると寝てしもて。15分ぐらいして目を覚まされました。冷めてしまったコーヒーを取りかえてお出しすると、遠い目をして何かを考えるようにゆっくりとお飲みになられ、『ありがとう。忘れ物を思い出したわ』と言って出て行かれました」
「コーヒーを飲んだのに寝たの? コーヒーって眠気を覚ますものじゃなかったけ?」
亜希は単純な疑問を口にする。いつも会議など頭をシャキッとさせなければいけないとき缶コーヒーに頼る。
「コーヒーの覚醒効果は飲んでから効きはじめるまでに長くて30分ぐらいかかるそうです。せやから、パワーナップを取る前にコーヒーを飲むと、すっきり目覚められていいみたいですよ」
「ご夫人が眠られてしまったのは、たぶん、時のコーヒーのせいやと思います。確信はありませんけど」
盆をカフェエプロンの前に提げて、女性は顔をかしげる。
「そうね。この椅子に座っているだけで、眠ってしまいそうだわ」
ゴブラン織の生地が張られた椅子は、背もたれも深く、座面もちょうどよいやわらかさで疲れた体をふわりと包んでくれる。カフェの椅子としては贅沢な造りといえる。亜希はヒールから踵を開放し、つま先に靴をひっかけながら椅子に身をゆだねていた。おそらく、それに気づいたのだろう。
「よろしければ、壁際のラックにある足置きをお使いください」
足もとを覗くと、壁とテーブルの間にマガジンラックがあり、そこに小さな畳が立て掛けられていた。ああ、これはうれしい。畳を足もとに置いてヒールを脱いだ。
「足が限界だったから、うれしい心遣いだわ」
「それも祖父のアイデアなんです。お気に召していただけて、よかった。
『カフェはお客様が疲れた体と心をひと休みさせるところやさかい、何時間でも居ていただけるようにせんとな』というのが祖父の口癖でした」
女性は少し上気した顔をほころばせ、ふわりと微笑む。
「ところで、ご注文はどうされますか」
「時のコーヒーは、無理にはお薦めしません。通常のコーヒーでも紅茶でも。お好きなものをご注文ください」
「ひとつ、訊いてもいいかしら」
「なんでしょう?」
女性が小首をかしげる。彼女のチャーミングな癖のようだ。
「メニューに書かれている時刻には、何か意味があるの?」
最初から一番気になっていたことを尋ねる。
「意味は‥‥わからないんです。意味があるか、ないかも」
「適当に書いてるって、こと?」
「うーん。どうでしょう? これは祖父が書いたものなんです。店を継ぐときに気になったから尋ねてみました。祖父は『おお、あれな。おもしろいやろ』といって、いたずらっぽく笑っただけで教えてくれなかったんです」
「だから、わかりません。祖父は昔からいたずら好きというか。なんでも楽しむ人だったので。意味があるのか、気まぐれで書いただけなのか」
きっとその時のおじい様との会話を思い出したのだろう。女性は、くすっと笑った。
「でも、何かの暗号みたいでしょ。お客様のいらっしゃらないときに、その時刻の意味を考えたりしてます」
いたずらっぽい目をして言う。
「そうそう。忘れるところでした。白い時計が指している時刻が、お客様の忘れ物と関係があるそうですよ。これも祖父の話なので、どこまで信ぴょう性があるかはわかりませんが」
白い優美な柱時計は、4時38分を指している。その時刻に私は何を忘れて来たのだろう。亜希は無性に知りたくなった。
「じゃあ、ミックスサンドと時のコーヒーを」
「かしこまりました。時のコーヒーは豆から挽くので、少々お時間がかかりますけど大丈夫ですか? サンドイッチを先にお持ちしますね。どうぞおくつろぎになって、お待ちください」
* * tick tack * *
ミルで丁寧に豆を挽く音が静かな店内に響く。微かにコーヒーの香りが店内に漂いはじめた頃合いで、ミックスサンドが運ばれてきた。
そういえば、サンドイッチにも流行があったな。少し前には玉子サンドが雑誌で特集されていたけれど、今はフルーツサンドがデパ地下に並んでいる。でも、亜希はサンドイッチといえばミックスサンドだと思っている。きれいな二等辺三角形に切りそろえられたミックスサンドをひとつ、つまんでほおばりながら、通り庭に目をやる。マスタードがいい具合に鼻に抜ける。御影石の手水が配された庭では、今が季節とばかりに連翹と雪柳がひと群れ、右に左にさわさわと振り子のように風にゆらされていた。
4時38分。いや16時38分だろうか。亜希にはその時刻にまるで心当たりがない。私はそこに、何を忘れてきたのだろう。どうして忘れてしまったのだろう。
朝からクライアントの要望や文句に押し潰されそうになりながら、ただぺこぺこと頭を下げてばかりいた。上司の不手際の尻ぬぐいもする。後輩の面倒もみる。時間に追われるだけの日常。それに何の疑問ももたずにいた。時間に追われていることが、働いていることへの実感につながっていたから。
でも。このカフェに入ったときから、時間に追われるのとは真逆な感覚に包まれていた。こんなにもたくさんの時計があるのに。みな規則正しく時を刻んでいるのに。追われるのではなく、時の揺りかごにゆられて、ゆるやかな時間の流れに身をゆだねているような。不思議な感覚に満たされていた。
亜希は柱時計をひとつひとつ、いとおしむように目で追う。
中庭では紋白蝶がひらひらと遊んでいた。
「お待たせしました。12番の時のコーヒーです」
ぼーん、ぼーん、ぼーん。白い柱時計がうれしそうに時を打つ。
湯気とともに立ちあがる香りが鼻から胸へと広がる。淹れたてのコーヒー特有のスモーキーで馥郁たる香り。丁寧にドリップされたことの証しだ。亜希はためらいがちにひと口すする。ほろ苦い中に広がる甘みがあり、ナッツのような香ばしさもあって、味が重奏になっている。「時のコーヒー」という、いわくつきであることを忘れるくらいふつうに美味しい。豆の種類を訊いてみようかと思って、やめた。きっとそんなものは関係ないのだ。
三口めを舌の上で転がすように味わうとやがて、亜希はゆっくりと時の彼方へとまどろんだ。
* * Time Coffee * *
まず意識の深淵に浮かびあがったのは、ポニーテールの後ろ姿だった。頭の高い位置でゴム留めした毛先に少しくせのある黒髪の束が、肩のあたりでせわしなく左右にゆれている。水色のフレンチスリーブのTシャツを着て学習机に座っている背が見える。机の端に筆洗が置かれ、左手でパレットを持っている。転がっている絵の具のチューブ。徐々に画像が鮮明になる。
突然、耳をつんざくほどの蝉時雨が降ってきて、目の前がぱっとクリアになった。映画のフィルムが回り出した感覚に似ていた。
あれは小学4年生の私だ。夏休みも残りわずかになったころ、宿題の絵を描いていた。「家族の思い出」みたいな課題だったから、2年前の夏、最後に家族で出かけた海の光景を描いた。
それは亜希にとって、家族で過ごしたかけがえのない思い出だった。
盆を過ぎたある日、日本海の海水浴場に1泊2日で出かけた。その前日、仕事から帰宅するなり父は、「竹野海岸の保養所の予約がとれたから、明日は朝早く出発するぞ」と意気揚々と告げた。姉と私は歓声をあげた。「お母さーん、水着、水着」とはしゃぎまわる。亜希は小学2年生、姉の早希は5年生。二人とも子どもだったから、そのときの母の反応には無頓着だった。夫から前触れもなく突然の予定を切り出されたら、戸惑い、うろたえ、苛立つであろうことは、大人になった今ならわかる。おそらく母は夫に文句を並べ立てたはずだ。でも、父はいつものごとく「いやー、ちょうどキャンセルが出てラッキーだったよ」などと、母の感情を無視するようなことを言ったのだと推測がつく。それでも、亜希の記憶の中の母は、車の中でも笑っていたから、娘たちのよろこぶ様子にじぶんの感情をしまい込んだのだろう。
盆が過ぎ海水浴客も減った海は、時折、高い波をあげる。
父が笑う。姉が笑う。母も笑っていた。つられて亜希も笑う。セルフタイマーをセットして、海を背景に顔を寄せ合って写真を撮った。4人ともこれ以上ないほどの笑顔。家族4人で過ごした最後のしあわせな記録だ。
その年、秋から冬へと季節がうつろう頃、父は家を出て行った。
テニスの部活に行っていた中学生の姉の早希が、「暑い、暑い」と言いながら階段をバタバタと派手な足音を立てながらのぼってくる。階段前の亜希の部屋にひょいっと顔をのぞかせた。
「何してるん?」
「夏休みの宿題の絵を描いてる」
ぼそぼそとしゃべる亜希の声は、シャワーのように降ってくる蝉の声にかき消されがちだ。
「もう、蝉がやかましすぎ。窓しめて、クーラー入れなよ」
「絵を描いてたの? 見せて」
姉は制服のまま部屋に入ってきて、描きかけの亜希の絵を取りあげる。砂浜で家族4人が笑っている絵だ。背景には海と空が広がる。
「えー、空がピンクなんて、ありえない」
「お母さーん。ちょっと見てよ。亜希の絵、おかしいよ」
その日、なぜ、母がいたのかは思い出せない。シングルマザーになる前から母は会計事務所で働いていた。常識がものさしの人だから、会計の仕事は向いていたと思う。家事もてきぱきとこなし、いつも忙しそうだった。その日は遅い夏休みでも取っていたのかもしれない。
「もう、何よ。帰って来るなり、にぎやかね」
パタパタと階段をのぼるスリッパの音がして、母が部屋に入ってきた。
「ほら、亜希の絵、見て」
姉が画用紙の端を両手でもって、くるりと振り返って母に見せる。
「空がピンクなんよ」
母はぴくりと眉をあげ、まじまじと絵を見た。
母は良くも悪くも常識人だった。母にとっては常識がすべての基準であり、そこから外れているものは認められない。父がある日突然、会社勤めを止めて絵描きになると宣言したことも大きかったのだと思う。クリエイティブなものを「まっとうではないもの」とレッテルを貼って嫌悪した。
「亜希、どうして空がピンクやの? 空は水色で雲は白でしょ」
小学生にとって、親は神様と同列といってもいい。とくに母親の言うことは絶対である。亜希はとまどった。なぜピンクになったのか。理由はあるといえばあった。でも、それを口下手な亜希にはどう説明すればいいのかわからなかったし、母の意見に抗う勇気もなく、ただうつむくしかなかった。「ああ、また失敗した」と唇をかんだ。
はじめは海も空も水色で塗っていた。けれど、それでは、どこからが海で、どこからが空なのかがわからなくなってしまう。同じ水色で空と海を描き分けるほどの技量は、小学生の亜希にはなかった。困り果て、子どもの単純さで海と空の境に線を引くことを思いついた。後から思えば、濃い青で引けばよかったのだ。
でも、青ではなくピンクを選んだ。
亜希はそのときの自分の感情を思い出した。父も笑っている。母も笑っている。家族みんなの笑顔を描くとしあわせな気分になって、明るい色を足したくなってしまった。
白が多めの淡いピンクをパレットの上で作って、水をふくませた筆に取り水平線にそっと塗った。すると、先に塗っていた空の水色とにじんで、所どころ、ほのかに薄紫になった。その偶然の色が、亜希には魔法の色のように思えた。海と空を分けるだけのつもりが、もっともっと、とピンクを塗る手が止まらなくなった。結局、空のほとんどにピンクをにじませた。できあがった空はピンクと薄紫と水色がまばらに溶け合って、亜希は我ながら美しく描けたと思ったのに。
それを‥‥。姉と母に全否定されてしまった。
亜希はいつも姉がうらやましかった。母の口からはふた言めには決まって「お姉ちゃんのように」という言葉が冠につく。「お姉ちゃんのようにしなさい」とか、「どうして、お姉ちゃんのようにできないの」とか。勉強もスポーツも何ごともそつなくこなす姉は、常識のレールを踏み外すこともなく、母の自慢の娘だった。亜希も母に認めてもらいたかった。
「空がピンクに見えるなんて。目に異常があったらたいへんやから、眼医者さんに行こか」
母にそんなふうに心配されるほど、ピンクの空はおかしなことなんだ。
うまく描けたかもしれない。お母さんにほめてもらえるかも。
さっきまで胸のうちでふくらんでいた、ふわふわとした淡い期待が、急速にしぼんでいくのがわかった。
――失敗した。失敗した。また、失敗した。
――どうして私はお姉ちゃんのようにできないの。
――どうして私はほめてもらえないの。
「早希、あんた、明日は部活ないでしょ。亜希の空を描き直すのを手伝ってやって」
「えー、明日はプールに行こうと思ってたのに。もう、しょうがないな」
「亜希、午前中にちゃっちゃと仕上げちゃうよ」
窓の傍の樫の木にとまった蝉が、渾身の鳴き声を轟かせる。亜希はたくさんの言葉を吞み込んだまま、力なくうなずくことしかできなかった。
その時だった。
ぼーん、ぼーん、ぼーん。
何かを告げるかのように柱時計の音が響いた。蝉の声が遠ざかり、画面がレンズを閉じるようにフェイドアウトしていく。代わりに浮かび上がった白い時計は、4時38分を示していた。
* * welcome back * *
ぼーん、ぼーん、ぼーん。
黒ずんだ真鍮の優美な植物装飾をまとった白い柱時計が、ぼんやりとほの暗い空間に浮かび上がる。ブラスの振り子が左右にゆれる。頭の奥のほうで響いていた柱時計の音が、じかに鼓膜を振動させる音として聞こえ、亜希は目が覚めた。意識がうつつと夢の間で振り子のようにまだゆれていたが、現実に戻ったことがわかった。壁という壁に掛かっている時計が心配そうに見下ろしている。うっすらと目を開けた亜希にはそんなふうに思えた。スローモーションで店内を見渡し、目尻に残った涙を人差し指でぬぐう。通り庭では、まだ、紋白蝶がひらひらと遊んでいた。
ぼーん、ぼーん、ぼーん。
白い柱時計が、亜希が目覚めたことを知らせるかのように時を打った。
その合図に気づいたのだろう。カフェの店員が新しく淹れなおしたコーヒーを盆に提げて持ってきた。
「忘れ物は見つかりましたか」
「コーヒーが冷めてしまっているので、お取り替えしますね」
これを飲むとまたあの夢に戻ってしまうのだろうか。
丁寧にローストされたふくよかな香りを纏う湯気を見つめながら、亜希はためらっていた。それに気づいたのだろう。
「いったん目覚めると『時のコーヒー』の力は失われてしまうんや、と祖父が言ってました」
「二人めのご夫人もお目覚めになってからは、ふたたび微睡まれることはなかったですよ」
ほっと、ひとつ息を吐いてコーヒーカップに口をつけた。まだ、頭のなかをさっき見たばかりの光景がぐるぐるとエンドレスで回っている。
亜希はあの絵のことをすっかり忘れていた。ひょっとすると、じぶんで記憶に蓋をして心の奥底にしまい込んでいたのかもしれない。いったん開いた蓋は、あの午後に続く記憶を次々に呼び覚ました。
* * memory * *
翌朝、姉の早希は朝食のパンをかじりながら早口で話しかける。
「亜希、ごはん食べたら、昨日の空を塗り直すよ。あんたの机じゃ二人でできないから、リビングのテーブルでしよう。絵の具とか用意しとってよ」
亜希はぼそぼそとトーストをかじりながら、向かいの席の姉を上目づかいで見あげ無言でうなずいた。姉の指示はいつも的確で要領を得ている。それだけに逆らう余地など1ミリもなく、亜希にはいつだって従う以外の選択肢がなかった。逆らうよりも従うほうがずっと楽だったというのもある。亜希はたいてい深く考えることもなく母や姉の指示どおりにしてきた。
でも、その日は、気持ちが前に進まなかった。はっきりと抵抗する気持ちがあったわけではないが、あの空を塗り直すのかと思うと心が下を向いてしまう。マーマレードをたっぷり塗ったトーストは、ふだんなら亜希のお気に入りだが、今朝は乾燥したフランスパンのように口の中でもたつく。亜希はもぞもぞとトーストを噛み続けた。
姉はさっさと食事を終えて食器を流しに片付け、2階にあがっていった。入れ違いにベランダで洗濯物を干していた母が、パタパタとスリッパの音をたてて階段を下りてくる。
「亜希、早く食べなさい。もう、お母さん仕事に行くからね。あんたが食べ終わるの待ってられんわ。じぶんで食器、洗っときなさいよ」
この家では、亜希以外のふたりはてきぱきしている。
亜希はあわてて口の中で形をなくしたパンを無理やり呑み込んだ。
亜希がパンを牛乳で流しこんでいると、トントントンと一定のリズム音を立てて姉が降りてくるのが見えた。
「えー、まだ食べてるの。もう、しょうがないな」
早希は階段の途中で方向転換をして、また、2階にあがっていった。亜希は一気に牛乳を飲みほすと、あわてて皿とマグカップを流しに運んだ。早希が今度は絵の具バッグを手に持って階段を降りてきた。準備まで姉にしてもらうことになり、亜希はますますじぶんが情けなくなった。
「で、なんで空をピンクに塗ったん?」
早希はパレットに白、青、水色を順に出しながらたずねる。
「はじめは、海も空も水色に塗ってたんやけど‥‥。どっから海で、どっから空かわからんようになって‥」
「海と空を分けよう‥思って‥」
ぽつりぽつりと亜希が理由を話す。なぜピンクだったのか。ピンクを塗ろうと思った気持ち。水色にピンクが溶け合って偶然きれいな薄紫になったこと。ピンクと水色と薄紫がまざりあった空に心うばわれたこと。それらをどの順番でどう説明すればいいのかわからず口ごもる。
「えー、それで空をピンクにしたん? 意味わかんない」
はじめから空を全部ピンクにするつもりはなかったことを伝えたかったのだが、亜希はことばを探して口を閉じる。
「そんなんはね、水平線から入道雲を描いときゃいいの。こんなふうに。ほらね、これで空と海の境めがわかるやろ」
「でも‥‥。写真には‥入道雲は写ってへんもん‥」
おずおずと亜希が言い返す。
「あんたは、ほんまにまじめやな。提出するのは絵だけ。写真もいっしょに提出するん? ちがうやろ。入道雲が出てたことにすれば、ええんよ」
「それに、夏といえば入道雲やろ」
早希はそう言うと、筆にたっぷり白い絵の具をとって、さっさと水平線に大きな入道雲をふたつ描いた。たちまち、空と海が分かれる。亜希があんなに苦労したことを姉はいとも簡単にやってのけた。
「あとは、雲以外のところを水色に塗り直すよ」
亜希の倍のスピードで早希がピンクの空を水色に塗り直す。またたく間に入道雲の湧く夏の空が広がる。どこかで見たことのある海の絵ができあがった。亜希がうっとりした空は、もうひと欠片も残っていなかった。
父がいた夏のしあわせな記憶まで色褪せ、平凡な夏の絵になってしまったように亜希には思え悲しかった。楽しかった夏はもう二度と帰って来ないのだと、単調な水色に塗りつぶされた空が告げているようだった。
ふつうの空が、皮肉にもふつうの家族の思い出を塗りつぶしてしまった。
同時に、亜希は「色」に対する自信を封印してしまった。
* * coloring * *
遠い過去に置き忘れてきた夏のひとコマを早回しのフィルムのように思い出し、亜希は深い吐息をはいた。小学生だった私が無意識に心の奥に鍵をかけてしまい込んだできごと。もうとっくに時間が洗い流してくれているから、今さら傷つくことはない。では、どうして。
亜希はコーヒーカップを少し持ち上げたまま、ゴブラン織の椅子に深く体をあずけ、ぼんやりと考え込んだ。白い柱時計に目をやる。あの美しい時計は、私に何を知らせようとしたのだろうか。カフェの女性は「忘れ物」といった。「時のはざまに置き忘れてきたもの」に気づかせてくれるのだと。
あの夏に何を置き忘れてきたのか。
挽きたてのコーヒーの香りを胸で味わいながら、記憶の紐を手繰り寄せる。白い柱時計の振り子は一定のリズム運動を繰り返している。時計が鳴った4時38分は空を塗り直すことが決まった時刻だった。
からからから。
小気味よい音をたて、若い女性店主が格子戸を開けて通り庭へと出て行った。何をするのかしら。窓からうかがうと、御影石の手水のたもとで揺れている連翹と雪柳を何本か剪定鋏で切っていた。手水の後ろに隠れていた山吹も加え小ぶりの花束をこしらえて、また、からからと引き戸の音をたてもどった。棚からガラスのピッチャーを出し無造作に活ける。格子戸のすき間を縫って射し込む光が、カウンターの上にきっちりと格子の幅の光と影のストライプを描き出している。
格子戸に近いカウンターの端に花を盛ったピッチャーが置かれた。それを見るともなしに眺めていて亜希は、ふと気づいた。戸外ほども明るくないからだろう。まっ白なはずの雪柳が、光と影のいたずらなのか、微妙に色をまとって見える。淡い黄の連翹に挟まれ光に照らされている一枝は、かすかに金色の輝きをまとい首をかしげる。みかん色の山吹の隣で影になっている枝は、濃い黄を帯びてゆらゆらと揺れている。光と目のふしぎな錯覚。パレットで絵の具を溶かなくても、色はこんなふうに互いに影響しあうのか。
戸を開けたときに迷い込んだのだろう。蝶がひらひらと時計から時計へと戯れている。窓から射しこむ光に鱗粉がくるくると踊るさまが浮かびあがる。蝶の羽の色は構造色だと聞いたことがある。羽や鱗粉には美しい色はなく、複雑な形が光を反射させ宝石のごとく輝く羽の色になるのだと。
雪柳から蝶へと。いざなわれるように色のふしぎに思いを巡らせていて、亜希はようやく気づいた。4時38分に何を忘れてきたのかを。
そうだ。私はあの時間に「色」を置き去りにしてきたのだ。臆病になったと言ってもいい。
「色」がずっと苦手だった。
「空は水色で、雲は白でしょ」
母のことばが呪文となって幼い亜希を縛った。引き金になった海の絵は、記憶の奥底に押し込んでしまっていたけれど。「正しい色」というのがあると信じ、そこから外れてはいけないと思い込んだ。図工や美術の授業では、周りをちらちら見るクセがついた。みんなと同じ色で塗る。そうすれば、まちがわずにすむから。
27歳になった今も、服のコーディネイトにまるで自信がない。仕事のときはたいてい制服のような黒かグレーのパンツスーツばかりを着る。そうしていれば、まちがっていない服を着ている安心感があった。だから、私服は苦手。トルソーにディスプレイされているのを全身まとめ買いすることもある。じぶんでコーディネイトなんて、怖くてできない。だって、どの色とどの色の組み合わせが正解なのかがわからないのだから。今日も、淡いグレージュのパンツスーツだ。
亜希は深いため息をついて、コーヒーをゆっくりと啜った。
ふふ。微妙なグレースーツのバリエーションばかりね。自嘲ぎみの笑いを漏らし、12番の白い柱時計を見上げる。
――忘れ物は‥‥色だったんだね。
そっと胸でつぶやく。
――ぼーん、ぼーん。
そうだ、というように白い時計が時を打つ。
考えてみれば「正しい色」なんてないのにね。
幼児はよく誰に教わるでもなく、太陽を赤のクレヨンで描く。大人たちはそれを微笑ましくみる。でも。昼の空にある太陽は、たいていまぶしい白か金だ。陽が傾くにつれてようやく朱から濃い赤になる。太陽を白で描く子どもがいれば、「ちがうよ」とまた大人は常識を持ち出すのだろうか。目に映る自然とは異なる色を定番にしたのは、いったい誰なのだろう。
亜希はあいづちを求めるように時計を見上げる。蝶が白い柱時計を飾る黒ずんだ真鍮の植物装飾のひと枝にとまった。まるで本物の枝葉がそこにあるように。亜希はコーヒーカップを両手で包みこみ、それを見つめる。
色への自信を取り戻そう。
簡単ではないだろうけれど。「正しい色」のトラウマから解放してやることはできそうだ。だって、「時のコーヒー」の夢でみたピンクと水色と薄紫のまじりあう空は、正しい空ではないと烙印を押されたけれど、大人になった今の亜希が見ても、美しいと思えたから。
まずは、そうだ。前からの懸案だったカラーコーディネイターの勉強をはじめよう。
亜希の名刺に印字されている店舗コーディネーターの肩書は、ただの飾りだ。短大を卒業して入った中堅の建設会社には、京都という土地柄から店舗事業部があった。店の新築を請け負うこともあるが、古くからの小さな店が軒をつらねる京では、町屋のリノベーションやリフォームの案件が多い。亜希はそこに配属された。コーディネーターというのは名ばかりで、要は、客と工事業者や設計士との伝言係にすぎない。壁材や床材、什器などのサンプルやカタログをもって客を訪問し、施工業者に客の要望を伝えるだけ。それでもごく稀に客から「どっちの色がいいかな」と尋ねられ、どぎまぎすることがある。当たり障りのないことを返してその場を凌ぐのだが、客の顔に失望がにじむ。それに気づかないふりをして、ずっと色を遠ざけてきた。
亜希は残りのコーヒーをひと息で飲み干した。
でも。逃げるのは、もう、やめよう。
きちんと基礎から勉強すれば、自信は取り戻せなくても、臆病にならずにすむ。胸を張ることはできなくても、「こちらの色のほうがすてきですね」と薦めることができるようになるだろう。センスを磨くのは難しくても‥。
そこまで考えて、亜希は不意に父を思い出した。
そうだ。お父さん。お父さんに相談してみよう。スペインに絵を描きに行って、もう、ずいぶん会っていないけれど。お母さんが嫌がるから、父の絵を見たことはないけれど。
あの夏の後、画家になるといって家を出た父は、ヨーロッパを放浪し、最後にたどり着いたスペインで画家として認められたらしい。5年も経ってようやく届いたハガキには「アンダルシアの空が気に入った」とだけ記されていた。常識人の母とはちがい、父は気ままな自由人だった。
亜希は幼稚園のころ、よく父とお絵かきをした。亜希の絵を父はどれも「おお、すごいな」とか「天才だな」とか手放しでほめ、「よし、お父さんも描くぞ」といって描きだすと、たちまち娘のことを忘れて夢中になる。父が描いた絵には、ピンクの象や水色のトラがいた。
「ピンクの象さんは、いるの?」
「いると思えば、いるんだよ。でも、ママには内緒な」
そう言って無理やり指切りをさせられた。ママには内緒。「いいことではないんだな」と幼い亜希は思った。父はよく母に叱られていた。今から思えば、家の中でいちばん子どもだったのは父かもしれない。幼い亜希は父をじぶんと同列に思っていたふしがある。やるべきことを示してくれるのは母であり、父は遊び友だちにすぎなかった。「いると思えば、いる」その自由な発想の大きさに気づくには、亜希は幼すぎた。
亜希は父とむしょうに話したくなった。
――父に会いに、スペインに行こう。今すぐは無理でも。
今朝、出がけに郵便受に入っていたハガキを内容を確かめもせずバッグに突っこんできたことを思い出した。ふつうのハガキよりも少し縦長の大判だった。赤でAir Mail の文字が走り書きされていた気がする。亜希はあわててバッグをさぐる。取り出した厚めのつるっとしたコート紙のハガキには、右肩上がりが特徴の父の字が躍っていた。
父の個展の案内状だった。
『脇坂悠斗 凱旋個展「蒼の幻想~スペインの空から」』
大仰なタイトルと開催期間のわずかなスペースにボールペンでひと言、「会おう」と書かれていた。
――えっ、お父さん帰って来るの? 京都で個展を開くの?
神のいたずらだろうか。願ってもないタイミングに亜希は目を疑う。さらに、ハガキを裏返してそこに印刷されている絵に、大きく目をみはった。
タイトルは『コスタ・デル・ソルの空』。
画面の中央下から右にゆるい傾斜でのぼるようにコスタ・デル・ソルの白い壁の家々が描かれている。それ以外は、ほとんどが空だ。それも‥‥。
淡いピンクと紫と水色とそれらがまじりあった色たちが、互いに浸食し、ぼかしあい、交錯し、溶けあって広がる幻想的な空が一面に描かれている。
亜希はことばを失い、まなじりに涙が小さな玉を作る。
「うわぁ、素敵な空ですね」
不意にハイキーの声が降って来て、亜希は顔をあげた。水の入ったピッチャーを持ってカフェの女性が立っていた。
「すみません。勝手に見ちゃって」
「父の絵なの」
亜希は掌を頬骨にあて、人差し指の先で涙の玉をそっとぬぐう。
「お父様は、画家さんですか」
「ええ。スペインでね。今度、帰って来て、個展を開くみたい」
「どこで? 京都だったら見に行きたいです」
亜希のグラスに水を注ぎながら言う。
「これ、個展の案内状なんだけど。今日届いたばかりで一枚しかないから差しあげることはできないの。でも、良かったら、のぞいてみて。父もきっと喜ぶわ」
「ギャラリーはどこですか。メモりますね」
ピッチャーをテーブルに置き、カフェエプロンのポケットから小ぶりのメモ帳と鉛筆を取り出す。
「四条西洞院のギャラリー『時枝』だって」
「わぁ。ギャラリー『時枝』ですか」
「知ってるの? 有名なギャラリーかしら」
「あ、いえ。有名かどうかは‥ちょっと。私は絵にくわしくないので、わからないんですけど。名前が‥。時枝って。時の枝でしょ。この店みたいだなって。なんか親近感が」
「あら、ほんとね」
「それに‥。この絵の空。すごく綺麗で。ぜひ実物を見てみたい」
「そうね。私も見たいわ」
この娘も、ピンクと紫と水色のまざりあった空を美しいという。亜希は、なんだか誇らしくなった。胸がふつふつとして、こそばゆくなった。正しい色なんてない。私はまちがっていなかったんだ。あの夏の日のじぶんを抱きしめてやりたくなった。
「ところで、忘れ物は見つかりましたか?」
カフェの女性が首を少しかしげながら訊く。
「ええ。見つかったわ。ありがとう」
亜希はピッチャーを胸に抱えて佇む女性を見つめ、それから白い柱時計に視線を滑らせる。
――ありがとう。忘れていた「色」に気づかせてくれて。
心でつぶやきながら、立ち上がる。
――ぼーん、ぼーん、ぼーん。
白い柱時計が、亜希の背を押すように時を打つ。蝶がびっくりして飛びたった。店中の時計が亜希にエールを贈るように、思い思いに時を鳴らす。それらが重奏になってひとつの曲を奏でていた。
「ありがとうございました。また、いらしてくださいね」
店員がぴょこんと頭をさげる。
亜希は格子戸を開けた。山吹が軒下で手をふる。陽ざしがまぶしい。父の個展の案内状をバッグに大切にしまうと、亜希は両手を前で組んで背筋をのばした。
そうだ、帰りに河原町の高島屋で春色のワンピースを買おう。
(1杯め Good Taste End )
「またのお越しをお待ちしております」 店主 敬白
サポートをいただけたら、勇気と元気がわいて、 これほどウレシイことはありません♡
