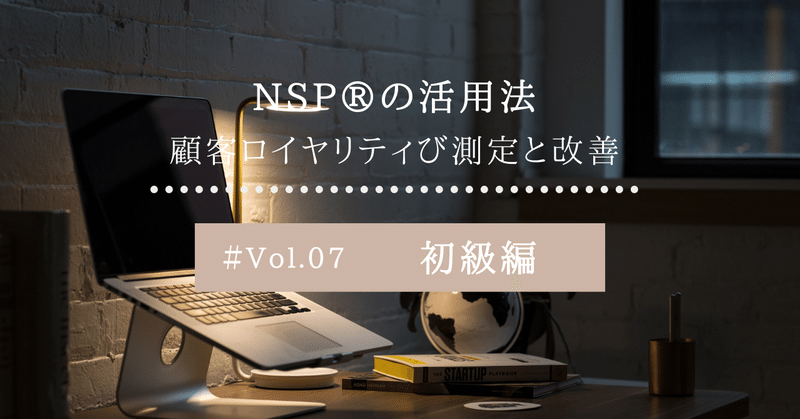
NSP®️の活用法
こんな方におすすめ
・事業責任者やプロダクトオーナーとして、これからNPS®︎を活用したい方
・顧客のロイヤリティを可視化したい方
NPS®︎とは
製品・サービスの顧客やユーザーのロイヤリティを測定する指標のこと。
ネットプロモータースコア(Net Promoter Score®︎)の略で、
コンサルティング会社「ベイン・アンド・カンパニー」が開発しました。
ロイヤリティの高い顧客とは、特定の企業やブランド、商品・サービスなどを好んで選択肢、継続的に繰り返して購入するなど高い愛着を持ってくれる顧客のことです。
口コミなどでも評判を高めてくれるため新規顧客の獲得にも影響を及ぼします。
NPS®︎では、あなたはこのサービスを他の人に勧めるかという推奨意向を問う質問をします。
この推奨意向は、ロイヤリティを含まれると考えるためNPS®︎は顧客のロイヤリティを明らかに示す指標とされています。
NPS®︎を指標として活用することで顧客のロイヤリティの現状を把握し、サービスの価値を継続的に観測することができます。
NPS®︎の算出方法
1. 質問する
「このサービス・製品を友人・知人に薦める可能性はどのくらいありますか?
0点から10点まででお答えください」
2. 回答を分類する
以下、3つに分類されます。
10〜9点:推奨者
友人・知人など親しい人に薦めるという企業にとってプラスとなる可能性が高くロイヤリティの高い顧客。
8〜7点:中立者
推奨者のように薦めることはせず、きっかけがあれば離れてしまい、他の商品・サービスに切り替えてしまうという顧客。
6〜0点:批判者
サービス・商品に不平・不満を感じていてすぐに離れてしまう可能性が高く周囲にネガティブな情報を発信するなど企業にとってマイナスな行動をとる可能性が高い顧客。
3. 「推奨者」の割合から「批判者」
最後に推奨者の割合から批判者の割合を引きます。
これがNPS®︎のスコアです。
例えば、100人のうち、推奨者が52人、中立者が29人、批判者が19人だったとします。
そうすると推奨者の割合が52%、批判者の割合が19%となります。
よってNPS®︎は、33となります。

NPS®︎では10点や9点などポジティブな評価がつかないと顧客ロイヤリティには繋がらないと考えます。
NPS®︎がプラスになるということは、批判者より推奨者が多いということになるので良い結果と言えるでしょう。
顧客満足度とNPS®︎の関係
NPS®︎と似た指標として顧客満足度があります。
顧客満足度調査は5段階で問うことが多いですが、両方とも顧客ロイヤリティの状況を把握するための指標です。
顧客満足度は製品やサービスを実際に経験した後に、その製品・サービスに満足したかを質問して測ります。
顧客が満足するのは製品やサービスに対して事前に抱いた期待より、提供された製品やサービスのプロセスおよび結果の経験が上回ったときです。
一般的には満足度が高くなるほど、リピート率は高くなります。
しかし、回答者は期待に対して経験が下回らなければ、
すなわち特に不満がなければ満足と回答しがちなため顧客満足度は良いのに売上が上がらないということがあります。
業界にもよりますが、単に満足させるだけではなく感激させるレベルでないとリピートに繋がらないというケースもあります。
そのレベルまでいけば顧客ロイヤリティも高いといえるでしょう。
こうしたことから、顧客満足度に変わる顧客ロイヤリティの調査手法として注目を浴びているのがNPS®︎です。
NPS®︎は、顧客満足度の数値よりも顧客のリピート意向や口コミと強く相関することが知られています。
NPS®︎が高い企業ほど企業業績とも正の相関があります。
NPS®︎の使い方①
NPS®︎が高い企業ほど企業業績とも正の相関があると説明した通り、
中長期的な企業成長の観点から、NPS®︎のスコアを上げ、顧客ロイヤリティを上げていくことが大切になります。
一般にロイヤリティの高い顧客は、そうでもない顧客より企業に大きな利益をもたらすことが明らかになっています。
もたらされる利益としては主に4つあります。
1. 購買・残高増利益:リピート購買に加え、利用頻度を増す傾向にある
2. 営業費削減利益:特に新規顧客の営業コスト減
3. 紹介利益:口コミ
4. 価格プレミアム利益:値引きに対する要求少、高価格の定時も容易
具体的にどのくらいのNPS®︎を目指すのかは、社内でNPS®︎の情報も考慮して微調整する必要があるでしょう。
業界によってスコアの出方が大きく異なることも留意しましょう。
NPS®︎の使い方②
NPS®︎を他の指標と一緒に見ていくことで、短期的な業績の予測や改善を行うことです。
例えば、ある企業ではNPS®︎が高くなるとユーザーのWebサイト内の平均滞在時間が長くなる傾向にあり、強い相関関係があることがわかりました。
そうすると、Webサイト内での平均滞在時間を改善するための指標としてNPS®︎を活用することができます。
あるいはコンテンツのレベルを上げたり導線を工夫することで平均滞在時間が長くなればNPS®︎も向上すると考えられます。
NPS®︎と相関関係のある他の指標を一緒に見ることで現状どこに問題があるかを把握することができるのです。
また、推奨度別に顧客をセグメンテーションすることで、施策の改善につなげることができます。
例えば、批判者や中立者のセグメント、または批判者の中でも特定のセグメントなどに分けそれらを推奨者に変えていくためにはどんな施策を打てば良いのかを検討するのです。
NPS®︎の事例
<アップルストアの場合>
ミッションを「酷悪と従業員の生活を豊かにすること」とおいています。
アップルストアでの購入体験を、1回で済ませるのではなく顧客との継続的な関係づくりによってミッションの実現を目指しているのです。
アップルストアは、このミッションを実現しているかの測定をNPS®︎を活用しています。
NPS®︎は他社と比較するベンチマークとして見ていくことでサービスの改善に役立てることができます。
例えば、NTTコム オンラインが2019年に航空業界を対象にしたNPS®︎ベンチマーク調査によると、
トップはANAでありNPS®︎は-6.6ポイントとなっています。
航空会社8社のNPS®︎平均は-17.1ポイントです。
業界平均やトップ企業とのNPSの差を検証することで、自社の改善ポイントが見えてきます。
コツ・留意点
NPS®︎の点数の付け方には国民性によって違いがあることに注意しましょう。
もともと指標が開発されたアメリカでは良いと思えば10点や9点をつけることが多いようです。
しかし、サービスレベルの高い日本では、満足していても8点程度の点数をつけるなど国民性や文化によっては点数を低くつけがちです。
8点はNPS®︎では中立者となり、カウントされないので真の顧客ロイヤリティを測ることができない時もあります。
そこでグローバル企業では地域ごとの差を修正するために、スコアの読み替えを行ったりなど工夫をする場合があります。
NPS®︎は究極の質問と呼ばれるシンプルでわかりやすい質問をすることが特徴ですが、逆にNPS®︎のスコアだけを受け取っても改善ポイントは明確にはわかりません。
そのため通常は推奨するまたは推奨しない理由を同時に聞きます。
この際、質問する相手によって質問の聞き方や質問内容が変わってくることに注意しましょう。
例えば法人の場合は、購買の意思決定者は誰かということになると目の前の担当者だけでなく、
その上司である役職者に質問する必要があるでしょう。
その時、質問文は担当者と上司で同じで良いとは一概には言えないのではないでしょうか。
多くの人が使用に関与するBtoBビジネスの場合は、関係者からバランス良く情報を得ることが望まれます。
NPS®︎を適切に把握し、製品やサービスの改善に活かしていきましょう!
この記事を読まれたあなたは、こんなふうに感じたことはありませんか?
・転職や資格、独立も考えたけど、どれも本気になれず、やりたいことが見つからない…
・時間や場所にとらわれない働き方をしたいけど、今のキャリアを捨てたくない…
・昇進のチャンスがありそう。でも今の働き方を続ける自信はない…
専属プロコーチが、内に秘めた価値観を引き出し、
理想の「未来」を叶えるプランを用意します。
自宅で簡単に体験セッションができるので、お気軽にお試しください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
