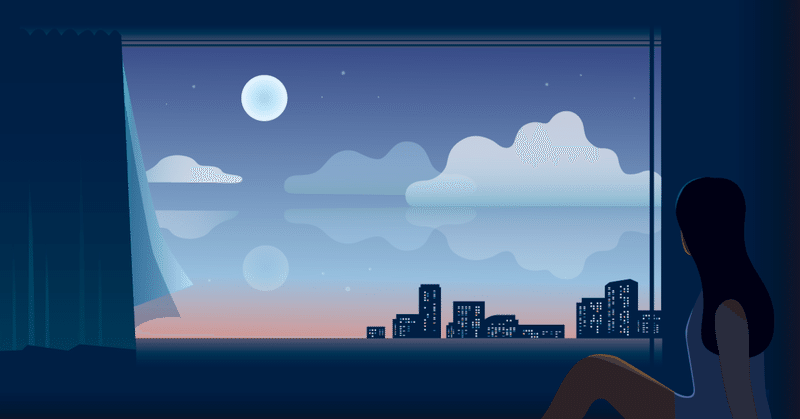
ビロードの掟 第30夜
【中編小説】
このお話は、全部で43話ある中の三十一番目の物語です。
※お詫び
これまで40話完結としてましたが、全体を見直した結果43話となりました。(これ以上延びることはない…と思います!)
◆前回の物語
第六章 白猫とタンゴ(2)
店の外では激しい雨が降っている。地面が陥没しそうな勢いだ。
凛太郎が駅から店に来る間、雨は降っていなかった。天気予報でも今日は雨が降ると言っていなかったはずだ。ということは、予想外の天気ということになる。日常の中で、想定していなかったことはたくさんある。これも、そのうちのひとつ。
パチパチと聞こえる雨の音を聞きながら、芹沢さんに対してどう言葉を発するべきか考えあぐねていた。
「そういえば、あの日も天気予報外れたよね」
あの日、というのが凛太郎と芹沢さんが初めてお互いを認識した日のことを指しているのだと途中で気がついた。
そうだ、あのとき優里と初めて出会ったのだ。最初はどちらかというと目立たない様子の女の子だった。少しずつ話をしていくうちに、彼女に惹かれて行ったんだった。
「ああ、バスの中にいる芹沢さんと目が合ったときだね──」
「ふふっ、そうそう。実を言うとね、あのとき初めに凛太郎くんを見つけたのは優里なんだよ。あの人、雨にぬれて大変そうって言ってね。あのとき優里、なぜか折り畳み傘を二つ持ってたの。無くしたと思って近くのコンビニで買ったら、カバンの中に入ってたんだって。次にバスが停車したらあの男の子に渡してこようかな、って言ってた」
凛太郎はハッとした。俺が最初に彼女のことを見つけたと思っていたけど、最初に認識してくれたのは優里の方だったのか──。
「そう……だったんだ」
「うん。それを聞いた私は彼女のことを止めたわ。優里、あなたそんなことしたらかなり目立つし、授業に遅れること間違いなし。それに見ず知らずの男の子にそんなことしたら絶対引かれるよ、って言ったの。今思うと言ってることめちゃくちゃよね。なんか私あのとき優里が遠くへ行ってしまうようで怖かったのかも。その後も──しばらく優里はあなたのことを気にしてた」
しばらくして、注文した刺身や魚の煮付けやらが運ばれてきた。芹沢さんの目の前には梅酒ソーダが置かれていて、凛太郎の前にはハイボールがある。ビールはプリン体が気になるからしばらく口にしていない。
どこからか、シュワシュワと炭酸の音がした。
「それで、芹沢さんは優里と会ったっていうけど、それ本当?ちょっと思考が追いついていなくてさ」
「うん、会った。その日彼女と待ち合わせしたのは、いかにもインスタ映えしそうなイタリアンのお店。彼女は赤いワンピースを着ていたわ。私、彼女に対してその服似合ってるねって言ったんだけど──」
ここでも深紅のワンピース、か。優奈は、優里がワンピースを着るときは特別な日だけだと言っていた。その話をどう捉えるべきか。
ここで考えつくのは、優奈が優里の代わりに芹沢さんに会いに行ったかもしれないという可能性だ。いや──それとも本当に優里本人だったのだろうか。そうであれば一体彼女は今どこにいるのだろうか。
「けど?」
「なんか、なんて表現したらいいかわからないんだけど、その時の優里、優里じゃないみたいだった」
「優里じゃない?」
「うん。心ここに在らずって感じでね。私たち定期的に会ってるんだけど、その時の彼女は前に会った時よりも痩せ細っていた。それからこんなこと言っていいのかわからないけど、まるで抜け殻みたいな感じでね。本人は躁鬱病気味なの、って言ってた。その頃仕事が忙しかったらしくて」
胸がザワザワとした。彼女は確かに優里と会ったと言っている。でも双子の妹である優奈によれば、優里は今年の3月に突然家から姿を消してしまったと言っていた。
「ちなみに、芹沢さんが会ったのは確かに優里だったんだよね」
「うん、間違いないよ。でも池澤くんから聞いたけど、優里ある日突然いなくなっちゃったんだよね。私、その話がいまだに信じられなくて。取り乱すべきなのかもしれないけど、その話なんだか胡散臭い気がして。あの日会ったのは優里だったもの。失踪したっていうのは、本当に正しい事実?」
凛太郎は再び考え込む。これはどういうことだろうか?優奈と芹沢さん、どちらかが嘘をついている?あるいはどちらも──?
「ちなみに、芹沢さんがあったのは本当に優里だった?その妹の優奈ってことはないかな?二人は一卵性双生児らしいんだ」
その瞬間、芹沢さんはハッとした表情になった。
しばらく凛太郎を正面から見据えて固まったまま動かない。その様子を見て、凛太郎の背中にじわりとした汗が滲む。いつかの夜、家から離れた場所にあるトイレに行くのが怖くて結局漏らしてしまった時のことが思い出された。
「凛太郎くん、あのね──」
いつだったか、布団の中で恐ろしさに体を震わせていた時のことを凛太郎はふと思い出していた。
<第29夜へ続く>
↓現在、毎日小説を投稿してます。
末筆ながら、応援いただけますと嬉しいです。いただいたご支援に関しましては、新たな本や映画を見たり次の旅の準備に備えるために使いたいと思います。
