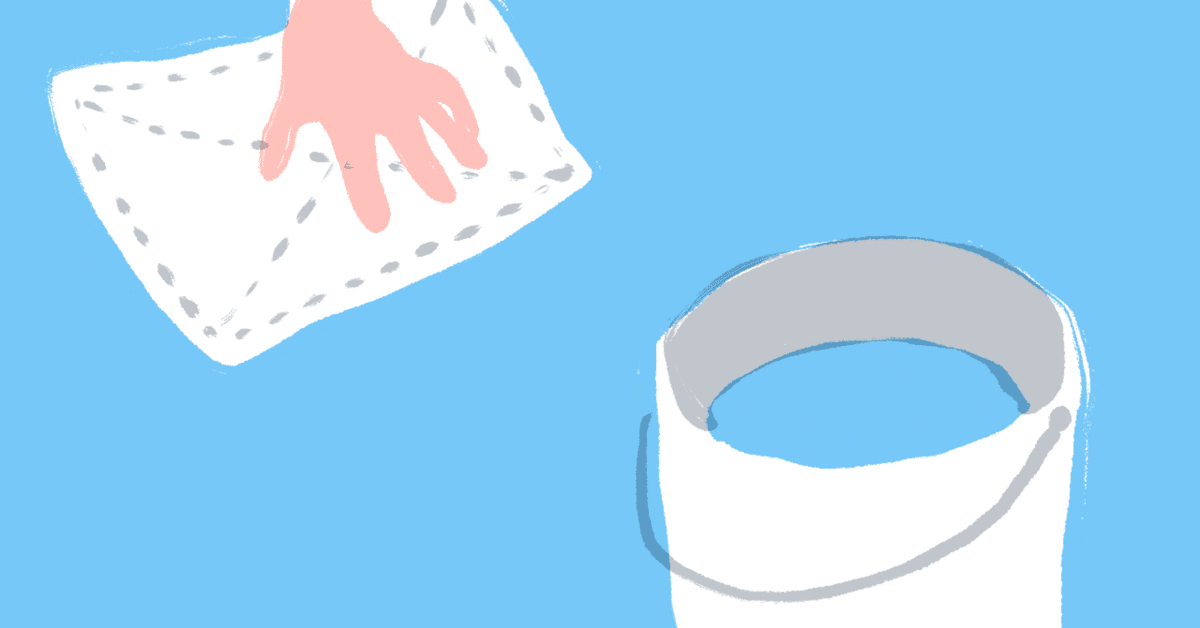
半竜の心臓 第5話 アクアマリンの勇者(1)
ロシェは、藍色の着物の裾を捲り上げて、枷のような傷跡が見えるのも気にせずに膝丈まで素足を出す。
心地よく日の当たる木目の廊下に膝を落とすと隣に置いた木桶に付けた雑巾を取り出す。水道というものから注いでから時間が経ったのに水はまだ冷たい。ロシェは、取り出した雑巾を固く絞る。
「お着物良し、水良し、雑巾良し!」
ロシェは、号令を取るようにそれぞれを確認すると、雑巾を広げて床に置き、足裏を木目の廊下につけて膝を立て、お尻を高く上げる。
「行きます!」
ロシェは、気合を入れて足を踏み出す。
固く絞った雑巾は、水の力を借りて滑り出す。
ロシェは、地面を蹴り上げて数歩前に出て・、転けた。
顔から思い切り廊下にぶつかり、鼻を打ち付ける。
ロシェは、目に涙を浮かべて鼻を押さえる。
その様子をアメノは、廊下のすぐ横の襖の開い畳の部屋でテーブルに肘をつき、煎餅を齧りながら猛禽類のような目を細めて見ていた。
「女将」
テーブルの左側で同じように座って醤油と海苔に巻かれた煎餅を齧る旅館の女将、ポコを見る。
「なんでございましょう?」
見かけは10歳にも満たないおかっぱ頭に茜色の着物を着た美少女なのに話し方はアメノより大人で落ち着いている。
「あいつは何をしてるんですか?」
「ご覧になってお分かりになりませんか?」
ポコは、煎餅を飲み込み、湯呑みに入れた焙じ茶を啜る。
「雑巾掛けです。それ以上の表現はございません」
「そんなのは分かってます」
アメノは、苛立ったように言う。
「なんであいつはそんなことをしてるのかと聞いてるんです」
ポコは、湯呑みから口を離し、ふうっと息を吐く。
「あの子が何か仕事はないかと言うのでお願いしました。手持ち無沙汰がお嫌だったみたいです」
昨晩、旅館"迷い家"に着いて入浴し、プリプリしながら大量の夕餉を摂り、就寝し、起床し、また、大量の朝餉を摂ってからロシェは昨日とは打って変わって暇を持て余していた。
何をするわけでもなく庭を見て、日差しを浴びて、鳥たちの声を聞いて・・。
普通に考えれば昨日のような慌ただしくも危険な日が異常なのだが、半竜であり、過酷な人生を送ってきたロシェに取って何もない時間というのは別の意味で落ち着かなかった。
だから、お願いしたのだ。
何かやることはないか、と。
そしてポコに割り振られたのが雑巾掛けなのだが・・。
「あんなに雑巾掛けの下手な方は見たことがございませんね」
ポコは、憮然とした表情を浮かべ、煎餅を齧る。
絞った雑巾を置く、膝を上げて、腰を上げ、そのまま床を蹴り上げるように進む。
それだけだ。
それだけの単純動作のはずなのに・・。
「ふぎゃっ」
ロシェは、蛙が潰れたような悲鳴を上げて床に倒れ込む。
呆れを通り越して華麗にすら見えるほど見事に。
今度は、お尻を思い切りぶつけたようで両手で押さえて摩っている。
アメノは、何度も同じことを繰り返し、ほとんど前に進んでいないロシェをじっと見る。
「ありゃ体幹がないからですかね?」
「発育がよろし過ぎてバランスが取れないか・・」
ポコは、焙じ茶を啜る。
「驚くほど雑巾掛けの才能がないかのどちらかでございましょうね」
アメノは、鼻の頭に皺を寄せ、煎餅を齧る。
「ロシェ」
アメノは、口の中の煎餅を飲み込み、声をかける。
もう一度、雑巾がけをしようと構えたロシェの動きが止まる。
「お前の分の宿泊費もちゃんと払ってるから無理に掃除なんてしなくていいぞ」
アメノは、煎餅の入った入れ物をロシェに見せる。
「こっち来て食べろ。美味いぞ」
「ザラメ付きもあります。甘うございますよ」
甘い・・。
その言葉にロシェは一瞬たじろぐものの、首を横に何度も振り、じとっとアメノを一瞥する。
まるで軽蔑するように。
ふんっとロシェは首を背けると再び雑巾がけをしようとして、今度は胸から倒れ込んだ。
アメノは、頬を掻く。
「なんだありゃ?」
「昨日のことをまだ根に持ってるのではないでしょうか?」
ポコは、半目にしてアメノを睨む。
アメノは、昨夜の温泉の件を思い出し、頬を赤らめる。
強面なのに純情な男の反応にポコは笑いを隠す。
「ありゃ不可抗力でしょう?」
アメノは、着物の袖を捲って小さな火傷の出来た左腕を見せる。
「俺だってやられたし。髪も縮れましたよ」
よく見るとアメノの左側の白髪の先端が少しだけ短くなっている。昨夜のロシェの竜の炎で焼けた髪を切ったからだ。
しかし、ポコは、まるで同情した様子を見せない。
「女の子に不可抗力なんて言葉はございませんよ。それにうちの温泉が入れ替わり制だって知ってるのですから確認しないのが悪いです」
「いやいや、勧めたのは女将でしょう?」
アメノが半眼にして睨むとポコは、素知らぬ顔で視線を反らして煎餅を食べる。
そんなポコの鼻頭に皺が寄る。
「アメノ様」
「なんですか?」
アメノは、拗ねたように言って煎餅を齧る。
「勇者様が来られました」
アメノの猛禽類のような目が微かに揺れる。
ロシェも雑巾がけの構えを止めてポコを見る。
ロシェの脳裏に鮮烈な赤に輝く全身鎧を纏い、大槍を携えた金髪の勇者の姿が浮かぶ。
ポコは、ロシェの思考を読み取ったのか、首を横に振る。
「紅玉様ではございません」
ポコは、大きな目を座らせる。
「アクアマリン様です」
アメノとロシェのいる畳の部屋に通された勇者はとても利発そうな顔をしていた。
利発で・・・とても弱々しそうだった。
年の頃は11・・いや、12歳と言ったところだろうか?
眉毛に掛からないくらいに切り揃えられた黒髪、黒曜のように輝く目、幼いが引き締まった顔つきからは知性が滲み出ている。しかし、その知性に溢れた顔に反比例してその身体はあまりに頼りない。
頭や左胸、腕や足、腰と言った必要最低限の部位のみを防御するように造られた海色の鎧から覗く手足は驚くほどに細く、ロシェの手どころかポコの幼い手の方が太いのではと感じるほどで鎧下垂れを脱いだら肋骨が浮き出ているのではないかと感じた。
ロシェは、勇者と呼ぶにはあまりにも儚い印象の少年をじっと見てしまった。
そして彼の隣に座るあまりにも対照的な人物にも。
ポコが客人用の若草色の湯呑みを二つ、丸いお盆に乗せてやってくる。
「粗茶でございますが」
ポコが丁寧に2人の前に湯呑みを置く。
「あっありがとうございます」
少年は、緊張した面持ちで丁寧に頭を下げる。
「ありがとうっす!」
少年の隣に座る長衣を着た絶世と言う言葉を絵に描いたような美しい顔立ちのエルフの女性、リンツは軽快にお礼を述べる。
「リンツ様・・」
「昨日ぶりっすね!」
リンツは、にこやかに笑って右手を上げる。
「まさかこんなに早く再会出来るとは思わなかったっすよ」
「私もです」
ロシェは、小さく笑みを浮かべる。
その顔にリンツは少し驚き、笑う。
「少し落ち着いたみたいっすね。良かった」
落ち着いた・・と言えるのだろうか?
リンツのいる保護施設を出て半日と少ししか時間は経ってないはずなのに非常に濃密な出来ごとが沢山あった。
特に・・。
思い出して、ロシェはむすっと頬を膨らませてアメノを睨む。
リンツは、怪訝な表情を浮かべてアメノを見る。
「旦那・・まさかもう手を出したんすか?」
「んな訳ねえだろう」
アメノは、不機嫌そうに言う。
「ちょいと不可抗力が働いただけだ」
どんな不可抗力なのか非常に気になってリンツは問い詰めようとする。が、隣にいる少年にそれを阻まれる。
「リンツさん、今は・・」
少年は、固い面持ちのままリンツを静止する。
緊張の為か、声が上擦っている。
「ああっ申し訳ないっす」
リンツは、苦笑いを浮かべて手を合わせる。
少年は、まったくと言った感じに肩を竦めると改めてアメノに向き直る。
「聖剣様」
「アメノです」
アメノは、自分に用意された焙じ茶を啜りながら少年を一瞥する。
「誰が付けたか分からない渾名です。名前でお呼び下さい」
口調はとても丁寧なのにその仕草は他者を萎縮させるのに十分な迫力があった。
案の定、少年の身体は一瞬で固まる。
それに気づいたリンツは、緑色の目を細めてアメノを睨む。
「うちの勇者様をビビらせないで欲しいっす」
リンツの苦情にアメノは、猛禽類のような目を大きく開いて驚く。
アメノからすれば普通に会話をしていただけでそんなつもりは微塵もなかった。
「ほら、ヘーゼルもちゃんと話すっす」
リンツは、ヘーゼルと呼んだ少年の肩をぱんっと叩く。
へーゼルは、びっくりしてリンツを見る。
その様子はまるで姉弟のように微笑ましくてロシェは小さく笑う。
「大変失礼を」
ヘーゼルは、頭を下げる。
「いえ、こちらこそ」
アメノは、少し戸惑いながら答える。
「改めまして、私はギルドより派遣されました勇者へーゼルと申します。等級はアクアマリンです」
ロシェは、眉を顰める。
ギルド?
等級?
アクアマリン?
その様子に気づいたリンツがロシェに目を向ける。
「旦那から聞いてないっすか?勇者ギルドのこと?」
勇者ギルド?
ロシェは、首を傾げてアメノを見る。
それに気づいたアメノは頬を掻く。
「そういや、まだ説明してなかったか」
「里親なんだからちゃんと自分の事を説明するっす」
リンツは、呆れて肩を竦める。
そしてロシェの方を向く。
「勇者ギルドって言うのはその名の通り勇者を取りまとめる組合のことっすよ」
勇者を取りまとめる?
「勇者って言うのは称号じゃなく職業なんすよ」
唯一無二の最高の存在。
勇者。
しかし、それがただ1人の持つ称号であったのはそれこそ魔王が顕現した千年も前のこと。
現在にはその才能を受け継ぐ人間種が数多く存在し、勇者として名乗りを上げていた。
そんな勇者を取りまとめ、正義の名の下に派遣するのが勇者ギルドなのだと言う。
その結果、勇者は名誉ある称号ではなく、星の数ほどある職業の一つになったのだ。
「ちなみに等級ってのはその勇者の実力に合わせた位のことっす」
リンツの話では等級は全部で7段階に分かれる。
第1位 金剛石
第2位 紅玉
第3位 青玉
第4位 緑玉
第5位 黄玉
第6位 紫玉
第7位 アクアマリン。
「ちなみに金剛石の等級を持つ勇者は歴史上では魔王を倒した勇者のみなので実質、王国最強の勇者は紅玉ということになるっす。そして・・」
リンツは、両手をアメノに向けて思い切り手をヒラヒラさせる。
「旦那は、そんな最強の勇者と肩を並べて戦うことの出来る唯一の剣士であり戦士なんす!」
リンツの説明にロシェは目を丸くする。
父たる白竜の王から勇者という存在のことは聞いていたから知ってはいたがまさかそんなシステマチックな仕組みになっているとは思いもしなかった。
ロシェは、じっとアメノを見る。
アメノも見られていることに気づき、眉を顰める。
「どうした。やっぱ煎餅食いたくなったのか?」
アメノの言葉にロシェはムッと頬を膨らます。
「いえ・・アメノ様は凄い方だったんだなと改めて思っただけですけど・・」
ロシェは、ぷいっと首を横に向ける。
「やっぱり訂正します」
ロシェの反応の意味が分からずアメノは首を傾げる。
襖の向こうに座ったポコがその様子をみてくすりっと笑い、リンツはやはり何かあったのではないかと疑いの目を向ける。
「あの・・話しを戻してもよろしいでしょうか?」
へーゼルが恐る恐る聞いてくる。
その言葉にアメノとロシェ、そしてリンツも姿勢を正す。
へーゼルは、緊張を払うように咳払いして改めてアメノを見る。
「最下位のアクアマリンである私が紅玉の勇者様の一行であるアメノ様に前に出てお願いするような立場ではないことは十分に承知しているのですが・・」
ヘーゼルは、正座したまま体を後ろに下げ、頭を下げる。
「どうか私の一行の前衛として協力してきただけないでしょうか?」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
