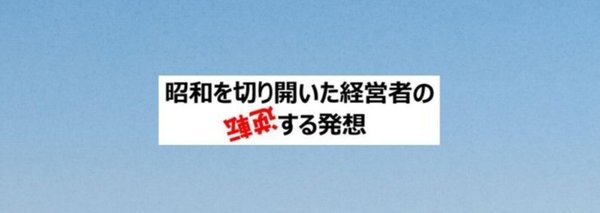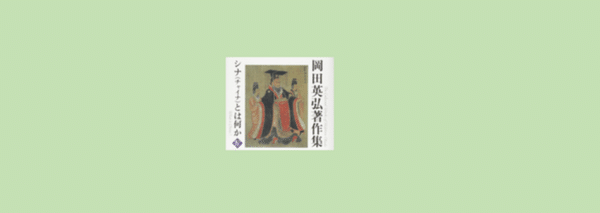記事一覧
『食人宴席 抹殺された中国現代史』
鄭義著 黄文雄訳 光文社カッパブックス 214p 1993
見ると、私はこのところ中国ばかりを話題にご紹介しているようだが、特に中国に関心をもって調べているわけではない。読む本も乱読で、この間積み上げるとかなりの高さになるがご紹介するまでもないと思い紹介していないだけのこと。中国関係の書籍紹介が続いているのは、中国関連で読む書籍の内容が重く、1冊読むと、参考文献にいろいろな図書が紹介されていて
不死の亡命者 野生的な知の群像
劉燕子(リュウ イェンヅ)(著)
集広舎、A5判、752ページ、重さ650g、2024.06.01
中国では、 1912年1月1日、清朝が滅び、孫文が臨時大総統に就任して中華民国が成立した。長年続いていた王朝体制がここで崩壊した。
その後、第二次大戦をはさんで1949年に「新中国」が成立した。1912年に王朝体制が崩壊したとはいえ、1949年から始まった中国共産党によって統治される中華人民共和国
「空飛ぶサーカス」021 サーカス危機一髪!
空を飛ぶようになってから、サーカスにはさまざまな冒険がありました。残念ながら、全部を紹介することはとてもできません。
でも、これだけは、どうしても紹介しておかなけれはならないでしょう。
それは、サーカスの人たちにとっても、忘れることができないできごとだからです。
ある時、サーカスがアメリカヘ行くことになりました。
アメリカヘ行くためには、大きい大西洋を越えなければなりませんが、その途中で大嵐
「空飛ぶサーカス」020 北海の孤島へ行く
サーカスが空を飛ぶようになってからというもの、団員にとっては世界中か自分の家のようになりました。
とくにしたくをしなくても、行きたいときに、行きたいところへ自由に行けるようになったのです。大都市だけでなく、これまでサーカスがきたこともないような小さな村や島にもすすんで飛んで行きました。
といっても、とても小さな村や島全部を回るというわけにはいきません。ギリシアだけでも483もの島があるのです。全
「空飛ぶサーカス」019 パリヘ、サーカス空の旅
空飛ぶサーカスの最初の外国への旅はパリでした。パパゲーナはじゅうたんの飛ばせ方を何回かの練習ですっかり覚えましたので、パリヘの旅もじゅうたんで空を飛んでみることになりました。初飛行です。
じゅうたんでサーカスを空に飛ばせるときには、パパゲーナはサーカスの切符売場のテーブルに座ります。透明のガラス窓をとおして、外を見るためです。
テーブル上には地図が置かれています。これでサーカスかどこを飛ん
「空飛ぶサーカス」018 サーカス空を飛ぶ
サーカスかある町から次の町へ移動してゆくのはとてもたいへんです。
大きなテントや観客席、舞台がたたまれ、猛獣たちはオリに入れられ、トランクに積まれて駅に運ばます。そして、そこから貨物列車でつぎの町に運ばれたり、外国へ行くときなどは、船で運ばれたりすることになります。
一方、団員たちはふだん自分たちが生活している移動車を連ねて移動します。新しい町に着いてからが、またたいへんです。
荷物をほどき
「空飛ぶサーカス」017 ずっこけ<魔笛(まてき)>
ある日のことでした。その日は〈魔笛)をやることになっていました。でも〈魔笛〉に出演するサーカスの団員たちは、そろって病気になってしまいました。そのため、いつもとは違う団員たちか出演しなければなりませんでした。
いったい大丈夫でしょうか?
どんなふうに舞台が進んだか、まあ、聞いてやってください。
まず問題はパパゲーナの病気でした。
魔笛の大蛇は、小さなトカゲをパパゲーナが魔法で大きくして
「空飛ぶサーカス」016 サーカスオペラ〈魔笛〉
サーカスではいつも新しいプログラムを工夫していますが、最もあたらしいものが〈魔笛〉……魔法の笛というプログラムです。これは有名な作曲家のモーツァルトが1791年に作曲した同じ名前のオペラをもとにしたものです。
オペラの(魔笛〉は、たぶん現在でも一番人気の高いオペラのプログラムのひとつでしょう。物語がおもしろく、音楽も楽しいので、このオペラが劇場でかかると、どこでもいつも満員になるほどです。
「空飛ぶサーカス」015 いれちがいサーカス
あべこベサーカスとともにこのサーカスでまた、たまにあるのが「いれちがいサーカス」です。このいれちがいサーカスもまた、観客にたいへんな人気なのです。
それはこういうぐあいにすすみます。
ライオン使いのレオナルドがライオンたちを連れて舞台に登場します。そして、ライオン使いのムチの合図でライオンたちか演技をする……というのがふつうのサーカスなのですが、このいれちがいサーカスではそんなふうにはな
「空飛ぶサーカス」014 あべこべサーカス
さて、失敗が多いこのサーカスのもう一つの売りものが、あべこベサーカスです。
これはまた、このサーカスならではのもので、たいへんな人気なのです。
えっ? あべこベサーカスなんて知らないって? キミたちは何も知らないのだな、困ったもんだ。
たとえばほら、キミがサーカスに行って自分の席を探したら、もうそこには知らないおばさんがどっしりと座っていて、汗をふきながら一生懸命ハンバーガーを食べ
「空飛ぶサーカス」013 サーカスの洪水、街を海にする
こうして団員や動物がもどって、新しいサーカスが始まりました。プログラムもいろいろと工夫されましたが、なかでも観客がもっとも喜んだのが”ノアの箱舟”です。”
ノアの箱舟“というのは、キリスト教の旧約聖書に出てくる船で、それは地球ができはじめた頃のお話です。
むかしむかし、神様は、ひとりの男ノアに大きな船を造っておくことを命じました。ノアが言われたとおり船を造りますと、ある時、雨が降りはじめて
「空飛ぶサーカス」012 パパゲーナ、魔法のほうきをもらう
レオナルドやビンボーと同じように、パパゲーナもまた、サーカスの団員や動物を連れもどそうと、世界中を飛びまわりました。
そんなある日のこと、パパゲーナはどこまで行っても終りがないような大きな森に入り込んでしまいました。陽の光もとどかない暗い森の奥で、パパゲーナは一軒の家を見つけました。近づいてみるとそれは、ヘンゼルとグレーテルの物語に出てくるようなお菓子でできた家でした。ちょうどお腹がすいてい
「空飛ぶサーカス」011 猛獣たちアフリカからもどる
こうして二人はライオン使いを連れ戻しました。こんどはライオンです。
「パパゲーナ、ライオンを魔法で連れてくるっていうわけにはいかないのかい?」レオナルドが聞きました。
「それはできないわ! だいいち、ライオンたちがまた一緒にサーカスをやりたいと思っているかどうか、よくわからないものね」パパゲーナは言いました。「レオナルド、あなたがアフリカに行って連れもどしてくるのが一番いいみたいよ!」
「それは
「空飛ぶサーカス」010 ライオン使いのレオナルド先生になる
サーカスをやめた後、レオナルドは先生として子供たちに教えていました。つまり、サーカスではライオンたちに、サーカス以外では子供たちに教えるというわけです。えっ、ライオンと子供は同じかって? さあ、どうかな?
レオナルドは先生になりましたが、すべてのライオン使いが、いい先生になれるというわけではありません。どうやらレオナルドも、子供より猛獣のほうが得意なようでした。
パバゲーナとアウグスティンが
「空飛ぶサーカス」009 月からもらった”空のじゅうたん”
サーカスを再開するため、アウグスティンはやめていった団員や動物をもう一度呼び戻さなければなりません。
そこで問題は、まずだれから探すか?ということです。しかし、アウグスティンにとっては、それは考える必要はありませんでした。ずーっと昔から、決っていたのです。
えっ?だれをさがしたかって?
なんだキミたちは可愛いい魔法使いのパパゲーナのことをアウグスティンが好きだったってことに気がつかなかった