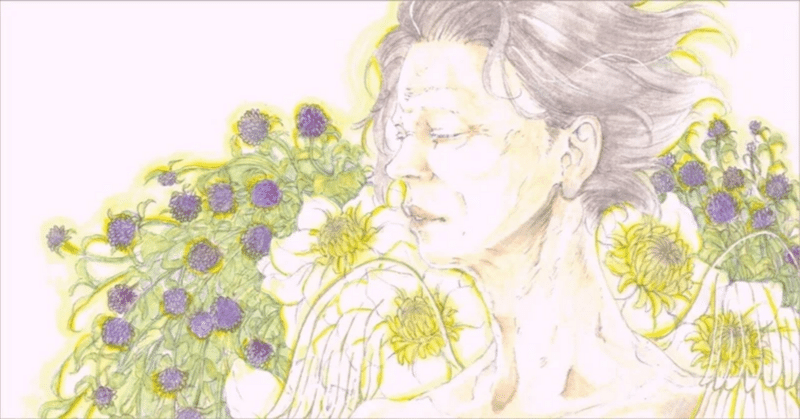
【知られざるアーティストの記憶】第34話 一世一代のラブレターを読んでくれない彼と、国際中医師のタケイさん
Illustration by 宮﨑英麻
第5章 プラトニックな日々
第34話 一世一代のラブレターを読んでくれない彼と、国際中医師のタケイさん
2021年8月の後半、彼は退院早々から大工仕事を始めた。まずはペンキの塗り直しから。何日もかけて、ペンキを塗っては乾かすことを繰り返している。その持ち手のついた正方形の板は何かと思ったら、汲み取り式である彼らのトイレの、汲み取り穴に被せる蓋であると言う。それが終わると今度は、玄関で存在感を放つ彼の手作りのポストに取り掛かった。
ポストが取り外されている数日間、彼は段ボールで仮のポストを作って据えた。それは「日田天領水」の段ボールであった。彼の母親が生きていたときには定期的に取り寄せていたというその水を、彼は部屋で恋人に試飲させた。コップを出してもらえなかったマリは、彼の目線を少し気にしながら日田天領水の2Lペットボトルをラッパ飲みした。その様子を察知した彼は、見ていないふりをして視線をそらした。
「私はこの先どうなるかわからないから、弟が一人になっても少しでも暮らしやすいように、やれることをやっておくんだよ。」
彼の語る突然のペンキ塗りのわけは、マリにとって複雑であった。
彼は大工仕事に没頭している間、普段はほとんど開けることのない、彼の部屋のマリの家の方向に向いた掃き出しの雨戸を開け放し、豊かな太陽光の下で作業をした。日中、彼の部屋の掃き出しが解放されている光景が自宅からも見えることはマリにとって嬉しく、作業中の彼をその縁側によく訪ねた。
プラトニックという言葉の前に揺らぐ理性と恋心について、マリは素直な気持ちを手紙にしたためたが、それはその時のマリの心情と同様にふらふらした手紙であった。それは、これまでの手紙の中で最も一所懸命に書いた、最も自信のない手紙だったので、その手渡し方も自信無げでためらいがちであった。しかしそれは、彼に最も読んでほしい一世一代のラブレターであった。
手紙を手渡した翌日、そのことについて彼が何も言って来なかった。
「ねえ、手紙読んでくれたんですか?」
「読んでないよ。だって、キミが読むなって言うから……。」
そんなバカな。読んでほしくない手紙を、書いて渡すはずがないじゃない。「読むな」なんて一言も言わなかったはずだが、マリのためらいがちな態度から繊細な彼がそう感じ取ってしまったのなら、訂正しなければならない。
「え、読んでよ……。読んでほしいから書いたんだよ。」
「いやだ、読みたくない。忙しいから手紙を読んでいる時間がないんだよ。」
そんなの嘘ばっかり。マリは今回の手紙だけは頑なに読んでもらえないことの意味が解らず、悲しくなって数日彼に会いに行くのをやめた。
数日のブランクを経てマリが彼の玄関の扉をノックしたのは、もう掃き出しの雨戸が閉められた夕方の17時過ぎであった。玄関を上がってすぐの3畳の居間で彼は夕飯を食べている最中で、口をもぐもぐさせながら出てきた。悪いときに来たと思った。彼が毎日17時に夕飯を食べることをマリはこの時に知った。17時に夕飯を食べたあと、ひとしきり原稿に向かい、18時半には歯を磨いて19時前には寝てしまうのだ。起きていても寂しいから、早くに寝てしまうのだという。マリの生活時間と何時間の差があるのか、マリは考えたくもなかった。
マリは話したいことがあって訪問したのだが、食事中だったので出直そうとすると、彼は
「あなたに会いたかったんだけど……。」
とマリを引き留め、食事を中断して玄関で小一時間マリとの会話に応じた。マリは食事の冷めるのを気にしたが、彼は
「いいんだよ!」
と強く念を押した。
彼はまだ手紙を読んでくれていないようだったが、マリが伝えたいことはそのことではなかった。マリはその日、国際中医師免許を持つタケイさんの治療院を初めて受診してきた。タケイさんは、マリが夫婦で施術を受けていた、中医学に基づく足つぼ師であるマリの友人メイの師匠であった。メイの勧めでまずマリの夫が先に受診し、その時のアドバイスに目から鱗が何枚も落ちた夫がマリにも受診を勧めたのだった。メイや夫が勧めた通り、中医学に基づくタケイさんの観察力と見立ては鋭く真実を突いているように感じられ、マリの知識欲を満たした。
しかも、仕事で体を酷使している夫よりは遥かに健康体であることを自負し、タケイさんを受診する動機は主に中医学への興味本位であったマリは、
「奥さんのほうが酷いですね。体質の改善には二週間に一度の受診を勧めます。」
というタケイさんの予想外の言葉には仰天した。そして、イクミが再発しないための体質改善に、タケイさんの施術がきっと役に立つはずだとマリが思わないはずがなかった。
マリは彼の興味を惹こうと、タケイさんの施術を受けた体験と感想を彼に懸命に話し、一度受診してみることを勧めた。彼は、
「施術って具体的に何をするの? 費用はいくらかかるの?」
と、以前に仙骨先生に関して訊いたのと同じことを訊いた。彼はむしろマリの体調のことを心配して、
「それより、早く体調を治してください。そうしないと、こうやって話したりもできなくなるから。」
と言った。
彼はこの日、
「あなたは落ちこぼれなんかじゃないです。大学院を出て、ちゃんとレベルを持った人なんだからね。」
という言葉で、マリが少し前の手紙で伝えた家族に対する劣等感を打ち消そうとし、マリを励ました。彼にとってマリの自己実現は、いかなる代替医療の検討においても費用対効果の天秤以下でしかない自らの体調よりも、高い関心事のようだった。自分の実態とは違う「ちゃんとレベルを持った人」という言葉にむずがゆさを感じつつも、彼が自分のことを肯定し、勇気づけようとしてくれたことに、マリは温かさと悦びを感じた。
結局マリの手紙は、それからさらに二週間ほど経過し、マリがすっかりそのことへの情熱を失った頃になって、
「ああ、読んだよ。」
と言われて終わった。
★この物語は著者の体験したノンフィクションですが、登場人物の名前はすべて仮名です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
