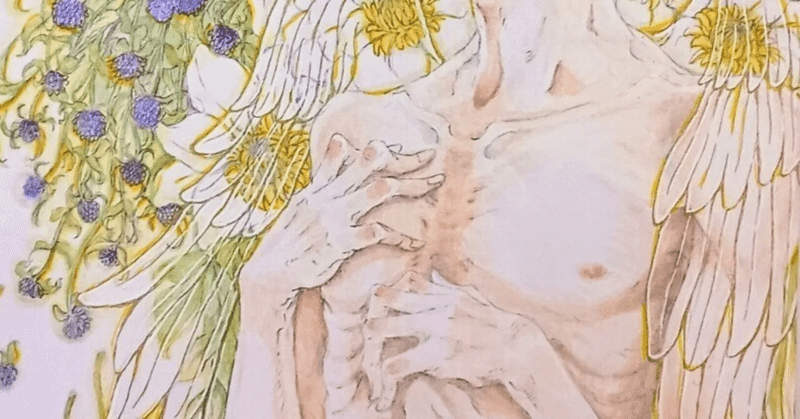
【知られざるアーティストの記憶】第53話 埋没するのは嫌いなんだ
Illustration by 宮﨑英麻
*彼は何も遺さずにひっそりとこの世を去った。
知られざるアーティストが最後の1年2ヶ月で
マリに遺した記憶の物語*
第8章 弟の入院
第53話 埋没するのは嫌いなんだ
ある日、マリが彼の家を訪ねると、中から彼の話す声が聞こえた。彼は大きな音で掃除機をかけていたが、その音に時折紛れ込む彼の声もまた負けずに大きかった。
(あれ、マサちゃんはいないのだから、独り言?)
音と声のする二階へ階段を上がるにつれ、彼の大声がどうやら誰かを罵っているらしいことをマリの耳が解読した。マリは驚いてその場にしばらく立ち尽くし、その言葉に耳を傾けた。それは、普段の彼が話す穏やかな言葉とはまるで別人のような乱暴な言葉づかいであった。その内容(註1)と、言葉に乗っている鮮烈な怒りのエネルギーから、彼が罵倒する相手はF町で彼の夢を邪魔したSさんや親戚たちであるとマリは確信した。
註1:彼の発していた言葉で明確に思い出せるものが一編もないので、文字にすることはやめました。聞き取りづらかったことと、断片であったことから意味を持って記憶に留めることができなかったのだと思います。
(マジか……。)
心の中で呟いた。すでに30年も経っているのに、彼の怒りのまるで昨日のことのように生々しいことよ。思いのほか深いことを知った彼の傷を前に、マリは決して逃げ出そうとは思わなかったが、途方にくれた。はたしてこの傷は自分に癒しきれるものなのだろうかと。
彼はマリに背中を向けて、ノズルを持ち上げながら鴨居などの高いところに掃除機をかけていた。
(ほほう、スーパー主婦は足元の畳だけでなく、そういう高い場所を吸いとるのね。)
感心しながらマリが近づくと、彼は耳に耳栓まで詰めている。だから余計にマリにちっとも気がつかない。しめしめとばかりに彼の背中にぴとっとくっつくと、
「うわあ!」
と言って彼はその場に膝から崩れ落ちた。マリは笑った。彼の怒りなんて、こうして笑い飛ばしてやればいいんだ。
「……なん、だよ……。」
彼は見開いた両目をしばたかせた。少し驚かせ過ぎてしまった彼の動悸はなかなか収まらないようだった。
「この掃除機、ちょっとうるさすぎるだろ?だからいつもイライラしちゃうんだよ。」
彼は怒鳴っていた理由を掃除機のせいにした。しかし、また別の日には手袋をはめて便器を拭き上げながら、もしくは彼の部屋の梁を水拭きしながらも、彼は同じように見えない誰かを罵っているのだった。マリはその場に居合わせてしまうたびに、そんな彼の想像を絶する繊細さを気の毒に感じた。それは、どこを切り取っても美しい彼の、唯一褒めることのできない癖のようでもあった。

あなたは言う
きみの体に触っても
きみの裸を見ても
性的に何も感じない
私はただ
きみの感情に惹かれているだけだから、
と。
きみも私も
潜在的な性的不満を抱えているのは事実だから
きみは
夫への不満の肩代わりとして
私を見ているのではないかと疑った
そして、私にもそれ(欲求不満)はあるから
それに埋没するのはいけない、
と。
そして、あなたは言う。
自分の中に何か制限があるみたいで
完全に気持ちを開放(ママ)できない
自分でも 自分の気持ちがよくわからない
ほんとうに、こんなことしてていいの?
と。
そして、何度も私にきく。
ほんとうに、愛していてかまわない?
と。
2021/10/29 「愛11」
2021年10月29日のマリのノートには、こんな彼の言葉が記されている。ということは、マサちゃんの入院を境に一旦中止していた二人の触れあいは、おそらくマリからの地道なアプローチによって、この頃までに徐々に再開されていたようである。もしも彼のほうから求めてくれたのなら、マリにはあまりにも嬉しい出来事であるから、必ずや記憶に残っているはずである。残念ながらそうではなかったようだし、マリからの再接近を彼がどのように受け入れたのかもあまり記憶に残っていないので、とりたてて抵抗もしなかったものと思われる。
「きみの体に触っても、きみの裸を見ても、性的に何も感じない。」
という言葉を、彼からまるで実感を確かめるように伝えられるたびに、マリの心は少しずつ負傷していった。彼の言葉は、彼の内側の真実を正直に発しているようにしか見えなかった。
「お互いの不満を埋めあったってしょうがないんだよ。」
彼は二人の愛や心の結びつきと、体の結びつきとを、どうしても分けて考えようとした。マリのことを、初めは自分の体目当てで接近してきたのではないかと疑ったことも素直に告白しているが、この過去形の言葉には、「そうではないことをそのあとで理解できたよ」という意味も含まれていた。
彼はまた、
「埋没するのは嫌いなんだよ。一度すれば、二度三度としたくなるに決まっているから。」
とも言った。その言葉には、体を重ねることの享楽に陥ってゆくことへの不安と抵抗が感じられた。もしかしたら、経験の無さからマリを十分に満足させられないかもしれないという不安も彼の中に入り交じっていたかもしれないが、とにかくマリと交われないありとあらゆる理由をデパートのように並べていた。
(この人は、私を抱く気がないな。)
マリはこの頃から、彼とは永遠に交われないのではないかという予感を心の隅に抱えた。
「完全に気持ちを開放できない」背景には、マリが既婚者であるという厳然たる事実があるのはもちろんである。そして、彼自身が正直に
「自分でも自分の気持ちがよくわからない」
と述べているように、この難しい愛の真ん中で、彼の意思は迷子になっていたのかもしれない。マリから見れば、彼がマリとの交わりを拒んでいることは、愛から逃げていることに他ならなかった。
「全部自分のものにしたい。」
彼がマリを見つめながらそうつぶやいたのも、たぶんこの頃であった。それは、前後の連なりもなくぽつんと発せられた言葉で、いったいどこから声を出しているのかと思うような、全く感情のなく平坦な、しゃがれた声であった。それはまるでこの世のどことも接していない、宇宙空間に直接吐き出された言葉のように浮かんでいた。
彼がああでもない、こうでもないと語るどの言葉も、地に足の着いた淡々とした物言いであるのだが、彼の、ほんとうはマリに伝えたくない、心の最も奥深いところにある本心は、このような声として吐き出されるのかもしれない、とマリはこのときに勘づいた。

ひとつ、覚えているエピソードがある。彼と服を着たまま抱き合っていた。彼は畳に座り、マリはその膝の上に跨っていた。彼はふと、両手をマリのズボンの中に差し入れ、弧を描くようにマリの両尻をこすった。マリは彼が何をしているのかわからず、きょとんとしていた。
「ほらな、キミのお尻を愛撫したって、お互いにちっとも気持ちよくもない。」
彼はがっかりしたように言った。
(ごめん、今のって愛撫してくれてたんだ……。手の動きが速かったから愛撫されているなんてわからなかった。)
マリはせっかくの彼の愛撫に気づけなかったことを申し訳なく思った。だけど焦らずに少しずつ、お互いの気持ちのいい触れかたを見つけていけばよいことであった。
★この物語は著者の体験したノンフィクションですが、登場人物の名前はすべて仮名です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
