
定年退職した65歳以上の編集者・エンジニア・マーケターが日本を救う

人生80年、セカンドライフ20年の長寿国「日本」
1970年の日本人の平均寿命は、男性が67.74歳、女性が72.92歳。多くの企業は「55歳が定年」という時代であった。2013年のWHO調べでは、日本人の平均寿命は男性80.21歳、女性は86.61歳で世界トップだ。今は65歳まで働けるようになった。一部では「70歳定年制」の議論も始まっている。
日本は「人生60年」と言われていた時代から「人生80年」という長寿の時代に入った。現代の65歳は、若々しく体力も十分あり、どう見ても老け込む歳ではない。実際は生存バイアスがかかるため、平均寿命よりさらに長生きすることになる。例えば、今60歳の男性なら平均余命は22.7歳となり、82歳まで寿命が伸びる(厚労省・平成23年簡易生命表)。100歳以上の高齢者は、58,820人で44年連続で過去最高となっている(2014年厚労省調べ)。最高齢は男性111歳、女性116歳で、ともにギネスに認定される世界最高齢である。この調査は1963年からスタートしているが、この年、100歳以上は153人しかいなかったが、2012年には5万人を突破している。
一方で、生活にまったく支障がなく自立できる「健康寿命」は男性70.4歳、女性73.6歳だ。医療費の削減が進めば、病気がちの高齢者にとっては厳しくなる。結果、在宅治療および介護が増えることになり、家族の生活も一変することになるだろう。政府にとっても、財政負担を軽減するため「健康寿命」をいかに伸ばすかが重要な課題になっている。平均寿命と健康寿命の差を短縮するための取り組みは、各地で進められており、例えば、筑波大学を中心に新潟市や三条市、見附市など7つの市が推進するスマートウエルネスシティなどがある。
東京都には、60歳以上の一人暮らしが約80万人いる。日本の孤独死は年間32,000人、その多くは高齢者である。亡くなる数週間前は買い物に出かけるなど普通に暮らしているため、周囲も気づかず、発見が遅れてしまうことが多い。また、高齢者の自殺率は韓国に次ぎ世界2位となっている。地域がより積極的に見守りの仕組みを導入していかないと解決しにくい問題だ。これからは、病院完結ではなく地域完結の医療およびケアシステムが必要になる。高齢者が多い日本は、年間130万人が死を迎える多死社会であることも理解しておいたほうがよいだろう。
WHOでは65歳以上の割合を高齢化率と定義し、7%超えで「高齢化社会」、14%超で「高齢社会」、21%を超えると「超高齢社会」としている。日本は、24%という高齢化率で「超」高齢社会の最先端を走っている。ただし、他の先進国も高齢化率が軒並み上昇しており、長期的には日本の後を追うことになる。中国などは、2050年に高齢者人口が4億8,000万人になると推計されており、全世界の高齢者20億人の4分の1を占め、世界最大の高齢社会となる(中国高齢社会青書2014)。先頭を突っ走る日本は、これから超高齢社会を迎える国々のモデルになっていく。逆の見方をすれば、超高齢社会を世界で初めて乗り越えられるのも日本なのである。

シニア・アントレプレナーが超高齢社会の新しいロールモデルになる
高齢の起業家をシニア・アントレプレナーと呼ぶ。国内の会社の創業時年齢は、55歳以上が全体の12%となり、60歳以上の起業を見ると20年前は全体の2.2%だったが6.6%に上昇している(日本政策金融公庫総合研究所調べ 2012年/2011年)。元気な高齢者(アクティブシニア)であっても、自身の健康維持や親の介護問題(老老介護)などを抱える可能性が高く、フルに一日を使える事業形態は難しいかもしれない。それでも、シニア・アントレプレナーは増えているのだ。
米国では、起業する年齢が2つのグループに分かれる。(大学院などを卒業した人が中心の)27歳から30歳前後と、50歳代である。27歳でサン・マイクロシステムズを創業したスコット・マクネリーのように、56歳になって一から起業したセカンドチャレンジも含むが、シニア世代の起業は確実に増えている。日本は「人生80年」をクリアした長寿国だ(100歳以上が58,820人もいる)。再雇用制度で65歳まで働いても、まだ20年近くのセカンドライフが残っている。65歳を超えても働き続けたいと思っている人が多いのは納得できると思う。
あと10年(2025年)で、団塊の世代が75歳以上になるが、彼等は全共闘世代であり、企業戦士としてパワフルに生き抜いてきた世代でもある。この巨大なアクティブシニア層に、現在の高齢者ニーズをそのまま当てはめて考えることはできない。企業は「アクティブシニア向けの新しいマーケットの開拓」と「就業機会を考慮した仕組みづくり」に取り組み始めている。東京ガスなどは、企業にとって伝承すべき豊富な経験知を持つ社員については、67歳まで就業機会を提供する制度がある。
シニア起業の多くは、前職の経験や実績を活かした起業、もしくは長年続けている趣味やサイドビジネスを発展させた起業である。稀に、夢を追い求めて未知の領域に挑戦する人もいるが、想像以上にハイリスクであることは言うまでもない。前職の実績を活かした起業は最も現実的だが、歳をとるのは自分だけではない、家族も親も同時に歳をとっていく。もっと言えば、現職時代の人脈も衰えていく。特に、会社の肩書きだけでつながっていた人たちとは、情け容赦なく切れていくものだ。
就業意欲の高い膨大な数のアクティブシニアがいる長寿国「日本」では、新たな成長戦略を考えていかなくてはいけない。徐々に増えているシニア・アントレプレナーは、自らの雇用の場をつくりだす自己雇用であると同時に、就業意欲を持つシニアに対して「雇用創出」の担い手になり、新市場開拓の牽引者としての活躍も期待できる。

引退したエンジニアでも「コードで世界を変えられる」ただしチームワークによる共創が条件
インターネットが商用化された1994年、皆さんは何をしてたか覚えているだろうか。当時、大学生ならすでに学校でインターネットを使っていたかもしれない。この頃、最も利用されていたブラウザーはMosaicだった。
Amazonの創業者であるジェフ・ベソスは、この年の9月22日、オレゴン州ポートランドで書店を開業するための4日間のセミナーに参加していた。本の売り方を勉強していたのである。この数ヶ月前の夏、ベソスはシアトル郊外の改造ガレージ付きの家を借りていた。同年11月、このガレージでベソス夫妻と2人のプログラマー計4人が開発をスタートさせる。サービス開始は1995年7月16日だが、すでにデータベースには100万タイトルの書籍が登録されていた。2人のプログラマーがAmazonの基礎をつくったのである。
Windows 95がリリースされ、”インターネット”が流行語大賞にノミネートされた1995年、感度の高い人たちは、インターネットビジネスに大きな可能性を感じていた。「コードで世界を変えられる」と確信したのだ。Googleが生まれたのは、3年後の1998年である。現在、私たちが毎日使っているウェブサービスの多くは、2000年半ばに登場している。2004年にFacebook、2005年にはYouTubeやEvernote、2006年はTwitterだ。さらに、2008年にはDropbox、2010年はPinterestやInstagram、Flipboardなど、次々とローンチする。これらは、莫大な予算を使った企業のプロジェクトではない。少数チームによるスモールスタートばかりだ。まさに、数人のプログラマーが書いたコードが私たちのライフスタイルを変えてきたのである。
2013年1月、起業家のハディ・パルトビとアリ・パルトビの兄弟は、世界的にプログラマーが不足していることに危機感を持ち、コンピュータプログラミングを必修科目にすべきと主張、非営利団体「Code.org」を立ち上げた。同年の2月26日には、キャンペーン動画を公開し、署名を求める。この動画には、ビル・ゲイツやFacebookのマーク・ザッカーバーグ、TwitterとSquareの創業者であるジャック・ドーシー、Dropbox創業者のアンドリュー・ヒューストンなど、IT業界の著名人が登場し、大きな話題になった。
米国では、これからの経済発展において、サイエンス(science)とテクノロジー(technology)、エンジニアリング(engineering)、数学(math)の4分野が中心になっていくと捉えており、STEM教育(ステム・エデュケーション)の普及を支援する取り組みを進めている。また、イギリスでも、5〜16歳の義務教育のカリキュラムに、プログラミング教育を導入。2014年9月からスタートした。5〜7歳のカリキュラムには、アルゴリズムについて理解させる学習もあり、世界中の教育関係者が注目している。
東京大学の坂村健教授は、オンラインメディアで「技術革新を主導しているのは「プログラミングの専門家」でなく、「プログラミングできるその分野の専門家」になってきている」と語っている。例えば、ICT教育の分野で革新を起こせるのは、プログラミングできる教育の専門家であり、デジタル出版で技術革新を起こすのは、プログラミングできる著者、編集者ということだ。
この領域は既存のウェブサービスやライブラリを組み合わせて、すぐにアイデアを具現化できるため、定年退職したエンジニアが、シニア・アントレプレナーとして活躍できる可能性が高い。長年エンジニアとして働き培ってきた「経験知」を活かしながら、他分野のメンバーと協働するスタイルでプロジェクトを動かすことができれば、小さなイノベーションを起こしていくことも夢ではない。ハイレベルなスキルを持つスーパーマンを目指すのではなく、スポーツチームのように力をあわせて取り組んでいくのである。エンジニアやデザイナーは、他人との密なコミュニケーションを最小限にとどめたい傾向にあり、対話重視のチームビルディング論にはうんざりしているかもしれないが、成功の鍵は「チーム」による共創しかない。

スポーツチームのように力をあわせて取り組んでいく
1986年、Harvard Business Reviewに「The New New Product Development Game」という論文が発表された。一橋大学の名誉教授である野中郁次郎氏と竹内弘高氏による新製品開発の手法についての論文だ。NASAやホンダ、キャノンなどの企業の製品開発のやり方を比較している。バトンを渡すリレーのような開発方法であるNASAに対して、ホンダやキャノンは、ラグビーチームがボールをパスしながら、ゴールに向かっていくような開発方法だと論じ、このようなチームをスクラムと名付け、特徴などを解説している。
アジャイル開発手法で現在、最も導入されているスクラムは、1993年末にこの論文を見たジェフ・サザーランドがリーダーを務める開発チームに導入したことで、その基礎が出来上がった。前述した「スポーツチームのように力をあわせて取り組んでいく」ための枠組みである。自分一人が能力を磨くのではなく、チームがそれぞれのスキルを現場で学び合う。「The New New Product Development Game」では、スクラムチームの6つの特徴を挙げているが、その中に「Multilearning(マルチ学習)」がある。さまざまな次元で「学習」が起こることを表している。異なる分野の人が集まれば、自分の専門外の知識についての「学習」が起こり、互いに学び合うことで共に成長していく。
言葉にすれば簡単だが、実践するには準備が必要だ。まず、やらなくてはいけないのがマインドセットである。ソフトウェア開発でいえば、ウォーターフォールの思考のまま、アジャイルチームに参加しても、不満がたまり、対話が中心の進め方に疑問を感じるようになるだろう。最初にクリアすべきは思考の転換である。アジャイルの哲学はとても参考になるが、造語が多く、同じ用語でも手法によって独自解釈が入っているため、本質を理解するのに時間がかかる。ここでは、問題解決の方法論として実績のある「デザイン思考」を糸口にしていく。

チームで起業するときに理解しておきたい「デザイン思考」の流儀
デザイン思考は、古くは1987年の建築家ピーター・G・ロウ著「Design Thinking」(デザインの思考過程)という本で知られているが、注目され始めたのは、2004年以降である。Business Week誌が「The Power of Design」という特集で、企業戦略におけるデザイン思考の有効性を紹介、その記事を見たハッソ・プラットナー(SAPの共同設立者)が、ソフトウェア開発にも応用できると考え、スタンフォード大学に35万ドルを寄付、2005年に「d.school(Institute of Design at Stanford)」を設立することになる。IDEOのデビッド・ケリーをディレクターとして招聘し、d.schoolは、デザイン思考を学び、実践していくための場となる。
その後、2008年にはIDEOのティム・ブラウンが、Harvard Business Reviewで「Design thinking」という論文を発表した。より具体的な内容は書籍「Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation」にまとめられている。日本では2010年に翻訳版の「デザイン思考が世界を変える」(ハヤカワ新書)が出版されているのでお薦めしたい。1987年の「Design Thinking」はシステム思考ベースで語られており、現在の人間中心の「デザイン思考」は、IDEOの積極的な啓蒙活動によって世界に広まったと考えてよいだろう。
デザイン思考を導入した現場では、マルチディシプリナリーと呼ばれる職域横断的なコラボレーションで進められる。異なる分野の人たちが一緒に作業をするのである。最初のアイデアは、建物の外に出て人を観察し、対話することで生み出される。「経験」から発想するアイデアであることが重要だ。そして、すぐにプロトタイプをつくり始める。ティムブラウンは、2009年のTEDカンファレンスで「何を作るかを考えるのではなく、考えるために作るのです」と語った。スクリーンには「BUILDING TO THINK」というキーワードが映し出されていた。
工業デザインにプロトタイプを本格導入したのは、ハーレイ・アール(GMのデザイナー)である。カーデザインにおけるクレイモデルやコンセプトモデルの手法は、他分野の製品開発でも採用されるようになったが、コストがかかるため、気軽に取り組めるものではなかった。社内に工作の設備を保有していたIDEOは、1つのプロジェクトで100以上のプロトタイプをつくることもあり、コスト増で何度も経営危機に陥ったほどだ。現在は、安価な3Dプリンターなどもあり、プロトタイプづくりのコストが飛躍的に下がっている。
人を説得するプレゼン資料に時間をかけることはない。まずは必要最小限のプロトタイプで有効性を確認し、メンバーが共に学びながら、何度も作り直すのが、デザイン思考のやり方だ。一人のスターデザイナーの閃きに頼るプロジェクトとは大きく異なる。
一部のデザイナーが「デザイン思考」を歓迎しないのは、既存のデザインワークを脅かす存在だと勘違いしているからだろう。現在のデザイナーの役割は変わらないし、仕事を奪われることもない。無闇にデザイン思考を導入しても、成果が得られるものではない。デザイン思考はあくまで問題解決のための方法論の一つであり、職域横断的な協働が基本である。さまざまな部署から人が集まり、互いに学びながら、プロジェクトを進めることが重要だ。多くの組織にとって、そう簡単に導入できるものではないことが理解できると思う。
デザイン思考の流儀を端的にまとめると、プロジェクトのメンバー全員がすべてのプロセスに参加すること。まずは建物の外に出て、観察し、対話をし、同じ体験をすること。フィールドワークで得た情報を共有し、プロトタイプを作りながら考えていくこと。繰り返しになるが、個人がハイレベルなスキルを持つスーパーマンを目指すのではなく、スポーツチームのように力をあわせて取り組んでいくことが重要なのである。
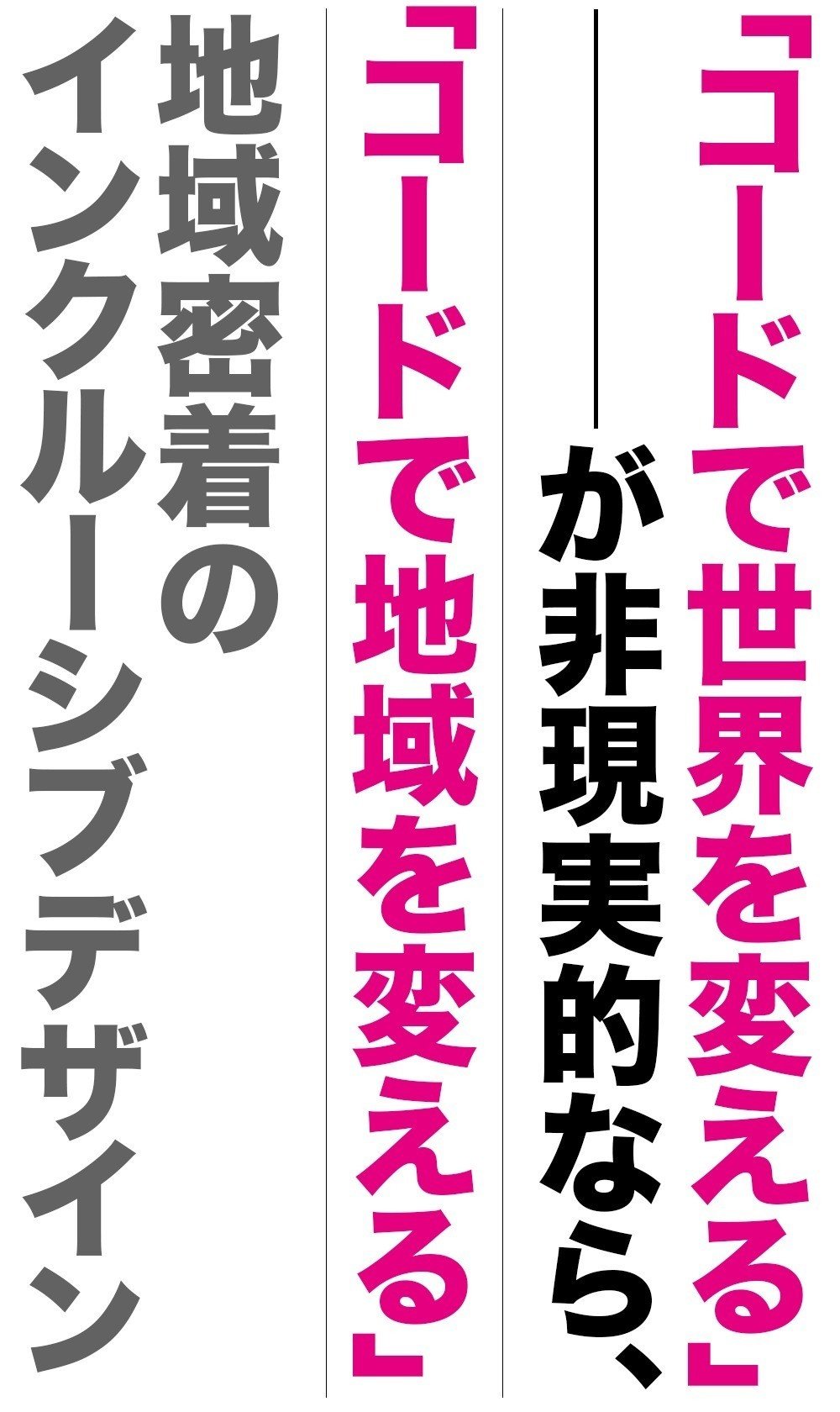
エクストリームユーザーを対象に身近な問題解決から始める
私たちのポケットの中には、仕事を効率化し、生活を豊かにしてくれる数々の道具(アプリ)が入っており、指で数回タップするだけで簡単に扱うことができる。その多くは、2000年半ばに登場したFacebookやTwitter、YouTubeなどである。電車に乗ると、乗客の多くはスマートフォンの小さな画面を見つめている。毎日、滝のように流れ落ちてくる大量の情報を消費し、どこまでスクロールさせるか、どれを共有しようか、と瞬間的な判断を繰り返しているのだ。
シニア向けのパソコン教室に行くと、そこには大きなキーボード付きのAndroidタブレットが並ぶ。パソコンは一台もない。「パソコンはOSの知識が不可欠でウイルス対策などの知識も必要になる。Androidに変えたことで長年苦しんでいたデジタルデバイドが大幅に解消された」「ここには、パソコン習得を諦めたお年寄りが集まっている」と担当講師が語る。授業では、専用アプリしか教えない。ウェブブラウザーも一切起動しない。基本操作はスクリーンタッチとキーボードだけだ。それでも、気になるニュースを見たり、天気予報をチェックしたり、電子書籍を買ったり、年賀状をつくってプリントするなど、最先端のデジタルワークをこなしている。
私たちにとってパソコンは欠くことのできない仕事の道具である。これから社会人になる学生にとってもパソコンを駆使した創造的学びを軽視することはできない。ただ、その他多くの人にとって現在のパソコンはオーバースペックで維持コストのかかるプロダクトなのかもしれない。
「コードで世界を変える」が大袈裟で非現実的なら、「コードで地域を変える」から始めていけばよい。身近な問題解決をビジネスにしていくのである。イギリスでは成人の4人に1人がインターネットを利用していない。そもそもアクセスできる環境を持っていないのである。政府は、デジタル・バイ・デフォルト(Digital by Default)政策の中で、急速なデジタル化によって排除(デジタル・エクスクルージョン)されてしまう人を減らすための取り組みを始めている。日本でも高齢のエクストリームユーザー層を中心に、デジタル・エクスクルージョンは存在するが、前述したパソコン教室のように数万円のAndroidタブレットで、敷居の低い学びの場をつくることはそれほど難しいことではない。まずは、地域密着のインクルーシブデザイン・プロジェクトから始めていき、その実績を世界に広めるというやり方も可能だ。
「建物の外に出て、観察し、対話をし、フィールドワークで得た情報を共有し、プロトタイプを作りながら考えていく」というデザイン思考を実践しながら、小さなイノベーションを達成していくのである。

70歳のエンジニアがイノベーションを起こす最初の国になる
これからの世界は複雑かつ変化の激しい問題に直面することが増えていく。子どもたちが社会に出て、これらの諸問題を乗り越えていくには、今の教育だけでは限界がある。米国が、STEM(サイエンス・テクノロジー・エンジニアリング・数学)教育に積極的である理由はよくわかった。また、英国など多くの先進国がプログラミング教育を推進しようとする動きも納得がいく。「プログラミング教育? もっと重要なことがたくさんあるだろう」という意見もよくわかるのだが、子どもたちが社会に出て直面するさまざまな問題、求められるスキルなどを考えると、学校で提供すべき「選択肢の一つ」として欠くことのできないものになったと考えるべきだろう。中等教育で実施されているプログラミング教育は、生徒全員をプログラマーにするものではなく、どのような分野であってもプログラミング的思考を活かすことができる人間を育成するためのエデュケーションプログラムなのである。
同じ道を歩く全員がスーパーマンにはなれない現実を理解しなくてはいけないが、チームワークによるシナジー効果についても知っておく必要がある。製品開発の分野では「意匠のデザイン」と「機能のデザイン」、「顧客価値を高めるデザイン」などを分離し、それぞれの専門家に分けてバトンリレーのようにプロジェクトを進めてきたが、このような開発手法に限界を感じた企業を中心に、職能横断的なチームづくりが実践されている。
教育機関で「デザイン」と「エンジニアリング」を同時に学んだ技術者を「デザインエンジニア」と呼ぶが、例えば、ダイソンの全技術者2000人のうち約800人は、デザインとエンジニアリングの専門教育を受けた人たち、つまり「デザインエンジニア」である。イギリスでは、デザインとエンジニアリングを同時に学べる学校が133校(大学は30校)あり、デザインエンジニア人材を育成する基盤が出来上がっている。ダイソンは、デザインエンジニアの重要性を啓蒙するため、大学などでワークショップを実施しており、国内では、2012年に東京大学駒場キャンパスでワークショップが開催されている。シニアデザインエンジニアのアンドリュー・マカロック氏が講師を務め、東京大学と東京藝術大学の学生が参加した。
日本のtakramは、デザインエンジニアが活躍している企業だ。エンジニアとデザイナーの役割分担はなく、デザインエンジニア一人が担当している。現在の製品は、スペックですべてを語ることはできず、ユーザーが製品を使い始める前から始まる「一連のエクスペリエンス」を考慮しなければいけない。また、サービスが前提となって設計されるハイブリッドプロダクトの重要性も増している。問題を分離せず、複雑なものを複雑なまま受け入れ、インテグレーティブなデザインを可能にする職能横断的な能力と視点が必要になってきたが、デザインエンジニアの存在は最もわかりやすいアプローチだといえる。
超高齢社会の日本には、アクティブシニアの中に経験豊富なエンジニアが揃っている。中には、メンターとして多くの若手を育ててきた人たちもいる。その膨大な数の「経験知(ディープスマート)」が消えていくのは日本にとっても大きな損失だ。企業の採用ニーズがないのであれば、リーンスタートアップ的に起業すればいい。今はペイドクラウドソーシングも活用できる。お金をかけず小さく始めるのだ。ただし、何度も強調しているが「チーム」による共創が前提となる。一番最初のチームづくりには、一年くらいかけてもいい。
2つの分野に精通したデザインエンジニアを見つけるのは大変だが、デザイナーとエンジニアが役割分担せず、すべてのプロセスに参加し、同じ体験をしながら、学び合うことで同質の効果を得られる。これは、現役でも引退したシニアでも変わらない。イノベーションとは「技術革新」のことではない。既存のアイデアの組み合わせで新しい価値を提供できれば、最新の技術である必要はないのだ。アクティブシニアのエンジニアに期待するのは、プログラミング能力よりも、「プログラミング的思考力」の方だ。公には流通しない経験知をいかにチームメンバーで共有できるかにかかっている。
65歳以上の高齢者人口は25%を超えて、4人1人が高齢者という状況だが、8割近くは元気なアクティブシニアである。2025年には、団塊の世代が75歳以上になり、医療介護問題がより深刻化するが、就業意欲の高い元気なシニアが活動しやすい環境になっていれば、自己雇用を促し、健康寿命を伸ばすことも可能になる(平均寿命との間を縮められる)。もっと言えば、若いエンジニアの刺激剤にもなるはずだ。
そのためには、新しいタイプのロールモデルが必要だ。理想をいえば「超高齢社会のイノベーター」として、世界にアクティブシニアの新しいモデルを示したい。
「70歳のエンジニアがイノベーションを起こす最初の国になる」実現不可能な夢ではない。
日本は、これから超高齢社会を迎える国々のモデルになり、超高齢社会を世界で初めて乗り越えられる国となる。

付録:
エンジニアの「経験知」獲得とチームづくりの考え方
「定年退職したエンジニアが日本を救う」を実現するためのプランニング
定年退職したエンジニアの「経験知」と「チーム」による共創による小さなイノベーション。これが本論だが、具体的にどうすればよいのか。思考法として「デザイン思考」を取り入れようとしているが、その前にロジャー・マーティン(トロント大学ロットマン・スクール・オブ・マネジメント学長)の「統合的思考(Integrative Thinking)」を知っておいた方がよいだろう。
世の中には、商才に長けた人たちがいる。新しい商売に挑戦し、何度も失敗し、そして必ず復活できる人たちである。なぜ、そんなことができるのか。私たちは、成功者が「何をやったか」に興味を持つ。そして、同じように成功しようとその「行動」を真似る。ところが、まったく状況は変わらない。毎年、ビジネスで成功をおさめた起業家の成功本や経営書が山ほど出版され、セミナーなども多数開催されているが、成功者で溢れかえる世界にはなっていない。
その理由は孫武の言葉から汲み取ることが可能だ。
「人は私がどのような戦略で勝利したかを知ることができるが、私がどのようにその戦略を考えたかは知ることはできない」
成功者が「どう行動したか」ではなく、「どう考えて、その行動を導き出したか」を学ばなければ、いくら本を読んで勉強しても、セミナーに参加しても、成功者が「何をやったか」の後追いにとどまる。
ロジャー・マーティンは15年間、各界のリーダーを研究し、成功をおさめた人たちの「共通点」を探していた。その研究結果は2007年に、Harvard Business Reviewで発表している。「The Opposable Mind: How Successful Leaders Win Through Integrative Thinking」という論文である。日本で刊行されているダイヤモンド・ハーバード・ビジネスレビューでは「偉大なるリーダーの思考法」という邦題で掲載されている(2007年9月号)。
ずばり、成功者の共通点は「相反する考えを並立、対比させ、検討する能力」。噛み砕いて言えば、「複雑な問題を、複雑なまま解こうとする能力」だ。物事をシンプルにするため優先順位を決めて単純化したり、専門化して分担するのは、統合的思考の大敵だという。
そして、重要なのは「一人の限界を知る」ということだ。成功者の陰には、チームもしくはチームに相当する協力者たちが存在する。「複雑な問題を、複雑なまま解こうとする」のだから、一人の力ではどうしようもない。
ロジャー・マーティンの著書「Opposable Mind: Winning Through Integrative Thinking」には、IDEOのティム・ブラウンがいかに「複雑な問題を、複雑なまま解こうとしたか」を実際のプロジェクトを紹介しながら解説しているが、まさに「デザイン思考」が、この力を生み出す原動力になっていることがわかる。
※日本では翻訳版の「インテグレーティブ・シンキング」(日本経済新聞出版社)が2009年に発行されている。
アクティブシニアで構成されるチームづくりには、まずマインドセットから入る必要がある。逆の見方をすれば、デザイン思考、および統合的思考、システム思考などをおさえたチーム作業ができれば、高度な専門スキルを必ずしも必要としない。さらに、どんな分野でも応用することができるため、より多くの人を巻き込むことが可能だ。
では、具体的に何から始めていけばよいのか。ワークショップ形式で記すことで、誰でも実践可能なプランを示すことができそうだ。記事は「THINK GCDeMO MAGAZINE」の中でまとめていくので、ご興味のある方はインフォメーションをチェックしてみてほしい。
投稿者:
Creative Edge School Books
@commonstyle
転載日:2018年9月23日(日)
更新日:2015年9月24日/投稿日:2015年9月24日
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
