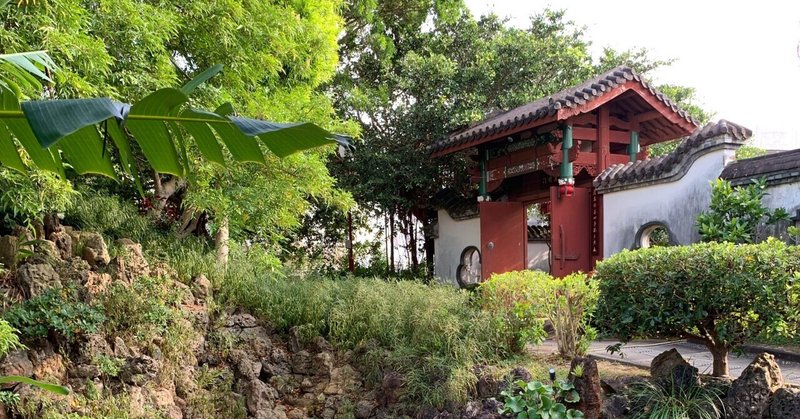
【漢詩解説】骆宾王:在狱咏蝉(竝序)〈書き下し文・日本語訳〉*前回の補足*
駱賓王:獄に在って蟬を咏ず 並びに序
在狱咏蝉 竝序
余禁所禁垣西,是法厅事也,有古槐数株焉。虽生意可知,同殷仲文之古树;而听讼斯在,即周召伯之甘棠,每至夕照低阴,秋蝉疏引,发声幽息,有切尝闻,岂人心异于曩时,将虫响悲于前听?嗟乎,声以动容,德以象贤。故洁其身也,禀君子达人之高行;蜕其皮也,有仙都羽化之灵姿。候时而来,顺阴阳之数; 应节为变,审藏用之机。有目斯开,不以道昏而昧其视;有翼自薄,不以俗厚而易其真。吟乔树之微风,韵姿天纵; 饮高秋之坠露,清畏人知。仆失路艰虞,遭时徽纆。不哀伤而自怨,未摇落而先衰。闻蟪蛄之流声,悟平反之已奏;见螳螂之抱影,怯危机之未安。感而缀诗,贻诸知己。庶情沿物应,哀弱羽之飘零; 道寄人知,悯余声之寂寞。非谓文墨,取代幽忧云尔。
この後に続く五言詩の解説はこちら。
【書き下し文】
余の禁所は禁垣の西にして、是れ法庁事なり。
古槐数株あり。
生意知る可きこと殷仲文の古樹に同じと雖も、
而も訟を聴くこと斯に在るは即ち周の召伯の甘棠なり。
乃ち夕照陰を低るるに至れば、秋蟬疏引し、発声幽息すること、嘗て聞くよりも切なる有り。
豈、人心の曩時に異なるか、はた蟲響の前に聴きしより悲しきか。
嗟乎、声は以て容を動かし、処することは以て賢に象る。
故にその身を潔うしては、君子達人の高行を稟け、其の皮を蛻するや、仙都羽化の霊姿有り。
時を候って来たるは、陰陽の数に順い、節に応じて変を為すは、蔵用の機を寄す。
目有りて斯に聞き、道の昏きを以て其の視を昧くせず。
喬樹の微風に吟じて韻姿天縦に、高秋の墜露を飲んで、清は人の知るを畏る。
僕、路を失いて艱虞し、時の徽纆に遭う。
哀傷せずして自ら怨み、未だ揺落せずして先ず衰う。
蟪蛄の声を流すを聞いて、平反の已に奏せらるるを悟り、蟷螂の影を抱くを見て、危機の未だ安からざるを怯る。
感じて詩を綴り、これを知己に貽る。
ねがわくは、情、物に沿うて応じ、弱羽の飄零を哀しみ、道、人に寄せて知らしめ、余声の寂寞憫れまれんことを。
文墨と謂うに非ず。
幽憂に代わるを取ると云うのみ。
【日本語訳】
私はいま宮城の西、司法庁の獄舎にいる。
ここに古い槐が数株あり、むかし
殷仲文が嘆じた司馬府の老槐のように、もはや枯れかかっているが、ここで訴訟を裁かれるのであれば、いわば周の召伯がその蔭で正しい裁きをしたという甘棠の木というところであろうか。
毎日、夕暮れになると、秋蟬がどこかで鳴いて、その声はかそけく、常に聞いていた声よりも哀切である。
自分の心がこれまでと違っているのか、それとも、蟬の声が前に聞いたよりも悲しいか。
ああ、その声は聞く者の心を動かし、その身の処し方は賢人にも似ている。
さればその身の潔さは君子達人の高い行を旨とし、その皮をぬけ出るのは、羽化登仙の姿である。
その時候を待ってやって来ることは、よく陰陽の循環に順い、時節に応じてその姿を変えることは、出処進退の機微を心得ている。
目は見開いて道の昏きにくらまされず、翼は薄くても世俗の厚きにならってその本質を易えぬ。
高樹の微風に吟じて生まれつきの風韻あり、秋の露をのんで、清き身の行いは人に知られるを畏る。
余は世路の艱難にあい、罪人となりはてたが、いたずらに悲傷するよりは自ら我が身を怨み、落葉をも待てず先ず衰えた。
この蝉の声が伝わってくるのを聞いて、今や再審が上奏されたことを知る。
しかも蟷螂が後ろに忍び寄る危機の不安におびえている。
これに感じて詩を作り、知己の諸君におくる。
ねがわくはこの蟬のごとく、弱き身の落ちぶれを哀しみ、人に訴えるこの声のわびしさを憫れまんことを。
詩の巧拙を云わず、ただ深い憂いに代えただけである。
解説は以上になります。
作者本人から詩の背景を語っているのは珍しいので、貴重な資料だと思いました。
この「序」のあとに五言詩が続きます。
ぜひもう一度読み返してみてほしいですね。
短いですが、
昨夜から熱と頭痛があるので
今回はこれで終わりにしたいと思います。
明日は記念日なのに寝たきりになりそうで、軽く落ち込んでいるところです。
そして
いつもご覧いただきありがとうございます。
応援したいと思ってくれたらうれしいです! これからも楽しく記事を書いていきます☆
