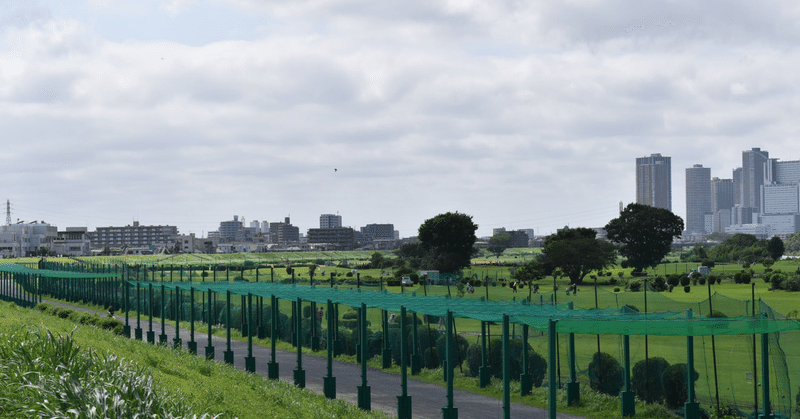
スキルを見える化および構造化してパフォーマンスアップにつなげよう
今回のテーマはスキルの見える化です。
ゲームのキャラクターのように能力値が数値化されていたら、スキルや能力を測ることが簡単ですよね。でも現実はそうではありません。AさんはExcelが得意、Bさんは接客が得意など、得意なことはなんとなく解るけど、具体的にどの程度か解らないのが現実です。そこで経験年数や実績、職位、資格などの目に見える指標が使われます。
正直なことを言うと私も能力やスキルを数値化する方法は持っていません。しかしジェネラリストとして、マネージャーとして仕事した経験と、転職回数の多さ(色々失敗があって多いので偉そうなことは言えませんが)から言えることがあります。
それが今回のテーマであるスキルの見える化です。スキルを構造で表すのです。今回はスキルを構造として表し解説します。それを踏まえた上でパフォーマンスを上げることについて解説します。
スキルを構造で表すと2階層
スキルを数値化することは難しいですが、スキルを構造化することは可能です。ビジネススクールや社会人向け教育事業会社、人材会社なども、スキルの構造を図で表したものを公表していたりするでしょう。
ここでは残念ながら私が昔どこかで見聞きしたものに私の経験をプラスした持論になってしまいますが、実態に近いと自負しているものを紹介します。下の図を見てください。

パフォーマンスは専門スキルだけで決まらない
スキルというと専ら専門スキルが注目されます。転職活動などは専門スキルを見られます。このスキルで実務経験が何年あり、どういう仕事の実績があるかを見られます。
でも経験年数が同じでも、同じ案件に所属していたとしても、人それぞれパフォーマンスは違います。中には経験年数が少ないのにパフォーマンスが高い人もいます。
その謎を解くのが上記の2レイヤーで考えたスキル構造です。
基礎スキルは様々なところに現れる
みなさんもご経験があると思いますが、年季は長いのに理解力が乏しい、いい発想が出てこない、何を言っているのかよく解らない人はたまにいると思います。一方で頭がよくて次から次へと良いアイディアが出てくる人に会ったこともあると思います。
また、文章の上手い下手はあまり経験年数が関係なく、経験豊富でも変な日本語を書いている人を見かけることは珍しくありません。スキルは高いのに説明が下手な人に苦労したこともあるかと思います。
つまりスキルは2レイヤーあるわけです。特に重要なのが思考力です。
下の階層は基礎スキル
レイヤー1のスキルが土台です。なぜならどの職種でも必要なスキルであり、どの職種のパフォーマンスにも影響するからです。
それでは基礎スキルを順に解説していきましょう。
思考力
いくら知識が豊富でも、知識を使いこなせる思考力がなければ仕事は速くなりません。また、思考力や理解力が高ければ、経験年数に対して難易度が高いことを理解できます。理解できれば実践もできます。
いわゆる地頭の良い人が強い理由は思考力です。地頭の良い人は知識の理解が速く使いこなしも上手く、発想も良く出てくるからです。そしてこれは先天的なものではなく、トレーニングによって高められます。
実は我々は学生時代までに国語と数学で論理的思考力を身に付けてきているのです。だから高学歴の人の方が地頭が良い人が多い傾向にあるのです。先天的な頭の良し悪しの差というよりはトレーニングの差によるところが大きいのです。
読み書き
文章の読み書き力も侮れません。仕事では多くの資料や書類を扱います。ということは、読むスキルすなわち読解力が高いほど素早く資料の意味を理解でき、書くスキルが高いほど他人が見て解りやすく誤解の少ない資料を作成できます。
また文法的にしっかりしていて読みやすい文章を書くと、知的あるいは地頭が良い、しっかりしているという印象を与えられます。セルフブランディングにもなるのです。
コミュニケーション
そして最後、コミュニケーションスキルは言うまでもありません。何を言っているのか解らない説明が下手な人よりも、説明が丁寧で解りやすい人の方が仕事はスムーズに進みます。仕事はチームでやるものなので、必ずコミュニケーションが必要になります。一人チームのことも稀にありますが、顧客がいるためコミュニケーションは存在します。
上の階層は実技
レイヤー2のスキルが一般的によく言われているスキルですね。転職活動で見られるのもこれらのスキルです。実技なので目に見えやすいスキルとも言えますね。
こちらについては見えやすいがために今回のテーマでは深く説明する必要がないと思います。
重要なのは基礎スキルと専門スキルの掛け算
そして何よりも重要なことはレイヤー1である基礎スキルとレイヤー2である専門スキルの掛け算でパフォーマンスが決まるということです。正確にはパフォーマンスは基礎スキル×専門スキル×適性ですが、今回はスキルがテーマですので適性は別の機会に解説します。

基礎スキル×専門スキルという視点で考えると、例えば下記のような選択肢が出てきます。
自分には基礎スキルと専門スキルのどちらが足りないのか考えてみて、足りない方を強化してみる。
経験の長い業務でパフォーマンスに頭打ちを感じたら、思考力や文章力のトレーニングをしてみる。
基礎スキルを強化しておくことで、未経験の業務に当たっても理解できるスピードを上げておく。
このモデルは不完全
ここまで解説しておいてなんですが、今回紹介したモデルは不完全です。そもそもマネジメントスキルについて一切書かれていないため、個人のプレイヤーとしてのパフォーマンスしか考慮していません。
今では多くの職種で必要になったPCスキルにも触れられていません。PCスキルについては思考力や読み書き、コミュニケーションとは性格が違うだろうということで除いています。また貿易会社や観光会社では英語も重要なスキルですが、今回紹介したモデルには載っていません。
また10年くらい前に私が受けた基礎ビジネススキル研修では、今回紹介した3つに加えてタイムマネジメントが入っていました。仕事にはスケジュールや納期がありますので、時間管理は欠かせませんよね。このように今回紹介したモデルは完全ではありません。
理由を一言でいうと、全てを網羅したモデルを作るのが大変だからです。そしてシンプルな方が解りやすく検証しやすいのです。今回は解説内容を最低限にしてシンプルにしようと思ったわけです。
よってみなさんなりにアレンジしたり付け加えたりしていただければと思います。他人の意見はあくまでも参考情報です。ご自身のお仕事に合った形に色々とアレンジしてみてください。
終わりに
何事も見える化してみることで、現状を分析したり対策を考えたりできるようになります。スキルも同様です。
そして図で形にしてみることで、構成要素やそれらの関係が明らかになってきます。こうやって曖昧模糊としたものを理解しやすくなります。
今回はスキルを見える化してみました。みなさんなりにアレンジしてスキルアップの肥やしにしていただければ幸いなことこの上ない限りです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
