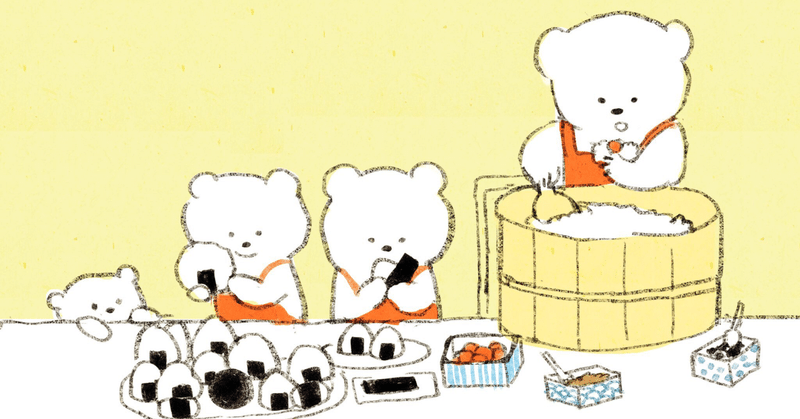
専業主婦が18年かけて我が子にしてきたこと。
私は専業主婦を18年続けている。
現代日本では希少価値のある生物だという自覚はもちろん、ある。
諸般の事情により専業主婦を続けることになったのだが、残念ながら割り切った気持ちで18年を生きてきたわけではない。
よく言われるように、社会(?)から取り残された感、ただ飯食い感は半端ではないのだ。
スケジュール確認などの事務的な意味での「お仕事してますか?」という質問に対して、あえて「今はしてないです」と答えてしまう虚しさよ。
「今は」とか要らないのに、誰に何をアピールしてるんだか。
さて私個人の内面のモヤモヤはさておき、専業主婦を続けてよかったことももちろんある。
なかでも育児面でのメリットは大きかったと思っている。それは大きく分けると「経験」と「(塾代を減らす目的の)勉強」になる。
家事の習慣づけ(料理や掃除のお手伝い)
反抗期になったらお手伝いなどしないだろうと予想されたので、とにかく小さいうちからなんでもやらせた。
子どもにやらせるのは忍耐が要る。
しかし専業主婦は「在宅時間の長さ」に関しては右に出るものがない。
反抗期の子どもに指導する面倒くささを考えたら、小さい子と遊びながらやるほうが、なんぼかラク。
小さい子は集中できる時間が短いので、今日は野菜を洗うだけ、明日はレタスをちぎるだけ・・・というように少しだけやればよい。
もう少し大きくなったら一連の流れでやらせるが、正規の家事時間内に取り組ませると時間が気になりイライラするからよくない。
子どもの遊び時間に「家事っぽい」遊びをしちゃって、なんだかうまいこと夕飯の一品もできあがっちゃったわー、得したわー・・・くらいの気持ちでいく。
実際のところ息子は、反抗期(主に中学生期)には家事などなにひとつやらなかった。
しかしそれもある意味仕方ない。学校・ブラック部活・ブラック塾・学校の課題・塾の課題で手一杯なのだ。ここまでで既に睡眠時間を削ってやっているのに、これ以上何をするというのか。
忙しすぎて常にイライラしていた息子。反抗期じゃなくても普通にイライラするよ…と同情を禁じ得ない3年間だった。
高校生になると、学校・グレー部活・ホワイト塾・学校の課題・塾の課題という構成になって、かなり余裕が出来た。
すると平日はともかく、長期休みには声をかければ普通に家事をやってくれるようになった。
教えなくても「やる気」さえあれば出来るので負担が少ないのだろう。
その証拠に小さいうちに教えなかった新しいことを頼むと、面倒がってなかなかやってくれない。
週末(や長期休み)のフィールドワーク
フィールドワークとは「野外調査」という意味だが、もちろんそこまででなくてよい。
海・山・川・里山での遊び。動物園・水族館や美術館・博物館のお散歩。ショッピングセンターなどで吹奏楽の無料コンサートなどがあればもれなく聴いてみる。観光地で大道芸をやっていれば足をとめて楽しむ。
いろいろな場所に連れ出し、多種多様な経験をさせる。
どこからどのように興味が芽生えて、それが将来の道へとつながっていくかまったく分からない。
ちなみにうちの息子は小学生の時にテレビ番組で「太平洋の島国が海に沈みそうな様子」を見て環境問題に興味をもったそうだ。
その後、自然にふれるたびに環境問題を考え続け、中学・高校でも総合の学習では一貫して環境問題を取り上げ、ついには大学もその道に進むことになった。
いくつか経験した習いごとは大した興味を持てないままに終わってしまったことを考えると好対照である。
毎日の学習習慣(チャレンジ)
赤ちゃん時代からベネッセのお世話になった流れで、小学生になっても自宅での勉強習慣にチャレンジを利用した。
毎日必ずチャレンジタイムをつくり、添削問題へとつなげる。
学年が上がるにしたがい苦手な科目がでてきたので、ネットでよさそうな問題集を探し、本屋に出かけて実物をチェックして購入し利用した。
しかし、ひとつ失敗したことがある。
私自身の勉強法の中に「試験問題の復習」という項目がなかったため、息子にも添削問題が返ってきたときに解き直しなどをさせなかったのだ。
これはあとあと受験生になっても習慣づかず、親子でモメる元になった。
中学の内申書対策
高校受験の年、分かってはいたが成績の悪さに(親が)泣かされた。
定期テストの得点のわりに、成績表がとても悪いタイプというのがいるのだ。我が子は思いっきりそのパターン。
原因は提出物。第一に調べる・書くなどのすべての作業が「雑」。
そして第二に、これがもっとも悪いのだけど、提出期限を守ったためしがなく、「未提出」のまま終わったことも数知れず。
これでは良い成績は望めない。
中三になって慌てて内申書対策のためガッチリ見張ることにしたが、反抗期でもあり、本人が(私に)申告しないと提出物の存在が分からないため(私が)途方に暮れる。
ママ友のツテを頼るのも限度があるのだ。
各教科ごとにプリント類をクリアファイルで管理させていたが、どうやらうまくいってなかったらしい。
教科書は持ってもクリアファイルを持ち忘れたり、逆もあったり。忘れ物大王には管理が難しかった。
ちなみに、高校では蛇腹タイプのクリアファイルブックのようなものをひとつだけ用意。
全教科のプリント類をそれにしまう方式に変更。
時間割がどのように変わろうとも、毎日必ずそのファイルを持てばいいので、本人は管理がしやすくなったと喜んでいた。
事実、高校生活では未提出事件はおこさなかったらしい。
高校受験で提出物のせいで成績が悪くなり大変困った経験から、高校生活では本人の意識が変わったのが一番の原因ではあったと思う。
中学・集団塾の補習
中学生の時は地元で一番安いけど、地域最大手の塾に通わせた。
我が家が塾に求めるものは「地域最大手ならではのデータと教材」。
しかし息子自身の教科による得意・不得意の差が激しすぎて、レベル別クラス分けが合わない。
不得意科目はレベルを下げて丁寧にみる必要があり、得意科目はレベルを上げてどんどん進ませる。
不得意科目は何が原因でつまづいているのか分析する。
たとえば英語では「文法は分かるが問題が解けない」という自己申告があったので、単語力不足ではないかと思いチェックしたところ、そのとおりだったことが判明。
高校受験用の単語帳とアプリを使用。
受験対策としては過去問をひたすら反復。
間違い直しをするのは当然だが、「なぜそうなるのか」を説明させる。
当然(?)説明できないので、その解説をしてあげる。
解説後にもう一度説明させる。
できなければもう一度解説してあげ、説明させる。
とにかく反復。
高校・個別指導塾の情報交換
中学での集団塾は「データと教材」を活用することを目的に通わせたが、途中で集団塾は向かないタイプだなと分かった。
そのため高校では個別指導塾に。もちろん本人の意向も確認した。
個別指導とはいえ大手なのでカリキュラムがある程度決まっていて、それに沿って進められていたようだ。
しかし最初から指定校推薦狙いであることを伝えておいたため、定期テスト前には普段指導を受けていない不得意教科の特別指導を受けることが出来た。
年に三回も保護者面談があり、保護者の考えを塾に伝えることが出来たので、高校の受験に対する雰囲気を伝えたり、保護者としての方針や息子の家庭学習状況などを伝えたりと積極的に活用した。
高校の定期テスト対策
あまりにも低空飛行で見ていられない教科が出現。
話を聞くとノーベン(無勉強)で中間テストにのぞんだとか。
ある意味大物だった。
詳細は「授業が難しい→つまらない→つまらないから授業を聞かない→分からない」だと。
この話を細かく聞いたのが期末テスト三日前のため、突貫工事で「テスト勉強のやり方」を指導。
「聞く」よりも「見る」ほうが理解が早いタイプのため、各教科ごとにテスト勉強のやり方を紙に書きだして、そのとおりに進めさせる。
結果、中間テストの倍以上の得点で、平均点をギリギリ超えることに成功。
先生からお褒めの言葉があったらしい。
授業を聞かなかったのがそもそもの原因ではあるが「テスト勉強のやり方」が何も分かっていなかったことが判明したのが、こちらとしては衝撃的。
たしかに「テスト勉強のやり方」を指導されることはあまりない。自然と分かるものだと思っていたのだが、「分かってこない人もいる」のが現実だった。
中一の段階で指導していれば…と思わないでもない。(この時点で高二)
高校の小テスト対策(指定校推薦狙い)
中学生のうちから大学へ行って環境問題を学びたいと言っていた息子。
しかし一般受験で希望の大学へ行くのは難しいと思われたので、高一の夏から指定校推薦対策を始めさせる。
提出物は絶対出す。
中身も手を抜かず、スペースいっぱいまで書き込む。
英語の単語テストが3年間にわたり毎週必ずあったので、対策として出題範囲の問題を作る。
EXCELで作成したものを一部印刷するごとにソートして、まったく同じ出題順番にならないように工夫。
当初、残念ながら、単語帳をぼーっと見ているだけの無駄な時間を過ごしていたのでこのようなやり方になった。
単語帳まるまる2冊を入力しきったことで、私の英語入力の力がついたことは思わぬ収穫だった。
大学受験関係の情報収集
高校では学校・部活・塾と忙しいうえに進路関係の情報収集もせねばならない。しかし本人に任せきりにも出来ない。
このあたりは別記事に詳しく書いた。
そしてこれから・・・
大学入学関係の書類や手続きも終わった。
入学式の会場が遠方のため、春休み中に一度連れて行って、当日ひとりで行けるように予習もさせた。
もうやることないな。
…と思いたいが、これからも履修登録やら単位取得やら卒業研究やら就職やら、怒涛の4年間になることだろう。
これまでも意識的に少しずつ手を離すように心がけてきたが、これからはもっと離れて「見守り」に徹さねばならない。
春が来た。
羽ばたけ、息子よ。
記事をお読みいただき、ありがとうございます! サポートをいただいたら、noteでより良い記事が書けるように使わせていただきます。
