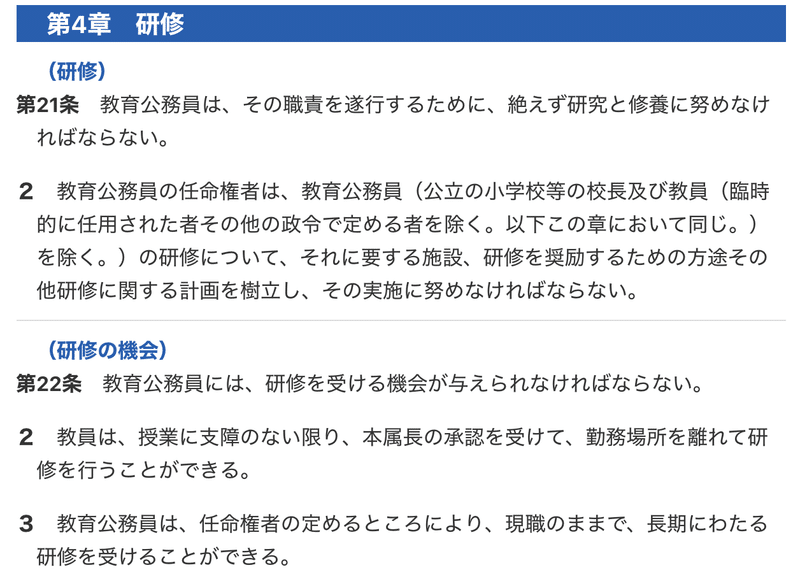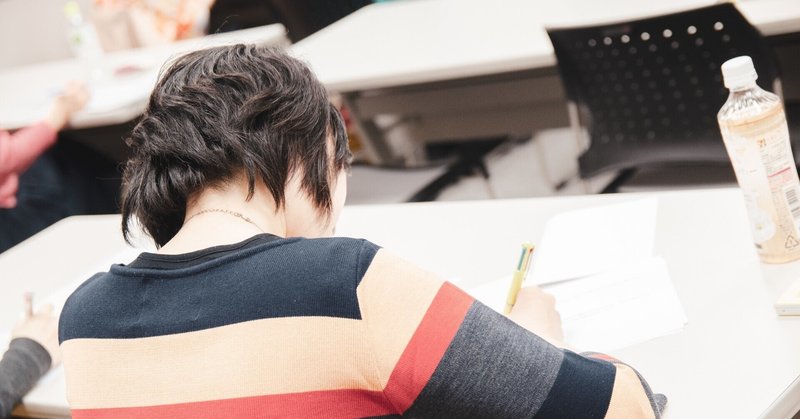
研修はいやいや受けるものではない!
学校の先生は研修を受ける権利と義務があります。
これは教育基本法の第9条に定められています。
他にも教育公務員特例法第21条・22条に記載があります。
つまり、研修は法律でやりなさいと決められているものなのです。
だから現場の先生たちはたまに研修で学校にいない場合があるのです。(1人2人ですが)
さて、そんな研修ですが、昨日自分も受けなければなりませんでした。
自分が選択したものは学校経営などに関する研修でした。
今年の研修はコロナウイルスのこともあり、オンラインでの研修でした。
Google MeetやZoom、Webexなど様々なオンライン会議用のツールがあるのでオンラインでも難なく研修は行うことができました。
そんな研修ですが、参加者の中にはこんな人もいました。
「これが一番簡単そうな研修だったからこの研修を選んだ」
「正直今更やる内容でもない」
「資料読んだから別のこと(採点など)やっていよ」
また、勤務校でも
「どの研修が簡単だった?」「あの研修楽らしいよ!」
などの声もたまーに聞こえてきます。
自分は研修を通して学びを深めたいなと思うし、新しいことを知るきっかけになればいいと思うので比較的研修は好きな方ですが中にはこういった人もいるということをしりました。
研修といっても自分が本当に受講したいものを受けられるのではなく、ある程度指定があり、日程的な縛りもあります。
また、そもそも研修の内容が3時間もかけてやる内容か?と疑問を抱きたくなる内容の研修も数多くあります(笑)
正直、一緒に働いている同じ学年の先生に聞いた方が早く解決したり、学びになったりすることの方が多い気がします。
それは状況を知っているからこそ、具体的な指導をしてもらえるからです。
研修中に具体的な事例で考えようと言われても、背景がだいたいしか決まっていないことが多いため、いまいちピンとこないことがあります。
だから、必要感が薄れめんどくさいなと感じてしまうこともあります。
本来研修は自己の成長のため、そしてその成長が周りにもいい影響を及ぼすので行うはずです。
みんながいやいや受けて特に何も学ばなかったら研修をやる必要がありません。
研修を行うことが目的になっている様な先生方が多い気がします。
本当だったら県外の研究授業とか講演会、企業の研修への参加などたくさんの研修があって、研修自体の質を向上していかなければならない部分もあるとは思いますが、学ぶ姿勢なしに学びはないと思います。
研修を受けるならいやいやではなく、積極的に発言したり、感想を述べ合いお互いに ”学んだ!” と思えるものにしていきたいものです。
※ちなみにオンラインだとみんなすごく静かです(笑)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?